|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
年譜
5 江戸に塾を開く
適塾で蘭学の力をメキメキつけてきた福沢論吉の元へ、安政五年二八五八)になると中津藩の江戸屋敷から呼び出しがきました。
安政五年は先にも述べたとおり、日米修好通商条約が結ばれた年です。
これによって日本とアメリカは、公使と領事をお互いに交換する事になり、江戸と大阪を外国人に開き、また神奈川(実際には横浜)・長崎・新潟(実際には明治元年まで開港せず)・兵庫を開港する事になりました。
そうして幕府は同じような条約を、オランダ・ロシア・イギリス・フランスの各国とも次々に結びました。
それで、これらの条約をまとめて五ヵ国条約といいますが、この五ヵ国条約によって日本はいよいよ市場として、各国に開かれたわけです。
このように、急に情勢が変ってきた事にあおられたのでしょう、江戸の中津藩邸では蘭学を勉強する会が開かれていました。
そうしてその教師として一時、薩摩出身の松木弘安(のちの外務卿寺島宗則、一八三二〜一八九三年)とか、のちに明六社の一員になる杉亨二(すぎ・こうじ)という人を、召し抱えていたのです。
しかし同じ教師を雇うのなら、何もよその藩の人にきてもらう必要はない。
藩の中の福沢が大阪で勉強しているではないか、という事になって、福沢諭吉が呼び出され、蘭学の教師となる事になったのでした。
彼二五歳のときでした。
今まで私たちは彼を諭吉とよんできましたが、いよいよ彼も独立したという意味で、これから福沢とよぶ事にしたいと思います。
もっとも中津藩へ戻るについては、福沢に多少のわだかまりがなかったとはいえません。
長崎で彼は家老の息子である奥平壱岐から意地悪をされ、それに反抗する形で、大阪へ飛び出してきていたのでした。
その壱岐が、いまや江戸詰めの家老となっていました。
けれども時勢のあわただしい雲ゆきは、二人のそうした小さなゆきがかりを、手もなくおし流してしまいました。
福沢にとって幸いな事に、壱岐はおうようにこだわりをみせませんでしたし、福沢も「ご家老さま」といって、さわらぬていで応対する事になります。
江戸へ呼び出された福沢はいったん中津へ帰って、母にいとまをつげたのち、大阪をたちます。
しかしこの時から、福沢には、家来が一人つきました。
何といっても藩の公用ですから、彼くらいの身分では家来を一人くれるのが、きまりとなっていたのです。
ただその家来は実際につけてくれたのでなく、家来一人分のお金を渡されたのです。
その金で福沢は適塾の塾生で江戸へゆきたいものをつのり、結局、広島出身の岡本周吉、のちの古川節蔵と同行する事になりました。
「君は飯を炊かなければならぬがよろしいか。江戸へ行けば米もあれば長屋もある。
鍋釜も貸してくれるが、本当の家来をやめにすれば飯炊きがない。
そのかわりに連れて行くのだが、どうだ。」
という条件でした。
思えば福沢が中津を逃げるように抜け出したのは、安政三年の事でした。
それからわずか二年にして彼は、中津藩邸から迎えられるようになったのです。
初めて下る東海道でおそらく様々の思いに包まれながら、途中、一日も川止めなどの災難にもあわず、福沢は江戸へつきました。
安政五年の十月下旬、もう少々寒い頃とはいえ、小春びよりにめぐまれた旅でした。
もっとも政界では、安政の大獄が吹き荒れていたのです。
中津藩邸は、木挽(こびき)町の汐留にありました。
そこへ出頭した福沢に、鉄砲洲に中屋敷がある、その長屋を貸すという指示がありました。
福沢と岡木はさっそくその長屋に住みこんで、男二人の自炊生活を始めるとともに、ここに蘭学塾を開きました。
藩の子弟が三人五人と学びにくるようになりました。
またほかからも五人六人とやってきましたので、福沢は彼らに蘭学を教えました。
下が六畳一室に上が十五畳という、妙なかっこうのこの長屋が、今日の慶応義塾の起源です。
上には塾生がおり、下の六畳――といっても板の間ですが――には三畳だけ畳(たた)みを敷いて、二畳分に福沢がおり、隅の一畳に岡本が起居しました。
鉄砲洲のこの慶応義塾発祥の地は、今日の聖ロカ病院のすぐまえにあり、義塾百年を記念してここに記念碑がたてられています。その隣は、もと浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)の屋敷があったところです。
またこの中津藩中屋敷は蘭学の先覚者である前野良沢(まえの・りょうたく)が中津藩士であったため、彼らがオランダ解剖書を読んだ地にもあたっています。
今は東京の下町の車のゆきかう殺風景な一隅にしかすぎませんが、ここはその意味では、日本の新しい学問の生誕地の一つといえるでしょう。
大阪から江戸へでてくるにあたり、福沢には一つの自負のようなものがありました。
それは、大阪の書生は江戸へ学びにゆくのではない、教えにゆくのだ、という自負でした。
そこで福沢は、江戸へきた初めのうちは、なかば他流試合いのつもりで、有名な蘭学者を訪れてはその学力をためしたりしました。
福沢も中々人の悪いところがあって、オランダ書のむずかしそうなところをえらんで聞きにゆき、その学者が読みそこなうのをみて、ひそかに安心したりしたのです。
そんなふうにして彼は、だんだん江戸の蘭学者仲間へ入ってゆきました。 |

鉄砲洲の慶応義塾発祥の地の碑
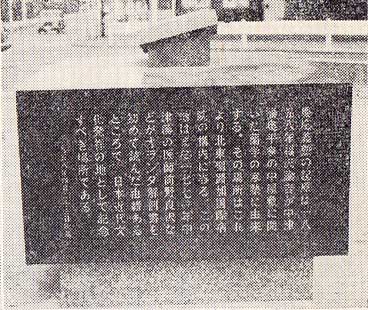
碑に刻まれた文章
|
江戸の蘭学の名家に桂川家がありました。
桂川家は初代の甫筑(ほちく)からずうっと続いてきた日本の蘭学の本山ともいうべき家柄でした。
代々幕府の奥医師を務めていました。
当主は七代の甫周(ほしゅう)でしたが、福沢はこの家にもたびたび出入りしては、書物を借りたりしたようです。
甫周の次女のみねは、この時母を失った四、五歳の幼女でしたが、父のもとへやってきた福沢の事を、晩年になってもよく覚えていました。
福沢はみねにとっては親切な若者で、よく話をきかせてくれたり、彼女をおぶって外出したりしました。
大変な勉強家で、そのふところはいつも本でいっぱいにふくらんでいました。
そうして桂川家から書物を借りていっても、ほかの人なら写すのに一、二ヵ月もかかるのが普通だのに、福沢は六、七日で返しにくるのでした。
子供にたいしても機嫌をとってあやすという事がなく、じゅんじゅんと教えてゆこうとする気骨がありました。
そんな福沢にみねは親しみを感じて、父の前にきちんと座って話をきいている彼の足袋の穴を、松葉でこちょこちょとつついたりしました。
|

横浜の異人館
|
いまや福沢は小なりとはいえ、一つの塾の責任をおう存在でした。
しかしその彼にはやくも、江戸へでてきた翌年にあたる安政六年には、大きなショックをあたえる出来事がおこりました。
それは、ふと思いたってある日、福沢が横浜見物にいった事がきっかけでした。
その年から開かれた横浜は、それまで東海道をはずれた小さな漁村にすぎませんでしたが、急に賑やかになってきました。
各地から進取的な商人が集って外国人と貿易を始めました。
土木工事や建築工事か次々に始められて、町が形づくられてゆきました。
そうした活気あふれる横浜を一度見ておこうと、福沢は、東京から一日がかりでやってきたのでした。
だがその横浜で、彼は何を見たでしょうか。
それはオランダ語が、今まで必死に学んできたあのオランダ語が、全く役にたたないという発見でした。
横浜でみる看板は英語であり、商品のラペルも英語であり、話す言葉も英語でした。
鎖国の時代、オランダだけが、日本にとってかすかに開かれたヨーロッパでした。
しかし日本が鎖国の眠りをむさぼっているうちに、世界は変わってしまっていたのでした。
十八世紀は大きな変革の世紀でした。
この世紀におこった産業革命は、イギリスを七つの海を支配する国家の地位へのしあがらせていました。
またこの世紀におこったアメリカの独立戦争は、アメリカを強国に育てるもとをつくりました。
オランダは日本が知らぬまに、ヨーロッパの“中小国家”の一つに変わり果てていたのです。
福沢はそれを嫌というほど思い知らされたのです。
彼はがっかりするとともに、今後は英語でなければならぬ、と決心します。
決心するとその行動は早いものでした。
横浜から帰ったあくる日以来、彼は英語の勉強にうちこむようになります。
これは、福沢にとって大きな転換でした。
しかしその大きな転換を、彼は決心してなしとげようとし、苦労に苦労をかされて、英語を勉強してゆきます。
1 英学発心 top
横浜は、まさしく開けたばかりのところ。そこで私は横浜に見物にでかけた。
その時の横浜というものは、外国人がチラホラ来ているだけで、掘立小屋みたいな家が諸方(しょほう=所々)にチョイチョイできて、外国人がそこに住まって店をだしている。
そこへ行ってみたところが、ちっとも言葉が通じない。
こちらのいう事もわからなければ、あっちのいう事ももちろんわからない。
店の看板も読めなければ、瓶のはり紙もわからぬ。何を見ても私の知っている文字というものはない。
英語だか仏語だか、一向わからない。
居留地をぶらぶら歩くうちに、ドイツ人でキュッフルという商人の店にぶちあたった。
その商人はドイツ人でこそあれ、蘭語蘭文がわかる。
こっちの言葉はろくにわからないけれども、蘭文を書けばどうか意味は通ずるというので、そこでいろいろな話をしたり、ちょいと買い物をしたりして江戸に帰って来た。
ご苦労な話でそれも屋敷に門限かあるので、前の晩の十二時から行って、その晩の十二時に帰ったから、ちょうど一昼夜歩いていたわけだ。
2 小石川に通う top
横浜から帰って私は足の疲れではない、実に落胆(らくたん=がっかり)してしまった。
これはこれは、どうも仕方がない。
今まで数年のあいだ死に物狂いになってオランダの書を読む事を勉強した。
その勉強したものが、今は何にもならない。
商売人の看板を見ても読む事ができない。
さりとは、まことにつまらぬ事をしたわいと、実に落胆してしまった。
けれどもけっして落胆していられる場合でない。
あすこに行われている言葉、書いてある文字は、英語か仏語に相違ない。
ところで、いま世界に英語の普通に行われているという事は、かねて知っている。
何でもあれは英語に違いない。
いまわが国は条約をむすんで、開けかかっている。
さすれば、こののちは英語が必要になるに違いない。
洋学者として英語を知らなけれは、とても何にも通ずる事ができない。
こののちは英語を読むよりほかに仕方がないと、横浜から帰った翌日だ。
ひとたびは落胆したが、同時にまた、あらたにこころざしを発して、それから以来は、いっさい万事英語と、覚悟をきめて、さてその英語を学ぶという事について、どうしてよいか取付き場がない。
江戸中にどこで英語を教えているというところのあろうわけもない。
けれどもだんだん聞いてみると、その時に条約を結ぶというがために、長崎の通詞の森山多吉郎という人が、江戸に来て幕府の御用を勤めている。
その人が英語を知っているという噂を聞きだしたから、そこで森山の家に行って習いましょうと、こう思ってその森山という人は小石川(今の文京区)の水道町に住居していたから、さっそく森山家に行って英語教授の事を頼み入ると、その森山のいうに、
「昨今ご用が多くて大変に忙しい。けれどもせっかく習おうというならば教えて進ぜよう。
ついては毎日出勤前、朝早くこい」
という事になって、その時私は鉄砲洲(中央区湊町)に住まっていて、鉄砲洲から小石川まで、やがて二里余りもありましょう。毎朝早く起きて行く。
ところが、今日はもう出勤前だからまた明朝きてくれ、あくる朝早く行くと、人がきていて行かないという。
どうしても教えてくれる暇がない。
それは森山の不親切というわけではない。
条約を結ぼうというときだから、中々忙しくて、実際に教える暇がありはしない。
そうするとこんなに毎朝きて、何も教える事ができんでは気の毒だ。晩にきてくれぬかという。
それじゃ晩にまいりましょうといって、今度は日ぐれからでかけて行く。
あの往来は、ちょうど今の神田橋、一橋外の高等商業学校(一橋大学の前身)のある辺りで、もと護持院ヶ原といって、大きな松の木などがおいしげっている、恐ろしい寂しいところで、おいはぎでもでそうな処だ。
そこを小石川から帰り道に夜の十一時十二時頃、通るときの恐さというものは、今でもよく覚えている。
ところがこの夜稽古もやっぱり同じ事で、今晩は客がある。
いえ、きゅうに外国方(外務省)からよびにきたから、でて行かなければならぬというようなわけでとんと仕方がない。
およそそこに二ヵ月か三ヵ月通ったけれどもどうにも暇がない。
とてもこんな事では、何もおぼえる事もできない。
加えるに森山という先生も、何も英語をたいそう知っている人ではない。
ようやく少し発音を心得ているというぐらい、とてもこれは仕方がないと、余儀なく断念。
3 蕃書調所(ばんしょしらべしょ)に入門
top
そのまえに私か横浜に行った時に、キニッフルの店で、うすい蘭英会話書を二冊買ってきた。
それを一人で読むとしたところで、字書がない。
英蘭対訳の字書があれば、先生なしで自分一人で解す事ができるから、どうか字書を欲しいものだといったところで、横浜に字書など売るところはない。何とも仕方がない。
ところが、その時に九段下(千代田区)に蕃書調所(ばんしょしらべしょ)という幕府の洋学校がある。
そこにはいろいろな字書があるという事を聞き出したから、どうかしてその字書を借りたいものだ。
借りるには人門しなければならぬ。
けれども藩士がだしぬけに公儀(幕府)の調所に入門したいといっても、許すものではない。
藩士の入門願いにはその藩の留守居というものが願書に奥印(おくいん)をして(書類の末尾にはんこを押すこと)、しかるのちに入門を許すという。
それから藩の留守居のところに行って奥印の事を頼み、私は裃(かみしも)を着て蕃所調所に行って、入門を願うた。
その時には箕作麟祥(みつくり・りんしょう=幕末から明治にかけての法学者)のお祖父さんの箕作阮甫(げんぽ=蘭医)という人が調所の頭取で、さっそく入門を許してくれて、入門すれば字書を借りる事ができる。
ただちに拝借を願うて、英蘭対訳の字書を手にうけとって、通学生のいる部屋があるから、そこでしばらく見て、それから懐中の風呂敷をだして、その字書をつつんで帰るうとすると、それはならぬ、ここで見るならば許して苦しくないが、家に持ち帰る事はできませぬと、その係の者がいう。こりゃ仕方がない。
鉄砲洲から九段坂下まで、毎日字引きを引きに行くという事は、とても間にあわぬ話だ。
それもようやく入門して、たった一日行ったきりで断念。
さて、どうしたらよかろうかと考えた。 |
 |
ところで、だんだん横浜に行く商人がある。何か英蘭対訳の字書はないかと頼んでおいたところが、ホルトロップという英蘭対訳発音つきの辞書一部二冊がある。まことに小さな字引きだけれども、価五両という。
それから私は奥平の藩に歎願して買いとってもらって、さあもうこれでよろしい。
この字引きさえあれば、もう先生はいらないと、自力研究の念をかたくして、ただその字引きと首っ引きで、毎日毎夜一人勉強、またあるいは英文の書を蘭語に翻訳してみて、英文になれる事ばかりこころがけていました。
4 英学の友を求む top
そこで自分の一身はそうきめたところで、これはどうしても朋友がなくてはならぬ。
私が自分で不便利を感ずるとおりに、今の蘭学者はことごとく不便を感じているに違いない。
とても今まで学んだのは役にたたない。
何でも朋友に相談してみようとこう思うのだが、このことも中々易くないというのは、その時の蘭学者全体の考えは、私を初めとしてみな数年のあいだ刻苦(苦しみぬいて)勉強した蘭学が役にたたないから、まるでこれを捨ててしまって、英学に移ろうとすれば、新たに元のとおりの苦しみをもう一度しなければならぬ。
まことに情けない、つらい話である。
たとえば五年も三年も水練を勉強して、ようやく泳ぐ事ができるようになったところで、その水練をやめて今度は木登りを始めようというのと同じ事で、以前の勉強がまるで空になると、こう考えたものだから、どうにも決断がむつかしい。
そこで学友の神田孝平に面会して、どうしても英語をやろうじゃないかと相談をかけると、神田のいうに、
「いや、もう僕もとうから考えていて、実は少し試みた。試みたが、いかにも取付き場がない。
どこから取付いてよいか、実にわけがわからない。
しかし年月を経れば、なにか英書を読むという小口がたつに違いないが、今のところでは何とも仕方がない。
まあ君たちは元気がいいからやってくれ。
大抵方角がつくと僕もきっとやるから、だが今のところでは、何分、自分でやろうと思わない。」
という。
それから番町(千代田区)の村田蔵六(のちに大村益次郎といい、近代軍制の創始者)のところに行って、その通りに勧めたところが、これはどうしてもやらぬという考えで、神田とまるで説がちがう。
「無益な事をするな、僕はそんなものは読まぬ。いらざる事だ。
何もそんな困難な英書を、辛苦して読む者はないじゃないか。
必要な書はみなオランダ人が翻訳するから、その翻訳書を読めばそれでたくさんじゃないか。」という。
「なるほどそれも一説だが、けれどもオランダ人が何もかも、いちいち翻訳するものじゃない。
僕は先ごろ横浜に行って、あきれてしまった。この案配では、とても蘭学は役にたたぬ。
ぜひ英書を読まなくてはならぬではないか。」と勧めれども、村田は中々同意せず、
「いや読まぬ。僕は、一切読まぬ。やるなら君たちは、やりたまえ。
僕は必要があれば闌人の翻訳したのを読むからかまわぬ。」と、いばっている。
これはとても仕方がないというので、今度は小石川にいる原田敬策にその話をすると、原田はごく熱心で、
「何でもやろう、誰がどういうてもかまわぬ、ぜひやろう。」というから、
「そうか、それは面白い。そんなら二人でやろう。どんな事があっても、やりとげようではないか。」
というので、原田とはごく説が合って、いよいよ英書を読むという時に、長崎からきていた子供がいて、その子供が英語を知っているというので、そんな子供をよんできて発音を習うたり、またあるいは漂流人で、おりふし帰る者がある、長くあっちへ漂流していた者だ。
開国になって船の便があるものだから、おりふし帰る者があるから、そんな漂流人が着くと、その宿屋に訪ねて行って聞いた事もある。
その時に英学で一番むつかしいというのは発音で、私どもは何もその意味を学ぼうというのではない。
ただスペリングを学ぶのであるから、子供でもよければ、漂流人でもかまわぬ。
そういう者を探し回っては学んでいました。
初めはまず英文を蘭文に翻訳する事を試み、一字々々字を引いて、それを蘭文に書きなおせば、ちゃんと蘭文になって文章の意味をとる事に苦労はない。
ただその英文の語音を正しくするのに苦しんだが、これもしだいに糸口がひらけてくれば、それほどの難渋でもない。
つまるところは最初、私どもが蘭学を捨てて英学に移ろうとする時に、真実に蘭学を捨ててしまい、数年勉強の結果をむなしうして、生涯二度の艱難辛苦と思ったのは大間違いの話だった。 |
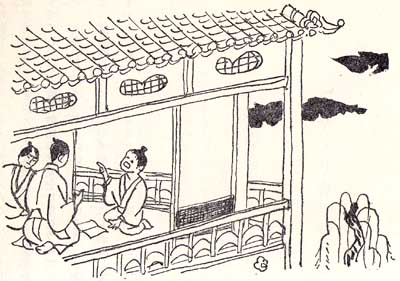 |
実際をみれば蘭といい英というも、ひとしく横文にして、その文法もほぼ相同じなれば、蘭書を読む力はおのずから英書にも適用して、けっして無益でない。
水を泳ぐと木に登ると全く別のように考えたのは、一時の迷いであったという事を発見しました。
|
top
****************************************
|