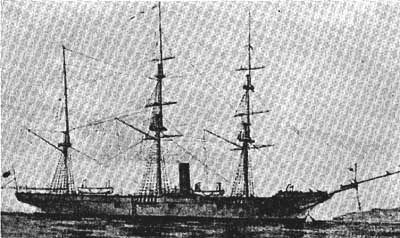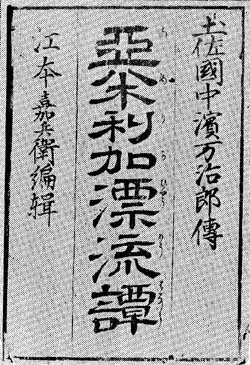|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
16 ブルーク大佐の咸臨丸搭乗日誌の発見
一八五九年(安政六年)、当時の江戸で、二人の難破船員の出会いがあった。
その二人は、これまで一度も会ったことのない人たちであった。
一人はアメリカ海軍の士官であり、一人は日本漁師のせがれであった。
後者は、いうまでもなく万次郎であり、アメリカ海軍士官というのは、当時、天文学者、海洋測量学者として名の通っていたジョン・マーサー・ブルーク大佐であった。
大佐は、さきに締結された日米条約によって開港される日本の港を測量するため、米国政府から派遣されて、はるばる日本に来たのだが、彼の乗艦フェニモア・クーパー号が、台風のため難破したので、やむなく江戸に滞留していたのである。
そして、この二人が咸臨丸に乗り組むまでの経緯は前に書いた。
ところで、幕府の海軍は、これまではオランダ人の指導による日本近海の航海しか経験していなかったので、いま咸臨丸で、いきなり大洋に乗りだすというのは、実のところ、大胆きわまる目論見であった。
そこで幕府は、形式的には便乗者としてではあるが、実際には相談役、ないしは顧問として、ブルーク大佐とその部下の咸臨丸乗り組みを要請したのであろう。
ところが、勝艦長はじめ日本人乗組員たちは、自分たちの力だけで大洋を初めて乗り切るのだと意気込んでいただけに、熟達したアメリカ海軍軍人が割り込んできたということに、あまりいい気持はしなかったらしい。
しかし、それも幕府の命令とあれば是非もなかった。
さて、咸臨丸がいよいよ太平洋に乗り出すと、とたんに大変な暴風雨に出くわし、艦は木の葉のように翻弄された。
熟達のアメリカ人船員でさえ、「こんなしけは初めてだ」と音をあげたほどの酷い荒天だった。
勝艦長も司令官の木村摂津守も、ひどい船酔いに弱り果て、船室に閉じこもったまま、殆んど艦橋に姿を見せなかった。 |

咸臨丸渡米当時の艦長勝麟太郎(右)と同乗者のジョン・ブレーク(左)
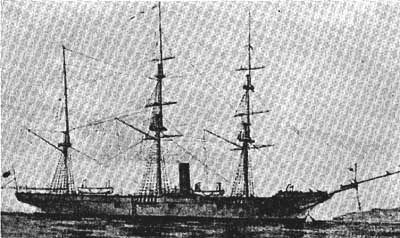
咸臨丸は、徳川幕府がオランダに注文して建造した最初の西欧型軍艦である。内車機関付きの木造三本マストのスクーナー・コルベット型、全長47.8m、幅7.7m排水量350トン、馬力100トン、速力6ノット、乗員76名。
兵装としては砲12門を備えた。
|
勝は海軍軍人ではあっても、大洋に乗り出すのは初めてだったし、木村は海軍大臣にあたる軍艦奉行の職にありながら、船乗りの真似をするのはこれが初めてであったから、無理もなかった。
だから、便乗者だった筈のブルーク大佐とその部下は、結局のところ、艦の運航の全責任を背負わされることになってしまったのである。
プルークは、通訳として乗艦していた万次郎が、アメリカ本土で教育を受け、そのうえ、船乗りとしても世界を何度か周航していると聞いて驚いた。
そして、この艦で、万次郎だけが頼りになる人物だと認識した。二人は、たちまち親友になった。
ブルークは、毎日の経験を詳細に日誌に書きとどめていた。
そしてこの日誌は、ブルーク家に保存され、今は大佐の孫、バージニア士官学校教授、哲学博士、ジョージ、ア−サー、ブルーク二世が管理者となっているが、ブルーク博士は、この祖父の日誌を、日米修好通商百年記念行事運営会に寄付したのである。
こうしてブルーク大佐の日誌は、「万延元年遣米使節史料集成・第五巻」に収録されることになったのである。
アメリカの歴史専門誌「アメリカン・ヘリテイジ」(American Heritage)は、一九六三年八月号で、プルーク日誌を再録し、これを“現象は歴史”の好例として賞讃した。
百年の歳月ののち、遂にこの文献は世に出て、万次郎の功績をも併せて顕彰する結果となったのである。
ブルークの日誌には、航海用語が多く、また天候についても専門家の立場から詳しく記され、それに伴なう操帆や操艦の記述も少くないが、ここでは、一般読者が読みやすいように、技術的な記述は省くことにした。
日誌は、嵐にもまれた小帆艦咸臨丸の様子を詳しく描写しているが、その陰に、当時の日本封建社会の一面が如実に表現されている。 、
咸臨丸乗組員のなかには、封建的階級意識が根強くはびこっていて、そのために、万次郎は様々な苦労をするのである。
たとえばブルークの助言を万次郎が日本語で乗組員に伝えると、これを快く思わない者が、万次郎を帆桁に吊るして殺すぞ、と脅迫するような事件も起こったのである。
また、当直士官を選ぶにしても、能力よりも陸にいるときの階級がものを言う有様であった。
司令官木村摂津守は、身分の低いものは、どんなに航海術にたけていても、艦橋の当直に立つことを許さなかった。
咸臨丸の乗組員は、ほとんど全員が、満足に訓練された船乗りとは言えなかった。
つまり、彼らには、この新式帆船は扱い切れなかったのである。
ブルークは、このことを日誌の中で、また一八六〇年三月二十五日付で――つまりサンフランシスコ到着後、ワシントンの海軍長官に送った報告書の中で――はっきりと書いている。
このブルークの日誌を翻訳した慶応義塾大学教授清岡露二氏は、「遣米使節史料集成」の中で次のように述べている。
「ブルークが選ばれたのは、ある意味では偶然ともいえるのだが、彼が熟達の航海士というだけでなく、科学者であり、かつ日本人に対し独特の理解と同情を持った人物であったことを考え合わせると、幕府と使節団はまさに最適の人材を得たといえよう……」
「ブルーク大佐はサンフランシスコで新聞記者たちに対し、日本人乗組員を褒め讃える談話をしているが、航海中の自身の役割りについては、一言も言及していない。
日本人にとって、このような精神の人を友人かつ助言者として持ったことは幸運であった……」
「中浜万次郎について語られるところ、まことに少ない現実にかんがみ、ブルーク日誌が彼に多く触れていることを私は嬉しく思う。
おそらく、当時、万次郎の真価について知っていたのはブルーク一人ではなかったろうか……」
ついては、そのブルーク日誌の一部をここに紹介しよう。
……一八六〇年二月十日(万廷元年正月十九日)午後二時浦賀出帆。出航の際、和船の間を縫って進む。
……艦長は下痢を起こし、提督は船に酔っている。
……明け方目を覚ました。船は激しく縦揺れしている。非常に荒い海で、しばしば波が打ちこむ。日本人は全員船酔いだ。船は大檣トラィスル(編者注:大檣(マスト)もしくは前檣のうしろ側についている補助的な小縦帆)で走っている。蒸気もたいている。陸地がどんどん遠ざかる
……潮流にのったのならよいのだが、そうなれば北ないし東に向け速度も加わるだろう。提督はまだ自室にいる。艦長も同様。
……万次郎は天候を気づかっている。
……三日分の石炭しか持っていないので、午後三時には蒸気をとめよう。
……もし米国産の石炭を積んでいたら、順風の吹きはじめるまで六日か七日は蒸気で走れるのに。
……日本人たちも、だんだん船酔いから回復してきた。……しかし提督と艦長はまだ病気である。陰うつな天候で、雲が濃く寒い。
……日本人がキャビンの天窓を踏み破ってこなごなにしてしまったので、我々は円窓のあかりだけになってしまった。
……午後十時、針路、東北東。日本人が無能なので、帆を十分あげることができない。
士官たちは全く無能である。たぶん悪天候の経験が全然ないのだろう。
命令はすべてオランダ語で下される。私は、日本人が彼等自身の航海用語を持つべきだと、その必要を強く感じる。
……甲板が非常に滑りやすいので、私は転んでしまった。
この船は砂を積んでいない。航海のはじめから不愉快なことだ。
……日本人たちは、なかなかよい油をひいた外套と手袋を持っている。
彼等は、だんだん船乗りらしくなってきている。
……日本人は火に関しては全く不注意だ。昨夜は料理室から火事を出した。
……万次郎がいうには、昨夜、彼が日本の水夫たちに登檣(帆柱登り)を命じると、彼らは万次郎を帆桁に吊すぞ、とおどしたそうだ。
彼らが、もし、そのおどしを実行に移すようなことをしたら、すぐ私に知らせろ。
命令に反抗するものは、艦長が私に権限を与えてくれ次第、すぐ吊してやると彼にいっておいた。
……日本人は本当に当直の役割りを果たしているとはいいがたい。
三、四人の例外を除いては、彼らはみな船室に入りこみ、デッキに出てくるのに十五分から二十分もかかる。
提督は、私にこんな情況のもとで船の指揮をする労をねぎらってくれた。
……当直に水夫は二人ずつしか立たない。船の中で、秩序とか規律とかいうものは全く見られない。
アメリカ海軍の軍艦にみるような規律とか秩序とかは、日本人の習慣と相容れないものらしい。
日本人水夫は船室で、火鉢と熱いお茶と、キセルとをそばに置かなければ満足しないのだ。
飲酒はそう厳しく取締まられていない。
これに加えて、命令がすべてオランダ語で下され、しかも極く僅かの水夫たちしか、その言葉を解しない。
これによって任務の遂行がどんな有様かは想像がつくだろう。
艦長はまだ寝台にねたきり、提督も同様。
士官たちはドアを開け放しにし、それがパタンパタンと風にあおられ、自分たちのコップや皿や、やかんが床の上を転がり廻るにまかせ、全くだらしないこと言語道断。
しかし、我々は、これが彼らの教官はオランダ人だったということを忘れてはならない。
日本の海軍にはどのような改革が必要であるかについて、意見を持っているのは、乗組員中、万次郎ただ一人である。
……晴雨計では苦労している。アディーは船が揺れるごとに一インチほども上下する。
そのうえ、一人の日本人がアネロイドのガラスに手をついて、突き破ってしまった。
私はいま自室にその残骸を持っている。他の一人は天窓を踏み破ってしまった。
今日は大波をかぶって、クロノメーターがもう少しで水につかるところであった。大変な航海だ。
しかし、珍妙な経験も悪くない。私は日本海軍の改革に努めよう。そして万次郎を援けるのだ。
……真夜中ごろ風が衰え、我々は午後五時までは進めなかった。
提督はわずかの間デッキにでてきた。長いあいだ船室に閉じこもっていたので、樵悴の色がみえる。
……日没に際し、トプスル(訳者註・上檣帆)を二つ縮帆した。日本人は自分だけでは縮帆できない。
我々アメリカ人便乗者が耳索その他をたぐってやる。
……真夜中まで南々東の風が非常に激しく吹いた。何度も帆が帆桁からちぎれるのではないかと思った。
午後十二時、雨が滝のように降ってきた。
空気が白く見える。風は西に変わり、やがてまた強く吹き出したが、これが最後の変化だろうと思われるので私はホッとした。三時に就寝。正午から真夜中までに九六マイル進んだ。
横になるやいなや、また呼ばれる。強いスコールがくる。
この日の夕方、私は日本人たちの無神経さに全く驚かされた。
暴風のきざしが現われているのに、ハッチもしっかり閉めていないし、そのうえ、羅針箱のあかりも非常に薄暗いままであった。
当直士官は船室に帰り、二、三人の水夫は甲板にうずくまっていた。
私は万次郎をして呼びにやり、やっとのことで当直士官のみならず、すべての士官達を船尾に呼び集めることに成功した。 彼らもやっと重大事態がわかりかけてきたのだ。
船はスコールにのって暗闇の中を疾走し、船の節々をふるわす。
トプスルとフォアスル(訳者註・前桶の大帆)が今にも吹飛ぶのではないかと思った。
真夜中、暴風のなかで船室に潜っている日本人は、砂の中に頭だけをつっこんで全身を隠しているつもりの駝鳥とよく似ている。
……今夕、万次郎が私に士官たちの当直の組分けができたと報告した。
そうすると、これまでの当直士官は特に決められていたのではなかったらしい。
……今日は水夫や士官の当直を割り当て、部署を決めるよう提案した。
しかし予期しなかった困離にぶつかった。六人の尉官級士官のうち、何人かは職務に全く無知である。
提督は能力のあるものを当直につけたがらない。
つまり、かれらが無能なものほどには身分が高くないからというのである。
結局、提督は誰にも部署、当直を割り当てず、もとのままにしておくことを望んでいるのだ。
提督自身も船舶運用に関してなにひとつ知っていない。
彼は、私が船を動かすことができるものだから安心だと思っている。
それで差し当たり、万事変わりなしということになった。
とはいえ、私が下船するまでに、なんとかこの点を議論して改めさせよう。
万次郎はひどく、うんざりしでいる。彼は仕方なしに提督に従っている。
しかし彼は当直の必要を士官達に納得させた。
私は彼に、もし私が部下を当直からはずし、船の仕事を拒否したら、提督はどうするだろう、と関いてみた。
「船を沈めてしまうでしょうよ」と彼は答えた。
そして万次郎は、自分自身としてはそんなことで死ぬのは惜しいといった。
……夕刻、私は縮帆している船の絵を描いて、水夫達に番号さえつければ、縮帆などをさせるための配置がわけなくできることを士官たちに示した。
彼らは喜んだようだった。万次郎は、誰はばかるところもなく自由に話すが、また同時に何か不安そうだ。
彼は非常に危険な地位にあり、非常に注意して亀裂を避けねばならないのだ。
……乗組長の当直も部署もまだきまっていない。
……四時三十分、船の方向を変えるために私はデッキに出た。
万次郎は私といっしょに来たが、他の日本人たちは余りにものろく、また関心がなさすぎるので――デッキに出てきたのは一人か二人だった――私は腹が立って船室に戻った。間もなく万次郎が降りてきて、皆をデッキに集めたと報告したので、私もデッキに上がって行き、船を北東微東に向けた。
……私は時々、癇癪をおこす。日本人たちは全くのろまだ。
彼らは荒天に対して全く無経験で、しかも部署を割り当てられていない。
従って私は非常に注意深くしていなくてはならず、また、できるだけ帆を小さくして航海せねばならない。
……今夜あたり一八○度を越えると思う。
正午前、経度観測を行なったが、 緯度が不明なので、あまり自信がない。
今日でちょうど十四回目である。この航海の後半には前半よりよく走れることを望む。
……ハッチはまだ当て木をしたままになっている。
日本人たちは、このあいだ、船が彼をかぶってから、だいぶ経験を身につけてきた。
……麟太郎艦長(注・勝海舟)は幾分気分が良さそうだったが、まだ寝たままである。
彼にスープとプドー酒を少々与えた。提督は部屋に籍っている。
……麟太郎艦長が起きてきた。彼は私と一緒にワシントンに行きたいという。
それはよい計画だと答える。
……一日(三月)、士官や艦長と話し合いがついた。
これまで日本人たちがあまり無能力だったため、私自身常時警戒していることが必要だったし、また私の部下を当直に立てねばならなかった。
向かい風になったので、私は士官たちに上手廻しの技術を教えようと申し出た。
ところが彼らは非常に物ぐさでデッキに出て来ない。いろいろの云いわけをしている。
そこで私は部下全員を集め、私の承諾なしには何もするなといい渡し、船室に入らせた。
そして艦長に、もし士官たちが協力しないなら、もうこの船の面倒をみないと申し送った。
艦長は士官を説き諭し、彼らを私の配下につけたので、私も当直をデッキに送った。
……両方の上檣および中檣のスタンスルは神慮の許す限りつけたままでゆこう。
なぜなら、私はできるだけ早くサンフランシスコに着きたいのだ。万次郎がデッキにいる。
羅針盤の灯が二つとも消えてしまったが、その明りが再びつくまで、万次郎は月の光で実に器用に舵をとった。
……万次郎がいうには、彼がかつて指揮したスクーナーは一八五四年、戸田でロシア人が造ったものだそうだ。
その船は「壹番丸」と呼ばれている。
……正岸、南ファラロンより二百五マイル、私は温度の変化によって起こるクロノメーターの経差の図表の構造を万次郎に説明した。彼にコピーを与える。
……明日着くという予想に日本人たちは大変陽気になっている。
午後六時、北ファラロンから一二五マイルの地点についた。万次郎が私の部下の名前と階級を調べに来た。
……彼は帰国する咸臨丸のために、八人の乗組員を雇いたいという。
……万次郎は、私がいままでに会った人々の中で最も注目にあたいする人物の一人である。
彼はボーデイッチの本を日本語に翻訳した。
それで私はボーデイッチのいったラ・プラースの天体力学についての言葉を想い出した。
彼は冒険精神に富んだ男だ。私は彼の生涯の主な出来事をきき出そう。
彼はたいそう話し好きで、日本の開国について彼は他の誰よりも功労が多かったということは私にも喜ばしいことだ。 |
この最後に引用した言葉こそ、ブルークが日本人に関して記録したなかで、もっとも有意義なものであろう。
さらに、万次郎自身にまつわる疑惑を取り除くものである。
一八五三年から四年にかけて日米間の交渉を成功に導いた蔭には万次郎が非常に大きい影響力を及ぼしたという事実を否定する人もある。
しかし、このブルークの言葉は万次郎の貢献を実に如実に物語っている。
再度の訪日で大手柄をたてたペリー提督は、実のところ、交渉成功の裏に万次郎がいたことを全く知らなかった。
そして遂にこのアメリカ教育を受けた日本青年の努力も貢献も知らされないまま、生涯を閉じたわけなのだが、日本側代表に、アメリカが提示した条件は要求ではなく“東”と“西”の双方を強める協力関係への招待なのだと悟らせたのは、この万次郎なのである。
ブルーク大佐は、三十七日の航海を終えてサンフランシスコに到着したとき、咸臨丸の安着を時の海軍長官アイサック・トウセイに報告した。
そのとき万次郎の半生を書き綴った書類を同封したのだが、これはブルーク大佐の日誌が日米修交通商百年記念行事の一環として、日本で発表されるまで、まるまる百年の間、ワシントンの公式文書綴りの中に埋もれていたことになる。
もっとも、この百年の間に日本はアジアで指導的地位を占めるまでに成長し、一人の漁師の息子が打ち首の危険をおかして帰国するとき夢みた姿よりも、はるかにすばらしい国となっている。
そして幕府を倒し、明治維新を展開して民主主義国家へ日本を引きずり込んだ年少気鋭の志士たちの理想さえ、今の日本を描いてはいなかったろう。
歴史家のG・B・サンソムはいった。「もともと階級制度の上にどっかりと腰を据えていた幕府が、身分の低い一群の武士たちによって倒されたとは、まことに皮肉な話である」
そうだ。万次郎も、その新しい波の中の一人だった。しかも彼は、武士でさえなかった。
最も身分の低い庶民の一人にすぎなかった。
それゆえに、彼は永いあいだ、歴史の評価から不当に抹殺されていたのだ。
しかし、歴史は冷厳に事実を追求する。
これまでの日本歴史を飾っていた英雄は、いずれも武力によって他を征服したか、戦争によって国土の拡大に尽した人たちであった。
だから、このような歴史のなかでは、万次郎が評価される余地はなかった。
しかし、今は違う。ペリーの黒船出現より十二年も前に、その頃としては想像することさえ田難だった逢かな逢かな太平洋の彼方、夷狄の国に渡り、孤愁に堪え、苦難と闘い、新しい知識を身につけ、鎖国の禁を犯して西欧文明の灯を祖国に持ち返った万次郎こそ、真の英雄といわねばならぬ。
また万次郎は、その頃、ハワイやアメリカ本土に十年間も滞留した唯一人の日本人であった。
そして彼の人となりと能力は、彼に接するすべてのアメリカ人を感服させた。
だから万次郎は、たった一人の日本人だが、すべての日本人を代表していたのだ。
いわば、事実上の初代駐米日本大使であり、そして彼は立派にその役目を果たしたのである。 |
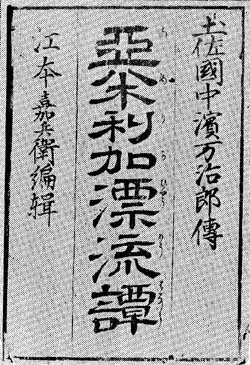
明治になってからは、万次郎の事蹟はかなり喧伝せられ、本になったり歌舞伎芝居になったりも、した。この本は「明治11年11月11日御届」と奥書のある版木刷りの本である
(中浜家所蔵) |
それから一世紀――いまや日本は世界有数の海運国、工業国に成長し、平和な民主主義国家として繁栄している。
いまこそ万次郎は、日本に黎明の光を点じた偉大なる英雄として、新しい日本歴史の中にクローズアップされなければならない。
新しい時代の脚光を浴びて万次郎はよみがえったのだ。万次郎万歳!
top
****************************************
|