|
****************************************
答申・着工 鉄道研究所 高速鉄道の研究 東海道 山陽 東北 上越 北陸 九州 秋田山形 成田
全幹網 JRと新幹線建設
三木忠直 小田急SE車 特攻機桜花 爆撃機銀河 松平精 零戦 新幹線ATC 弾丸列車と新幹線 技術者の軍民転換 HOME
JR発足後の新幹線建設
(新幹線の軌跡と展望 野沢太三 2010年刊 第二章のみ)
国鉄時代は新幹線を含め鉄道建設費は、国鉄の収入でまかなっていました。
JR発足後はそれを国費から出してもらうようになり、以下はその頃に国鉄幹部から参議院議員になった野沢太三氏の、国(運輸省)からその費用を出してもらう苦心談です。
JR発足後25年になりますが、その間に出来たのは盛岡〜青森178キロ、高崎〜長野117キロ、博多〜鹿児島289キロ、合計わずか585キロです。
2005年から新幹線建設を始めた中国は9350キロで、すでに日本の新幹線の全長2630キロの3倍強になっています。
野沢氏は土木屋出の議員ですが、国鉄時代は総裁と話をつければ済んだことが、JR発足後はミニ新幹線(三線軌条式)、スーパー特急、フリーゲージ、リニアと旧国鉄工作局の提案を運輸省は積極的に取り上げて、新幹線建設にブレーキを掛けてきた結果です。
そしてこの功績で当時の石井幸孝工作局長はJR九州の社長、会長に抜擢されたのです。
第一章 国鉄改革と新幹線
第二章 運輸省案の特徴と問題点
1 見直し検討委員会の審議
2 運輸省案の内容
3 泣く泣く呑んだ運輸省案
4 運輸省案の問題点
5 ミニ新幹線をどう利用するか
6 地方の意見
7 途中での変更は困難
8 新幹線の誘致合戦
9 軽井沢へのルート変更
10 駅選定の難しさ
11 二○年かかった「うな井」
第三章 財源について
第四章 新幹線の実績と見通し
第五章 新幹線の必要性と効果
第六章 全国新幹線鉄道整備法
第七章 各線区の展望
第八章 新幹線の地震対策
第九章 犬深度地下利用
第十章 国会で活路を拓く
整備新幹線関連資料(別ページ) |
野沢太三氏経歴(同書より)
昭和8年5月 長野県辰野町に生まれる
昭和31年3月 東京大学工学部土木工学科卒
昭和31年4月 日本国有鉄道入社
昭和56年4月 長野鉄道管理局長技術士(建設部門)
昭和57年12月 本社施設局長工学博士
昭和61年7月 参議院議員(比例区)当選
北海道開発政務次官
平成4年7月 参議院議員(比例区)2期目当選
参議院外務委員長、決算委員長
平成10年7月 参議院議員(比例区)3期目当選
自民党整備新幹線建設促進特別委員長、
弾劾裁判所裁判長、参議院憲法調査会長
平成15年9月 法務大臣就任
平成16年7月 参議院議員任期満了・辞任 |
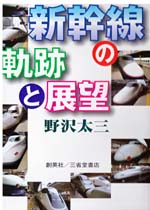 |
1 見直し検討委員会の審議
top
国鉄改革が成功したという見極めがついた段階になり、将来の鉄道を伸ばしていくためには整備新幹線に着手すべきではないかという動きが出てくる。
そこで、政府与党から構成する「見直し検討委員会」が昭和六三年の年初に設置され、整備新幹線の再開や凍結されていた新幹線の解除などの審議が開始されたのである。
各地方の意見を聞きながら、約半年間という時間をかけて行われたこの審議は、建設の費用はどのくらいかかるか、収支採算性がどの程度に見込まれるか、地方の経済にどのような影響を与えるか、それを建設する主体はどこが一番ふさわしいかなど、様々な議論が重ねられた。
年初から始まった審議も夏になり、議論が大詰めとなったところで、運輸省が集約した形で案をまとめることとなったのが、いわゆる「運輸省案」である。
この運輸省案は、当時の値段で整備計画全体が七兆円あったものを二兆円の内容にしたもので、規格を圧縮し、区間を限定して実施するというものであった。
2 運輸省案の内容 top
この運輸省が打ち出した案を簡潔に述べると、まず、東北新幹線は盛岡〜沼宮内間をミニ新幹線にし、沼宮内から八戸まではフルの新幹線、そして、八戸から青森まではミニ新幹線にするというもので、ミニ新幹線とフル新幹線を組み合わせたのが運輸省案であった。
北陸新幹線については、まず、高崎から軽井沢までをフル新幹線とし、軽井沢から長野まではミニ新幹線で、とりあえず長野までで打ち切ることとなった。
また、北陸は北越北緯を使い、在来線で越後湯沢から直江津まで短絡ルートを作ることを前提にした上で、この在来線を経由しながら新幹線の機能を取り入れた「スーパー方式」というものを打ち出した。
このスーパー方式で作ろうとなった二区間が、糸魚川〜魚津間と高岡〜金沢間であった。
ミニ新幹線とは、在来線の線路にもう一本、広軌の線路を付け加えて三線化するという方式。一〇六七ミリという国鉄が普通に使用する在来線のゲージに、一四三五ミリという新幹線のゲージの線路をもう一本付け加えるというものである。
したがって、路盤その他は、全て在来線の路盤を使うことができることになる。
路盤、橋梁、トンネル、停車場といった構造物すべてをそのままにし、在来線の規格で行われるので、広軌線路を一本付け加えるだけの工事費で済む。
一キロあたり五億円程度ででき、コストが安いというのがこのミニ新幹線の一番の眼目である。
しかし、ミニ新幹線には利点が多いものの、踏切が残るといった大きな問題もあった。
一方、スーパー方式は、路盤そのものは全く新幹線と同じ物を作り、原則として立体交差とする方式。
曲線半径も四〇〇〇メートルなど、勾配もできるだけ線く作ることで、新幹線と同じ路盤を作る。
その上で、軌道のゲージや幅だけを在来線と同じ一〇六七ミリを敷くようにするため、在来線からその新幹線ルートに直接乗り入れができるようになる。
また、列車は在来線の列車を使用し、速度は一六○キロから二〇〇キロ程度までをいちおう想定するというのがスーパー方式の特徴である。そして、北陸はこのスーパー方式で、糸魚川〜魚津間と高岡〜金沢間の二区間だけを着工することが打ち出されたのである。
九州については、全線三〇〇キロほどある博多から西鹿児島間のうちの南半分、約一二○キロの八代〜西鹿児島間を尻尾のほうからスーパー方式で工事を始め、非常に曲線の多いことで知られる鹿児島本線の南半分の時間を短縮しようという案が打ち出されたのである。
この三線五区間だけをミニ新幹線とスーパー方式という方法で行うことにより、その区間の時間短縮効果も含めて、新幹線が「効果的に安い費用でその目的を達成できるのではないか」という印象を与えるのが、運輸省案の狙いであったのである。
3 泣く泣く呑んだ運輸省案 top
こうした運輸省案は、新幹線をすべてフル規格で作っていくという私どもがイメージしていた計画とはかなり異なり、予定していなかったミニ新幹線とかスーパー方式を盛り込んだ整備計画案であり、これには大変なショックを受けたものである。
まるで、「うな丼を注文して二〇年も待っていたら、なぜかあなご丼とどじょう汁が出てきた」そんな印象であった。
うなぎに近いあなごのどんぶりということで、これはスーパー方式の比喩だが、ミニ新幹線のほうは全くイメージが違うので、こちらは差し詰めどじょう汁といったところになる。
無論、このような運輸省案を認めるわけにはいかないし、かなりの議論をしたのだが、この段階で会議をパンクさせてしまえば、また初めから議論のやり直しになり、さらに二年も三年も時間がかかってしまう。
そこで、提案された中でフル新幹線の部分、高崎〜軽井沢と沼宮内〜八戸の二区間に関しては、手を付けてもいいだろうということで、着工に同意することにしたのである。
また、スーパー方式に関しては、軌道工事は路盤ができてから本格的な着工となるので、その時に見直しをしてフル新幹線に戻すというチャンスがある。
そこで、それを前提にして、スーパー方式の部分も手を付けることにしたのである。
したがって、北陸の二区間ならびに九州の南半分についても、着工することには同意したのだった。
ただし、その時の見直しについては、政府も誠意をもって対応して下さいといった注文はしたのだが、とりあえず運輸省案を泣く泣く呑んだというのが実情であった。
もちろん、この運輸省案には多くの問題があり、早晩見直しをせざるを得ないということを、私どもは当初から覚悟の上で取り組んだのである。
4 運輸省案の問題点 top
こうした論議を行っていた当時、既に「新幹線整備法」ができていたのだが、その整備法の中に、新幹線鉄道とは「時速二〇〇キロ以上で走行できる鉄道」という規定がある。
ミニ新幹線は一三〇キロでしか走れないので、当然、「新幹線とは違うではないか」という議論が出る。
また、スーパー方式についても、一六○キロないし二〇〇キロと言ってはいるか、実は、レールの間隔が一四三五ミリの標準軌間より狭い一〇六七ミリの「狭軌」については、当時の技術力では一六〇キロ走行ですら実現していなかった。運輸省案にはまず、こういう問題点があったのである。
私自身が、湖西線という新しい在来線で再三実験を繰り返しだのだが、一六〇キロに近くなると片方の車輪が浮き上がってしまう『輪重抜け』と称する現象がしばしば発生するということが判っていた。
当時、湖西線では一六〇キロ運転は無理だということで、一三〇キロ程度で留めたという経緯もあったのである。
平成一七年四月に尼崎で脱線事故が起きてしまったが、あのケースは、半径三〇〇メートル、速度制限七〇キロのところへ、一一六キロという猛スピードで列車が突っ込んで行ったため、『輪重抜け』が起きてしまったのだ。
そして、片方の車輪が浮いてしまっただけでなく、そのまま脱線してマンションに飛び込んでしまったのが、あの尼崎の脱線事故であった。
将来は可能となるかもしれないが、在来線では一六〇キロというスピード、いわんや二〇〇キロというスピードは、運輸省案を決めた昭和六三年の段階ではまだ技術的には実現できていなかったのである。
運輸省案は、まず、法律的に問題があり、スピードの面でも、ミニ新幹線で一三〇キロ、スーパー方式でも二六○キロ程度の車速が限界という制限があった。
こうした点を私も指摘し、速くて安全で確実だという新幹線の特徴、新幹線としての時間短縮効果という速さが犠牲にされてしまうと主張したのであった。
例えば東北の場合、盛岡から青森に行くとすると、盛岡を出て沼宮内までの約三〇キロを時速一三〇キロのミニ新幹線で行き、そこから沼宮内から八戸までは時速二六〇キロのフル新幹線で走った後に、さらに八戸から青森までミニ新幹線でまたゆっくり行ったのでは、青森まで行くのに五時間近くかかってしまう。
新幹線をさらに北海道へ延ばしていこうと計画している時に、こんな状況では飛行機に勝てないし、北海道新幹線は絶対にあり得ないということが結果的に予測できてしまう。
このようにミニ新幹線にはスピードの面で非常に問題があり、とても了承できるものではなかった。
5 ミニ新幹線をどう利用するか top
このようにスピードの面で非常に問題があるミニ新幹線ではあったが、地域によっては効果的なケースもあった。
当時、福島から山形までの間をミニ新幹線でやることになっており、既に実現しつつあった。
東京始発で考えて山形までミニ新幹線で行く場合、福島までが一時間余で、そこから在来線でも二時間半あれば山形まで行ける。
山形空港はさらに奥にあるため、飛行機を使うよりも速く、ミニ新幹線は効果的ということで実現したのである。
この山形のケースのように、『枝』の部分に効果的にミニ新幹線を使うことは構わないのだが、大事な『幹』の部分、幹線にミニ新幹線を使うことは絶対に駄目だと、この段階から指摘した上で同意し、運輸省案を了承したのである。
その後、ミニ新幹線には効果的に利用できる良い点もあるということになり、山形から新庄まで、さらに延ばしたのである。また、盛岡から横に枝分れしていく秋田にも、ミニ新幹線が採用されることとなった。
今では秋田「こまち」という名前の愛称になっているが、「こまち」は「はやて」と一緒に走って盛岡で分かれ、半分は秋田、半分は八戸へ行く。
山形へ行く時には、福島までは一緒に「はやて」と走り、ミニ新幹線は「つばさ」という列車がこの在来線に入っている。
「はやて」はそのまま仙台や盛岡、ハ戸まで行くのだが、このように、山形とか秋田ならば、ミニ新幹線は効果的に利用できるのだ。
要するに、到達時間がトータルとして三時間前後、せめて四時間以内であれば、飛行場の待ち時間やアクセスを含めたトータルの時間にほぼ匹敵し、競争力がある。こういう線区がミニ新幹線の効果的な区間となる。
それを幹線でやろうとしているところに、運輸省案の無理があったのである。
当時の石原慎太郎運輸大臣は、幹線までミニ新幹線を使うという運輸省案を「ドジョウ汁」と称しながら、「結構たんぱく質があるよ」などと冗談を言っていたが、結局、全て見直され、運輸省の幹線にミニ新幹線を使うという案はなくなったのである。
一方のスーーパー方式も、一六○キロまで走れるとはいえ、それでもやはり時間が相当かかる。
北陸で考えた場合、富山とか小松から飛んでいる飛行機から鉄道に乗客を奪えるかというと、そう筒単にはいかない。
そこで、政府与党の『見直し検討委員会』で、スーパー方式もフル規格に見直すことになったのである。
6 地方の意見 top
運輸省の案には、法的問題、スピードの制限に加え、三つ目の問題として、特殊分岐器の構造が難しいという『軌道構造の問題』があった。
二本でも線路が分岐しているところは、相当細かな部品を組み合わせて、線路が右左分かれるようにする「分岐器」というものがある。
それにもう一本レールがあると三線分岐器となり、非常に構造が複雑になる。
もちろん、三線分岐器も作っていて実績もあるが、これから作るところは、東北、北海道、北陸と雪国が多い。
「雪国では三線分岐できない」と断言して、「それでは止めよう」と言われても困るので、「保守管理上、安心できない」と指摘するに留め、「何とか工夫しよう」ということになった。
当時は伏せていたのだが、実際は、こうした軌道構造の複雑さがあり、安全上も保守管理上も非常に問題があったのである。
もう一点、地方がとにかく納得しないという問題もあった。
「東海、山陽、東北、上越といった新幹線だけが時速二〇〇キロ、三〇〇キロで走行し、なぜこちらは一二○キロ、一六〇キロなんだ」といった不満の声があった。
日本中を一つの同じレベルの社会資本で整備し、地域格差を是正する。
東京や大阪といった主要都市に対して、高速道路、新幹線、飛行場という三つの機関を適切に組み合わせた形で連絡し、日本中どこでも格差がなく、住み心地は変わらないようにする。
こうした理念を実現するのに、最も有力な手段であるはずの新幹線に初めから差をつけてしまうということに納得できない地方の意見が相当強かった。
こうした地方の声が、四つ目の問題点であり、また、運輸省案を見直す原動力にもなっていたのである。
7 途中での変更は困難 top
五つ目は、一度ミニ新幹線なりスーパー方式なりで開業してしまうと、それを将来フル規格に変更しようとしても容易にはできないという点。
営業をしながら工事をするということは安全対策上も非常に難しく、規格を変更しようとすると一年とか二年とか休業しないと工事ができない。また、そんな事態になっては大混乱が起きてしまう。
こうした理由で結局、このミニ新幹線ならびにスーパー方式は、いずれ見直すという前提で、できるところから『一部』手をつけることにしたのである。
一番先に着工したのが高崎〜軽井沢間であったが、これは、将来、長野に冬季オリンピックを持ってこようという見通しがあり、至急着工する必要があったからである。
当面の輸送量も一番多く、収支採算性も良いので、長野から始めることとなったのだが、その起工式の時長野の塚田佐市長が、「めでたさも 中ぐらいなり おらが春」という一茶の句を引用し、なんとかフル規格に直してくださいという皮肉を込めた陳情があった。
そんな析、「鍬入れ式」になったのが平成元年で、いよいよソルトレークなどの世界の各都市と競争し、長野にオリンピックを誘致するために、イギリスのバーミンガムに決選投票に行くことになったのが平成三年。
だが、オリンピック誘致には、やはりミニ新幹線では時問的にも量的にも、とてもお客を運びきれないし、イメージ的にも良くない。
東京から一時間半で行け、長野のホテルが足りないなら東京のホテルに泊まっても通え、プレスも応援団も大丈夫だと説得力を持たせるには、どうしてもフル規格の新幹線でなくてはバーミンガムに行っても勝てない。
そんな相談をして、長野をまずミニからフルに直すように働きかけたのであった。
その結果平成二年一二月の政府与党申し合せで長野までのフル規格が決定した。
8 新幹線の誘致合戦 top
信越線の軽井沢の先に小諸という所があり、ミニ新幹線ならば在来線にくっつけるので小諸を通るのだが、フル新幹線だと別線で通らなくなる。
小諸の人たちは「ミニ新幹線になるんだ」とすごく喜んで、町中挙げてミニ新幹線の誘致運動をしたのだが、一方、佐久市が南にあり、佐久の皆さんは、ミニ新幹線になってしまったのでは佐久に来なくなってしまうと悲しがる。
こういう状況下で、小諸と佐久の誘致合戦が始まってしまった。
小諸の皆さんに、それは『見せかけの案』そのショーウィンドウにはミニ新幹線というメニューが並んでいるけど、実際は食べられない。だから運動しても駄目ですよと言ったのだが、町中挙げて運動をした。
新聞に大きな全面広告を打ち出し、『ミニ新幹線歓迎』と表明もした。
多額の広告費を使ったのだろうが、結局、オリンピック招致のためにもフル新幹線にしようとなり、ミニ新幹線は夢と消えたのである。
それで、現在、軽井沢の次は佐久平で、軽井沢、佐久平、上田、長野、飯山という並びになったのだが、これにも随分と色んな苦労があった。
フル新幹線にすることは決まったが、できるだけ小諸の皆さんにも利用しやすいようにと、佐久市の限界ぎりぎりの所まで北のほうへ寄せることにしたのである。
ちょうどその辺りは農業振興の地域指定があったため、全くただの田んぼで、そこに新幹線を通したものだから、結果的に都市計画が非常にうまくいった。ただ、駅名を付ける際は、もう一苦労あった。
これまで「那須塩原」とか「三条燕」とか、両方の名前を取って付けるという例が多くあったこともあり、小諸の皆さんが「小諸も近いのだから、『小諸佐久』もしくは『佐久小諸』というような名前にしてくれないか」と嘆願するのだが、佐久の人たちにとっては、あくまで佐久市にあるのだからおもしろくない。
考えたあげく、「平」と付ければ、その辺一帯であるとなるので、「佐久平」という名を付けようと提案があり、結局、県知事が乗り出し、両方の町の顔を立てて「佐久平」という名前を付けたという経緯があったのである。
9 軽井沢へのルート変更 top
また、当初のルート案は、高崎を出て群馬県の松井田という町を通り、長野県の佐久にある中込という地区を経て、それから上田に入るというものであった。
ところが、ちょうど私が長野の鉄道管理局長をしている頃、時の総裁である大蔵省出身の高木文雄さんが、「君、年に八○○万人ものお客様が来る軽井沢を通らない新幹線というのは、いかがなものだね。なんとかならんかね」と、こういう話が出て、軽井沢に新幹線を通す方向になるのである。
営業の関係者は、「これはもう、是非そういう風にできるなら、そうしてほしい」と早速この話に飛びついたのだが、建設施設を担当している土木グループとか、電気を供給したり信号を扱ったりする電気のグループ、あるいは、車の所管をしている工作グループなどは、軽井沢に新幹線を通すことについて、どのような影響があるかなどを改めて議論したのである。
私自身は建設施設の技術者であったが、色々と勉強してみると、どうも難しいことが判ってきたのである。
当初の新幹線は、勾配が大体一二パーミルとか一五パーミルぐらいで、一〇〇〇メートル行って一五メートル上がるような勾配の計画を立てていた。だが、その勾配で軽井沢に寄るとなると、ぐるぐる回りの「たこ坊主」にするとか、ループトンネルを掘って上がって行かなければ難しく、軽井沢まで登り切らない。
横川から今の線路まで古い線路は六六・七パーミルという一五分の一の急勾配で上がっていたわけだが、それを一五パーミルぐらいの線の勾配で行くと、ぐるぐる何周も回らなければならなくなるのだが、それでは新幹線の価値がなくなってしまう。
そこで、一〇〇〇メートル行って三〇メートル上がるという三〇パーミルの案なら軽井沢に寄れるのだが、今度は、その三〇パーミルを登り降りできる車が作れるかどうかという点が問題となった。
電気屋さんは「どちらでもやれます」ということだったが、工作屋さんは「そんな新幹線は作るのは無理」と主張する。東海道も山陽、東北、上越もみんな一五パーミル以下でやっているのだから、そうでないとブレーキがもたない、従来のブレーキでこの下り勾配でブレーキをかけると、その熱でブレーキの抵抗器が真っ赤になって焼けただれるくらい大きな力がいる」というのだ。
新幹線のブレーキには抵抗器があり、出てくる電力を抵抗器で吸収する仕組みとなっているが、それが焼けただれて落ちてしまうぐらい大変であるという。
結局、「できません」という返事が高木総裁のところに行ったのだが、これに対して高木総裁は、「そうか、それは仕方がない。残念だな。だが、フランスのTGVという車は五〇パーミルを上がったり下ったりできるそうじゃないか。貿易摩擦の解消のためにも非常に役に立つだろうから、そのTGVを買ってこい」と言い出したのである。
これにはさすがに工作屋さんも慌て、「これは日本の恥だ」「急勾配を上り下りできる電車を作ろう」となり、開発したのが、今走っている「あさま」である。
10 駅選定の難しさ top
この「あさま」については、上りは全部モーターを付ければどんどん登れるからいいが、下りではブレーキの加熱が問題となるので一六○キロで制限しようと、速度制限を設けることになったのである。実際は、その後の技術の進歩もあり、現在は二一〇キロまでスピードを上げて下れることになったが、そういう技術的な条件などもあり、今も長野に行く新幹線は、上りと下りで一分時間が違うのである。
常識とは逆となるが、東京から行く下り列車が軽井沢の坂を上るのだが、これは二六〇キロで走れるが、上りの長野から東京へ来る列車は、軽井沢から高崎にかけて二一○キロに速度制限しているのである。
このような経緯で、軽井沢に駅ができることになり、現在の軽井沢は、一時間そこそこで東京から来られるようにもなり、非常に便利になった。
近年は、夏場は軽井沢に暮らし、東京に通うという人も既に出てきている。
だが、ここで問題になったのは、山の中を迂回するルートになってしまったため、松井田という町に寄れなくなった点。
群馬県には駅が一つもできないということになり、そのかわり長野県に駅が一つ増えたのだが、群馬県の人が非常に怒ったのである。「群馬県は、福田さん、中曽根さん、そして小渕さんと、三人も総理大臣を輩出していながら、何をしているんだ!」ということで、県民からずいぶん突き上げをくらったのである。
色々と困った挙げ句、山の中でも一つ駅を作るかということでできたのが、現在の「安中榛名」という駅である。
周りに民家も何もない、山と森しかない所に駅を作ったのだ。
現在、周辺は整備・開発され、新しい団地もでき、立派な町づくりも始まっているが、作った当初は、本当に山の中にあったのである。
大野伴睦さんが岐阜羽島に田んぼの中に駅を作って随分と批判されたこともあったが、あそこも今は立派な町になっている。 最初は田んぼの中でも、それと同じことだから「まあやってみようや」ということになったのである。
11 二○年かかった「うな丼」 top
結局、長野オリンピックのお陰で長野までは行けたが、そこから先はまだ全く雲の中であった。
北陸は北陸でほくほく線回りのスーパー特急でいくことになっていたから、長野から直江津のほうへ抜けるには、飯山トンネルという二二キロもある大トンネルを掘らなくてはならない。
これはお金もかかるし、馬鹿馬鹿しいというのが、節約論者の言い分であった。
スーパー方式はそういう事情でそのままになっていたのだが、長野から先へ延ばすという話が徐々に決まっていく流れの中で、長野までフル新幹線で来ているのだから、当然その先もフルでいいのではないかという方向となる。
まずは上越までで、二回目の見直しが富山までとなり、そして今回、二〇〇五年の暮れに金沢までフルで延ばしていくとなって、結局、スーパー方式は消えたのであった。
「あなご丼は餌をしっかりくれたら、うな丼になってくれた」のである。
だが、九州は少しまた違った事情があった。九州新幹線の八代〜西鹿児島間は、それまでスーパー方式で作っていたのだが、ちょうど四〜五年前にフリーゲージトレインというのが出てきたために状況が変わったのである。
このフリーゲージというのは、軌間可変電車とも言うのだが、要するに在来線の一〇六七ミリの線路と新幹線とを自由に出入りできる車で、ゲージ変換点という二〇メートル程の装置を通り抜けることによって、その車輪が広がったり狭まったりする仕組みとなっているのである。
南の半分をフル規格でやっても、このフリーゲージを導入すれば十分いけるという含みがあったため、フリーゲージを入れる前提で工事を速めたのだ。
だが、実際はまだ間発中なので間に合わない。そこで、八代の駅で新幹線と在来線を同一ホームの乗り換えで結ぶという方策を考えたのである。
同一ホームの乗り換えというのは、新幹線が着くと、それを受けて運ぶ在来線の特急が待っているやり方で、時刻表上では三分で乗り換えることになっているが、同じホームなので一分半もあれば乗り換えられる。
買った席は次の列車にも確実に用意されていて、一枚の切符で二つの列車を乗り継げるようにしたので、荷物を持って走らなくて済むのだ。
それまで鹿児島から博多まで四時間かかっていたのが、二時間ちょっとで行けるようになったため、飛行機や高速道路のお客がどっと来て利用者は、昔の二倍半となった。
そういうことで、鹿児島も結局フル規格になったのである。
“どじょう”と“あなご”を“うなぎ”に育てるために二〇年近くかかったが、整備新幹線一五〇〇キロは、当初の運輸省案を卒業し、ようやく全てフル規格で作れる方向になったのである。
top
****************************************
|