|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18
11 玄奘(げんそう)の西遊
1 ハルシャ王の盛典
top
およそ、どのくらいの人数があつまったのであろうか。
王とよばれる人だけでも、十八ヵ国から参じてきていた。
仏教の僧侶は三千余人、バラモン教やジャイナ教の学者が二千人、いずれも当代において一流の人びとであった。
みな従者をつれているから、おびただしい数にのぽったのである。
それらの人びとが、隊列をくんで進むのは壮観であった。
ときに西暦の六四一年、唐の年号でいえば、太宗の貞観(じょうがん)十五年である、ところは北インド。
おりしもインドの大部分は、ハルシャ・ヴァルダーナ王によって統一されていた。
インドでは三世紀になると北のクシャーン王朝、南のサータバーハナ(アーンドラ)王朝が、ともにおとろえ、分裂の状態におちいった。
それを統一したのが、グプタ王朝である。
四世紀から五世紀の後半にかけておよそ百五十年、このグプタ王朝のもとに、インドの古典文化は花をひらかせた。
公用語がサンスクリットに統一されたのも、この時代である。
ヒンズー教が全土にゆきわたり、国民宗教の地位を占めるようになったのも、この時代である。
しかしグプタ朝がおとろえてからのち、またもインドは分裂の状態となった。
それを七世紀のはじめ、ハルシャ王があらわれるにおよんで統一を実現した。
南インドを除き、ガンジス流域からパンジャブ地方にいたる一帯が、その支配下におさめられた。
都はカニャークブジャ(カナウジ)におかれた。中国では「曲女城」と訳された。
ハルシャ王は、戦争に強かったばかりではない。文化の興隆にも、すこぶる熱心であった。
それだけに、チーナの国から、全インドの僧もかなわないほどの学僧がきていると聞くや、礼をつくしてその僧をまねいた。さらに全インドの仏僧や学者たち、配下の国王たちにも、参集を命じたのであった。
満身をかざりたてた巨象の上に、目もまばゆい厨子(ずし)がのっている。
そのなかには黄金の仏像が安置されている。
ハルシャ王みずからは、仏を守護する帝釈天(たいしゃくてん)の姿になって、仏像の右側に坐した。クマーラの国王が梵天(ぼんてん)の姿になって、左側に侍した。
そしてチーナの僧は、大象にのってこれにつづいた。
そのあとには、さらに三百頭の象がしたがっている。諸国の王や大臣や、高僧たちが分乗し、二列になって進んだ。
ゆくさきには会場として、草ぶきの仮殿が二棟つくられてある。それぞれ千人あまりも収容できるものであった。 |
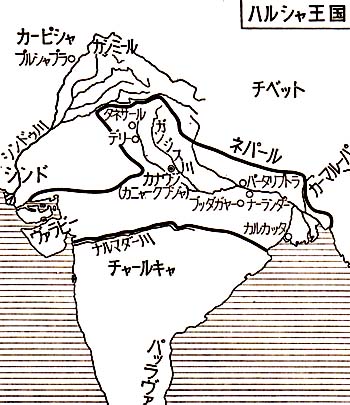 |
仏に供物(くもつ)をささげ、人びとに食事と布施(ふせ)をほどこしおわると、ハルシャ王は中央のきらびやかな壇上に、チーナの僧をまねいた。
その日の論主としては、なにゆえに大乗の仏教を正しいと信じるかをチーナの僧に書かせ、会場の人に読みきかせようというのである。
外にあふれた人びとには、写しを掲示した。
このチーナの僧こそ、三蔵法師とよばれる玄奘(げんじょう)であった。ときに三十九歳。
このときのことは、のちに弟子たちが編集した『大唐大慈恩寺 三蔵法師伝』にくわしく見えている。
そこでは、ハルシャ・バルダーナのことを「戒日王」、チーナのことを「支那」と書いている。
この「支那」という字は、はじめ仏典でもちいられたものであった。
さて玄奘は、大乗を論じて最後に説いた。
「もし、この文に一字でも不合理な点があり、それを論破する者があれば、私の首を断っておわびいたしましょう」。
その日が暮れても、だれひとりとして異論をはさむ者はいない。このようにして五日たった。
小乗や、ほかの宗教を奉じる者のなかには、みごとな玄奘の論破をうらみ、暗殺をくわだてるものがあった。
よってハルシャ王は、玄奘法師に傷をあたえた者は、ただちに首を斬り、法師をののしった者は舌を切ると宣言した。
不心得の者は姿をひそめ、十八日の会期はぶじに終わった。
最後まで、ひとりとして玄奘に論をいどんだ者はなかった。
2 玄奘のおいたち top
玄奘は俗名を陳褘(ちんい)といい、隋の文帝の仁寿二年(六〇二)、洛陽の東方に生まれた。
曾祖父も、祖父も、北朝の大官であった。父は儒学の研究に専念し、おりから隋末の乱世にあたっていたので、官につくことを求められても応じなかった。
玄奘は、その四男である。
小さいときから秀才のほまれがたかく、見世物がかかっても、見にいったことがない。
そのうえ孝行で、まじめという、非のうちどころのない少年であった。
二番目の兄は長捷(ちょうしょう)といい、さきに出家して洛陽の浄土寺にいた。
そこで弟の玄奘も僧侶にしようと思い、じぶんの寺につれてきて、経典を習わせた。
ちょうどそのとき、隋の煬帝(ようだい)から詔勅がでて、洛陽で十四人に僧侶となる許可があたえられることになった。
僧侶となると、税役の免除などいろいろ恩典がある。
そこで度牒(どちょう)という正式の許可書がないと、僧侶になれなかったのである。
洛陽には、すぐれた候補者が数百人もいる。玄奘は幼少のため出願できず、役所の門のそばに立っていた。
この試験の最高責任官の鄭善果(ていぜんか)は、人を見る眼があることで有名であった。
それが玄奘をみとめて、姓名をたずね、度牒の希望を問うた。
玄奘は、僧侶になりたくても、応募の資格がないと答えた。さらに出家の意図をたずねた。
玄奘は答えた、「遠くは如来(にょらい)の遺法(いほう)をつぎ、近くはその遺法を輝かしたいのです」。
鄭善果は、そのかしこそうな風貌(ふうぼう)を見て、特別に度牒をあたえた。
こうして出家してから、玄奘は兄の長捷法師とおなじ寺にいて、『涅槃(ねはん)経』や『摂大乗論(しょうだいじょうろん)』を熱心に学んだ。
いちど講義を聞けば、ほとんど理解し、もういちど復習すれば、疑義がまったくなくなるというありさまである。
みな、おどろいた。そこで講義をさせてみると、完全に師の教えを会得している。
いよいよ評判となった。それが十三歳のときのことであった。
やがて隋はたおれ、唐の天下となる。長安には、ぞくぞく民衆があつまった。
そこで玄奘も、兄といっしょに長安へおもむく。しかし、まだ唐朝も建国したばかりである
。長安でも戦争の話ばかりで、学問どころではない。仏教の講席もなかった。
ただ聞くところによると、蜀(しょく=四川省)には仏法にくわしい人がたくさんいるとのことであった。
そこで玄奘は、ふたたび兄といっしょに、けわしい桟道(さんどう)をとおって蜀の成都(せいと)にむかった。
成都では、すでに多くの高僧があつまり、講席もひらかれていた。
玄奘は寸暇を惜しんで学び、二〜三年で仏典の諸部に精通するようになった。
天下の僧侶たちがあつまった成都でも、もはや玄奘の才能にかなうものはなく、その名声は長江下流の方面まで伝わっていった。
こうして蜀(しょく)で学びうることは、すっかり学びつくした玄奘は、南方の各地をめぐったうえ、ふたたび都の長安へおもむく。
ここでも玄奘の右に出る者はなかった。
そのころ中国において究(きわ)められていた奥義(おうぎ)は、ことごとく知りつくしてしまったといえよう。
この上にも研究をふかめようとすれば、仏教の発祥の地であるインドに行って学ぶよりほかはない。
よってインドへおもむきたいと願いでたが、国外への旅行は禁止されていた。
3 苦しい求法の旅 top
ついに玄奘は、国法をやぶってインドへ旅だつ。ときに貞観元年(六二九)八月、二十六歳であった。
小説として有名な『西遊記(さいゆうき)』は、この旅行をテーマとしたものである。
主人公の三蔵法師は、孫悟空(そんごくう)をはじめ、猪八戒(ちょはっかい)や沙悟浄(しゃごじょう)とともに、太宗より白馬をたまわって出かけることになっている。
しかし、ほんとうの玄奘は、国禁をおかしての、ひそかな旅立ちであった。
さて長安を出発した玄奘は、まっすぐ西へむかう。
涼州(甘粛省武威)までゆき、一ヵ月とどまって仏典の講義をした。
ここまでくると、目の色や服装のかわった胡(こ)人(イラン系の人)も往来している。
ここの長官の都督は、外国への往来の取りしまりも重要な任務のひとつであるから、インドへ脱出しようとする僧侶が通るのでは、だまっておれない。 |
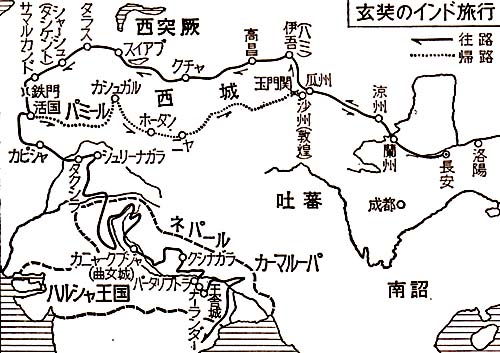
往きと帰りで行路が異なるのに注意
|
しかしここで声望のあった慧威(えい)法師のはからいで、なんとか脱出することができた。
このころ、この方面では霜害で飢饉がおこり、民衆に疎開をゆるしていたので、それに乗ずることのできたのは、さいわいであった。
ついで国境の町、爪(か)州(甘粛省安西)についた。
ここに一ヵ月ほど滞在しているうちに、涼州から、玄奘という僧が西方へ脱出しようとしているので逮捕せよ、という通牒がきてしまった。
しかし係りのものが仏教の信者であった。
その通牒を玄奘の前で破りすて、早く出発しなさいといってくれた。
こうして、あやうく脱出することができた。
玉門関(ぎょくもんかん)も迂回して通りぬけた。
これから西北へ百里(およそ四五キロ)ごとに五つの烽(ほう=敵の来襲を見張る所)がある。
第一の烽の近くまでゆくと、一本の矢が飛んできた。つづいて、もう一本。
玄奘は「都からきた僧だ。射ないでくれ」と大声をあげた。
指揮官も玄奘を見て畏敬の念をおこし、第四烽へ紹介までしてくれた。
第五烽はうまく避けて通り、ついにはじめて八百余里にわたる大砂漠へはいった。空には飛ぶ鳥もなく、地上を走る獣もない。もちろん水も草もない。
玄奘は、ひたすら観音菩薩(ぼさつ)と般若心経(はんにゃしんきょう)を心に念じつつ、進んでいった。およそ七日ほど歩いて、伊吾(いご=ハミ)についた。
ひとりの老僧が帯もつけず、はだしで飛びだして、「今日、ふたたび故国の人におあいできるとは」といって泣きだした。
玄奘も思わずもらい泣きをする。
ここの近辺にいた異国人の僧や、伊吾の王も玄奘のもとにきて、供養した。
ゆく先にある高昌(こうしょう=トルハン)国の国王麹文泰(きくぶんたい)は、玄奘のことを聞き、伊吾王に命じて、玄奘を高昌におくらせようとした。 |

西域の絵画に描かれた玄奘(げんそう)
|
はじめ玄奘は高昌国を通るつもりはなく、よって固辞したがゆるされない。
ついに伊吾を出て七日目の朝、高昌(トルハン)についた。
すでに長安を出てから半年ちかくを経過している。
高昌王は宮殿を出て玄奘をむかえ、厚くもてなした。
十日あまりたって、玄奘がでかけようとすると、王は懇請した。
この国にはよい導師がいないから、ぜひとどまって、民衆をみちびいていただきたい、というのである。
辞退すると、ついに怒りだした。玄奘は三日間も断食し、ようやく王を断念させた。
ただ帰路には、かならず立ちより、三年とどまって供養をうけることを約束した。
王は、これからの道中の法服を三十着、防寒具、黄金百両、銀銭三万、そのほか絹たくさんと馬三十頭、人夫二十五人をおくって、往復二十年の経費にあてた。
ここからさきは、西突厥(とっけつ)の勢力範囲である。
高昌王は、西突厥のハガンの妹を妻としていたので、玄奘をハガンのところまで送らせ、沿道二十四ヵ国の王にも依頼状を書いた。
出発の日、王は大臣や高僧らと城のはずれまで見おくった。
わかれにのぞんでは玄奘をだいて泣き、さらに数十里もついてきて、やっと王宮にひきかえすありさまであった。
高昌国から九百里ほど行って、アグユ国についた。
そのてまえで盗賊におそわれ、物をうばわれた。アグェ国から九百里で、クチャ(亀茲)についた。
ここは仏典の漢訳で名だかい鳩摩羅什(くまらじゅう=クマーラ・ジーバ)の故郷である。
羅什訳の『法華経(ほけきょう)』や『阿弥陀(あみだ)経』は、いまでも読まれている。
ここでも王をはじめ、群臣や近辺の僧、数千の歓迎をうけた。
さきの山が雪で通れないので、六十日あまり滞在した。クチャの王からは人夫やラクダ、馬などを支給されて出発した。
六百里ほど行って、バルカ国に一泊し、さらに西北へ三百里、砂漠をすぎて、パミール高原の北隅に達する。
山はけわしく天にそびえ、万年雪におおわれている。道は難渋をきわめた。
七日の山旅で、凍死者は十三〜四人を数え、牛馬も多くたおれた。
山を越して周囲一千四〜五百里の湖に出た。いまのイシク・クルである。
風がないのに、数丈の波がたっていた。湖岸を西北に五百里ほど進んで、スイアブ(砕葉)城にいたった。
ここで西突厥のハガン(君主のこと)に会った。
ハガンは緑色の綾絹(あやぎぬ)の上衣を着て頭髪は一丈ばかり、練り絹で額をつつんで、うしろに垂らしていた。
ハガンをとりまく高官二百余人も錦の上衣を着て、髪をあんでいる。
軍兵たちは皮衣や毛織物を着て、矛(ほこ)や弓をもち、ラクダや馬にのり、その数はかぞえきれず、威容さかんなものであった。
ハガンも玄奘を歓待した。音楽を奏して大宴会をひらき、羊や牛の肉が山のように積まれたが、とくに玄奘には精進料理をつくってすすめた。
またハガンは玄奘に説法を請い、歓喜して教えをうけた。
ここに数日とどまり、惜しまれつつふたたびインドヘとむかう。
ハガンは通訳をつけて、インドの西北境のカピシャ国まで送らせてくれた。
ついでダラス城をすぎた。ここは百二十年後に、唐軍がイスラム軍とたたかって大敗したところである。そこから西南にむかい、シャーシュ国(タシケント)をへて、サマルカンドについた。
その国王はペルシアのゾロアスター教(後述)を奉じていたが、西突厥にしたがっていたので、ハガンの手紙をしめすと、玄奘の法話をきき、態度はかわった。
サマルカンドから鉄門の険をすぎ、クンズス(活国)に至った。もはや、いまのアフガニスタンである。
ここからバクトラをへて、インドにはいることになった。
バクトラは百の仏寺、三千余の僧がいる小乗仏教の国であった。
一ヵ月とどまってから出発し、ヒンズクシュ山脈をこえ、バーに着いた。
深山のなかで、寒さもきびしいが、仏教はさかんであった。
ここで十五日ほどすごし、ついでカピシャ国をへて東に六百里、黒嶺をこえて、ついに北インドにはいった。
貞観二年(六二八)おわりごろのことである。
これから、いよいよブッダの聖跡を巡拝しながら、目的地たる大本山のナーランダーに到着したが、それまでに長安を出発してから、満三年の歳月が流れていた。
ナーランダーでは、りっぱな僧房と最上の食事をあたえられ、雑役は免除された。
外出には象に乗ることをゆるされ、最高の待遇をうけたのであった。
ここはインドでもっとも権威のある大学で、大乗仏教研究の中心であったが、ほかの学問の権威者もあつまって数千の学徒がおり、すでに七百年の歴史があった。
玄奘は瑜伽(ゆか)論をはじめとして、さまざまの仏典をおさめ、中国では満たされなかった疑問もつぎつぎと氷解した。
その知識がますます精妙になったことは、いうまでもない。 |

ナーランダー遺跡
|
4 帰国して訳経 top
玄奘が帰国の途についたのは、貞観十五年(六四一)、四十歳のときのことであった。
ハルシャ王からは南方の海路をとるようにすすめられたが、高昌国王との約束があるので、ふたたび北方の陸路をとった。
ハルシャ王、タマーラ王からのたくさんの贈りものもすべて辞退し、経典と仏像だけをもって出発した。
だいたい往路と同じコースをたどり、各地でさかんな歓迎をうける。
クンズスからは、往路とちがって南路をとることになった。
それは、帰路に三年とどまることを約束した高昌国が貞観十四年(六四〇)に唐にほろぽされ、王は急死したことが、ここまできてわかったからである。
クンズスを発したのは、貞観十七年(六四三)、玄奘は四十二歳であった。
パミールをこえ、カバンタ国に二十日ほど滞在して出発したが、五日目に群盗におそわれて、インドから経典や仏像をのせてきた巨象が、このさわぎで溺死してしまった。
カシュガル(疏勒=そろく)をへて、クスタナ(コータン)についた。
ここは肥沃なオアシスで、果物もゆたかに産する。毛織物もさかんで、住民もみやびやかな生活をしていた。
文字はインドふう、大乗仏教がさかえ、百の寺、五千の僧がおり、国王も熱心な信者であった。
ここには相当ながく滞在し、途中でうしなった経典を補充する処置もとった。
そもそも玄奘は、国法をやぶって出国したのである。
よって特別に帰国の許可をえなければならなかった。
そこで、ここから太宗に上表文を書き、これまでの経過をのべて許可をねがった。
太宗は玄奘の帰国を歓迎し、そのためさまざまの便宜をあたえる詔勅も発せられた。
その間、クスタナには七〜八ヵ月も滞在したのである。
クスタナからは、ニヤをへて、大流砂をわたった。風につれて砂丘が移動し、前に通った人のあとも、わからないところである。
ロブ・ノール湖畔のナヴァパ(楼蘭)をへて、いよいよ長安についたのは、貞観十九年(六四五)正月六日のことであった。
運河からはいると、舟着き場は出むかえの群衆でごったがえしている。その夜は舟のうえですごした。
八日には、はるばるインドからもってきた経典や仏像をならべて、民衆に見せた。
仏典は総計五百二十包、六百五十七部、これをはこぶのに二十二頭の馬を要した。
このころ太宗は、高句麗遠征のため洛陽におもむいていたので、玄奘も洛陽におもむいて拝謁した。
太宗はその長旅を慰労し、西方の話をこまかく聞いたのち、それをまとめて書くように命じた。
その結果できたのが『大唐西域記』十二巻である。
およそ百四十ヵ国にわたる国ごとの記載があるが、実際には行かず、伝聞で記したところもあった。
しかし内容は正確であり、西域の国のことだけでなく、インド史の資料としても貴重なものである。
太宗は玄奘の人物をたのもしく思った。還俗(げんぞく)して政務を補佐してほしいと望んだが、玄奘は固辞した。
せめて高句麗の遠征には同行させようとしたが、これも辞退した。
玄奘としては、インドからもちかえったサンスクリット(梵語)仏典の翻訳に、一日も早く着手したかったのである。
これを願うと太宗は、訳経の場所として、なき母后のために建立した長安の弘福寺をえらんだ。
訳経は大規模な組織でおこなわれた。証義(訳語の考証)、綴文(てつぶん=文体の統一)、筆受(口述筆記)、書手(浄書者)とわけて、証義に十二名、綴文に九人の高僧があつめられ、みるみる進行した。
これよりさき、インドのハルシャ王は、玄奘より唐のことを聞いて、使節を長安に送った。
太宗もその答礼使として王玄策(おうげんさく)らをインドにつかわした。
王玄策は貞観十九年に帰朝したが、太宗は翌年、ふたたび王玄策らを派遣し、その勅書は玄奘がサンスクリットで書いた。
しかし王玄策がインドについたとき、すでにハルシャ王は死んでいたのであった。
かねてから玄奘は、その訳経に太宗の序文を願っていたが、貞観二十二年、太宗はみずから筆をとって書きあげた。
これが「大唐三蔵聖経序」で、すべて七百八十一字、戦乱のなかで成長した太宗であるが、文章も筆跡も、ともにみごとなものであった。
貞観二十三年(六四九)、玄奘訳経のよき後援者であり、中国史上きっての名君であった太宗が崩御した。
その夜、玄奘は宮中に宿直していた。遺詔によって皇太子が即位し、高宗となった。
そののちも玄奘は訳経を続行し、龍朔(りゅうさく)三年(六六三)六十二歳のときに『大般若(だいはんにゃ)波羅蜜多(はらみた)経(きょう)』六百巻の翻訳を終えた。
これに玄奘は精魂を傾けすぎたためであろうか、このころから気力も体力も、とみに衰えた。
しかし、なお訳経の仕事をつづけて六十三歳をむかえ、『大宝積経(たいほうしゃくきょう)』の訳にとりかかる。
仰臥して数行を訳したが、いまは気力のつきたことを感じた。
弟子に、じぶんの訳し終わった経典の目録を書き上げさせると、すべてで七十四部、一千三百三十八巻あった。
かくて麟徳(りんとく)元年(六六四)二月五日、ついに玄奘は大往生をとげた。
勅によって国葬がおこなわれ、四月十四日には、長安の東郊に葬られた。
墓所で通夜をしたものは三万人におよんだ。
top
**************************************** |