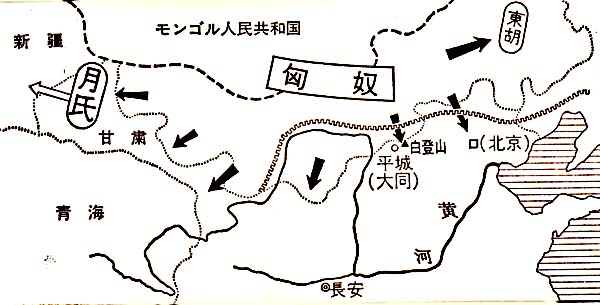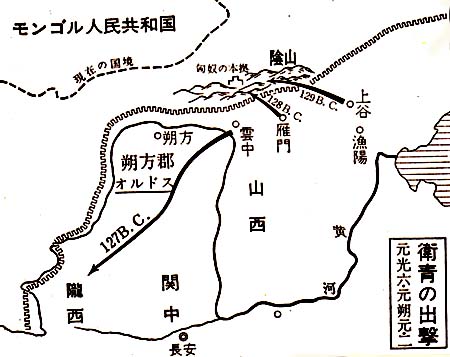|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16
17 18
13 匈奴(きょうど)と西域
1 騎馬の英雄 top
平城の下(もと) 亦 誠に苦し、
七日食せず、弓をひく能わず。 |
平城のもとでは まことに苦しんだ、
七日の間 食もなく、弓ひくこともできなんだ。 |
漢の高祖は、皇帝となってから三年目(前二〇〇)の冬、みずから兵をひきいて、匈奴(きょうど)を討つた。
しかし平城(へいじょう=今の大同)から白登(はくとう)山に達したところで、匈奴の兵四十万にかこまれた。
高祖は、いのちからがら逃げかえった。みごとな敗北であった。
これより漢は、皇族の女を匈奴につかわし、さまざまの贈りものをあたえて、匈奴をなだめることにつとめた。
おかげで、わずかな小ぜりあいはあったにしても、七十年あまりにわたって、北辺に平和はつづいた。
ただし漢にとっては、屈辱(くつじょく)の平和にちがいなかった。
高祖の軍をくるしめたのは、冒頓単于(ボクトツ・ゼンウ)である。
単于(ゼンウ)とは、匈奴の言葉で君主のことであり、冒頓は匈奴帝国の統一をなしとげた英雄であった。
冒頓の父を頭曼(トウマン)単于という。これまた偉大な君主であった。
秦の始皇帝とおなじ時代にあらわれ、匈奴の統一をおしすすめて、威力をふるった。
やがて頭曼は、わかい夫人のうんだ末子を愛するようになり、しだいに長子の冒頓を遠ざけるようになる。
冒頓は、その身に不安をいだいた。そこで鏑矢(かぶらや)をつくって、親愛する部下たちに命令をくだした。
「この鍋矢で射たものを、そのとおり射るのだ。射ない者は、斬る」。
でかけて鳥獣を狩りした。鏑矢で射たものを、おなじように射なければ、斬られた。
数日たった。冒頓は鏑矢をつがえて、じぶんの愛馬を射た。
はばかって射ない者があった。たちどころにその者を斬った。
つぎのときには、鏑矢で愛妻を射た。左右のなかには、すこぶるおそれて、射ようとしない者があった。
また、その者を斬った。もはや冒頓が射るところ、部下はためらわずに矢をはなった。
冐頓は、その意のままに部下たちがうごくことを知った。
ついに父の単于といっしょに狩りにでる日がきた。鏑矢が父にむかって飛んだ。
部下たちの矢も、いっせいに頭曼(トーマン)を射た。
冒頓(ボクトツ)は、継母や異母弟や、服従しない者をことごとく殺し、みずから立って単于(ゼンウ=君主)となった。
|
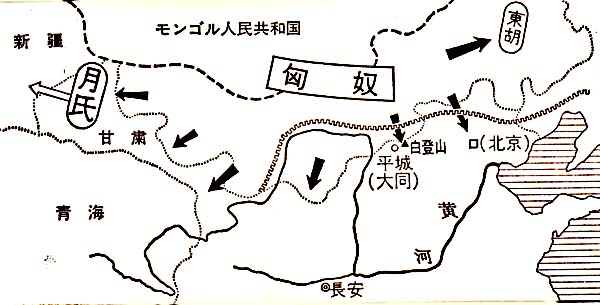
|
そのころ、匈奴の東方に、東胡(とうこ)とよばれる部族があった。
興安嶺のふもとにすみ、きわめて強勢であった。
冐頓が父を殺して自立したことをきくと、さっそくいってきた。
「なき頭曼どのが持っておられた千里の馬を、いただきたい」。
部下たちに相談すると、みないった。
「千里の馬は、匈奴の宝であります。あたえるわけにはまいりますまい」。
しかし冒頓は、「隣国のよしみだ、たかが馬の一頭くらい」といって、千里の馬をおくった。
しばらくすると、東胡はまた要求してきた。
「単于どのの夫人のうち、一人いただきたい」。
部下たちは、おこって反対した。しかし冒頓は「これも隣国のよしみだ。
たかが女ひとり」といって、愛する夫人の一人を東胡にあたえた。東胡は、いよいよ匈奴をみくびった。
匈奴と東胡とのあいだには、ひろい不毛の地があった。
そこに東胡は進入してきて、「この空地(あきち)を所有したい」と申しいれた。
部下たちは「どうせ捨て地です、やってもよし、やらなくてもよし」といった。
すると冒頓は、大いにおこっていった。
「土地は国の基(もとい)だ。どうして、やれるものか」。
いうなり馬にのって、命令を発した。
「われに遅れをとる者は、斬る」。
こうして東胡の不意をおそった。たちまちにして東胡をやぶり、その王を殺して、人民と家畜をうばった。
東の遠征からかえると、西に兵をすすめた。
いまの甘粛の地方には月氏(げつし)という部族がいる。
その月氏をうって、さらに西方へ追いはらった。
ついで冒頓の軍は、南へむかった。かつて秦にうばわれた地をとりかえし、さらに長城をこえた。
そして反撃してきた漢の高祖を、平城においてやぶったのであった。
2 名将ふたり top
冒頓単于(ボクトツ・ゼンウ)と、その子の老上(ろうじょう)単于の時代は、まさしく匈奴帝国の最盛期であった。
国家としての組織もととのえられ、東西にそれぞれ王をおいて、両翼をかためた。
単于みずからは綏遠(すいえん)の陰山(いんざん)山中に本拠をかまえた。
やがて漢では、武帝が立つ。祖先の恥をすすぐため、いよいよ匈奴への攻撃をとろうと、計画をすすめた。
匈奴では、老上単于のあとをついで、軍臣(ぐんしん)単于の代となっていた。
元光六年(前二一九)、武帝は四人の将軍に、それぞれ一万騎をさずけて、匈奴をうたせた。
三人の将軍はやぶれたが、衛青(えいせい)のひきいる部隊は、はるかに匈奴の本拠をつき、数百の首級(しゅきゅう)と捕虜(ほりょ)とをえて帰った。
漢の軍が、長城のそとに討って出たのは、これが最初のことである。
あくる元朔(げんさく)元年(前二一八)、衛青の姉は皇子をうんで、皇后に立てられた。
その秋、そして翌年、衛青はつづいて出撃した。ついにオルドスの地をうばいかえして、そこに朔方郡をひらいたのである。かさなる大功によって、衛青は大名にとりたてられた。
元朔五年には、三万騎をもって出撃し、一万五干の捕虜をえた。その功によって衛青は、大将軍(総司令官)に任ぜられた。
翌年は十余万騎をひきい、二回にわたって討って出た。またしても一万余の戦果をあげたが、漢も三干余騎をうしない、ひとりの将軍は逃げもどり、ひとりの将軍は匈奴にくたった。
このたびは褒賞(ほうしょう)はなかった。
ただ大将軍のもとにあって、ひとり大きな功をたてた者がいる。衛青(および衛皇后)の姉の子で、十八歳の霍去病(かくきょへい)であった。
八百騎をひきいて敵中ふかくはいり、単于の一族を斬り、また捕え、首級と捕虜二千余をえた。
はなばなしい武勲を賞せられて、霍去病は大名に取りたてられた。たくましい若武者の武勲に接して、武帝の胸はますますふくらんだ。
いまや北方の匈奴に対しては、相当の打撃をあたえたのである。つぎは西方の討伐である。 |
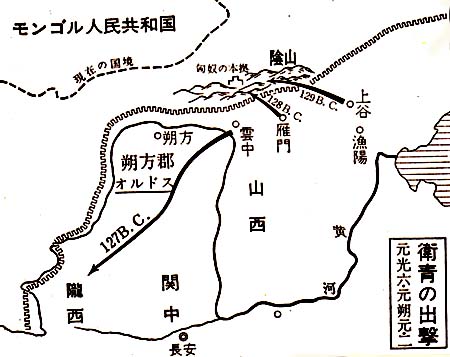 |
地図をみれば、中国の西北方に長く、ヒョウタンの形をして西にのびている地域が、みとめられよう。
いまの甘粛(かんしゅく)省である。その地域は、かつての月氏(げつし)の住地であった。
しかし月氏は匈奴に追われ、遠く西へうつった。
したがって武帝のころ、甘粛の地を占めているのは、匈奴である。
そして甘粛の地に、いまだ中国の勢力はおよんでいない。
いまや武帝は、甘粛の平定を思いたった。
3 張騫(ちょうけん)の旅行
top
西方に対する武帝の関心は、その即位のころにさかのぼる。
月氏のことを、匈奴の捕虜から聞いたのであった。
すなわち月氏は、匈奴から追われたことを恨みにおもい、匈奴をあだとしているが、ともに同盟して討とうとする国がない、というのである。
武帝は考えた。
しからば月氏とともに、東西から匈奴を討とう。そのためには、月氏へ使者を出さねばならぬ。
匈奴の領内をとおってゆくのだから、その任務はきわめてむずかしい。
そこで、ひろく使者をつのった。これに応募してきたのが、張騫(ちょうけん)であった。
武帝は、張騫のために百人あまりの家来をつけてやった。
それをともなって、張騫は長安の都を出発した。しかし、それきり張騫の消息はきこえなかった。
張騫は、甘粛において匈奴につかまってしまったのである。単于の前につれてゆかれた。
月氏にゆく、というと、そのまま拘留(こうりゅう)された。
そうして十年あまり、その間には匈奴人の妻をあてがわれ、子まで生まれた。
すっかり匈奴の土地になじみ、監視もゆるやかになった。
ついに機会をとらえて、張騫は逃げだした。妻も仲間も、いっしょだった。
いっさんに西へと走ること、十数日、ゆきついたところが、大宛(だいえん)という国であった(今のソ連領内、フェルガール地方)。
大宛の国では、漢が物資のゆたかな国であることを知っていた。
張賽をみるとよろこんで、大いに歓迎した。
かくて張賽は、大宛の国王にたのみこんで、道案内をつけてもらい、康居(こうきょ)の国をへて、月氏の国におもむいたのである。 |

胡人(北方民族)の像:銀製
|
そこは、いまのソグディアナ(ソ連領内)であった。
そこは肥沃な土地であり、敵もなく、やすらかに暮らしていた。
匈奴へのうらみなど、すっかりわすれさっている。
しかも月氏は、南方の大夏をも属国としていて、いよいよ得意なのである。
張騫は一年あまりとどまって、漢との同盟を説いたが、効果はなかった。
張騫(ちょうけん)は、大夏へもおもむいた。いまのアフガニスタンの北部である。
この地には、かつてバクトリア王国がさかえていた。
バクトリアとは、ギリシアのアレクサンダー大王の遠征の名ごりとして、ギリシア人の建てた国である。
張賽がいたときより十年ちょっと前、このギリシア人の国は、北方からきたトラハ人にほろぼされた。
そして張騫のゆく直前、月氏に服属したのである。
だから大夏には、ギリシア文化の影響が根づよくのこっていた。
この大宛(だいえん)や大夏は、アーリヤ人の国である。
つまりヨーロッパ人と同系の、青い目の人々の国である。
いっぼう康居(こうきょ)や、その東北にいた烏孫(うそん)は、トルコ系の国であった。
また月氏は、アーリヤ系とも、トルコ系ともいわれ、定説はない。
匈奴にしても、アジア人であることはたしかだが、トルコ系なのか、モンゴル系なのか、はっきりわかっていない。
さて張騫(ちょうけん)は、月氏との同盟に成功せぬまま帰国の途についた。途中、またも匈奴につかまる。
しかし一年あまり後、軍臣単于が死んで国内に争いがおこったすきに、脱走した。
そして十三年ぶりに、長安へかえってきた。
匈奴人の妻をつれていたが、出発するとき百余人の一行は、張騫と従者との二人きりになっていた。
ときに元朔三年(前一二六)である。
張騫の報告によって、武帝の胸はいよいよ大きくふくらんだ。
北方の匈奴を討ったのちは、西方を平定せねばならぬ。
そして甘粛(かんしゅく)こそは、西域への通路であり、なお匈奴の領域である。
甘粛を征すべし。命令は霍去病(かくきょへい)にくだされた。
4 匈奴(きょうど)の落日
top
元狩二年(前一二一)の春、二十歳の霍去病(かくきょへい)は一万騎をひきいて甘粛に出撃した。
そして大いに匈奴をやぶり、斬首と捕虜は八千余、斬った者のなかには、匈奴の属国の王二名がふくまれていた。
つづいて夏、ふたたび霍去病は討ってでた。
その足跡は居延(きょえん)水から祁連山(きれんざん)をこえ、甘粛の西境をきわめた。
戦果は三万二百、そして五人の王が捕えられた。
匈奴にとって西の守りに任じていたのが、渾邪(こんや)王である。
この敗戦を、単于はおこった。単于は、渾邪王を召しよせて殺そうとした。
これを知った渾邪王は、その年の秋、漢に降伏を申しでた。
王と、その数万の軍は、霍去病がひきいて、長安におくられた。
いまや匈奴の王が、降伏して長安にきたのである。武帝にとって、まさしく晴れの盛事であった。
その恩威をしめすために、二万台の馬車が用意され、手あつくもてなした。
渾邪王は大名にとりたてられ、その兵は北辺において、もとの風俗のまま住むことをゆるされた。
もはや武帝にとって、あとは匈奴の本拠をつくことばかりである。
二年後の元狩四年(前一一九)春、最大の遠征軍が発せられた。
衛青(えいせい)と霍去病(かくきょへい)が、それぞれ五万騎をひきい、そのあとに歩兵と輜重(しちょう=輸送部隊)の数十万がつづいた。
匈奴はゴビ砂浜の北方まで軍をひきいて、漢の大軍をむかえ討った。
漢の人馬をつかれさせる作戦であった。
しかし漢軍は、ついに砂漠の北で単于の軍をとらえた。
兵力にまさった漢軍は、じりじりと単于の軍を包囲してゆく。
おりから日が没し、大風がおこった。砂や小石が顔にあたった。
暗さのなかで、両軍は入りみだれて戦った。不利と知って、単丁は西北へのがれた。
匈奴の兵も、ちりぢりになって敗北した。
これを斬り、捕えること数万、しかも衛青にくらべて、霍去病の戦果は数倍に達した。
恩賞の沙汰は霍去病およびその部下にのみくだり、衛青に沙汰はなかった。
こうして霍去病は、その地位も封禄も、まったく叔父の衛青とならぶにいだったのである。
しかし霍去病(かくきょへい)は、それから二年半の後、まだ二十四歳のわかさで世を去った。
武帝はふかく悲しみ、盛大な葬礼をもって、その軍功にむくいた。
その墓は、いとなまれつつあった武帝の陵のかたわらに、祁連(きれん)山にかたどって、つくられた。
霍去病は死んだが、その奮戦によって、すでに匈奴も往年の勢威はない。
その本拠たる陰山の地方も、漢におさえられ、いまは漠北(ばくほく=ゴビ砂漠の北)をたもつのみとなった。
武帝の目は、ふたたび西方へむけられた。
5 帝国の拡大 top
張騫(ちょうけん)は、月氏のかわりに烏孫(うそん)とむすぶことを武帝にすすめた。
その地は、かつて匈奴に追われた月氏が拠っていたところである。
それを烏孫は、匈奴のたすけをえて西方に追い、そのあとにすみついたのであった。
しかも、勢力が強くなってからは、鳥孫とて、かならずしも匈奴にしたがってばかりはいない。
そこで、いま漢が烏孫とむすべば、匈奴の右腕を切りおとすことになろう。
烏孫から西の諸国も漢に通じてくるに違いない。 |
 |
かくて張騫は、烏孫への使者にたった。烏孫につくと、さらに西方の諸国へも、それぞれ部下をつかわした。
張騫の帰国にあたっては、烏孫からも数十人の使者が立てられ、数十頭の名馬をもたらした。
武帝は名馬をえて大いによろこび、天馬と名づけた。
やがて張騫が西方につかねした使者もあいついで帰ってきた。
いずれも、西方のめずらしい物産をもちかえった。
馬があった。玉(ぎょく)があった。葡萄(ぶどう)があった。葡萄からつくった酒があった。
苜蓿(もくしゅく=ウマゴヤシ)があった。これは豆科の草で、牛馬の飼料であった。
また胡桃(クルミ)があった。駝鳥(だちょう)の卵もあった。さらに奇術師をともなってきた者さえあった。
長安の宮廷には、こうした異国の珍奇な品が、うずたかくつみあげられ、その前では青い目の男がふしぎな術を演じてみせた。
やがて張騫(ちょうけん)は死んだが、その開いた道を、いく組もの探検隊が、次々に西域へとむかっていった。
西域との交通は、年ごとにさかんとなる。
いっぽう烏孫は、匈奴の圧力に対抗するため、さらに漢との接近をはかった。
そのため千頭の馬をおくって、漢の皇女を王妃にほしい、と求めてきた。
武帝は一族の娘を公主(こうしゅ=皇帝の娘)として鳥孫王へつかわした。
この姫の名が細君(さいくん)であった。
その身は皇族として生まれながら、ゆくさきは万里の西、とつぐ夫は言葉も通ぜぬ異国の老王である。
かなしい運命に泣く細君の歌は、こののちもながく人びとの口につたえられ、涙をそそった。
吾が家(いえ)は我を天の一方に嫁(とつ)がせ、
遠く託(たく)しぬ、異国の烏孫王、
穹廬(きゅうろ=弓なりにまるく張った天幕)を室(いえ)と為(な)し、旃(せん=毛織物)を牆(かべ)と為し、
肉をもって食となし、酪(らく=牛や羊の乳)を漿(しる)となす、
居常(つね)に土(くに)を思いて心の内に傷(いた)む、
願わくは黄鵠(こうこく=黄色いおおとり)となりて故郷(ふるさと)へ帰りなむ。 |
こうして漢の勢力が西方にのびるや、その通路となる甘粛地方の経営もすすめられた。
そこは匈奴(きょうど)の渾邪(こんや)王が投降してから後、すむ者もなくなっていたのである。
すなわち、まず酒泉郡がおかれ、ついで敦煌(とんこう)郡など三郡が、次々に設置されていったのであった。
ここに甘粛は、はじめて漢人の住地となる。西域との交通は、いっそう便利になった。
漢の勢力は、西方へ伸びたばかりではない。西南へも伸びた。いまの貴州から雲南の方面である。
その方面にあった小国の一つ、夜郎(やろう)では、漢の使者にむかって国王がたずねた。
「わが国と、漢とでは、どちらが大きいのか」。
井の中の蛙(かわず)と同じ意味の「夜郎自大(やろうじだい)」という言葉は、ここからうまれた。
東南の広東(カントン)地方には、南越という国があった。
その王は、もと秦の始皇帝によって派遣された地方官の子孫である。
したがって漢民族であったが、人民は土着の人たちである。
服属せよという武帝の命令に反抗した。
そこで元鼎(げんてい)六年(一一一)、違征軍がさしむけられ、たちまち南越もほろぽされた。
漢の領土は、広東から北ベトナムの地方にまでおよんだ。
それから三年後、すなわち元封三年(前一〇八)には、朝鮮半島の北半も、漢の領土にくわえられた。
いまの平壌(ピョンヤン)を中心にして、かねてから「朝鮮」と号する国が建てられていた。
それが漢に反抗して、討伐をうけたのである。
朝觧国はほろぼされ、平壌には楽浪(らくろう)郡がもうけられた。
6 悲運の将軍 top
「朝鮮」の征服から二年ののち、大将軍の衛青(えいせい)が死んだ。
その姉の衛皇后も、もはや皇帝の愛をうける年齢ではなかった。
武帝みずからが、すでに五十の坂をこえていたのである。
このころの武帝が愛したのは、李夫人であった。その家は、一族すべて芸人として立っている。
はじめ宮中へはいったのは、李夫人の兄の李延年であった。
歌舞がたくみで、とくに作曲がうまかった。あるとき李延年は、武帝の前で舞い、かつ歌った。
北方有佳人、絶世而独立、
一顧傾人城、
再顧傾人国、
寧不知傾城与傾国、
佳人難再得。 |
北方に佳人(かじん)あり、絶世にしてひとり立つ、
ひとたびかえりみれば、人の城を傾けん、
ふたたびかえりみれば、人の国を傾けん、
いずくんぞ知らざらん、傾城(けいせい)と 傾国(けいこく)と、
佳人は ふたたび 得がたきものを。 |
それが妹の李夫人であった。しかも佳人はあまりにも薄命(はくめい)であった。
皇子ひとりをうむと、たちまち病床に伏し、そのまま世を去ってしまった。
武帝は李夫人の死をいたみ、とくに皇后の礼をもってほうむった。
また夫人の兄の李延年を、舞楽の取締(とりしまり=協律都尉)に任じ、もうひとりの兄の李広利(こうり)を、将軍にとりたてた。
こうして李広利が登場する。
かねてから武帝は、西域に産する名馬をほしがっていた。
ことに大宛(だいえん)の馬は、天下一との名が高い。
よって大宛に使者をおくり、その名馬をもとめた。
しかるに大宛では、漢の使者を殺し、その財物をうばった。武帝はおおいに怒った。
かくて李広利に命じ、数万の兵をひきいて、大宛にむかわせた。ときに太初元年(前一〇四)であった。
おりから中国ではイナゴの害がひどく、西のかた敦煌(とんこう)まで飛んでいった。
その下を、大軍が進む。甘粛をとおって、玉門関を出れば、もはや漢の領域ではない。
沿道の小国は、いずれも大軍をみておそれ、城をとざして、かたく守った。
攻めくださなければ、食糧はえられない。いたずらに死傷はふえ、兵士たちは飢え、つかれた。
たおれる者、にげる者が、あいついだ。ついに李広利は、軍をかえした。
二年の後、ようやく敦煌までたどりつき、他日の再挙をはかりたい、と上申した。
武帝はおこった、「あえて玉門関をはいろうとする軍兵は、斬る」。
李広利は、敦惶に軍をとどめた。一年あまりたって、あらたに六万の兵がくりだされた。
武器もじゅうぶんに用意された。
前回に数倍する大軍に接して、こんどは沿道の国も、おとなしく食糧をさしだした。
ほとんど抵抗もなく、めざす大宛の王城に達する。
城をかこんで攻めること四十日あまり。その間に、漢からつれてきた水路工夫が、城内の水源を絶った。
ついに大宛も屈服し、その国王を殺して、和をもとめた。
最高の名馬を数十頭、ほかにも三千余頭の名馬をえて、李広利は四年ぶりに長安へもどった。
軍兵は一万余にへっていたが、武帝は万里の遠征をたたえて、李広利ほか、功あった将軍たちを大名にとりたてた。
こえて天漢二年(前九九)、李広利は匈奴(きょうど)の討伐を命ぜられ、三万騎をひきいて進発した。
すでに匈奴は漠北にしりぞいている。その息の根をとめようというのが、ねらいであった。
漢軍は甘粛から出て北に進んだ。しかし李広利の軍は匈奴の迎撃にあって、過半をうしなった。
部将の李陵も、五千の歩兵をひきいて単于(ゼンウ=匈奴の君主)の軍と戦い、その一万余人を殺傷したが、ついに刀おれ矢つきて、漢軍ほとんど全滅、李陵は捕えられた。
中島敦の名作『李陵』は、この悲運をえがいたものである。
なお、敵にくだった李陵の罪が武帝の前で論ぜられたとき、ただひとり、李陵を弁護したのが、太史公(史記)の司馬遷であった。
ために武帝の怒りにふれ、司馬遷は肉体のいちばん大事なところを切りとられる刑(宮刑)に処せられた。
その間の事情も、また『李陵』においてくわしい。
さて李広利は、その後も二回、すなわち天漢三年と、それから六年をへだてた征和二年(前九一)とに、匈奴へ出撃している。しかも三回目の遠征には、やはり戦つて利あらず、生きのこった兵をまとめて、匈奴にくだってしまった。
芸人の家からでた将軍は、あくまでも武運にめぐまれない。
匈奴では好遇されたものの、かえってねたまれ、殺されてしまったのである。
武帝が死んだのは、それから四年後の後元二年(前八七)であった。 |

新潮文庫
|
7 王昭君の話 top
武帝の死から三十余年をへた。すでに匈奴も、往年のおもかげはない。
くわうるに内乱がおこって、五人の単于(ゼンウ)がならび立つありさまとなった。
これを統一したのが呼韓邪(こかんや)単于である。
しかし、やがて兄の郅支(しっし)も立って、単于を称した。
やむなく呼韓邪は、これまでの体面をすてて、漢に降伏を申しいれた。その助力をえようとしたのであった。
ときに宣帝の代である。
その甘露三年(前五一)、呼韓邪単于はみずから長安におもむき、宣帝に謁見(えっけん)した。
単于の入朝は、もちろん漢にとって、はじめてのことである。
よろこんだ漢の朝廷は、これをあつくもてなし、諸侯王の上に位する待遇をあたえた。
郅支(しっし)単于は、西へ走った。
鳥孫(うそん)をやぶり、大宛をしたがえ、そのいきおいは西域を圧するほどとなった。
漢の軍がこれを敗死せしめたのは、つぎの元帝の建昭三年(前三六)である。
あくる年のはじめ、郅支(しっし)の首は長安でさらしものとなった。
いよいよ喜んだのは、呼韓邪である。
さらに漢への忠誠をちかい、公主(皇帝の娘)をたまわって漢の帝京の姻戚(いんせき)になりたい、と請うた。
元帝の来年(前三三)、ふたたび呼韓邪は来朝した。
このとき、呼韓邪にあたえられたのが、宮女の王昭君であった。
元帝のころ、後宮にはあまたの宮女がおり、そのすべてを皇帝が見るわけにはいかない。
そこで画工に宮女たちの姿をえがかせ、美しい者を召すことにしていた。
王昭君は、じぶんの容姿に自信があったので、画工につけとどけをしない。
したがって、せっかくの豊容(ポッチャリした美人)も、皇帝の目にとどかなかった。
さて匈奴へ女をあたえるに際し、元帝は、みにくくえがかれた昭君をえらんだ、という。
しかし、この話は、のちになってつくられたものである(晋代の『西京雑記』)。
はたして事実であったかは、うたがわしい。
呼韓邪にたまわった宮女は五人あって、王昭君はそのうちの一人にすぎなかった。
王昭君は、えらばれて宮中へはいったものの、数年たっても皇帝から召されず、うらみ悲しんでいた。
そこで、みずから望んで五人のなかに加わったのである。
さて、わ彼のために、はじめて王昭君は、元帝のまえにでた。
ここで元帝はおどろいた。まさに後宮第一の美女であろう。
呼韓邪にあたえるのが惜しまれ、とどめようと欲した。
しかし、すでに示してしまったのである。いまさら信をうしなうことをおそれた。
いっぼう呼韓邪はよろこんだ。ともない帰って一子をあげた。
しかも王昭君がとついで二年の後に、呼韓邪は世を去ったのである。
匈奴の風習では、父が死ねば、その妻妾は(母をのぞき)ことごとく子がめとる。
呼韓邪の長男が立って単于となるや、また昭君を妻とした。
これは中国の女として、たえがたい屈辱である。
母と名のつく女と通ずることは、禽獣にひとしい行為と、考えられていたのであった。
王昭君は、漢の朝廷に上書して、帰国を請うた。
しかし、ゆるされなかった。
二度目の結婚で、また二女をうんだ。そして、相手の単于も九年にして死んだ。
呼韓邪の子は次々に単于となったが、王昭君のうんだ子だけは、単于になれなかった。
あるいは、殺されたとも伝えられる。
その後の王昭君は、どうなったか。おそらくは漢の国をのぞみつつ、さびしく匈奴の地で、その数奇な生涯をおわったことであろう。
黄河の上流に、その墓と伝えられているものがあるが、もとより真偽のほどはあきらかでない。
ともあれ王昭君は、史実よりも小説によって、後世の人びとに伝えられたのである。
はやくも六朝(りくちょう)時代(四世紀)には物語がつくられ、歌曲としてうたわれた。
唐代になると、李白や杜甫も、詩のなかに詠じた。海をこえて、平安時代の日本にも伝えられた。
その曲は、雅楽にとりいれられ、その哀話は、このんで詩によまれた。
さらにくだって元(げん)の世には、戯曲にもなった。なかでも傑作が「漢宮秋」である。
ここにおける王昭君は、匈奴におくられる途中、国境の大河に身をなげて死んだ。
それは、異国の男に身をまかせまいとする、中華の女の誇りをしめしたものであった。
おりから中国は、モンゴル人に支配されていたのである。
top
**************************************** |