|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17 18
16 斜陽の帝国
1 年少の皇帝 top
後漢の皇帝は、はじめの三代を除くと、いずれも幼少にして位につき、しかもおどろくほど短命であった。わかい皇帝が即位すれば、政治の実権をにぎるのは、おおむね皇太后である。
そうして皇太后の一族、つまり外戚が勢力をふるうことになる。そのきざしは、はやくも四代目の和帝のときからあらわれた。
第二代の明帝の皇后は、建国の功臣たる馬援(ばえん)の娘であった。 |
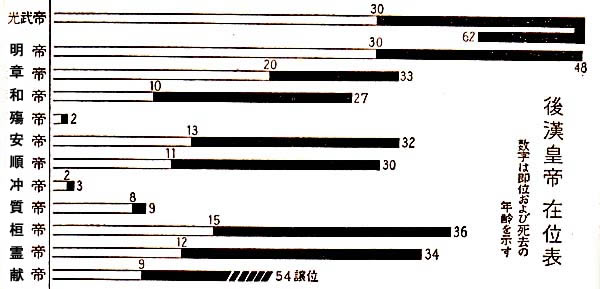 |
美人のほまれ高く、かつ才媛(さいえん)であったが、身を持することも固く、皇太后となったのちも、馬氏の一族をおさえて、政治に口をださせなかった。
したがって三代の章帝まで、外戚のわざわいはなかった。
章帝が三十三歳のわかさで世を去ると、ついで立ったのは、十歳の和帝である。
ここで実権をにぎったのが竇(とう)太后であり、その兄の竇憲(とうけん)であった。
竇憲は、北匈奴をうって大功を立て、みずからは大将軍となったほか、父子も兄弟もそろって高官にのぼった。
その専横には、おさない和帝の目にもあまるものがあった。
こうしたとき、つねに皇帝のそばにいて相談の相手となったのが、宦官(かんがん)である。
和帝も、宦官をたよりとした。
そして、その力によって竇憲の非行をあばかせ、大将軍の地位から追放したあげく、自殺せしめたのであった。
外戚を除くことはできたが、今度は宦官の力がつよくなった。
本来ならば、宮中の奥ふかくにいて、雑用をつとめるのが宦官の役割である。
その肉体は、男としてもっとも大事なところをうしなっているのであるから、結婚もできなければ、子孫をつくることも不可能である。健全な人たちからは、人間以下のものとして軽蔑されている。
それだけに宦官のなかには、ひと一倍の権勢欲をもっている者が、すくなくなかった。
そうして、ひとたび皇帝のあつい信任をえると、つぎには政治をも左右しようとするにいたる。
政務をとるところは府中とよばれ、宮中からは、これにくちばしをいれることはできない、というのが原則である。
宦官が政治にのりだすことは、宮中と府中の別をみだすことに、ほかならなかった。
その悪例は、和帝のときにひらかれたのである。
つぎに立った殤(しょう)帝は、うまれてから百余日の乳幼児であった。
それも数ヵ月で死去し、ついで十三歳の安帝が立つ。
政権をにぎったのは、やはり皇太后と、その一族であった。
安帝が即位してから十五年(一三)、皇太后が死ぬ。
すると安帝のそばにいた宦官たちは、地方の豪族と手をむすび、外戚たる鄧(とう)氏をたおした。
またも宦官は、大きな役割をになった。
それから五年して、安帝が死んだ。皇后が政権をにぎり、安帝の皇子をさしおいて、いとこを位につけた(少帝)。
しかし、これには宮中や世間の不満も大きい。
内外の空気をさとった宦官たちは、しきりに暗躍して太后の一族をたおし、しりぞけられた皇子をむかえて即位させた。
これが順帝である。功労のあった宦官たちは、大名にとりたてられた。
2 宦官と外戚 top
宦官と外戚とは、いまや幼少の皇帝をとりまいて、わがもの顔にふるまう。
順帝が死ぬと、その子の冲帝がわずか二歳で即位した。
順帝の皇后であった梁(りょう)氏が、太后として政権をにぎった。
兄の梁糞(りょうき)がうしろにいて、これをあやつった。
冲帝が五ヵ月で死去すると、太后と梁糞とは、八歳の質帝を立てた。
こうした少年の皇帝でも、梁糞のふるまいは目についたらしい。
ある日のこと、梁糞のすがたをみかけた質帝は「跋扈(ばっこ)将軍」とよんだ。
すでに梁糞は、順帝のときに大将軍に任ぜられていたのである。
質帝は帝位につくと、わずかに一年半、梁糞のために毒殺された。
ついでむかえられたのは、遠縁の桓帝である。これも十五歳の少年であった。
即位の四年後に梁太后は死去したが、もはや梁氏の勢力はゆるがなかった。
梁冀の妹は皇后にたてられ、梁氏の一族からは、大名となる者が七人、大将軍たる者が二人、そうして高位を占める者は五十人をこえた。
まさしく後漢の朝廷は、梁氏の天下であった。
桓帝が即位してから三十年、梁皇后(梁冀の妹)が死んだ。
梁冀と宮中とをむすぶ大きな糸の一本がきれた。
その専横をにがにがしく思っていた桓帝は、かねてから宦官たちと意を通じ、機会をうかがっていたのである。
ついに、その時がきた。皇帝と宦官とのひそかな計画が、実行にうつされた。
桓帝は兵を発して梁冀の邸宅をかこませた。
さしもの梁冀も、妻とともに自殺した。梁氏の一族は、ことごとく処刑され、その死体は市場でさらしものとなった。
しかし梁氏はたおされても、かわって宦官が勢力をえた。 |
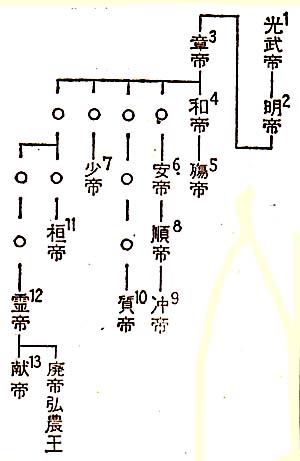 |
大功のあった五人の宦官は大名となり、将軍となり、政権をほしいままにして「五邪」とよばれるにいたる。
彼らにとって、権力につづくものは、物欲であった。
宦官たちは、その権力にまかせて、田をうばう、家をうばう。
そして宏壮な邸宅をいくつもいとなむ。
そこには高楼あり、池苑(ちえん)あり、堂閣あり、いずれも美々(びび)しくかざりたてて、宮殿さながらであった。
さらに、ひとの居室をこわし、墳墓をあばいては、財宝をぬすむ。
男をかどわかしては奴隷とし、女をかすめとっては妻妾とするというありさまであった。
ところで後漢の外戚となったものは、地方の名門である。
ひろい土地を所有して羽ぶりをきかす豪族であった。
それが権力をにぎると、中央の高官となり、要職を独占した。
いっぽう宦官は、おおむねひくい身分の出身である。
みずからは肉体の一部をなくした不具者である。
それが権力をにぎると、ふだんは下づみになっている官僚や、力をのばせないでいる豪族と結託した。
彼らもまた、宦官のもとにあつまって、あまい汁をすおうとしたのであった。
中央の官界ばかりでなく、地方の官職まで、こうして宦官の息のかかった者に、独占されるようになった。
当然のこととして、反撥がおこった。
3 清流と濁流 top
後漢の朝廷において高級の官吏となるためには、儒学の教養が必須であった。中央に設けられた国立の太学は、年を追うて発展し、その学生も後漢の末ごろには三万人に達する。
地方における私塾もますますさかんとなり、なかには数百から数千の門弟をかかえるものもあった。
こうして儒学を奨励し、名節をたっとぶ傾向が、やがては極端に走ってゆく。官吏たるべき者を推挙することを、選挙(選び、あげるの意)と称したが、そうした選挙にも、また昇進にも、実務の才能はかえりみられない。
重んぜられるものは「名節」であった。 |
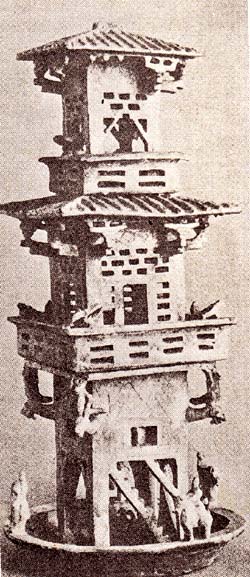
陶製の楼閣
|
しかも名節というものは、基準のあるものではないから、太学生たちの人気が、これを大きく左右した。
そこから、学者のなかには人気をえるために、派手な言動をする者があらわれてくる。
学生たちもまた、しきりに政治を批判し、学問よりも運動に身を投ずるという傾向がつよまってゆく。
さて儒学を勉強して、正規のコースから官界へはいった者は、清流(せいりゅう)とよばれた。
これに対して宦官や、その推挙によって官吏となった者は、濁流とよばれる。
濁流がはびこることは清流にとって、がまんのできないものにちがいなかった。
そこで気骨のある者、または名節の士として人気をえたい者は、濁流の非行をあばきたて、法にてらしてきびしく処分した。
いまを時めく宦官の一族でも、容赦はしなかった。
すると宦官のほうでも、その権力を悪用して、法の正しい適用をおこなった者を、免官にする。
さらに投獄する。さらには処刑する。清流と濁流との争いは、時とともに激しさを加えていった。
桓帝の延熹(えんき)九年(一六六)十二月、いまでいえば警視総監にあたる司隷校尉(しれいこうい)の李膺(りよう)をはじめ、二百余人に対して逮捕令が発せられた。
もちろん、宦官たちが策動した結果である。
すなわち李膺は、太学の学生たちと交遊し、こもごもゆききして徒党をつくり、朝廷を非難し、風俗を惑乱している、というのであった。
李膺こそ、いわゆる清流の中心人物として、太学生のあいだで声望が高い。
そこで先輩たる太尉(軍政長官)の陳蕃(ちんばん)から推挙をうけて、司隷校尉に任ぜられた。
さしもの宦官たちも、李膺のもとでは行動をつつしんだ。それだけに李膺は、濁流にとって目の上のコブであった。
さて逮捕令は発せられたが、これに署名することを陳蕃がこばんだ。
ほまれ高く、国をうれうる人たちを、罪名もあきらかでないのに捕えることは道理にあわぬ、というのであった。
しかし逮捕は強行された。洛陽でも、地方でも、名節の士たちは次々に検挙された。
陳蕃は桓帝に対して、このことの不当を訴えたが、かえって太尉の職を免ぜられた。
ところが捕えてはみたものの、いざ取りしらべをおこなおうとするや、李膺たちは逆に、宦官の非行を申したてる。
これには宦官たちがおそれをいだいた。
ついに取りしらべを中止し、それぞれ郷里に送りかえして、庶人(しょじん=平民)の身分におとし、こののち官吏となることができないようにしてしまった。
当時の言葉でいえば、禁錮(きんこ)の刑に処したわけである。
党派をつくったというわけで禁錮となる、それゆえに、その事件は「党錮(とうこ)の獄」とよばれた。
いわゆる党人は処分されたが、その人気は、いよいよ高まるばかりであった。
党人たちは、おのおのの郷里において、熱烈な歓迎をうけたのである。
濁流に抗して罪せられたことは、清流たるものの名誉とかんがえられたのであった。
4 空前の大獄 top
やがて垣帝が死去し、一族から霊帝がむかえられて即位した(一六七)。
この迎立には、外戚の竇武(とうぶ)の力が大きかったので、またも外戚が力をもりかえす。
竇武(とうぶ)は大将軍となり、陳幕も太尉にかえり咲いた。李膺たち党人も、禁錮をゆるされてふたたび官途についた。
まきかえしである。
陳蕃と賓武は、この勢いに乗じて、有力な宦官たちを一掃しようとくわだてた。
はかりごとは着々とすすんだ。
しかし宦官たちの結束も固い。陳・賢の上奏文が、宦官の一人にぬすみみされたのが、運のつきであった。
彼らは先手をうった。
陳蕃と竇武(とうぶ)とが天子の廃立をはかっている、と騒ぎたてたのである。
たちまち少年の皇帝をとりかこみ、近衛の軍をおさえてしまった。
急を知って宮中にかけつけた陳蕃は、宦官のひきいる兵にかこまれて、召しとられた。
そのまま獄におくられ、その日のうちに処刑された。
竇武(とうぶ)もまた、召しとりの兵にかこまれて、自殺した。
霊帝の建寧(けんねい)元年(一六八)九月のことである。
こうして宦官の天下が復活したとなれば、もはや党人たちも朝廷にとどまっているわけにはいかない。
みな、たもとをつらねて辞職し、ふたたび郷里へかえっていった。
しかし宦官たちにとって、人気のある党人どもを、そのままにしておくことはなんとしても不女であった。
またしても陰謀がめぐらされた。罪なき罪を党人にきせ、一挙にほうむってしまおうというのであった。
機会はきた。
あくる建寧二年(一六九)、党人のなかの有力な一人が「部党を立てて、社稷(しゃしょく=国家)をあやうくしようとする陰謀あり」という上奏があった。
宦官のつくりごとである。霊帝は、その部党の逮捕を命じた。
党人たちも、かくごをきめていた。今度こそ、いのちのないことは、あきらかであった。
李膚は、まわりの人たちから、逃げることをすすめられたが、「すでに六十の老齢、死生は天にゆだねよう」と語って、しずかにしばられた。
かくて獄におくられ、拷問によって殺された。
党人たちの投獄された者は、ことごとく獄中でいのちをおとした。
みずから生命を断った者もいる。たくみに逃亡した者もいる。
逃げようとおもえば、どこにでも正義を愛する士があった。よろこんでむかえられた。
しかし党人をかくまったことが発覚すれば、ただちに処刑されたのである。
こうして獄中に非業の死をとげた党人は、百人をこえた。
その妻子や一族も、あるいは殺され、あるいは辺地に流された。
二回にわたる党錮の獄は、清流のおもだった者を抹殺しつくした。
これから後の世は、まさしく濁流の天下である。
宦官にあやつられた霊帝の治世は二十一年あまり、その末期には、ついに天下の大乱がおこった。
いわゆる黄巾(こうきん)の乱である。
政治のみだれから、国家の財政はとぼしくなるばかりであり、それは年貢の増徴となって、人民の上にかかってくる。
おまけに宦官とむすんだ豪族は、その権力をかさにきて、ますます土地をひろげようとする。
たよるところのない人民の暮らしは、窮乏の極に達した。
これでは農民が反乱をおこすのも、当然であった。
中平元年(一八四)、黄巾の乱がおこった翌月(三月)のこと、宦官のなかからも党人をゆるすように、と上奏する者があった。
党錮のことでは、うらみをいだく者がすくなくない。いつまでも放置しておけば、反乱にくわわる者もでてくるであろう。
いまのうちに、手をうっておかなければ、くやんでも追いつかぬことになろう、というわけであった。
霊帝は、党人を大赦(たいしゃ)するという詔令を発した。
ゆるされた党人や、その家族たちは、歓呼の声のなかで天下に晴れの身となった。
しかし、すでに遅かったのである。後漢の王朝の命脈ももはや風の前のともしびにひとしかった。
top
**************************************** |