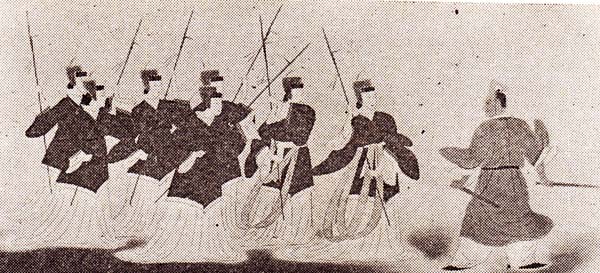|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
7 権謀と術数
1 非運の名将 top
戦国の世ともなれば、すぐれた政治家ばかりでなく、兵法家も必要である。謀略家も必要である。
そうした才能の士を、諸国は争って招き、かつ用いた。
開明君主として名高い魏の文侯は、おりから仕官をもとめてきた呉起について、「いかなる人物か」と、宰相の李悝(りかい=李克)にたずねた。
李悝は答えた、「呉起は貪欲で奸色でありますが、用兵の術にいたっては当代にならぶ者はござりますまい」。
こうして魏の将軍となった呉起は、衛の国の出身である。
富豪の家にうまれながら、仕官をもとめて四方に遊歴し、家産をつかい果たしてしまった。
郷里の人びとが嘲笑すると、自分をそしった者三十人あまりを殺し、故国をあとに東へ去った。
斉(せい)をへて、魯(ろ)国にはいり、孔子の高弟たる曾子について学ぶ。
やがて故郷にのこしてきた母が死んだが、帰って喪に服そうともしない。曾子は、孝心のうすい男だとして、呉起を破門してしまった。
ついで呉起は兵法を学んだ。たまたま斉の大軍が魯に改めこんでくる。
魯の国では呉起を将軍に任じたいと考えたが、その妻が斉の女であるために、ためらった。 |

仕官で魏の将軍となった呉起は、衛の国の出身であった
|
すると呉起は、名声をあげるべき機会をうしなうことをおそれ、妻を殺して、斉に与(くみ)しないことをあきらかにした。
ついに魯は呉起をもちい、斉と戦って大いに破った。
しかも魯の国人は、なお呉起を信用しない。
呉起の酷薄(こくはく)な人柄をきらったのである。
さらに魯と衛とは、かねてから兄弟の国として親しんできた。
いまにして呉起を用い、衛と仲たがいすることをおそれたのであった。
こうした意見に、魯の君主もうごかされた。呉起は、しりぞけられた。
そこで呉起は、魏の文侯の評判を聞き、これに仕えようと思って、魏におもむいたわけである。
魏の将軍となった呉起は、秦を攻めて五城をぬいた。
軍略にたくみなだけではない。
最下級の士卒と衣食を同じくし、寢るときも席(しとね)を設けず、進むときも車馬に乗らず、みずから食禄をつつんで担い、士卒と労苦をわけあった。こ
うして呉起は、全軍の将兵の心をつかんだ。
文候は、呉起が用兵に長じたうえ、廉直(れんちょく)にして公平であり、かつ士卒の人望をあつめているところをみこんで、西河(せいか=陜西の東部、黄河以西の地)の太守に任じた。
もって泰や韓にそなえさせたわけである。
西河の太守としても、呉起の名声はすこぶる上がった。
やがて文候が死去し、その子の武侯が立った。
あるとき武侯は西河に遊び、舟をうかべて流れを下った。
呉起をかえりみていう。
「見事だのう、この険阻な山河は。これこそ魏の宝であるぞ」。
すると呉起は答えていった、
「国の宝は、君徳にあって、山河の険要にあるのではございません。
もし主君が徳を修めないならば、この舟のなかの人も、ことごとく敵国の人となりましょう」。
しかし魏における呉起の栄光も、長くはつづかなかった。
公叔座が宰相になると、すこぶる呉起を忌(い)みきらった。
公叔座こそは、のちに商鞅(公孫鞅)が衛からきて頼った人物である。
それが呉起をしりぞけようと、さまざまに手段をつくす。
ついに武侯も、呉起をうたがうにいたった。
呉起は罪せられるのをおそれ、魏を去って、そのまま楚の国におもむいた。
楚の悼(とう)王は、かねてから呉起の賢才を聞いていたので、喜んでむかえ、宰相に任じた。
あらたに活躍の場をえた呉起は、法律をあきらかにし、不急の官を廃し、公族であっても疏遠(そえん)な者は、資格を剥奪(はくだつ)した。
こうして財政を引きしめ、ひたすら戦士の養成につとめたのであった。
その施策は成功し、楚の国力はにわかに強大となる。
いまや楚は、東は越を圧し、北は陳(ちん)・祭(さい)の二国をあわせ、さらに韓・魏の兵を撃退し、西は秦を攻めて、その威勢を天下にほこった。
しかし呉起は、一方で公族たちのうらみを買っていたのである。
悼(とう)王が死ぬと、公族や大臣たちは乱をおこして、呉起を攻めた。
呉起は走って、悼王の屍殿におもむき、王の屍(しかばね)の上にうちふした。
乱入した徒輩が呉起を射ると、矢は同時に悼王の屍体に刺さった。
やがて大葬がおわり、粛王が即位すると、呉起を討って悼王の屍を射た者を、ことごとく誅殺(ちゅうさつ)した。
2 二人の軍師 top
さて魏の国においては、武侯のあとをうけて恵王が立つ。この恵王につかえて将軍となったのが、龐涓(ほうけん)であった。
龐涓は、鬼谷子(きこくし)について兵法を学んだ。
鬼谷子に関しては、いかなる人物なのか、その出身も正しい姓名も、まったくわからない。
山のなかに隠棲して学を講じ、その門下から多くの人材が輩出したという。
龐涓もその一人であったし、同門に孫臏(そんひん)もいた。
軍略家としての実力は、孫臏のほうがすぐれていた。
もとより龐涓も、自分の才能が孫臏よりおとることを知っている。
そこで、ひそかに使いをやって、臏をまねいた。
孫臏が魏にくると、龐涓はさまざまに画策し、これを無実の罪におとしいれた。
かくて孫臏が受けた刑は、両足の筋を切られ、額に黥(いれずみ)をほどこされる、というものであった。
刑余の片輪者となったからには、おもてだって人に会うこともできない。
たまたま斉の国から使者がやってきた。
孫臏は、ひそかに斉の使者と会って、身の上のことを語った。
使者は孫臏の人物をみぬいた。
そこで帰国するにあたり、こっそり自分の車に孫臏をのせて、斉につれていった。
斉の将軍の田忌(でんき)も、孫臏の才能をみとめ、賓客として待遇した。
田忌は、しばしば斉の公子たちと競馬の賭けをして遊んだ。
孫臏がみるに、馬には上中下の等級があるが、速力では大差がない。
そこで田忌にいった。「うんとお睹けなさい。かならずあなたを勝たしてさしあげましょう」。
このことばを田忌は信じ、王や公子たちと、千金を賭けて勝負することにした。
馬場にのぞみ、いよいよ馬をだす間際になって、孫臏はいった。
「あなたの下(げ)の馬を、相手の上(じょう)の馬と取り組ませなさい。
あなたの上の馬は相手の中の馬に、あなたの中の馬は相手の下の馬に、それぞれ取り組ませるのです」。
こうして三組の競馬がおわると、田忌は二勝一敗となって、王の千金を獲得した。
田忌は、威王に孫臏を推挙した。威王は兵法について問うた後、孫臏を軍師に取りたてた。
さて威王の二十六年(前三五四)、魏の恵王は大軍を発して趙を攻め、その都の邯鄲(かんたん)を囲んだ。
趙は斉に救援を求めた。そこで威王は、田忌を将軍とし、孫臏を軍師に任じて、趙の救援におもむかせた。
足の不自由な孫臏は、輜車(ししゃ=ホロ付の車で非戦闘員の乗用)のなかで、はかりごとをめぐらした。
いま魏の精鋭は、かならずや国外に出つくし、国内に残るのは老弱のものばかりであろう。
されば斉の甲は魏の都の大梁に急行し、街路に布陣して、魏の虚をつくがよい。
魏軍はかならず趙をすてて、自衛を講ずるであろう。この作戦を、田忌は採用した。
魏の軍は、はたして邯鄲を去り、本国に舞いもどった。
斉の軍は、これを桂陵でむかえ討ち、大いに破った。
魏の将軍は、ほかならぬ龐涓(ほうけん)であった。
それから十三年たった。すでに威王は死し、宣王の二年(前三四一)となっている。
こんどは魏と趙が連盟して、韓を攻めた。
韓は危急を斉につげ、斉は田忌を将軍として、またも魏の都に直進した。
これを聞いて魏の将軍の龐涓は、韓を去り、斉にむかった。
しかし斉の軍はすでに国境をこえ、魏の領内にはいっている。
ここで軍師の孫臏は兵法を説いていった。
「百里の遠きを、利につられておもむく者は、上将をうしなう。
五十里を利につられておもむく者は、軍のなかばが到達するのみ」。
この兵法を逆に利用しよう、というのであった。
魏の地にはいると、斉軍はまず十万の竈(かまど)をつくらせたが、翌日は五万にへらし、その翌日は三万にへらした。
龐涓は、斉軍を迫うこと三日、大いに喜んでいった。
「わが地に入ること三日にして、斉軍の士卒は過半が逃亡したぞ」。
そこで歩兵を捨て、軽装精鋭の騎兵ばかりをひきい、二日の行程を一日で急迫した。
孫臏は相手の行程を計算し、まさしく日没には馬陵に達するものと推定した。
馬陵は道がせまく、かたわらに険阻が多く、伏兵をおくには絶好の地である。
そこで大木の幹を白くけずり、「龐涓(ほうけん)、この木の下に死せん」と書いた。
かつ、弓の上手な者をえらび、一万の弩(いしゆみ)をそなえて、道をはさんで伏せさせた。
あらかじめ命じて、いわく「夜になって、火の光のあがるのを見たならば、いっせいに矢を放て」。
日が暮れて、はたして龐涓は、白くけずった大木の下についた。白い幹に字が書いてある。
火打ち石をたたいて、火をつけた。その字を読みだすやいなや、斉軍の一万の弩がいっせいに放たれた。
魏軍は大混乱におちいり、あいついで倒れた。さしもの龐涓も、おのれの知恵が窮し、軍の敗れたことを知った。
「ついに豎子(じゅんし=あの野郎)をして名をなさしめたか」。
そのまま龐涓(ほうけん)は捕らわれた。別の説によると龐涓は、みずから首をはねて死んだ、ともいう。
いずれにせよ、斉は勝ちに乗じて魏軍を全滅させ、太子も捕らえて帰った。
この大勝によって、孫臏の名は天下にあらわれ、その兵法は長く後世に伝えられることとなった。
3 孫武の伝説 top
兵法の書といえば、だれでも『孫子』の兵法をまず思いうかべるであろう。
ところで『孫子』の著者、あるいは孫子その人といわれてきたのは、戦国の世の孫臏ではない。
それより百年ほど前、呉の国に孫武という兵法家があった。
この孫武こそ、名高い孫子その人と伝えられてきたのであった。
司馬遷の『史記』によれば、孫武もまた斉の人であり、孫臏はその子孫であった、という。
そして孫武は十三編の兵法書(孫子)をあらわし、呉王の闔廬(こうりょ=夫差の父)に仕えた。
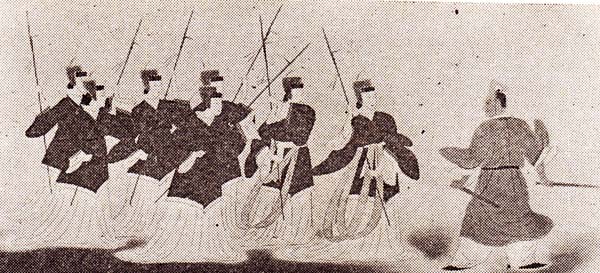
「孫子勒姫兵」安田靫彦 |
さて孫武が、はじめて闔廬に見(まみ)えたときのこと、王はいった。
「そなたの書かれた十三編は、ことごとく読んだ。ひとつ、実際に兵を動かして見せてくれまいか」。
「よろしゅうございます」。
「婦人をつかって見せてくれるか」。
「よろしゅうございます」。
そこで宮中の美女百八十人が召しだされた。
孫武は、これを二隊にわけ、王の寵姫(ちょうき)二人をおのおの隊長とした。
さて一同に戟(げき=左右に枝のあるホコ)を持たせ、命令していった、
「お前たちは、自分の胸と、左右の手と、背中とを知っておるか」。
「知っております」と、女たちは答えた。
そこで孫武はいった。
「前、と言ったら胸を見よ。左、と言ったら左手を見よ。右、と言ったら右手を見よ。後、と言ったら背中を見よ」。
女人たちが「はい」と答えたので、軍令を布(し)き、鉄鉞(まさかり)を用意したうえ、三たび軍令を示して、五たびこれを説明した。
そうして鼓(つづみ)をうち、「右ッ」と号令した。女たちは大いに笑うばかりであった。
孫武は「軍令があきらかならず、号令が徹底せぬのは、将たる者の罪である」といって、また三たび命令を示し、五たび説明した。
そうして鼓をうち、「左ッ」と号令した。女たちは、またも大いに笑うばかりであった。
孫武はいった「軍令があきらかならず、号令が徹底せぬのは、将たる者の罪である。
しかし、すでに軍令があきらかなるに、なお兵が号令にしたがわぬのは、隊長の罪である」。
たちまち左右の隊長を斬ろうとした。
呉王は台上からみていたが、愛姫が斬られようとするので、大いに驚き、あわてて伝令を発していわせた。
「もはや将軍が用兵の達人たることはわかった。わしは、この二人の女がいないと、何を食べても、うまくない。
どうか斬らないでくれ」。
孫武はいった、「私はすでに命を受けて、将となっております。
将たる者は軍中にあれば、君命をもきかぬことがあります」。
ついに隊長二人を斬って、みせしめとした。そして、その次の者を隊長とし、鼓をうって号令を発した。
女たちは、左に右に、前に後に、ひざまずくも起(た)ちあがるも、すべて規則どおりに動き、声をだす者さえなかった。
かくて孫武は伝令をもって王に報告した。
「すでに兵は整いました。こころみに王みずから台よりおりて、動かしてごらんください。
もはや王の意のままに、水火のなかといえども進んでまいりましょう」。
しかし呉王は、あえて台からおりようとはしなかった。
孫武はいった、「王は、いたずらに議論をこのまれるばかりなのだ。それを実地に用いることはできない」。
孫武にかんする話は、これが唯一のものであって、そのほかの事跡はあきらかでない。
後世の書物には、孫武という名も、孫武が兵法の書をあらわしたということも、記されていない。
そこで、孫武とは架空(かくう)の人物ではなかったか、また『孫子』は孫武の著作ではなく、むしろ孫臏(そんひん)の兵法をつたえたものではないか、と疑う学者が多くなった。
さらに『孫子』を、後世の偽作(ぎさく)である、と主張する学者もあらわれた。
そこまで否定しなくとも、学界では『孫子』が一人の著作ではなく、孫武から孫臏にいたって完成したものであり、春秋時代の末期から戦国時代に至る兵法を示したもの、という見解が大勢を占めてきたのである。
しかし一九七二年四月、山東省の一角(臨沂=りんき)において、前二世紀末ごろ、すなわち前漢時代の二つの墓が発掘されたところ、なかからたくさんの兵法書が出土した。
それには「孫子の兵法」と「孫臏の兵法」との両者がふくまれていた。
孫子といわれる人と、孫臏とは、はっきり別人であることが、これによつて証明された。
やはり「孫子の兵法」は孫武の著作であり、それとは別に「孫臏の兵法」があったのである。
また孫臏は、孫武の孫にあたるらしいこともわかった。
このように、二千年以上も前の古い書物が発見されたというのは、まことに驚くべきことである。
この内容の大略については、一九七四年三月に発表されたが、研究がすすめば『孫子』にまつわる従来の疑問も、はっきり解明されるであろう。
4 孫子の兵法 top
戦争は国家の重大事である。死活の決まるところ、存亡のわかれ道である。
事前に、よくよく熟慮してかからねばならない。
このように『孫子』は、その冒頭において説いた(計編)。
「孫子いわく、兵は国の大事、死生の地、存亡の道、察せざるべからず」。
またいわく、「兵とは詭道(きどう)なり」。つまり戦争とは、謀略の争いだ、というのである。
そうして開戦したとなれば、戦車千台、輜重(しちょう)車(輸送用の馬車)千台、武装兵十万を、千里の外に派遣して、その糧食を送らねばならぬ。
そこで内外の経費、賓客の接待費、膠(にかわ)や漆(うるし)の材料から、戦車や武器の供給など、一日に千金をついやして、はじめて十万の軍隊をうごかすことができるわけである。
「ゆえに、兵には拙速を聞くも、いまだ巧久(こうきゅう=うまくて長引く)を睹(み)ざるなり」。
ひと時代まえの戦争は、戦車による射戦が主体であった。
軍隊の大きさは、車の数(乗)であらわされた。
万乗といえば天子の、千乗といえば諸侯の軍隊であった。
そして春秋時代までは、歴史に残るほどの大戦争であっても、各国の動員量はせいぜい数百乗にすぎない。
戦闘の主力は馬車に乗った貴族であった。それに歩兵が十名ほど従っていたのである。
ようやく春秋時代の後半になって、しだいに歩兵が重要視されるにいたる。
歩兵による密集戦法を活用し、大いに効果をあげたのが、南方の呉や越であった。
呉は一万の歩兵部隊を動員したという。
河川や湖沼の多い呉越の地では、戦車をもちいることもほとんど不可能であった。
しかも呉越の強勢にしげきされて、歩兵による作戦は、たちまち中原の諸国に普及してゆく。
武器の変革もめざましかった。かつては銅製の矛(ほこ)や剣が主としてもちいられていたが、戦国時代には鉄器の発明と普及によって、鉄製の鋭利なものがもちいられる。
弓矢もまた、弩(ど=いしゆみ)と呼ばれる発射用具の発明によって、射程がいちじるしく長くなった。
威力も倍加した。車上の射戦は、弩の出現によって効力をうしなった。
こうして戦闘の初期、ひとつの合戦に動員される兵は十万に達する。
もはや貴族の従臣だけでは補充がつかない。
一般の農民が駆りだされ、大群の歩兵部隊が編成されたのであった。
戦車ならば、その活動の範囲は、地形によって限定されよう。
しかし歩兵の部隊ならば、山林でも沼沢でも、自在に、神出鬼没の活動をすることができる。
「兵は詐(さ)をもって(意表をつくことによって)立ち、利をもって動き、分合(分散と統合)をなすものなり。
故に、その疾(はや)きこと風のごとく、その徐(しず)かなること林のごとく、侵掠(しんりゃく)すること火のごとく、動かざること山のごとく、知り難(がた)きこと陰(いん=くらやみ)のごとく、動くこと雷(いかずち)の震うがごとし」。
「敵の近くして静かなる者は、その険を恃(たの)むなり。
遠くして戦(たたかい)を挑む者は、人の進むを欲するなり、その居る所のみなる者は、利するなり(こちらを誘い出そうとする)。
衆樹の動く者は、来(きた)るなり。衆草の障の多き者(積み上げて壁のようにしてある)は、疑(留まっていることを偽装する)なり。
鳥の起(た)つ者は、伏(伏兵)なり。
獣のおどろく者は、覆(ふく=奇襲)なり。塵の高くして鋭き者は、車の来るなり。
卑(ひく)くして広き者は、徒(歩兵)の来るなり」。 |
このような『孫子』の兵法は、中国のみならず、わが国の軍学においても、最高の典籍(てんせき)とされた。
しかも『孫子』は、実戦の用兵のみを説いたのではない。
実戦の体験より発して、それは高度の戦争論となり、さらには深遠な人生哲学ともなった。
孫武そのひとが軍師としての名声におぼれることなく、内省をかさねた結果でもあったろうか。
「彼を知り、己(おのれ)を知れば、百戦して殆(あや)うからず。
彼を知らずして己を知れば、ひとたびは勝ち、ひとたびは負く。
彼を知らず己を知らざれば、戦うごとに必ず殆うし」。
「百戦百勝は、善の善なるものにあらざるなり。戦わずして人の兵を屈するは、善の善なるものなり」。 |
たしかに、戦争という手段にうったえることなく、国家の意思を実現することができるならば、それは最善の道であろう。
それは外交である。弁論によって有利な外交をすすめようとする者が、やはり同じ時代にあらわれていた。
5 弁舌の使徒 top
戦国の世の外交家としては、まず張儀(ちょうぎ)の名があげられよう。
張儀は魏の人で、孫臏(そんひん)と同じように、鬼谷子(きこうし)の門にはいった。
そこで外交の術を学んだという。学業をおえると、諸侯に遊説して歩いた。
あるとき楚の大臣からご馳走(ちそう)になったが、たまたま大臣の宝玉が紛失した。
大臣の家来たちは、張儀が貧乏で品行もよくないというところから、ぬすみの疑いをかけた。
そこで張儀をとらえ、笞うつこと数百、それでも白状しなかったので、ついにゆるされた。その妻が、
「ああ、あなたが読書や遊説などしなかったら、こんな恥辱(ちじょく)も受けずにすんだろうに」
と嘆くと、張儀はいった、「おれの舌を見てくれ。まだ、あるか、どうだ」。
妻が笑って、「舌!? ありますよ」というと、「それならいい」 といった。
やがて張儀は、秦へおもむいた。秦は恵文王の代であった。
うまく恵文王に取りいって用いられ、思うままに腕をふるうにいたる。
張儀がめざしたものは、外交の力によって中原の諸国を秦の威勢に従わせる、というところにあった。
それは諸国が秦に対して横に同盟をむすぶ、実質においては秦の配下に立たせる、というものである。
これは連衡(れんこう、衡とはヨコの意)の策と呼ばれた。
ところが連衡に対しては、合従(従とはタテ)の策があった。
秦の国力に脅威(きょうい)をおぼえはじめてきた諸国が、縦に同盟を結んで共にあたろう、とするものであった。
それを張儀は、得意の弁舌をもって、つぎつぎに諸国の合従をくずしつつ、連衡の策をすすめてゆく。
まずねらったのが、生国たる魏であった。
秦の恵文王の十年(前三二八)、張儀は兵をひきいて魏を攻め、蒲陽(ほよう)を占領した。
それから秦王に建言して、蒲陽を魏にかえし、さらに秦の公子を魏にいれて人質とした。
そうしておいて魏王のもとにいたり、秦に返礼すぺきことを説く。
魏は、上郡と少梁(共に黄河の西方にあり)を秦におくって、感謝の意をあらわした。
その功によって張儀は、泰の大臣に任ぜられたのである。
こうして張儀は秦の大臣たること四年、そのめざしたところは、魏を完全に秦の勢力下におくことであった。
しかも魏がなびかぬとみるや、秦の大臣を辞して魏に乗りこむ。
そして魏の大臣となって、秦に臣事させることをはかった。
こうして張儀は魏の大臣たること四年、その間に魏の襄王が亡くなり、哀王が立った。
しかし襄王も、哀王も、秦に臣事することは承服しない。
よって張儀は、ひそかに秦と通謀して、秦の軍を国内に引きいれた。
秦軍はおおいに魏の軍を破ったうえ、ついで韓を攻めて、首を切ること八万におよんだ。
その威力に、諸国はふるえあがった。
ここで張儀は哀王に説いた。得意の弁舌によって、ついに哀王を説きふせた。
魏は秦に対して和睦を請い、張儀は秦にかえって、ふたたび大臣の地位についた。
ついで張儀がめざしたのは、斉と楚との合従を破ることである。
張儀はみすがら楚におもむいた。時に恵王の二十五年(前三一三)である。楚は懷王の代であった。
張儀がくると聞いて、懐王は下におかぬ歓待を示す。張儀は懐王にむかって、おもむろに説いた。
「大王が私のことばを聞きいれ、関所をとじて、斉との合従の盟約を絶たれるならば、私は秦の商於(しょうお)の地(かって商鞅の封ぜられた所)六百里を大王に献上し、秦の王女を大王のおそば仕えの妾といたすよう、取りはからいましょう。
かくて秦と楚は、ながく兄弟の国となるでありましょう」。 |
懐王は喜んで承諾し、群臣もみな慶賀した。ひとり硬骨の士(陳軫=ちんしん)が、かえって秦と斉とが同盟する結果になろうと懸案し、反対したが、懐王は取りあわなかった。
張儀に大臣の印綬をさずけ、斉と断交した。
ところが張儀は秦に帰ってから、負傷したと称して三ヵ月も王宮に参朝しない。
懐王は、張儀の機嫌を取り結ぼうとして、勇士を斉に送りこみ、無礼を働かせた。
斉王は大いに怒り、これまでの節をまげて、秦に膝を屈した。こうして秦と斉とが結ばれた。
もとより張儀は、懐王との約束を実行する気はない。
楚の使者に対して、自分の領地六里を献上しよう、と申しいれた。
これを聞いて懐王は怒り、兵を発した。
秦と斉は、共に楚を攻めて、首を切ること八万、その北方の要地をうばった。ついに楚は和を請うた。
和議が成ると、楚の懐王は張儀の身柄の引きわたしを求めた。
かつての食言をうらみ、とらえて殺そうと思ったのである。張儀は平然として楚におもむいた。
はたして捕えられたが、このたびは楚の権臣や、懐王の愛妾をだきこんで、たちまち身柄を釈放させることに成功した。
そのうえで、ふたたび懐王に説く。
たくみな説得は、またしても懐王の心をとらえ、秦と楚との和親を促進させた。
このとき屈原が反対したが、懐王は聞きいれなかった。
楚からの帰路に、張儀は韓によった。そして韓王に説き、秦につかえることを承服させた。
この後も張儀は、斉にゆき、趙にゆき、また燕にゆき、いずれも秦につかえることの有利を説得する。
こうして連衡の策は見事に成ったのであった。
しかし任務をはたして張儀が秦に帰ったとき、すでに恵文王は死んでいた。
ついで立った武王は、太子の時代から張儀がきらいであった。
群臣も、張儀のことを悪(あ)しざまに申したてた。
いまや形勢はまったく不利である。
張儀は武王にむかって、身を引いて魏におもむこうと申しいれた。
自分が魏にはいることによって、魏と斉とを戦わせ、そのすきに秦が韓を討ち、かくて王者の業を達成するがよい、と説いたのである。
武王は兵車三十乗をそなえて、張儀を魏に送りとどけた。
張儀は魏において大臣たること一年、無事にその生涯を終えた(前三〇九)。
6 合従(がっしょう)と連衡(れんこう)
top
合従(がっしょう)か、連衡(れんこう)か、いずれにしても戦国時代の群雄のなかで最強の国に成長した秦を対象とするものであった。
こもごもの立場、それぞれの思わくから、あるいは合従によって結ばれ、あるいは連衡によって国の安全をたもとうとした。
ところで連衡の策を推進した代表者としては、張儀の名があげられる。
これに対して、合従の策の代表者としては、蘇秦(そしん)の名が伝えられてきた。
すなわち蘇秦と張儀は、ライバルの外交家として併称されてきたのである。
蘇秦は周の都の洛陽にうまれ、張儀と同じく、鬼谷子(きこくし)について外交の術を学んだという。
その後、放浪すること数年、困窮したあげく、洛陽に帰ってきた。
兄弟姉妹も妻妾たちも、みな嘲笑(ちょうしょう)していった。
「周の習わしでは、田畑を耕したり、商工に励んだりして、利益をあげることが務めとなっているのに、本業をすてて口さきの議論ばかりやっているんじゃ、苦しむのもあたりまえさ」。
これを聞いて発憤(はっぷん)した蘇秦は、一室にとじこもって読書にふけり、一年にして人を説得する術を案出した。
その術をもって諸国の王に対し、合従の策をとなえたのである。
燕にゆき、趙にゆき、韓にゆき、魏にゆき、さらに斉にゆき、楚にゆき、それぞれの国情に応じて、たくみに諸侯を説得してまわった。
これらの諸国の土地を合すれば秦の五倍、軍勢を合すれば秦の十倍にあまる。
もし六国(りっこく)が合従して、ひたすら力をあわせ、心を一にしたならば、かならず秦のわざわいを避けることができるであろう。
連衡の論者のごとく、西にむかって秦に仕えるのは、まさに国の恥である。
この議論は諸侯の心をうごかした。ついに六国は、蘇秦の意見にしたがって縱に同盟し、秦に対抗するにいたった。
いまや蘇秦は従約(しょうやく)の長となり、同時に六国の宰相を兼任する。
その洛陽を通過したとき、諸侯は使者を発して贈りものをとどけ、王者の行列とみまがうほどであった。
周の顕(けん)王(前三六八〜三二一在位)も恐縮(きょうしゅく)して、沿道の往来をとどめ、使者をして郊外まででむかえさせた。
兄弟も、その妻たちも、目をそばめて仰ぎみることもできない。そのありさまに、蘇秦はいった。
「前には、あれほどいばっていたのに、どうして今は、こんなにもうやうやしいのか」。
すると兄嫁は身をかがめてうちふし、顔を地につけ、わびていった。
「あなたの位が高く、金の多いのを見たからでございます」。
蘇秦は嘆息していった、「同じ一人の身でありながら、富貴となれば親戚も畏伏し、貧賎となればあなどられる。
他人であれば、なおさらであろう。もし私が洛陽の郊外に二町ほどの田地を持っていたならば、今日のごとく六国の宰相たることが、できたであろうか」。
そこで蘇秦は千金を散じて、一族や友だちにほどこした。
ともあれ蘇秦の主唱によって、合従(がっしょう)の策は成ったのである。
六国(りっこく)が同盟すれば、秦も手出しはできない。
そこで秦としては、どうにかして合従の盟約を破ろうとする。連衡の論者が、その間に活躍した。
秦は、斉と魏とに働きかけ、両国をそそのかして、趙を討たせた。
両国の兵をうけると、趙王は蘇秦を責めた。蘇秦はおそれて趙を去り、燕におもむいた。
斉に報復するため、というのが、その名目であった。こうして合従の約は、たちまちにして破れた。
この後の蘇秦は、燕と斉との間を往復し、いずれの国においても優遇はされたけれども、もはや往年の名望はなかった。
その最後も悲惨である。晩年の蘇秦は、斉において大臣の地位にあったが、大夫たちからきらわれた。
ついに刺客をさしむけられ、瀕死(ひんし)の重傷を負った。
刺客は逃亡し、斉王の命令による探索にもかかわらず、とらえることができない。
死のまぎわに、蘇秦は王に言上した。
「私が死にましたら、車裂の刑に処して市場にさらしてください。
そして蘇秦は燕のためをはかって斉に謀叛(むほん)した、と触れてください。
そうすれば、かならず賊は抑えられましょう」。
その通りにしたところ、はたして下手人があらわれた。褒美(ほうび)をめあてに自首して出たのである。
斉王は、それを捕えて誅した。
蘇秦の物語は、むかしからすこぶる有名である。しかし、これは実際にあったことなのであろうか。
司馬遷も、蘇秦の伝記を述べたあと、つぎのように論じている。
「蘇秦らの術に権謀と変詐(へんさ=いつわり)に長じていたが、蘇秦に反間(スパイ)の名を負うて殺され、天下の者は共にこれを笑って、その術を学ぶ者をきらった。
しかも、世に蘇秦について言われるものには、異説が多い。
これは時代の異なる類似事件を、みな蘇秦に付会(ふかい)したのであろう」。 |
いったい蘇秦その人が、実在の人物であったのか、うたがう者もすくなくないのである。
蘇秦が活躍した時期(前四世紀の後半)、秦の勢力は他の六国を圧するほどに強大とはなっていなかった。
したがって六国が、秦を対象として合従しなければならぬ必然性はなかった。
ほかの記録に徴してみても、この時期に合従の約がむすばれたという形跡は、みあたらない。
やはり蘇秦と、その合従の策は、架空の物語であったのではないだろうか。
かりに蘇秦が実在の人物であったにしても、その出現は張儀よりも後のこと(前三世紀の初め)であったに違いない。
この時期ともなれば、すでに秦は群雄のなかで最強をほこり、諸国はその東進に悩まされていたのである。
合従にせよ、連衡にせよ、秦を対象とする外交の秘策は、こうしてめぐらされるようになったものと考えられる。
もはや戦国の群雄のうち、強国とみなされるものは、秦と、他の六国にすぎなかった。
あわせて戦国の七雄という。
そして七雄の君主は、いずれも周の王室をしのいで、みずから「王」を称するにいたっていたのであった。
top
**************************************** |