|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
|
18 校長が殺したか |
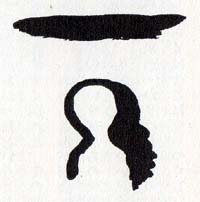 |
電報――この頃、かろうじて救いあげられた遭難者たちは、疲れきってむなしい頭の底にそのことを考えていた。
仲宗根正男は鹿児島市にとどけられると、いきなり隊列をはなれた。
おんボロの服をまとい、やけた皮膚にハダシのまま、眼だけをギラギラさせて、彼は郵便局をさがそうと考えた。
釣道具を売る店があって老婆が店番をしていた。
彼が郵便局への道をきいても老婆はけげんな顔で、この異様な少年をみつめるばかりであった。
仲宗根は癇癪(かんしゃく)をおこして、「標準語もわからんのか」と怒鳴った。 |
標準語教育の徹底した沖縄をはなれた少年が、はじめて他府県で体験した奇妙な対話であった。
ようやく郵便局をさがしあて、頼信紙をもらった。
無事着いた、とあからさまに打電することが禁じられていることを知っていたから、「〇オクレ」と書いて窓口に出すと、それを一瞥した局員は、「これは、打てません」と断わった。
なぜ打てないのか不満であったが、反問をせずに葉書を求めた。
「○月○日、無事に着きました。毎日、一緒う懸命やっています。山里、小那覇、真栄城の三人は惜しかった……」
そこまで書いて手をとめた。
そんなことを書いてはいけないという自覚が、彼の体をしめつけた。
そこで、「山里」からあとを丹念に消しはじめた……。
沖縄では、船出の日には出船「ンジフニ」の祝いをやる。
つまり船を送ったあと、航路の平安を祈るために、その家には一家、親族、知人が集まる。
だんじゅ かりゆしや
いらで さしみせる
船の綱とれば 風や まとも |
めでたい日をえらんだ
この船出
船の綱を とけば 風は はや まともに |
静かな中にも敬虔な祈りをこめた旋律のこの歌をうたう。
老婆などは針突「手の甲のいれずみ」をした手をたたいて和する。
船出から三日目、またつどいがある。無事に目的地に着いた祝いである。
三日の航程といえば薩摩の山川港であろう。
つまりこの三日の祝いは、王朝時代の「大和上り」「本土へ行くこと」の名残りである。
奇しくも、今度の疎開船も目的地はこれと似ていた。
三日の祝いまでには、無事に目的地に着いたという通信を受ける。
そしてその時には、乏しいなかでもどうにかメリケン粉や油を用意して、三日の祝いをしようという素朴な願いを家族たちは抱いていたのである。
こうしたある日、那覇国民学校の疎開学童、金城春子の家で、母が仏壇に茶をささげようとすると、丈夫な湯のみが割れた。
手から取り落としたものではなかったので、母はこのことが気になった。
名城妙子が金城春子と気まずい思いで永久の別れをしたときと、どちらが先であったかはわからない。
「おたくは電報きましたか、うちは、まだこないですけど」「どうしたんでしょう」こういう会話が学童を送った家庭どうしで交された。
同じ日に那覇を出ていながら、電報の来たところと来ないところがある。
このことは、疎開学童の家庭に大きなショックをあたえた。
ほんの数日前に、ひとつながりの感情で子供たちを送った留守宅が、三つの紋様に分けられてゆらいだ。
電報をうけた家の子は、元気で着いた。電報をうけていない家の子は船と運命をともにしたか、それとも海の上で救いを待っているか――。
そして対馬丸に乗った者のほとんどの留守宅が、電報を受取っていなかった。
八月二十三日朝、沖縄県特別援護室の中原知光は、いつものように出勤した。
出勤するなり、暁部隊「第七船舶輸送隊」司令部の大尉に呼ばれた。大尉は、軍に接収された沖縄製糖社宅にいた。
中原は、朝のさわやかな空気を吸いながらそこへ急いだ。
社宅の玄関に立ち案内をこうと、大尉の当番兵はいったん奥へ消えたが、やがて姿を現して、あがるように言った。
「お早うございます」
中原は、ていねいに挨拶をして部屋へはいった。
ところが中原は、自分のこうした挨拶にすぐに応えてくるはずの大尉の声が今朝はなく、自分の声がそのままつっ走って部屋の壁にくだけるのを感じ、首をかしげた。
大尉は机の前に両手を腰にあてがって立っていた。軍刀をはずした丸腰にバランスを失なったおかしさがあった。
中原はそれに苦笑しようとしたが、唇から微笑はすぐに消えた。
大尉の体には、中原の親しみをこめたまなざしをはねかえすような、不思議な緊迫感があった。
「およびだそうですが……」
中原は、もう一度声をかけた。
「ああ」
大尉はうなずいて、やっと椅子をすすめた。
椅子に腰をおろすと、中原は大尉の言葉を待った。
しかし、大尉はなかなか口をひらかない。中原はいらいらしてきた。
こういう緊迫感はまっぴらだと思う。叱るなら、はやく叱ってくれたほうがいい――
中原がうわ眼づかいに大尉に視線をおくったとき、
「実は……」
大尉が口をひらいた。
「はあ……」
「これから話すことは絶対秘密だ」
「はい」
軍との話には秘密という言葉がつきものだ。中原は、またかと思った。
「疎開船がやられた」
「えっ」
中原は、自分の耳をうたがった。
反射的に聞きかえそうとする中原の眼に、大尉の苦痛の表情が走った。
中原は冷水をぶっかけられたようになった。
「疎開船が……やられた……んですか」
中原はふるえる声で、ようやく、それだけ言った。
「一隻、沈没した」
「どちらのほうですか……なに丸……」
確かめようとする中原の声をおしつぶすように、大尉の声が重なった。
「わからない。とにかく一隻やられた。情報はそれだけだ」
きっぱりと言いきる大尉には、いまさきの苦痛の表情はなく、軍人らしい硬質なものになっていた。
「これは大変なことになった……」
中原の体に次第に焦燥感がひろがり、彼は落着きを失なった。どうしようという、次に考えるべきことも浮かばなかった。
「もしも……」
中原は、やっと自分の言うべき言葉の端をつかんだ。
「もしも、学校から問いあわせが来ましたら、校長にだけは、知らせておいてもいいでしょうか」
「いかん!」
大尉は、はげしく叱りつけるように、
「絶対に秘密だ!」
「では……」
何と答えたらいいか――中原の頭は混乱する。
「問いあわせがきたら、まだ情報がないからわからない、と答えておいたらいいだろう」
「はい」
中原は力なくうなずくよりほか仕方がなかった。彼は一礼して大尉のもとをはなれた。
事務所へ戻ると、
「大尉の御用は何でしたか」
同僚の一人が声をかけたが、それに答えず、自分の席にすわると、用もない用紙をひろげたりした。
「何か情報でもあったんですか」
向かいがわの席から声がかかった。はじかれたように中原は顔をあげたが、すぐに用紙に眼をおとすと、平静をよそおって。
「何にもなかったよ。つぎの疎開のちょっとした連絡だけ……」
答えたが、中原はおれの声はふるえていると、はっきり感じていた。そして、この重大な秘密をおなじ仕事をしている同僚たちに、そのまま黙っていていいものだろうかと、しだいに息苦しくなってきた。
知事には、いちおう報告しよう、と思ったが、こんなとき室長さえいてくれたら――中原は疎開地調査のために本土へ出張している浦崎純室長のことを考えた。
本部国民学校の教務主任新里清篤は、体がだるくてかなわなかった。
風邪をひいたのでもないし、また、どこといって痛いところもないのに、体の具合が普通でなかった。
養母と妻、そして三人の子供たちを対馬丸で疎開させ、がらんとした家に一人残されていると、気も滅入るものだ。
そのことが原因になって、柄にもなく憂欝になっている。
体のだるいのもそのせいだろう――日頃から、あまり物事に頓着しない自分を知っている彼は、そう思っていた。
ある日、彼は対馬丸が遭難したという噂を聞いた。
那覇から二十里余りも離れているこの本部(もとぶ)町だが、そのような情報が届くのに、それほど時間はかからなかった。
新里は胸にひびくものがあった。これは単なる噂ではない。確かな情報だと直感的に感じるものがあった。
彼は名護へ走った。そして、憲兵分隊の玄関をはいった。
「先生、どうしたんですか」
いっも磊落(らいらく)な新里にしてはめずらしく緊張した顔であるのを見た憲兵の岸本本秀が、椅子から立ちあがった。
「実は岸本君、お聞きしたいことがあるのだが」
「なんですか」
「私の家族は疎開したのだが……」のまえの対馬丸で……」
岸本の顔が一瞬くもるのを、新里は見のがさなかった。
「対馬丸が沈んだってこと、本当か」
「対馬丸が……そんなバカな!」
岸本は笑ってそれをうち消そうとしたが、そのこわばった表情をどうすることもできない――新里にはそう見えた。
「自分は、まだ何も聞いていません」
「本当に、まだ何も……」
気負いこんでたずねる新里の言葉を途中でおさえて、
「分隊長にきいてみましょう」
と、岸本は立ちあがった。
しばらくして、岸本は分隊長をともなって現れた。
「やあ新里さん」
分隊長は大股で近づいてきたが、
「どこでそんな話をききましたか? デマですよ。そんなことありません。
あるのでしたら、こちらにも情報ははいるはずです」
「そうですか」
「あまり、御心配なさらないほうが、いいですね」
新里は分隊長の言葉をそのまま信じようと思った。
だが、あの噂をきいたときの直感と、岸本の表情、分隊長の言葉の裹にひそむものを結びあわせると、対馬丸は本当に沈んだ、ということしか感じられない。
憲兵隊を出て一人になると、急に悲しみがおしよせてきた。
「母も、千代も、清好、清秀、清子、皆死んだ……」
垣花(かきのはな)国民学校の父兄たちは、疎開学童が目的地に着いたらしいという噂に祝賀会をやった。
しかし「どうもおかしい。何故なら、子供たちから着いたというはっきりした知らせはない」
首をかしげる父兄がでてきた。
そういえば電報をうけたという留守宅は、対馬丸と同じ日に出た和浦丸、暁空丸に乗り組んだ子供たちの家である。
垣花の父兄の一人宮里雄喜は、日頃知りあっている県庁の真栄平課長にあった。
「どうも様子が変だ。やられたらしい」と真栄平は声をひそめて言った。
宮里は、飛ぶようにして家に戻った。そして妻を呼んだ。
「対馬は、やられたらしい」
「えーッ」
顔色をかえる妻を叱りつけるようにして、
「取り乱すな!」
と言ったが、はらわたが煮えくりかえるような苦痛に、宮里自身、懸命に耐えていた。
兵隊たちから何となく洩れてきた情報に、しだいに裏打ちが厚くなってきた。
学童を送った家庭が、いよいよいらだった。いらだたしさがざわめきにふくれた。
だが、このざわめきには一種のベールがかけられていた。
時局――防諜という眼に見えないものがざわめきを牽制していた。
疎開学童を送っていない市民たちにも、ざわめきは充分感じられた。
しかしそれは、ちょうど無声映画のそれのように、声にならない人間たちの激しい動作に似ていた。
もし、そのかけられたベールを一針つついたら、その孔から埋まっていた声が、いちどきにどっと奔流しそうな、そんな感じのものであった。
垣花国民学校の区域は漁師が多い。渡久地政功校長は、ある日、通りを歩いていて、一人の漁師に出会った。 |
 |
疎開させた学童の親であった。渡久地は身を切られる思いでいると、漁師から親しげに肩をたたかれた。
「元気を出してくださいよ。校長が、そんなでは、どうかと思いますね。それより家へ来ませんか。
今日は大漁で、いい魚がとれました。刺身でも食べながらお話しましょう」
渡久地は、意外な応待におどろきながら、その好意をうけることにした。
しかし、漁師の家へついて、刺身が食卓をかざり、配給の酒が出て酔いがまわった頃、あかがね色の肌をもった骨太の漁師は号泣した。
「運がよければ帰ってきますよ、ね、校長先生……」
八月二十五日、那覇国民学校長の渡嘉敷真睦は奥村視学から「疎開船がうまくいかなかったらしい」との内達をうけた。
「沈没したのか」と問い返すと、「それはわからない」との返事であった。
渡嘉敷の内部で、重苦しい責任感と僥倖への期待とが、はげしくせめぎあった。
その暗い表情の前に、やがて疎開学童の父兄のひきしまった表情が、いくつとなくおしよせてきた。
「校長先生、うちの子供はどうなったんでしょう」
父兄の言う言葉はきまっていた。
「はっきりした発表もありませんので……」
校長の答えるべき言葉もきまっていた。
この簡単なふたつの言葉が、いくたびともなく交された。
父兄の言葉には、自分の愛する子供政ことだけしかなかった。
そして、校長の答えには、自分の力ではどうにもならない事件、それにたいして、はっきり返事をすることもできない、結局何にもわかっていない――そのもどかしさが、激しい苦悶になってよどんでいた。
「せんせい! うちの子供は死んだのでしょうか」
校長の家に鳴咽の声がみちた。
「おそれていた事態がとうとうやってきた……」
教育者渡嘉敷真睦は、巨大な体躯を泣きわめく父兄の前にちぢめて苦しんだ。
「お母さん、子供さんは、きっと、どこかの島に、無事に着いていますよ。それを信じて神さまに祈って……」
と言いたかった。
しかしこのさい、このような気休めを言う余裕はなかった。
彼は父兄を前にして、父兄と一緒に泣くよりほか、すべがなかった。
島のあちこちで思いがけない対決が生まれた。
校長対父兄――その双方がひとしく子供たちへの愛情をにぎりしめ、そのために理解しあおうとつとめながら、ともすれば憎しみにまでおちこむ危機をはらんでいた。
しかもそれは、彼らだけの問題ではなかった。
その奥にひそむものは、必勝を叫びながらも、事実敗れつつある戦争、滅亡にむかいつつある自分たちの運命を見つめる島じゅうの人々の絶望と願望とであった。世間の関心が一挙にここに集まった。
「うちの子供を殺したのは、あなただ!」
「校長先生がすすめなければ疎開はさせなかった。責任をとれ!」
このような激しい言葉が吐きだされたという話が、日々、街の人たちの間に広がった。
県庁庁舎のなかにも、何となくあわただしい空気がながれはじめた。
正確な情報が伝わらないままに、課長会議が事故を秘密にするよう決議したのだ、という噂が流れ、職員たちはあちらの部屋、こちらの窓ぎわに顔をよせあい、ひそひそ話しあった。
「校長先生が、大変だろうね」
「校長の住宅に父兄がおしよせて、子供を返せと、わめいているそうだ」
「日頃は気の弱い男が、毎日酒をのんでは暴れこんでくるのもいるという……」
「親ともなれは、それも仕方のないことだ。だからといって、校長に、なんの責任もない」
「あるさ。だって、すすめたんだろう。ほとんど強制的に」
「強制的ではなかったそうだよ」
「家に石を投げられて、とうとう夜逃げ同様に引越した校長もいるそうな」
県衛生課につとめる武富良松は、このような会話を耳にするたびに胸をえぐられる思いをした。
「俺は、いやがる息子を無理に疎開させた。俺は子供を殺してしまった……」
対馬丸の沈没は、もはや事実として、人々の胸のなかに影を落としていた。
それが決定的になるにつれて、激しい悔いと何者かへの怒りが彼らをせめた。
ただ怒りだけは、公然と口にすることができなかった。
top
**************************************** |