|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
|
8 今晩はあぶない |
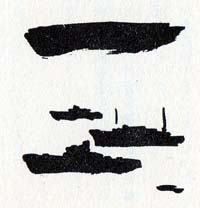 |
「無事だね」
「あすは着くかな」
二十二日の朝、引率教師たちは笑顔であいさつしあった。
あいかわらず曇りがちの天気で、乱層雲や積乱雲など夏型の雲が空の半分以上を覆い、時々スコールが通った。
台風は夜半のうちにいよいよ西に折れ、午前三時には沖縄の東南東七百五十キロメートルの海上で、七百四十五ミリメートル(九百九十三ミリバール)に発達していた。
浪のうねりが高かった。
船団の隊列は、砲艦「宇治」を先頭に和浦丸、暁空丸、対馬丸の順序、そしてしんがりを駆逐艦「蓮」がつとめたが、船団の速力は、台風のおかげでいっそう船足の落ちた対馬丸に合せなければならなかった。 |
駆逐艦「蓮」が、遅れがちな対馬丸につきっきりになった。
「宇治」の艦橋の口径十二センチ望遠鏡でのぞくと、和浦丸、暁空丸の二隻だけが見えた。
この調子では目的地鹿児島につくのに、定期船の二倍はかかると思われた。
朝、船室では船長西沢武雄と輸送指揮官の若い少尉とが議論をした。
西沢船長は四十八歳、日本郵船の外航船長で日米開戦の直前に交換船の船長をつとめたこともあった。
彼はこの頃日本近海がきわめて危険であることをよく知っており、常識としてジグザグコースをとるべきだと主張した。
「本船は半老朽で船足がのろいから、ねらわれたら危ない。ジグザグでさけるほかはない」
船長の意見は先例をふまえていた。
ひと月ほど前に宇品港をでて沖縄へむかった輸送船富山(とやま)丸は、この近海で直線コースをとって進んでいたのを、魚雷攻撃をうけて沈没した。
対馬丸と同じ型の日本郵船所有船で、そのときのせていた最新兵器の全部と兵隊四千五百人とがうしなわれた。
しかし、この意見に指揮官は承服しなかった。
「それでは到着がおくれる……」
ながい議論のすえ指揮官が船長をおさえ、船はほとんど直線にすすんでいった。
しかしやはり朝のうちに、疎開者の幹部は船室によばれ、指揮官から命令と注意をうけた。
「この近海が、この航路で最も危険な水域である。
昨日からたびたびいってある注意を厳重に守らせるよう。
今晩さえ無事にすごせば、きっと無事に鹿児島に着くことができる」
そこで、引率教師たちは、昼間全員に救命具のつけかたと退避のしかたを訓練することになった。
「この近海が一番危ないといわれる。今夜さえすごせば、あすは無事内地につく。
引率教師は今晩は眠らないで警戒してもらいたい」
田名(だな)は指揮官からいわれたとおり、大きな声で怒鳴った。
「だから、今夜は皆救命胴着をつけて甲板にねるようにする。
万一の場合は、船の傾いた方へとびこむ。わかったな」
ハイッと威勢のよい返事がひびいた。朝礼場の返事と同様、無邪気な反応であった。
田名はそれから、救命胴着のつけ方をおしえ、海のなかは冷たいから皆服をつけておくようにと強調した。
あいかわらず、裸の者が多かった。
田名は、手ぢかにいた学童から洋服をつけた者と裸の者をひっぱりだして、荷物の上にたたせ、皆に紹介した。
「こんな裸では、海のなかでじきに凍え死ぬぞ」
しかし、やはり裸は少なくならなかった。また救命胴着は、子供の体格には大きすぎた。
それをつけるとほとんど息ができない、と言ってはずしてしまうのもいた。
名城妙子は、学校の炊事婦から「ヒモを股の下からめぐらしてくくると、はずれないよ」と教えられ、そのとおりにした。 はたして、のちに海にほうりだされたあとも、それはゆるまなかった。
退避訓練もした。
船艙から甲板へ出るには、ふつうは板梯子が一つかけられているきりだが、他の三辺に縄梯子がかけられた。
「元気な者しだい、伝ってのぼれ」
しかし、板梯子ならともかく、縄梯子は全く不安定で、教師たちが下をつかまえていても、ブランブランして怖かった。
桃原信子(那覇市上之山校三年生)は、二、三段あがったが、こわくてやめた。
縄梯子を平気であがっていったのは、高等科の元気な者ぐらいだった。
船に酔(よ)った者も少なくなかったし、それに何より誰もがちっとも危機感をもっていなかった。
しかたなしに訓練をうけているといった感じが、大部分の者の態度にあった。
午後三時をまわったころ、友軍機一機が船団の上空に低く飛来し、旋回して去った。乗員の姿まで見えた。
「たのもしい!」
甲板で疎問者たちは、眼を輝かせて仰いだ。
ボートほどの大きさのフロートを機体の下に取りつけた水偵(すいてい=水上偵察機)で、奄美大島を基地にしていた。
午後四時頃、田名は左舷についている軍艦が、急速に前後に走るるのを見た。
いつもより少し動きがはやいとは思ったが、それがどうしたわけであるか、考えようともしなかった。
やがて、「敵潜発見一六○○」水偵の発した暗号電報である。
一六〇〇とは十六時、つまり午後四時のことだ。
むろん船団は知らず、受けた「宇治」では兵員各自に戦闘配置を命じた。
船団後方の警戒にあたっていた駆逐艦「蓮(はす)」の動きは急で、取舵(とりかじ)一杯、艦首を左にまわし、Uターンすると、水偵の姿を求めて、はるか後方の海に全速で突進して行った。 |
 |
水偵の空からの誘導によって海空一体で攻めたてれば、「蓮」の爆雷攻撃は決定的な威力を示すはずであった。
「宇治」ではそれを期待した。しかし、それはむなしかった。
日没ちかく、一度だけ「蓮」は爆雷を投じたが、「効果不明」との報告を「宇治」に送った。
水偵からは、「われ帰投す一七三〇」と打電してきた。
五時半に基地に戻ったということで日没ちかく、滞空時間にも限度があったから、索敵(さくてき=敵をさがすこと)を断念したのだ。
駆逐艦「蓮」もまた、老朽艦であった。
大正十一年の建造で、当時さかんに建造された二等駆逐艦の一隻だが、この艦種は近代的な艦隊行動に適しないとされ、今度の戦争がなければとっくに廃艦にされていたはずのものである。
東シナ海の船団護衛を任務にして海洋に出ていくと、海洋の荒波にメリメリと大きな音をたて、乗組員は今にも解体しそうな恐怖を覚え、出港ごとに今度は駄目かも知れないと覚悟をきめて出ていく、という有様であった。
無理はきかなかった。
そうしてこの時期、レーダー(電波探知器)を米海軍は持っていたが、日本海軍は持だなかった。
後部船艙にいた一般疎開者の新川正太郎は家族八人づれの父親であるが、若いころ騎兵で斥候にも出た元気者であった。
夕刻六時頃、左舷側のはるかむこうに潜水艦の潜望鏡らしいもののかたちをみとめた。
彼はそばにいた男に、それを報告してこいと、ほとんど命令するように言った。
その男は、船尾の砲座で娼婦たちとたわむれている兵隊のところへ行って、そのことを告げたが、「バカをいえ」と一言ではねつけられた。
今度は新川が行って同じことを報告したが、兵隊は相手にしなかった。
「なにも見えんじやないか」
「見張りはおれたちがする。きさまらが干渉することはない」
そして、なおも食いさがろうとする新川を、
「さがらぬと、たたっ切るぞ」とおどかした。
新川は、船艙にもどってくると、家族にこっそり言った。
「一大事だ。間違いないぞ。今夜はデッキに上っておこう」
しかし、妻は、前の晩も子供たちを甲板にねかせたので、
「二晩も夜露にうたせてはいけません」 と反対した。
新川はしかたなしに自分だけ甲板にもどろうとしたが、小学校にあがって間もない二人の子が、父親についてきた。
また、やはり一般疎開者として後部船艙に家族五名と一緒にいた宮城啓子(国頭村安波校四年生)は、救命胴着をもらって、六年生の兄壮吉々同じく四年生のいとこの時子らと、その大きさやら丈夫さやらをくらべあい、「私のは小さくて心配だな」などといったが、それでも甲板へあがれと命令されてあがるとき、「防空演習かね」などとしか言わなかった。
甲板にあがってみると、浪のうねりの高いのがみえた。
女学校二年生の姉の常子が、その遠くを指して弟妹たちにきいた。
「潜水艦にやられたら、ここからとびこんで向こうまで泳げる?」
指されたところには、白波がたっていた。
「たった百メートルだろう。できるさ」
六年生の壮吉は威勢よくこたえた。だが、四年生の啓子は「できない」とこたえた。
海も空も暗くなるし、少し不安がきざしてきた。祖母や妹たちが「どうしようかね、どうしようかね」とおちつかないふうにぼやいているうちに、それでも啓子は祖母のひざの上に眠ってしまった。
名城妙子は、金城春子と一緒に甲板に休んでいたが、夕方ちかくになって、
「機動部隊発見。見えなくなった。また見えた。警戒を要す……」
などと、緊張した声を断続してきいた。
「危ないのかしら」
「今晩は、なかにはいらないで、甲板で寝よう」
二人は話しあった。
だが、晩になってその甲板で寝たのは、名城妙子だけであった。
彼女は金城春子とちょっとした仲たがいをしてしまったのである。
この二人はもともと仲良しであったが、こうした女生徒のクラスにありがちな嫉妬をうけていた。
このときの仲たがいも、それがきっかけになっていた。
ちょうど夕食の飯上げの時刻であった。飯上げは分団長に班長が二名ついて勤めることになっていた。
金城春子が分団長で名城妙子は班長であったが、その日は名城の当番でないのに金城がさそった。
このとき名城は自分にヤキモチをやいている言葉を耳にしたので、「私は行かない」とすねた。
「誰が行ってもいいじやないの」と金城は、ヤキモチをやいた友だちへのあてつけ半分に腹をたてたが、名城はとうとう行かなかった。
配膳のころになって、名城は金城をさがしたが、見つからなかった。
怒ってどこかへ行ってしまったんだ、と思って名城は、夕食をとらずに一人で甲板にあがった。
名城はそこで夕暮れになって、船員室のあたりで犬と猫のはげしい啼き声をきいた。
それは、しつこいほど長くつづき、いかにも不気味であった。
彼女の背を、さむざむとした予感がなでた。
時々心配になって金城春子をさがしたが、どこにも見あたらなかった。
彼女はとうとう一人で寝た。
金城は一般疎開者のいる後部船艙のほうへ行ってしまったのだと、名城は上陸後にうわさをきいたが、それだけのことであった。
親友とのふとした別れであったが、それはこの時にはまだ宿命的な予感をともなわず、きわめて小さな事故にすぎなかった。
愉快にかけずりまわった仲間、ちょっとしたことで仲違いをする仲間たちの、小さな平凡な生活は、まだつづいていた。
そしてこの無邪気な乗客たちは、引率教師の話す注意をよく聞いているようでも、話を聞いている最中に、ひろい船のどこかへ行っていたり、ちょっとしたはずみに気が散ったりするので、こうした異常な場所で、少数の引率教師が八百人もの児童の気分を統制するのは、なかなか難しいことらしく、「甲板にあがって寝るように」という指示がなかなか徹底しないようであった。
佐久川和子たちは「今夜は甲板で寝てもよい」と聞いたつもりで、よろこんで甲板にでた。
仲宗根正男たちは、どれほどか暑い船内からはいだして寝たかったが、ついにそんな許しがでないものと、その夜も船艙でがまんして寝た。
桃原(とうばる)信子は、ついている母と一緒にいったんは甲板にあがったが、夜露にうたれてはいけないというので、また船艙におりて寝た。
高等科生の具志清興は生来のんきな性格で、前の晩も船内で寝ろと言われたのをきかずに甲板に寝たが、この晩もべつに命令を聞いたわけでもないが甲板で寝た。
彼は、あまり誰とも口をきかず、裸で救命胴着もっけずに寝た。
八百人そこらの学童と教師のうち、甲板に出て寝たのは、おそらく三分の一にも満たない二百人ぐらいだったとおもわれる。
那覇国民学校の岸本幸勇、嘉手川重幸の両教師が協力して追いあげた高等科生が多かった。
しかし、それだけの人数でも、甲板はほとんど足の踏み場がなかった。
甲板には、一坪半ぐらいのイカダがたくさんあったので、学童たちはそのイカダを通路にもハッチにも、いっぱい敷きひろげて寝揚所をつくっていたが、二百人が足をのばして寝るだけの広さはなく、皆膝をかかえるようにして、寄りあいもたれあって寝ていた。
かりに八百人が命令を守って甲板に上って寝ようにも、無理なことであった。
田名はそれでもやはり気になって、船内をひとまわりしてみた。
夜になると船内は遮蔽された灯がポツン、ポツンとついているだけで、とても全体を充分に見きわめることはできなかったが、船艙に残った者は、広くなったと手足をのばして寝ているようであった。
そこには危険にたいする警戒心がみじんもなかった。
田名(だな)は、叱って甲板にあげようかと思ったが、思いとどまった。
甲板にあげても、もうはいりこむ余地はないと思いついたのである。
暗さは暗し、足許には人の身体がつまって歩きにくいし、田名は今夜はこれ以上の命令、連絡はできないと断念した。
学童や引率教師がそれぞれの処置を講じているものと、期待するほかはなかった。
彼は自分の家族を甲板に移したが、母と妻と八歳になる長女との四人の家族をいれる余地がみつからず、ようやく船首楼にのぼるタラップの下に小さな隙間をみつけて、そこにひそんだ。
しばらくして、兵隊が砲の手入れにやってきたが、彼らは、
「この船は満州からくる途中も、玄海灘で魚雷を二発くらったが、二発とも不発でした。なかなか運のいい船ですよ」
などと言った。
そのころ、一番若い教師の石川裕子(みつこ)は、医務室にいて病人につき添っていた。
病人は奥間という高等科の男生徒で、午後から腹痛をうったえたので、養護教員の勢理客(ぜつきゃく)ユキが医務室へ連れていったところ、軍医は急性盲腸炎と診断したうえで、船内では手術ができないから港へつくまで待てと言った。
熱が高かった。
だが勢理客(ぜつきゃく)は生後二か月の乳呑児(ちのみご)をかかえていて、彼女に看護をまかせるのは気の毒だというので、嘉手川重幸(かでかわじゅうこう)、瑞慶村智仁(ずけむらちじん)の二人の教師が石川裕子にすすめてつき添わせた。
四、五人の男生徒と一緒に、石川は昏睡状態の病人につききった。
部屋は非常にせまく、病人用として低い板敷きのベッドが一つあるほかは、いくらの余地もないので、つき添いの生徒たちは室外の荷物の上に寝た。
石川は教員免許状などをいれた非常鞄を壁にかけ、救命具だけつけて病人のそばにすわり、ベッドに両腕をおき頭をのせた。
そのまま彼女はぐっすり眠りこんだ。
前の晩にほとんど眠っていなかったので、この晩は疎開者皆が、早くから眠りこけていた。
暁空丸でも、学童が早く眠りにはいった。
師範付属校の引率教師、当真嗣永(とうましえい)は、空を見た。
陰暦四日で、細い月がかなり西に傾いていた。
月の色はかなりよごれてつやがなく、汚いという感じであった。
当真はそれを見ていると、へんに落ちつけない気がした。
しかし、甲板の上では、皆よく眠っていた。
同じ暁空(ぎょうくう)丸の事務長室で、指揮官の若い少尉や付属校の真栄城朝教そのほか二、三の教師たちが、事務長と話しあっていた。
事務長は上海あたりをへてきた人らしく、よほど洗練された感じを教師たちにあたえたが、めずらしくウィスキーなど出してサービスした。
当真が汚いと感じた月も、九時半ごろには沈んでしまった。
あとは、足のはやい雲のあいだに星がみえたとおもったら消えたりした。
時々、雨がバラついた。それに気がっいて、なんとなく船室にもどって寝る者もいた。
教師たちは、眠らずに用心するようにいわれていたので甲板に頑張っていたが眠気はたまらなかった。
海は真っ暗で、僚船のかたちは全然見えなかった。
どの船でも、甲板で目覚めている者は、前晩とちがって静まりかえったなかで、船が荒い浪を切る音だけを、しめった闇をとおして聞いた。
top
**************************************** |