|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
|
3 親と子と |
 |
島の北部の本部(もとぶ)町本部(もとぶ)国民学校教務主任新里清篤(しんざとせいとく)は、名護(なご)町まで用事で出たついでに、憲兵分遣隊をたずねた。
知人の岸本軍曹(きしもとぐんそう)がいたし、かねて決心したことではあるが、家族の疎開(そかい)について、なんらかの情報が得られたらと考えたからである。
勤務先の学校では、疎開を勧奨(かんしょう)しても、父兄がそれほど乗り気ではなく、村落にも兵隊の姿が見られるようになってはいたが、那覇などのように、さしせまっているという緊迫(きんぱく)感はないから、無理もないと思われた。
しかし通達文書を受取って、それが国策にそった至上命令(しじょうめいれい)とあれば、何とかして疎開希望者をつのらねばならなかった。
「まず、我々の家族をやりましょう。そうすれば、ついてくる」
新里(しんざと)教務主任は、勧奨の困難にぶっかったとき、校長にそう進言した。 |
率先垂範(そっせんすいはん)で、家族を説得し、疎開させる決心をしていたのである。
しかし、決心はしたものの、疎開しなければならない緊迫感が、周囲に感じられないのだから、いくら国策にかかわる切実な問題であっても、一家が散り散りになってしまうことは、無謀(むぼう)ではないかと迷ったりするのである。
自分の決心をゆるぎないものにする努力が必要であった。
それは戦局について一般に知らされている、勝った勝ったという情報のほかにある何かを、知ることだと思われた。
さすがに北部国頭(くにかみ)郡で一番大きな町である名護(なご)町に入ると、兵隊の数が急速に増えていることに気づかないわけにはいかない。
こんな田舎にまで兵隊が来ている。これはただごとではないぞ、という予感を持たないわけにはいかなかった。
今日、明日にどうということではなくても、南方の戦線で不利ないくさを戦っていて、やがてここが戦場になるかも知れない……。
そう思いそれの裏づけになる情報が、彼の決心の支えになる。
そんな気持で、憲兵隊の玄関を入ったのである。
あいにく岸本軍曹はいなかったが、これもよく知っている憲兵分隊長がいたので、新里(しんざと)は相談してみた。
「疎開はした方がいいでしょう」
分隊長は言い、それからいろいろと雑談をした。
軍服のあいだにいると、妙に緊張した雰囲気を感じることができて、しばらくは、疎開の重要性――戦力の増強――ということについて、意識の昂揚(こうよう)をおぼえさせられた。
この日のあと、父兄が、
「疎開させようと思うが、海上は大丈夫ですか」
と質問してくると、「おそらく大丈夫でしょう。私は、大丈夫だと思うので、家内も子供も全部やります」と笑って答えることにした。
駐屯(ちゅうとん)部隊の将校の一人と親しくなって、それが本部(もとぶ)の家によく遊びにきたので、彼からときには重大なニュースの片麟(へんりん)――南方の島で守備軍が玉砕したこととか、大戦果(せんか)の割に友軍機動部隊の被害が少ないようだが、実は倍以上の損害だったことなど――を聞くことがあった。
彼は、新里(しんざと)が疎開の決心をしたと知ると、
「それはいい。出発のときは手伝いましょう。
荷物の運搬などに人手もいるでしょうし、そのときはご遠慮なく言いつけて下さい」と言ってくれた。
ありがたいと思った。本当のところ、家族を疎開させるというのは、一家の引っ越しを意味する。
本部(もとぶ)町から那覇まで出ていくことの困難は、バスの便が急に悪くなって、出張などで単身出かけて行くとき経験ずみであった。
大の男が、荷物一つ持たなくてさえ難業だと思う那覇への道中を、引越荷物とともに年よりをまじえた女、子供連れで行くことの苦労を思うと、よくも率先垂範などと大きな口をきいたものだ、と後悔したりしているところだったから、将校の厚意は心の底からありがたいと思われた。
さすがに妻は、夫一人を残して異郷(いきょう)へ旅立っていくことの心細さに、なかなか決心しかねるようであったが、彼はときには叱りつけ、ときにはなだめて、着々と準備をすすめていた。
彼の決心も、こうと思いさだめたときから、何度も動揺した。
妻や老母の動揺(どうよう)が、そのまま自身に伝わった。
口では強いことをいいながら、迷いは常に彼の心にあったのである。
率先垂範(そっせんすいはん)だという誇(ほこ)りが彼を支えているので、それがなかったら中止していたかも知れない。
「ではやめようか」
このひと言も幾度か彼の口をついて出た。
しかし将校と親しくなって、その人の口からじかに戦局の重大さを聞くと、母や妻もしだいに覚悟が決まっていくようで、彼はほっとした。
県の衛生課につとめている武富良松(たけとみりょうしょう)も、似たような事情にあった。
兵隊と接する機会が多くなって、戦争の状況を知らされ、県庁につとめていて、しばしば軍の機密という情報を耳にすると、どうしても疎開は緊急不可欠だと思われるのである。
できるならば自分も行きたいが、それははばかる気持ちが強かった。
県庁の職員として県民に率先して範(はん)を垂(た)れなければならぬ、と示達(したつ)されて、妻子の疎開にだけは喜んで応じることにした。
ただ、養子に行った二男良紀(りょうき)が気になった。初等科四年生である。
わが子でありながら、養子にやる約束をしているので、自分の思うとおりにはならない。
しかし彼は養家に行き、口を酸(す)っぱくして疎開の必要を説き、自分たちも行くからとすすめた。
養家は首里市の旧家与那原(よなばる)――妻の実家である。
良紀の祖母が、良紀をたんに孫だというだけでなく、養子だというので、掌(しょう)中の玉のように愛していた。
妻子を疎開させる決心をして、まず考えなければならないのは良紀のことであった。
彼一人を残すことが心残りなのは、親として当然であった。だからといって、祖母の意向を無視するわけにもいかない。
祖母は、掌中の玉を惜しがったし、良紀も行きたい気持ちにはなれないようであった。
「どうする? 良紀はおばあちゃんのところに残そうかしら――」
妻は、荷物をかたづけながら夫にきいた。
「残しちゃいけない」
良松(りょうまつ)は断乎(だんこ)とした調子でいった。
「沖縄が戦場になるのは時間の問題だ。残るのは、玉砕(ぎょくさい)を意味する。
途中の海上が危険だというが、その心配は一晩だけさ」
「そうね。わたしだって、良紀一人だけ残して行くのは心残りだわ」
疎開は家族全員ですることにしたが、養家の了解を求めなければならぬ良紀が問題であった。
おばあさん子で、ほかの子とはちがった芯(しん)の弱さがあると思っていたし、男の子を甘やかし育てるのは将来によくない、疎開は良紀の将来にきっといい影響を与えるだろう、と考えた。
学童疎開の話をきいたとき、こんないい機会はないと思った。
「このさい、学校の先生にくっつけてやろうじゃないか。
友だちも一緒だし、まるで遠足か修学旅行に行くようなもんだ。良紀も淋しくないだろう」
「そうね、どうせ私もすぐあとで行くのだし、学校と一緒ならおばあちゃんだって承知してくださるわね」
「それはどうか知らないが、やっぱり説得はしないといけないだろう」
夫婦の意見は一致していた。
しかし、良紀はうんと言わない。
「そんなことでどうする。学校の先生も、お友だちも一緒じゃないか。甘えん坊になっていると兵隊さんになれないぞ」
「お母さんもみんな、すぐ行くのよ。沖縄で戦争がはじまったら大変よ。ニ
ュース映画でも見たでしょう。みんなちりぢりになったり、弾丸(たま)にあたったり――ね、いきましょう」
「ヤマトに行ったら、電車や汽車も見られるし、雪だるまをつくったりすることもできるし、いいじゃないか」
良松は、沖縄が戦場になるという想像におびえていた。県庁に出入りする兵隊が多くなったこと、庁内にどこからともなく伝わって来る南方戦線の情報、それらを総合すると、沖縄が戦場になるのは、時間の問題であるような気がした。
良松は、幼い息子をなだめたりすかしたり、無理やり説得した。
それは彼自身は気がついていないが、息子のためというより、むしろ自分の怯(おび)えを落ちつかせるためのものであった。
そして、妻もそれに感染し、同調した。
祖母は、良松夫婦の熱心さに負けた。寄る年波(としなみ)のせいか、生まれ故郷で死ぬことをむしろ本懐(ほんかい)だと観念していたが、しかし可愛い孫を道連れにするにはしのびない。
学校で団体として行くのなら心配はいらない、戦局の判断よりは学校に対する絶対の信頼が、この際は勝った。
「どうせヤマトでは一家がそろうことだし、良紀は一人さきに行っていたほうがいいね」
「淋しいのもいっときですよ。良紀もおばあちゃんも――」
行くと決めて、学校に確かな申込みをして、出発を待っている間、国民学校四年生、十歳にしかならぬ良紀は、時にだだをこねて父母を困らせた。そのたびに良松は叱った。
島元洋倫(しまもとひろみち)と山里昌永(やまさとしょうえい)は、甲辰(こうしん)国民学校の五年生で、大変仲が良かった。洋倫はほっそりとおとなしかったが、昌永は運動選手で、けんかにも強かった。
性格が違うので、かえって仲がいいのかも知れぬ、と両方の家族では言っていた。
昌永は、家へかけこむなり、「父兄会だよ」と言った。
「何だって?」
と姉がきき返した時は、もう外に飛び出していた。
「島元君の所へ遊びに行って来る」という声だけ残して、姉をめんくらわせた。
「しょうがない子だよ。父兄会だと言っていたようだが――」
時間は聞かなかったが、それでも早目に支度(したく)して、行くだけは行っておかなくてはと思った。
「山里さん」
呼び声は、島元治子(はるこ)であった。島元治子と山里和子は、県立一高女四年の同級生である。
山里和子は母親が亡くなった後に、母親代りに幼い弟の面倒を見ていた。
「疎開(そかい)のことで父兄会をやるんですって」
「エー?」
「国民学校生を集団疎開させるお話だから、お家の人すぐおいでって――そう言っているの、うち洋倫(ひろみち)は――」
「ヘエ。うちの昌永は何もいわないわ。ただ父兄会だからって言い残して、洋倫ちゃんと遊びに行くって飛び出したのよ」
「どんなお話だか、行って見ましょうか」
異存(いぞん)はなかった。二人は連れ立って山里家を出た。
「あんたのお家では、洋倫(ひろみち)ちゃんを行かすつもりでいるの?」
「疎開した方がいいって、話はしているけど、さあ――」
島元治子は、続けて「あんたのところは?」ときいた。
「うちはやるつもり。昌男(まさお)も一緒にやれば安心だから」
昌男は、昌永の兄で高等科二年生だった。
「そうね。昌男ちゃんや昌永ちゃんが一緒なら、うちの洋倫(ひろみち)もやれるわね」
彼女は、おとなしく内攻的な性質の弟を、集団の中に一人で入れた時、誰もかばってやる者がいなかったら、つらい思いをするだろう、と姉さんらしい心配をしていたが、仲のいい山里兄弟と一緒なら、淋しい思いをしなくてもすむと考えた。
二人が学校についた時、教室にはすでに先着の婦人たちが、児童の腰かけに窮屈(きゅうくつ)なのを我慢してすわ
っていた。
教室の仕切りをはずした会場に、百名ばかり集まったころ会は始まった。
「暑い上にお忙しいところをようこそお集まりいただいて感謝申し上げます。実は重大な相談だし、緊急を要することなので、生徒を通じてお集まり願った次第であります」
大城(おおしろ)校長は、簡単な挨拶の後、疎開の本題にはいった。
「逃げるというのではありません。人的資源の確保と戦力の増強という点から、重大な戦局に当面している現在、沖縄に来冦(らいこう)する敵を殲滅(せんめつ)せんとして、国家の政策として行なわれるのが、今回の疎開であります。
だから疎開該当(がいとう)者は、あくまでも制限があり、いざという時に働きのない老幼婦女子と病人に限られています」
婦人たちは、真剣な目の色をして聞いていたが、校長の挨拶がすむと、隣どうしで私語(しご)をかわしあった。
その多くは、子供を手放すことの不安を語っているようであった。島元治子と山里和子の二人は、親たちのそういう不安がわからなくもないが、それよりは、本土へ行けることをうらやましいと思う気持ちのほうが強かった。
「いいわね。修学旅行に行くのと同じじゃないの――」
「校長先生がああいうことをおっしゃらなければ、私たちも行くのにね」
校長先生というのは、自分たちの一高女の西岡一義(にしおかかずよし)のことである。
「お前たちが、自分の故郷を見捨てて、誰がこの沖縄をを守るか。疎開するのは卑怯者だぞ」
西岡校長は朝礼で、そう叱咤(しった)したことがある。そのことを、弟たちの国民学校の校長先生の話を開いているうちに思い出していたのである。
つづいて、校長の紹介で県庁の役人が壇(だん)上に上った。
甲辰(こうしん)校は県庁に近い下泉(しもいずみ)町にあって、校区には県庁の課長クラスも多かった。その役人の話は、校長と大同小異であったが、時局の説明をくどくどとやった。
「沖縄を含めた南西諸島一円の島々が、特別防衛地域に包含(ほうがん)されていまして、強制的に疎開させられます。 |
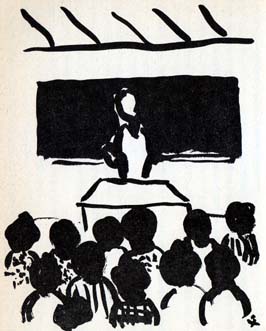 |
国家総動員法によりまして、戦力を増強するための緊急かつ必要な措置(そち)であることを知ってもらいたい。
国防上の要求により、児童の学校教育を中断されることがないよう疎開させられるのであるから、父兄としてこういう非常の際にも将来の立派な国民の教育を忘れることのない当局の親心に、大いに感謝申し上げ、喜んで協力しなければならない」
あらましこんな趣旨の話であった。
その人が壇をおりると、校長は、みんなに何か質問はないかときいた。
「むこうで、子供たちの生活はどうなるのですか」
はでな布地のモンペをつけた婦人が立った。若い頃の着物をつぶしてモンペにしたのであろう。
「集団でやりますし、学校が、ヤマト(大和=本土)に分教場を建てたと考えてよい」
「お金の仕送りは簡単にできますか」
「できます。しかし、子供たちがお金の必要を感じるほど苦しい生活をさせるはずがない」
「期間は?」
「来年の三月までの予定でありますが、これは断言できない」
「沖縄に上陸して来る公算が大きいと見て疎開させるのでしょうね」
「上陸だけでなく、空襲も考えておるわけです」
「持ちものの制限もありますか」
「ありません。ただ、何でも、いくらでもというわけにはいかないと思う。荷になっても困りますからな」
「来年の三月といえば、寒い冬中むこうにいるわけで、その間の夜具、衣料等は是非(ぜひ)必要だが、それに対する制限は?」
「ない。いくらでも持たしてやっていい。しかし、そんな心配は杞憂(きゆう)にすぎないでしょう」
疎開児童たちの受入れについては、文部次官通達が日本全国各府県に行っているし、各県とも態勢を整(ととの)えて待っていてくれるから。受入れられた後の教育および生活については、何の心配もいらないということが、校長と県庁の役人とでくりかえし説明された。
参会者の誰かが質問し、それについて答える。それをくりかえしている間に、婦人たちのささやきが多くなり、それは次第にふくれあかって来た。耳は質疑応答に傾け、口は互いにその決心のほどを確かめあっていた。
むこうについてからの不安が杞憂(きゆう)に過ぎないとすれば、それは実質的に、楽しい修学旅行であった。
婦人たちも、それならやってもよい、と思いはじめたようすであった。二人も、ますます弟たちをうらやましいと思う気持ちをつのらせた。
「途中の海上の危険はどうでしょうか」
みんなの不安は、そこに集約された。今まで私語をささやきあっていた人たちも一瞬、シーンと黙った。
「それも、大丈夫なように万全の処置がとられることになっています。なるべく軍艦か、軍艦でなくても、充分な護衛がつくに違いありません」
参会者は納得し、やがて解散した。県庁の職員が軍艦で行ったという話が、世間には流れていた。
軍艦なら洋上の不安は一掃される。
しかし、よく考えて見れば、疎開させた後の教育も生活も、途中の脅威も、大丈夫というのはすべて予想に過ぎなかった。
万に一つの見込み違いもないということではなかった。そのことが、母親たちにはまだ不安であった。
島元洋倫(しまもとひろみち)の父親は県会議員で、母親は真和志村楚辺(まわしそんぺ)国民学校の教師であった。
ここでも父親が積極的であった。海上の危険、疎開先での生活不安ということがないわけではないが、彼はいわゆる指導者としての立場からも、自信を持っている戦局の判断の上からも、家族を疎開させておくべきだと信じた。
できるなら、母親も疎開児童引率教師として行かせ、気が弱くて集団生活についていけるかどうか不安のある洋倫(ひろみち)を見てやれるようにしたい、と願ったが、これは結局実現しなかった。
彼女の学校では、引率教師の人選はすでに決まっていたのである。
ただ洋倫の友人の山里昌男(やまさとまさお)、昌永(しょうえい)兄弟が行くと決まったので、やや安心した。
仲の良い三名は、朝から晩まで一つ屋根の下に寝起きできる期待に、子供らしい喜びを得て有頂天になっていた。
行くと決めてからは、互いに行き来して、出発の日を待ちわびた。
一高女にいっている姉たちの山里和子と島元治子が相談しあって、型どおりの鰹節、黒砂糖、油味噌、麦こがし等の食料品が準備されて、あとは集合、出発を待つばかりとなった。
那覇国民学校高等科二年生の仲宗根正男(なかそねまさお)は、授業の日に、担任の教師から疎開(そかい)希望者は手をあげろといわれて、胸が高鳴った。
――ヤマト――に行ける。
彼は雪が見たかった。本物の汽車や電車が見たかった。
映画でしか知らない大都会の雑踏(ざっとう)の雰囲気に浸(ひた)ってみたかった。
勢いよく手を上げてから、「いつ、帰って来ますか」と質問した。
「来年の三月までの予定だが、どうなるかわからん」
彼は卒業してから後、父と一緒に海に出て、石灰の原料となる海石を採取するような生活には入りたくなかった。
飛行機工揚に行くか、あるいは少年航空兵を志願するかしたいと思った。
「行ってからむこうで少年航空兵に志願できますか」
教師は、「うん」と力強くうなずいた。
「できるよ。君たちは、ここで勉強ができなくなるかも知れないので、むこうに行って勉強を続けようということだからな。
つまり、学校が引っ越しをするだけの話だ。上級学校へ受験することも、少年航空兵を志願することも、何でもできる」
教師は、仲宗根正男だけでなく、全生徒に言い聞かせた。
仲宗根正男は、家に帰るとさっそく、夕食のとき両親に話した。
「いけないよ」
母親がまず反対した。父親は黙々と箸(はし)をつかっていたが、決して賛成ではなかった。
「考えてもごらん。潜水艦が、ウジャウジャいるというのに、どうして行けるかね」
「軍艦で行くんだよ」と正男は答えた。
「軍艦?」と、国民学校生の弟と妹が同時に言った。
「うん。瑞慶村(ずけむら)先生が言ったもん」正男は目を輝かした。
「軍艦ならまあ、安全だろうな」と父親は言った。
「だけどお前、行ってすぐ帰って来るんじゃないだろう。
長い間、ヤマトでお前一人暮らすんだよ。お金はどうするのさ」
母親らしい心配であったが、正男はそこまで思い及ぶことではなかった。
「むこうで少年航空兵を志願するんだ。
それに学校で寄宿舎みたいにして、みんな一緒に暮らすのだから、お金はいらないのだそうだ」
正男の心はもう、疎開先にとんでいた。
それからしばらく、父と母が交互に反対したが、正男は是が非でも行きたいと根気づよくうったえつづけた。
疎開しないのは。この非常時に国策に協力しないことだとも言った。
沖縄が戦場になったら飛行兵になって仇(かたき)を討(う)つのだ、とも言った。
「お前がそれほど行きたいなら、行ってもいいさ」
父親は、根負(こんま)けした。母親は、「行かせるのですか」と父親にびっくりしてきいた。
「こんなに行きたがっているし、海だって危ないというが、大したことはあるまい」
父親が許してくれれば、母は問題ではない。母親もついにしぶしぶながら承諾(しょうだく)した。
「大丈夫だよ。船がやられても僕は泳げるもん」
正男は目を輝かした。
行くと決まると、母親が積極的に支度(したく)をはじめた。
旅に行く――母親の言葉である――のに、何も持たせてやれないと正男が気の毒だ。
友だちの手前もあるし、半年も行っているとすれば、着るものでも冬物まで持たさねばならぬ。
母親は、不足なものは親戚のあいだを合力(ごうりき)してまわった。
こういう準備に父親はまるで無力であった。妻の言うとおりに動くほか何もできない。
「これはいいものだよ」
母親は、いそいそと外から帰ってきた。母親の親戚筋に年廻りのいい女の人がいる。
年廻りがいいのは運が強いからあやかりたいと、行って頼んだら綿入れをくれたのである。
包みを開いたら、女ものの丹前(たんぜん)が入っていた。
「これがあると、ヤマトの冬も大丈夫だ」と、母親はよろこんだ。
少しばかりおしろいくさいのと、女ものの模様襟(もようえり)なんかが、少し気になるが、そんなことをいうのはぜいたくというものであった。
仲宗根正男と同級の具志清興(ぐしせいこう)の場合は、両親がはじめから疎開に積極的であった。
彼は六男で上の兄姉たちは嫁いだり、出征(しゅっせい)していたり、ヤマトで職を得て働いていたりしていた。
家には父母と国民学校生の妹と、四人家族だった。
五十になっていた父親は、自分たちもできるなら、あとから疎開するつもりでいた。
「疎開先についたら、すぐ兄さんと連絡をとれ。いいか」
父親と母親は、清興(せいこう)の荷物にいろいろ気をつかいながら、そうくりかえした。
「家族はみんなあとですぐ行くと言っていた、と言うことも忘れるなよ」
黒砂糖や鰹節(かつおぶし)などの当座の食料のほかに、冬になっても困らぬように父の着物を仕立てなおしたり、ふとんのつくろいをしたり、母親は急に忙しくなった。
具志と仲宗根は、翌日瑞慶村(ずけむら)先生に正式に疎開の申込みをした。
どこでも親がためらう前で、子供は浮きうきと疎開したがった。
国頭(くにがみ)郡国頭村安波(あは)という山間集落では、七世帯が疎開をなかば強制された。
宮城(みやぎ)という家で、三人の子をもつ母がためらっているとき、壮吉(そうきち)という六年生になる長男が、こっそりと手続きをした。
結局この家では、祖母をまじえて五人の女と、壮吉とが、疎開準備をはじめることになった。
疎開勧奨(そかいかんしょう)の通途文書によるまでもなく、国民学校長たちは、引率教員の人選の条件を、優秀教員であ
ることにしぼっていた。
理由は他府県に行って恥(はじ)をかかないようにという期待と、父兄たちを安心させるためであった。
さらに優秀な上に家族が少ないこと、若いことも条件であった。
身軽に学童たちの世話に献心できるようにという心遣(づか)いからであった。
夫婦者であったほうが望ましいともされた。
教育だけでなく、親の手をはなれた幼い学童たちの親がわりに親身に面倒を見る女手(おんなで)も必要だったからである。
各学校とも、優秀で若くてできるだけ家族のない夫婦ものという条件で、引率教員の人選にあたっていた。
二十二日に報告された児童数および引率教員より、二十八日に報告されたそれがはるかに多くなっていたのは当然であった。
その数とても満足すべきではないが、第一次送り出しとして、あとから続々と希望者が増加するだろうという期待が持てた。
学校では実際に、受付の教師が交替で事務に忙殺(ぼうさつ)されるようになっていた。
申込みにしたがって名簿を作成し、学籍簿の整理をすることが仕事の主なものであった。
教学課との連絡も、市の視学(しがく)との事務連絡も、電話ではらちがあかないことが多く、そのつど、あいもかわらず雨のない炎天が続いている中を、自転車を走らせた。
学童の父兄たちは、しだいに高まる疎開への関心に刺激されて、申込みというのではなく、単なる相談または情況聴取(ちょうしゅ)ということで、受持ち教師のところに来るのも多く、そういった人の応対にも時間がさかれた。
そして、申込みをすませた父兄たちは、まだ残る一沫(まつ)の不安と、子供たちを安全地帯に移す期待とに、複雑な感懐(かんがい)を味わっているのに、子供たちは、雪や船や電車や、まだ見たことのないヤマトの風物(ふうぶつ)にあこがれて、修学旅行にでも行くようなつもりで、出発の日を心待ちに待っていた。
top
**************************************** |