|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
|
7 無邪気な乗客 |
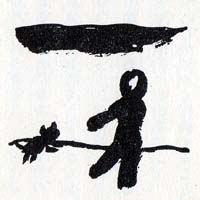 |
対馬丸は大きな貨物船で、船艙の大きなのが船首のほうに二つ、船尾のほうに三つ、小さなのが中央に二つ、合わせて七つあった。
船尾には一般疎開者が入り、学童は船首の第二番船艙に入れられた。
底は二重になっていて、彼らのいたのは中デッキである。
勾配の急な梯子段をおりると、とてつもなく大きな暑くて臭い船艙(せんそう)が、無邪気な幼い客たちを迎えた。
天井の高さが三メートルちかくあるが、まわりの鉄板の壁に沿うて二段に仕切られ、その上下が八百人にちかい疎開学童と引率教師との寝床であった。
ダンブルの中央は、ひろい空間である。 |
船底のダンブルに貨物を出し入れする孔が、木の板で盖をされ、それがキャンバスをかぶっていた。
具志清興(ぐしせいこう=高等科二年生)は、そのキャンバスの裾をおそるおそるめくったことがある。
そこからは、おそろしい広さを思わせる暗い船底がのぞかれた。
彼は翌晩、退船騒ぎのなかであやうくこの孔におち込みそうになろうとは、このとき予想もしなかった。
孔のまわりは、寝床とのあいだが通路になっている。
そこらの空き間に、疎開者の荷物が積みあげられていた。
もともと兵隊をのせて満州、台湾、上海、マニラなど、それこそ北へ南へとまわった御用船である。
ひどいときはこの二段がまえの床に、タタミ一枚の広さあたる二人も寝かせるのであった。
そんなふうに幾日も幾日もジグザグコースをとってゆく習慣のある船のなかで、後部船艙の一般疎開者のなかには、シラミをみつけた者もあった。
その夜は、暑いのと群衆気分とのために、皆なかなか寝つかなかった。
早くも船に酔う者がでたが、そのまわりで元気な者は、男は裸で、女はシュミーズ一枚で、夜っぴて騒ぎたてた。
寝床の二階は簀の子ばりであった。
下にいる男生徒が持ってきたサトウキビとか棒切れなどで、上にいる女生徒の尻をつついたりした。
「センセエィ。男のひとがァ……」
と、女生徒は悲鳴をあげたが、引率教師たちは、それをいちいち取りしまるいとまはなかった。そのうちに、教師のなかにも酔うて参る者がでたが、元気な者が騒ぎをしずめようとしても、きりがなかった。
船には、輸送指揮官として若い少尉が一人乗っていた。彼は、疎開者のなかから、人員を掌握する代表をえらび、たびたび指揮官室によんで、いろんな注意をあたえた。
一 敵の潜水艦に襲撃されるおそれがあるから。航海中よく指揮官の指示にしたがって行動すること。
ニ 昼間はデッキに出ないこと。
三 夜は灯火をつけないこと。
四 海中に紙くずやサトウキビの食べかすなどを流すと、航跡を発見されるおそれがあるから、厳にいましめること。
などというのが、そのおもなものであった。
対馬丸にのっている学童には、団体のほかに家族同伴の個人がいたが、学童疎開団の総指揮者には、那覇市天妃国民学校の田名宗徳(だなそうとく)が命じられた。
引率教師が総員三十名、養護教員と炊事婦が各校一名、ほかに各校それぞれ任意に父兄からつのった世話人がついていた。
学童は数の多いところは分団に分けられ、さらに必要に応じて班に分け、分団長には高等科生があたった。
高等科生は世話人と一緒に、飯上げや船酔いの世話にもよく立ちはたらいた。
戦時中のこうした訓練はよくゆきとどいていたので、田名は引率教師を集めて、指揮官の注意を伝えたうえ、学童のいっそうの規律統制を要望し、自らも中央の通路に立って、大きな声で学童たちに伝えた。
学童たちは、「注目!」と号令がかかると、すぐ静かになって号令者に注意を集中する訓練が、ゆきとどいていた。
だからこのような伝達はいちおうもれなく行なわれたようにみえた。
けれども、しばらくするとまた耳をおおうばかりの騒ぎになるのは、やむをえないことであった。
この騒ぎは指揮官の耳にも入ったらしく、田名はそのため特別に幾度もよびつけられた。
「子供がさわぐのは、最もいけない。場合によっては、それで敵に知れるおそれがある――」
田名は、船艙に帰っては真剣にそれを八百名に伝えるよう努力した。引率教師の一人は、
「敵は電波探知機を持っているから、お前たちがさわぐと、それにひっかかるぞ」とおどかした。
引率教師自身半信半疑のこのおどしに、子供たちの幾分かは、「ほんとだ!」といった表情で唇をとじ、幾分かはゲラゲラ笑った。
その笑いは、そんなことがあるかという確信によるものではなくて、たぶんに言った教師の不安定な表情につり込まれたものであるらしかった。
全く、学童と教師と合せて八百人の者が、半ばは命令によって恐怖感のなかにおし込められながら、その実、全く楽しんでいた。
あるいは恐怖というもの自体を、楽しいもののように錯覚していたのかもしれない。
なにしろ、少年少女たち皆が、戦場の兵隊さんの弾丸雨飛のなかでの苦労というものに、英雄的なあこがれをもつように教育されてきていながら、いま自分がさらされている危険については、神国の国民だし大きな御用船だもの、危ないことがあるものか、という奇妙な安定感に包まれていた。
教師たちが「潜水艦……」ということばを出すとすぐ静かになるが、長続きしなかった。
静粛(せいじゃく)を長時間まもらなければならないということが、実感として湧いてこなかった。
「君らが掌握できなければ、この俺がやるぞ」
若い指揮官は、ついにそんなことを言った。
何時間かたって、騒ぎはいくらかおさまった。
騒ぎつかれたせいもあるが、あまり暑いので、急な梯子をよじのぼり甲板にはい出る者がかなりいたのである。
少し落ちっくと、彼らはいろいろの雰囲気をそれぞれつくりはじめた。 |
 |
疎開していったら、むこうではどうだろうこうだろう、という想像を語りあっているのが多かった。
仲宗根正男たちは、まだ見たことのない雪の話から、雪合戦というものはおもしろいそうだという話をした。
「雪は、さわったら熱いそうだよ」
と誰かが言った。
「そんなことがあるものか」
とまた誰かが言った。
「でも、うちの伯父さんが言ったよ」
「ふしぎだなあ、雪は零度より以下だと雑誌に書いてあったがな」
「理科でも習ったさ」
「それから、雪のなかで遊んできたら、急に火にはあたるな、と伯父さんがいったよ」
「へえ。なぜかな」
「ますます霜焼けがひどくなるんだとさ」
「霜焼けって、なんだ?」
「やけどみたいなものだと」
「へえ。雪でもやけどするかね」
「みたいなものだと言ったんじゃないか。伯父さんは東京にながいあいだいたんだから、嘘でないよ」
それから、九州に行ったら東京にも行けるだろうか、などという話になった。
同じく高等科女生徒の佐久川和子、高良みつい。嘉数文子たちは、やはり本土をあこがれる話をたくさんしたが、なんといっても、むこうへ行ったら落着いて勉強ができるだろうということが、皆の小さな顔をほころばせた。
「むこうへ行ったら、教科書があるはずよ」
「本当かしら。教科書があるの?」
「あるさ。沖縄は遠いから来ないのよ」
「内地はいいね」
彼女らは、この年度に入ってから、どうしたわけか教科書がなく、学校でつくったプリントで勉強していた。本土へわたればちやんとした教科書があるというのが、彼女らの"平和な本土”へのあこがれであった。
「作業もないはずよ」
「そうかしら。作業はあるはずよ。だって、むこうにも飛行場はあるはずだもの」
「でも、学校に兵隊はいないはずよ」
それからさきの憶測はとうていできる年齢でもなかったが、なんにつけても本土へ渡れば、毎日軍馬のひづめと車両のひびきがたえまなく耳に入るような、いらだたしい生活から遠ざかって、落ちついた勉強ができる。
そして、男ならやがて中学枚や大学へあがるにも、沖縄よりよい学校があるだろうから便利だ、といったふうな夢想の灯が、ほとんどの者の小さな胸に明るくともっていた。
ある一団、那覇国民学校高等科女生徒の数人が、師範学校を出たばかりの若くて元気な石川裕子先生をかこんで、合唱していた。
さらば沖縄よ、また来るまでは
しばし別れの涙をかくし
恋しなつかし島々みれば
椰子の葉蔭に十字星 |
「さらばラバウルよ……」という歌の、ラバウルを「沖縄」にかえただけの歌であった。
沖縄全島にみちみちた兵隊がもってきて流行させたのだが、戦争の歌であるにもかかわらず、たまらない哀愁(あいしゅう)がみなぎっているこの歌を、兵隊も地方人(当時一般社会人のことを軍隊ではこうよんだ)も、よく歌った。
やがて沖縄もラバウルのようになるという真実の暗合であったのか。……
しかし、歌う人々自らはいつも、けっして悲しい表情などをしていなかった。
その意識の下にはなにかしらの敗北感があるにしても、表面のあたまにはいっも力強い戦争への関心があって、それで歌うのだと考えていた。
石川裕子たちも、歌いながら時々大きな声をあげて、楽しく笑った。
名城妙子はこの歌を歌った雰囲気と、そのときの強烈な潮風の匂いとを、その後もずっと忘れかねた。
ちょうど同じころ、船尾の一般疎開者も、同じように甲板にはいでて海風にあたっていたが、船尾の一段あがった砲座のある甲板(船尾楼)に――そこはふつう、兵隊のほかには出入りを禁じられている場所だが――このとき数人の女たちが、兵隊たちと肩をくんでふざけながら、やはり少女たちと同じく、「さらば沖縄よ……」を歌っていた。
彼女らは娼婦であった。
本来なら戦力の一部として、沖縄からの出域を禁じられているはずなのをうまくのがれてきて、その喜びまじりに兵隊とふざけながら、少女たちと同じく故郷に歌をおくっていた。
沖縄ははるかに離れたことであろう。陰暦三日の月はもうなく、星が見えていた。
でも、その星も空一面に輝いているのではなく、足のはやい雲のあいだにまばらであった。
船では、甲板上はすっかり灯火管制をしていたから、人の顔はさだかでない。
ただ、かすかに輪廓の見える黒い影がたくさん、強い海風ときそうように、笑ったり歌ったりしていた。
そして口のひまになった者が、ガリガリッとおやつがわりに誰もがかならず持ってきた黒砂糖を歯でかみ割った。
この晩、船団が沖縄本島北部に近い瀬底(せそこ)島を通過するころ、その付近に待機していた他の三隻の船団がひそかにこの船団に加わった。
咸鏡(かんきょう)丸ほか二隻で、もともと船足の快速をたのんで、十九日に護衛なしの単独出航をしたのだが、海に出てから「沖縄本島近海に敵潜水艦あらわる」との情報を入手して、護衛航行に合流を希望したのであった。
船団は六隻にふくれた。
新入りの輸送船団は、別に一列縦隊をつくって伴走した。
しかし、翌日の午前中に脱けて、また元通りの単独行動で、急速に北上した。
そこには、船足の遅い船団と伴走しては、むしろ危険だという判断がはたらいていた。
それどころか、もし敵潜水艦がこの船団を狙うとすれば、当然に船足の遅いほうに集中するであろうから、その間に逃げることはむしろ容易であり、安全度が高い、という計算が加わっていた。
ひと晩じゅう眠らずにさわいだ者もいた。
あけがたわずかに眠った者も目ざめは早かった。
睡眠不足のままに、二日めの昼間じゅう、彼らには楽しい一日であった。
船員や兵隊もひまのあるかぎり、幼い無邪気な乗客たちとつきあった。
戦争の話や、前に遭難して助かった話などをした。
そして、「この船はいつでも運がいいんだ。今度も大丈夫だよ、きっと」などと言った。
名城妙子(高等科一年生)は朝、親友の金城春子と連れだって、炊事場に行った。
甲板にある洗面用のタンクは、早く水がきれてしまって、顔の洗えない者が多かった。
水タンクは船尾の一般疎開船室の甲板にもあったので、そこまで行ってみたが、やはり出なかった。
オシメを洗ってほしていたおばさんが、「いまさきまであったよ」と言ったが、もうなくなっていた。
「炊事場に行ってみよう」。
彼女たちは、前の晩に飯上げで炊事場に出入りしたことがあるので、そこへ行けば顔が洗えると考えた。
炊事係の船員は、「君たちだけにあげよう。誰にも言うんじやないよ」と言って、彼女らに水をくれた。
そのとき二人は、カボチャが煮られているのを見た。「またカボチャか」二人は、顔を見あわせた。
船のなかの食事はカボチャばかりであった。
わんぱくな田場兼靖は、しじゆう元気ではしやぎまわった。
いとこで同級にいる田場兼源や伊波という兄弟どうしの友たちと一緒に、鬼ごっこなどで、船いっぱいを暴れまわった。
彼らは、最上甲板にボートがあって、そこの四隅に監視哨が海を見張っていることも知った。
炊事場あたりで船員がねずみをとっているのを、彼らはおもしろかって見た。
炊事場には大きな猫がいて、学童たちがお茶をくみに行くと、大きなうなり声をあげてそれを追っかけたが、田場たちはそれをからかっては、追われて逃げまわった。
そのでかい猫は、非常にこわかった。
学童たちは、船に酔っても、一般疎開者よりはるかに元気であった。
top
**************************************** |