|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
|
6 たそがれの出航 |
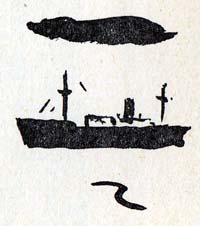 |
午後四時頃、約五千名にのぼる疎開(そかい)者の群れが、真っ黒な大河のように移動をはじめた。疎開者は、敵からの狙撃の危険をさけるために、できるだけ黒っぽい服装をつけるように命じられていた。
男の大人は国防色とよばれるカーキ色の国民服、女は黒っぽく目だたない色で、腕も足もきちんと覆ってしまうモンペ、学童も男が霜降(しもふ)り学生服に、女がモンペ。暑いのに頭巾(ずきん)をかぶっている者も多かった。
それらが手荷物を持って、国民劇場前広場から二百メートルほど南へ移動するさまは、真っ黒な大河というにふさわしかった。
途中、山川橋あたりまで、見送り人が荒れた堤(つつみ)のように真っ黒にかたまって、わめきあっていた。彼らは疎開者の手荷物を持ってやったり、もうじき別れていく赤ン坊を名残り惜しそうに抱きしめていたりした。 |
なかなかおとろえない日射(ひざ)しの下で、彼らの声と汗の臭いとが、いよいよ異常な興奮をかきたてた。
この道行きが戦争に勝つためであり、したがって自分の身を護るためのものである、と送る者も送られる者も信じているようすであったが、その姿と声とを遠く広くながめると、恐ろしい悲劇の涯(はて)におしやられていく者の不安感に充ち満ちていた。
那覇港を少し出はずれたところに水上警察があって、そのそばから石段で海へ降りた。
海には「大発(だいはつ)」という舟艇(しゅうてい)が待っていて、兵隊が器用に老人や子供を手伝って乗せてやった。
底の深い箱のような舟艇は、乗せられるだけ呑みこむと、なんの感傷もなく、あっというまに出た。
大人たちには、岸壁の見送り人をはるかに見上げて涙を流す者が多かったが、学童たちの多くは泣かなかった。
泣きべそをかく者もいたが、すぐ多くのはしゃぐ仲間の気分にとけて、見送りの群衆に手をふりちぎった。
「せんせェい(先生)、よろしくおねがいしまァす」
岸壁からそのような声が、幾重(いくえ)にも舟艇になげられてきて、海風に散った。
しかし、舟艇の舷側は高すぎたので、学童たちは岸壁をはなれたかと思うと、じき見送りの人たちを見ることができなくなった。
仲宗根正男(高等科二年生)のような、少し大人びた子供は、家を出る前に
「見送りなんて、ぼくきらいだから、顔を出さないよ」と言ったとおり、舟艇のなかでうずくまってじっとしていたが、多くの学童は、本当に旅行に行くようにはしやぎながら、海の上をすべっていった。
そのにぎやかな舟艇のなかが、ほとんど物音もたてないようになったのは、いつからであったろう。
気がついたとき、舟艇は大きな船と船とのあいだを縫いながらはしっていた。
そして泊まったところで、学童たちは、上を見上げたとたんに、幼い唇をとじて息をのんだ。
陸軍御用船(ごようせん)「対馬丸」――それはまるで、絶壁のようであった。
総トン数六千七百五十四トン、長さ百三十五・六四メートルという図体にのっている貨物はいくらもなかった。
上海で積んだ乾繭(ほしまゆ)一千七百七十五梱(こん)、胡麻(ごま)一千梱というのが、いまの搭載貨物の全部であった。
吃水(きっすい)が、疎開者をのせた上で、船首三メートル八十二、船尾五メール九十にすぎなかった。
船体をつつんでいる鉄板は、土色と灰色とをませたような重苦しい色肌をもっていて、それが海面から甲板まで何メートルあったろう。
学童たちは、みんなが同時に絶壁を連想した。
吃水線の朱色が海面からはるかに浮きあかっていたし、この絶壁は戦争の気分とないまぜて、すさまじい圧力となって、幼い体をおしつぶしにかかっているようにみえた。
彼らが島国に育った者の常として、幼い日から慣らされてきたところの「お船にのって青い海を渡ってヤマトにいく」というロマンチックな想像が、この時いきなりぶちこわされたようであった。
絶壁の下は、ドス黒く底の知れない海である。
その絶壁に沿って、いくつにも折れまがっておろされた吊梯子を、彼らは蟻のようにつづいてよじのぼっていった。
手摺(てすり)は肩よりも高く、小さな手でつかまるには太すぎた。 |
 |
手荷物を持っていると、それにもつかまれなかった。
高等科生はできるだけ低学年生の手をひいてやったが、高等科生の数は、はるかに少なかった。
いまにも落っこちそうな不安をこらえて、それでも眼をつぶるわけにはいかないので、足元だけを見つめたが、いまどのくらいの高さまでのぼっているかもわからず、黙々と小さな足をはこんだ。
吊梯子の上から、いくつかの荷物が幼い手をはなれて海中におちこんだが、それは簡単な事故で、あっという間にあきらめるほかはなかった。
そして彼らは、いつのまにか甲板についていた。
甲板にとどくと、にわかにまたはしやぎはじめた。
こわい吊り梯子を無事にのぼりきった安心と、大きな船にのることができた喜びとが、一緒になったのであった。
なかには名城妙子(なしろたえこ=那覇国民学校高等科二年生)などのように、船にのったとたんになにやら心細くなり、もう行く気がしなくなってベソをかく者もいたが、気の強いわんぱくは、田場兼靖(たばけんせい=泊校五年生)などのように、泣く者を見つけてははやしたてたりした。
船艙(せんそう)におりて自分の席をとると、彼らの多くはまた、いっぱいイカダを積んである甲板にあがってきて、船出までいた。
彼らは、故郷の島が離れていくのを見ようと楽しみにして、はしやいでいたが、低学年の子には舷側(げんそく)が高くて、遠くが見えなかった。
この舷側の高さは、のちに事故がおきたとき、幼い子供たちが海へとび込むのを邪魔したが、この時はもちろん、彼らにその予想はつかなかった。
この時しかし、舷側の手前には船の道具やらイカダやら、とにかくいくつか踏み台になるものがあったので、二十人ほどの子供たちが、その上に立って海を見下した。
田場兼靖は、わりかた早く乗りこんだので、彼が見下したとき、あとのほうの人数を運んできた舟艇がまだ下にいた。
その舟艇から乗りこみがおわると、船舶兵の一人が、舟艇の舷側の上に立ち、手信号で舟艇のバックを案内していた。
すると、舟艇があやまって本船に衝突したはずみに、その兵隊は舟艇の内部にまっさかさまに転落した。
本船の舷側からみていると、はるか下のできごとで、音がつたわってこないだけに、倒れたまま動こうともしないのが即死したのではないかと、不安が体をこわばらせた。
一種奇妙な不気味さが、見ている子供たちの気持ちを沈ませた。
みんなはしゃぎあっているといっても、一人ずつの心の底はさまざまであった。
六時三十五分に船は動きだしたが、そのときあいにく、小雨が降りはじめた。
昼間から蒸し暑かった天気は、彼らが本船に着く頃には雲が厚さをまして空をいっぱい覆(おお)ってしまったが、とうとう崩れたのである。
この日の午前三時、沖縄の南東約九百五十キロメートルの海上に、気圧七百五十ミリメートルの台風が発生し、北東へ向けて沖鳥島(おきのとりしま)を通過したが、午後三時頃進路を北に変え、少しずつ西に折れつつあった。
朝は快晴だったのが雨になり、風向きも前日(二十日)の夕刻は南南東であったのが、この日の朝は無風になったかと思うと、夕刻になって北北西に回っていた。
疎開者たちは甲板に出て、ふるさとの島を見おさめようとしたが、島は小雨にかくれておぼろげにしか見えなかった。
「沖縄は見えないもん。この旅行はけがれたな」
仲宗根正男たち高等科の生徒は肩をぬらしながら、ませた冗談を言って笑いあった。
巨大な分捕り船が三隻に護衛艦二隻、那覇港外をはるかに出はなれた。
見送りの人たちは、安心したような顔、まだ心残りがするような顔、しいてうなずくような顔で、棧橋を立ち去った。
母たちは、はやく家へ帰って仏前にお茶湯(ちゃとう)をささげようと考えていた。
しかしその帰途につく人たちにさからって、具志清興(ぐしせいこう=高等科二年生)の母が、眼の色をかえてやってきた。
船の出航は遅れるのに弁当の用意はないというので、旅立ちの息子に食べさせるために、わざわざ二キロもはなれた家へかえってにぎりめしを用意してきたのであった。
だが、息子の出発に間に合わず、この母は非常になげいた。
仲宗根正男の家では、折りあしく家族が見送りに出るひまをもたなかった。
家業は海の岩礁(がんしょう)から石灰石を採取することであったが、ちょうど父が仕事を終えて海からあがるころ、それらしい船がたのもしげに連らなって港を出ていくのを見た。
彼らは、護岸(ごがん)の上に立ちつくして、暗くなるまで見送った。
日の沈む頃には小雨がはれて、太陽のまわりの雲が切れた。
沖縄の海の日没はなんとも言えず赤々と美しい。
対馬丸の甲板で、泊(とまり)校五年生の、クラスでも小柄でおとなしい当真嗣松(とうまししょう)は、小雨にぬ
れたイカダの上にたたずんで、その夕陽の姿を眼底にやきつけた。
top
**************************************** |