|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
|
2 行くも地獄、残るも地獄 |
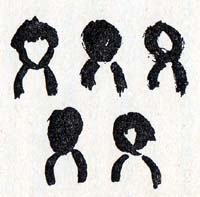 |
首里(しゅり)市の古城の麓(ふもと)、深い木立の間の表面静かな師範学校男子部付属国民学校の主事(しゅじ)室に、三十歳をすぎたばかりの当真嗣永(とうましえい)が新崎寛直(あらさきかんちょく)主事と向きあっていた。
「行ってくれるかね……」
当真は、窓の外の木の緑を見ていた。
六月に梅雨があがって七月にはいると、雨らしい雨が降らなくなった。
乾燥してほこりっぽくなっていたから、深い緑も艶(つや)がなくなっていた。
「どうかね。……四十名につき引率一人だというが、もう一人安里(あさと)先生に頼むつもりでいる」 |
安里盛市(あさとせいいち)はまだ二十代の元気な教師であった。
一世代だけ先輩の当真と組めば、お互い確かに優秀な引率教師となるはずであった。
「考えて見ます」と慎重に答えると、
「ここの隊長さんの話では、上陸は時間の問題だという。直接本州を衝(つ)くより、南方(なんぽう)の補給路を断って
しまうだろうというのが、専門家の勘(かん)だそうだ」と、主事は言った。
「専門家って何のですか?」
「戦略のさ、もちろん」
「さァ、どんなものでしょうか。たしかに、地理上の位置からいうと可能性はありそうですが。……
すぐ本土を衝くことを考えるんじゃないでしょうか」
「どっちとも言えんなァ」
主事は、そう言って、ふと笑顔になったが、すぐに頬をこわばらせて声をひそめた。
「軍は、南方(なんぽう)のどの戦線でも後退しているんだそうだよ」
「転進(てんしん)――ですか」
――うん――と主事は、声に出さずにうなずいた。
「そう急には弱くなるはずがないと思いますがね。そのうちに挽回(ばんかい)するんじゃないですか」
「そうなければならないだろう……」
話している間は気がつかなかったが、話が中断すると、窓のそとのせんだんの木からの蝉(せみ)の声がやかましかった。
疎開はすでに準備がはじまっていた。
保護者もひととおりの話を聞くと、すぐ納得が行ったようで、申込みはその日からあった。
四十名は軽く突破しそうで、引率の教師が、もう一人はぜひ必要なのだが、希望者はいなかった。
疎開学童の引率となると、これはたんなる修学旅行の引率ではない。
短くて半年から一年、長ければ二年も三年も、九州の田舎で学童と一緒に生活していなければならない。
そのあいだ保護者の手を離れた児童を団体で預かる責任の重大さを思うと、誰でも尻ごみしたくなった。
しかし、断わると教育者としての良心の問題があげつらわれるかも知れないし、希望してもしも戦局がいよいよ我が方に不利となり、敵の沖縄上陸の公算が大きくなってくると、郷里を捨てて生命(いのち)を完(まつと)うしようとする、と非
難されまいものでもない。
教師たちは進退を決しかねていたが、当真(とうま)も主事から引率の話をもちかけられると、同じようなジレンマにおちいった。
それに、沖縄から奄美大島、鹿児島へと北上する海域における敵潜水艦の跳梁(ちょうりゃく)ははなはだしいものがあるといわれ、現に沖縄に輸送されつつあった陸軍部隊が、徳之島(とくのしま)近海で撃沈され、救われて命からがら沖縄に上陸したものは、わずかに数名、という情報もはいっている。
郷土護持(ごじ)の大義(たいぎ)のもとに残るか、あるいは国策の線にそう戦力増強の名分(めいぶん)のもとに疎開するか、どちらにしても、死の影はつきまとっている。
ただ、敵潜水艦の脅威は眼前にあって、沖縄が戦場になる公算は、あくまで憶測の域を出ない……。
あれを思い、これを考えれば、疎開をすることについて、児童の父兄にしても教師にしても、簡単に決断の下せるものではなかった。
新崎(あらさき)主事は、「考えることはないよ君。大急ぎで準備しなくちやならないことでもあるし――
ここはひとつ、引受けて貰(もら)いたいな」と笑って立った。
「お帰りですか」
当真(とうま)は、「承知」と返事するのをためらった。
「明日から休みにはいる。明日から明後日の午前中には報告書をまとめて、明後日の午後には教学課に報告。――いいね」
主事は立ちあがると、腰かけに足をのせて、巻脚絆(まききゃはん)を巻きなおした。
「はァ……」
当真(とうま)は、また、窓外に目をやっていた。ぼんやりとその目は、何も見ていはしない。
「家族も一緒だからな。費用は県と国で負担するそうだ。向こうでの生活に困るようなことはさせまい」
主事は、当真のうつろな目は、家族の心配につながっていると見たのかも知れない。
当真は、主事の話を命令と聞いた。
行ってくれるかね――という言い方は、相談しているようで、実際はことわれない強い響きがひそんでいた。
断わるとも引受けたとも、確たる返事がないうちに、主事の方でも、確たる命令をしないうちに、――どちらも、命じ命じられた了解が成立して行くようであった。
「ぼくは、那覇に帰らなけりゃならん。ちょっと先に失礼するよ。バスが大変だからな。――じゃ失敬(しっけい)」
戦闘帽、国民服、巻脚絆、半張(はんば)りを幾度もはりかえたボロの靴――典型的な戦時服装だ。
主事は将校のように崩れた挙手(きょしゅ)の礼をし、当真は兵隊のように十五度に上体を曲げて敬礼(けいれい)をする。
「行くのかい」
職員室に戻ると、残務整理をやっていた同僚がきいた。
「ウン……」と、軽くうなずく。
それで、なんとなく、自分自身にはっきりと決断をつけられたような気がした。
「申し込んできた子供たちは、雪が見られると張り切ってるんだ。無邪気なものだね」
当真は、椅子にすわった。
「残ったほうがいいのか、引率で行ったほうがいいのか――よくわからん」
「行ったほうがいいにきまっている」
当真は、その断定的な言い方にびっくりして同僚の顔を見た。
「上陸はどうか知らんが、空襲は覚悟しないといけない。
空襲されたら、こんな沖縄なんか、ひとたまりもないよ。
一発で円山号(まるやまごう=那覇の大きなデパート、コンクリート三階建)ぐらいこっぱみじんになる爆弾を落すんだそうだ。学校も教育どころの騒ぎじゃないね」
同僚は声をひそめて彼の目をにらむようにささやいた。ギラギラ光る瞳であった。
そして、一語一語低いが力のこもった話しかたには、不思議な迫力があった。
「子供たちを全部――学校ごと九州へ移した方がいいと思うんだ。学校は軍へ全部明け渡して」
当真は大きくうなずいた。
ところが、そこへ他の教師たちが来て話に加わると、不可解なことに当真に疎開をすすめた同僚は、みんなには残留すべきであると説(と)くのである。
海上危険を説いて、同じ死ぬ運命なら郷土護持(ごじ)の大義(たいぎ)に生きるべしというのが、その論旨(ろんし)であった。
実際、海上が危険なことはあまねく知られていた。
本土と沖縄を結ぶ大阪商船の定期船は、小型の不定期船となり、それさえ発着は秘密であった。
公務の出張も私用も、家族の見送りさえ許されないのである。
そんなことから人々の想像では、島に居残って空襲にあうか、あるいは戦闘にまきこまれるかもしれないというおそれより、疎開すれば海でやられる危険が大きいということのほうが、より強い実感として、うったえていた。
だから残留したほうがよいと、大部分の人は信じた。
しかし、生命(いのち)が惜しいから残るのだとは言えなかった。
話題としては、「生命の危険」というふうにはあつかわれなかった。
「郷土護持」の大義名分が謳(うた)われた。
「敵の侵攻怖(おそ)るるに足らない。迎え撃つのみ」と勇ましいことをいうのがはやった。
疎開の引率を命じられるのは貧乏籤(くじ)を引きあてたものとして、表面は解釈したがるふうがあった。
それなのに、学童の疎開は積極的に父兄に勧奨する。――教師たちは、矛盾を感じないわけにはいかなかった。
「保護者のなかには、子供を半分に分けて二人は疎開させ、二人は残らせる、というのもいるんだ。
理由は、そうしておけば、どっちがやられても、一方は残るというんだ。おもしろいことを考えるもんだ」
保護者父兄は、おおかた子供を手放すことの不安を訴えた。
途中の危険、向こうでの生活、なにひとつ安心できる材料はない。
問いあわせて学校にくる者にも、こちらから家庭訪問に行って説得するのでも、教師たちはその不安を消し去らせるほど、確信をもって説明することはできなかった。
――そうですねェ。海上は海軍が護衛をつけてくれるでしょうし、向こうでの生活は国家が全部見てくれるでしょうから、心配はいらないと思います。
なにしろ戦力増強の国策にそって御奉公の道につながるものですから、少々の不利不便は我慢しなければならないですよ――
国策、戦力の増強、軍の要請、戦略上の措置――そういう言葉をふんだんにつかって、説明する教師も説明を聞く親も、互いに納得しようと努力しているのであった。
首里城(しゅりじょう)の城壁は、うっそうと茂る老樹(ろうじゅ)の間にそびえていた。
日が暮れて城門からだらだらと降りてくる冷え冷えとした石垣のあいだを、当真(とうま)は家へいそぐ。
家には妻子が、こんなこととは少しも知らずに、待っていよう。
しかし、彼の胸の中では、疎開はすでに与えられた任務として生きていた。
ジレンマや矛盾は、疎開学童引率を任務として割り切ってひき受ける以外に解決の道はない、と心に決していた。
引率教師の決定は、学童のそれにおとらず、どの学校でも困難をきわめた。
付属校では、こうして当真嗣永(とうましえい)と安里盛市(あさとせいいち)とを決定したが、そのうち安里の老母が、息子を手ばなすことをひどく嫌がったので、緊急に安里を真栄城朝教(まえしろちょうきょう)に切換た。
この四月に師範学校を卒業して赴任(ふにん)して来たばかりの、那覇国民学校の石川裕子(いしかわみつこ)の一家は教員一家であった。
父は南部島尻(しまじり)郡具志頭(ぐしちゃん)国民学校の教務主任だったし、姉は那覇市上之山(うえのやま)国民学校につとめていた。
母も今は辞めて家にいるが、以前にはやはり教師であった。
父は土曜日でないと那覇の家に帰らなかった。そして、日曜日の夕方には南部に戻った。
家には祖母と母、姉、弟二人でいた。
疎開勧奨の職員会議があった日、上之山校に勤めている姉は、「疎開しよう」と、ひどく思いつめたように言った。
母が輪番で隣組長をやっていたし、疎開の話はよく家でも出てはいたが、これまでは、そんなに身近なこととは考えてもみなかった。
東京の疎開をあつかったニュース映画で見た、児童たちの嬉(うれ)しそうな顔を食事のとき話題にしたことはあったが、空襲から子供たちを守るための当然の措置(そち)とだけしか考えなかった。しかし、
「サイパンが落ちたのだから、当然ここも危険なのよ」と、姉はいった。
それまで土曜日ごとに帰って来ていた父は、疎開したほうがよいとは思っているらしかったが、積極的に行けとは言わなかった。
「私は、児童の引率を希望するつもりよ。もし選に洩れたら、学校をやめても行くわ」
「お父さんと相談してからになさい」
母は、乗り気ではないようであった。理由は簡単、海上が危険だからである。
那覇から出た船や、入ってくるはずだった船の遭難は、そのたびに厳重な隠蔽策(いんぺいさく)を講じていたにもかかわらず、いちはやく皆のあいだに知れ渡っていた。
「ほんとに空襲や敵の上陸があるのかね」
それがはっきりしていれば、疎開の決心も容易であった。
残っているほうの危険率が、海上の危険率より高ければ疎開すべきだし、その反対なら残っていたほうが安全である。
しかし、誰もそれを知らない。疎開はいわば、ばくちを打つようなものであった。
「残っているより行ったほうがよいと思う。――たとえ上陸して来ることはなくても、空襲はあるわ。
空襲されたら、那覇なんか、ふっとんでしまうわ」
姉の意志は疎開に決まっているようであったが、裕子(みつこ)は決心しかねた。
残っているほうに賭けてもよい、と思ったりした。
たびたび親戚の者が集まって疎開の相談をした。母方の親戚は、多くは反対であった。
沖縄の空襲や上陸についてはもちろん、戦局そのものについても楽観的であったからである。
裕子(みつこ)の考え方には、それも大きく影響しているようであった。
父が帰って来てから相談し、その上で家族の態度をきめることにしたが、姉はすでに申込みをしているのかも知れなかった。
床にはいってからも、疎開したほうがよいと主張した。
親戚の者の意見は、父方と母方をあわせると、賛成と反対が相半(あいなか)ばしていた。
行くのも残るのも、各自の生命のこととつながりのある問題だけに、どうしなさいと、たとえ親戚でも他の人に指示できることではなかった。
「自分ならこうしたい」というふうにしか言えなかった。
「そうだね、お前と弘ちゃん(中学二年の弟)でも行かせてやりたいね」
話しているうちに残るほうにも不安はあって、両方に家族を分散させておけば、全滅はまぬがれると、ふと母は考えついたらしかった。
学校では県からの文書通達にしたがって児童の希望者を募(つの)った。
教室で、挙手(きょしゅ)をさせて希望者の概数(がいすう)をつかもうとしたが、それはきわめて不確かであった。
児童の家庭でも決心がつきかねているのだとは、容易に想像がついた。
父は夏休みにはいってすぐの土曜日に帰って来た。例の通達文書は、父の学校にも行っている。
「みんな行きなさい」
父はそう言った。
具志頭(ぐしちゃん)村といえば、砂糖のほかに建築材の粟石(あわいし)が出る農村であるが、そこにも兵隊が入っていて、校舎は軍に接収(せっしゅう)されていた。
村の東側がわずかに海に面していて、その海は洋々たる太平洋であった。
その水のつながるむこうの涯(はて)で、苛烈(かれつ)な死闘が繰り返されているに違いなかった。
兵隊は、そこの海岸に陣地を構築していた。
上陸して来たら水際撃滅(みずぎわげきめつ)だ、というのが兵隊たちの合言葉(あいことば)であった。
静かだった農村に兵隊が溢(あふ)れたので、それだけで戦局の緊迫感を皮膚にじかに感得させられた。
「十八日には東条大将が総理大臣を辞めて小磯(こいそ)・米内(よない)連立内閣が成立した。
サイパン失陥(しっかん)の責任を取ってのことだそうだ。
内閣が総辞職し交替するくらい事態は逼迫(ひっぱく)していると見たほうがよさそうだ」と父は説明した。
「みんなが疎開したら、お父さんはどうしますか」と母が心配した。
「私は残っていてもいいわ」と裕子(みつこ)はいった。
「いや、お前も行ったほうがいい。お父さんは、今でも田舎で一人でなんとかやっている。
経済上のことだって、いまでも、結局は二世帯ということで不経済な点は一緒だ」
「そうね。お父さんが、家のことを心配して食料をかついで日曜ごとに帰っていらっしやる苦労も助かるわけね」
母親らしい気のくばりようであった。
父は帰ってくる時は、きまってリュック・サックに野菜や芋をつめて来た。
おかげで家族は助かったが、公務を持っていて、定期便のように家と往復することはしだいに困難になって来ていた。 |
 |
「帰ってくることは別に苦労とも思わないが、汽車(製糖工場のある村を縫って軽便鉄道があった)は軍の輸送に使われて、我々の乗る余地もないのに、そのうえ時間もずいぶん狂って来た。
それから疎開事務や軍が校舎を使っている関係の仕事や何やかやまで雑務が多くなってくると、帰って来ることができなくなってしまうだろうよ」
父はさらに、学校では那覇の学校と同じように、児童や父兄に、疎開の重要な意義を説明し、勧奨(かんしょう)していると言った。
職責の上からも、家族を疎開させることが必要であった。
疎開することにきまると、海上の不安、疎開先での生活の不安、父一人を残して行く心残り、そういったことはすべて不問に付して口にしない、という暗黙(あんもく)の約束も同時に成立した。
家族全部が疎開するときまると、それまでは残ってもよいと考えていた裕子(みつこ)も、ぜひ行きたいと考えるようになっていた。
彼女は翌日渡嘉敷(とがしき)校長に、もし引率教員にしてもらえるなら、そうしてほしいと申し込んだ。
裕子(みつこ)の父も、わざわざ渡嘉敷校長に会って。娘を引率教員にしてやってほしいと頼んだが、選考して内定していることだから、悪(あ)しからず了承(りょうしょう)してもらいたい、と断わられた。
養護教員としてでもいいからと頼め、と娘に伝えて、自分の学枚に帰って行った。
引率教員は、児童四十名に一人の割り合いだから、児童の数が多ければ多いほど、引率教員の数もふえる。
彼女は、児童の希望者がふえることを願った。
後になって彼女の願いどおり、児童の希望者がふえたため、彼女は新しく引率教員に追加されることになった。
教師たちはほこりにまみれて、児童の家を一軒一軒訪問して歩いた。
彼らは、便法(べんぽう)として、疎開させそうな家庭を見当つけて廻ることにしていた。
経済的にゆとりのない家を廻っても大てい無駄であると、一日歩いただけで充分にわかった。
父親が役人だとか、町の顔役であるとか、そういう家庭ならまず大丈夫であった。
学校には受付係が残っていて、教師たちは説得して受付た申込みを係の教師に報告した。
その間に、自分ですすんで申し込む児童もいたし、あとで取消しに来る児童もあった。
級主任も、自分の級の誰が疎開するのか、正確には知っていなかった。
通達の指示によれば、二十二日までには電話でもよいから疎開希望学童の概数を報告せよということであった。
だからこそ奥村視学(しがく)は、二十日には全校長を集めて、処理の状況を聴取し、ただちに家庭訪問等によって疎開を勧奨し、希望者をつのるように命じたのだが、二十二日までに報告されてきた概数は、満足すべき数ではないと思われた。
二十八日までには確実な数が報告されてくるだろうが、昨日から夏休みにはいったこと、
学童も父兄も連日飛行場づくりやら陣地構築(じんちこうちく)、防空壕(ぼうくうごう)つくりなどの作業に動員されるから、連絡がかならずしも充分になされるとはかぎらないこと、
これらのことから推しはかると、二十八日までに報告されてくるはずの確実な数もまた、満足できないのではないか、とあやぶんだ奥村視学(しがく)は、二十二日に電話で各校の状況をいちいち聞いて市長に報告した。
報告を聞くや、富山(とみやま)市長は「そんな、手ぬるい!」と叫んでテーブルを叩いた。
「全学童を疎開させる意気ごみでやらないと、軍の要請にも沿いえないではないか。
それでは、戦時下の教育行政にはならん」
奥村視学は、市長の絶叫にはなれていたから、眉(まゆ)ひとつ動かさずに、次の指示を待っていた。
自分から策を進言することはしない方針であった。――
戦時下の教育行政という言いかたなどが、あまり気にいらなかった。
教育の専門家でもないのに、市長だというだけで、学校の問題に口を出しすぎるきらいがあるのだ。
「ただちに校長を集めて、具体的な方策を講じよう。大至急電話させてもらおう」
「そうしましょう」
奥村視学は、職員を使って八校長に電話で連絡させた。
通達の指示による疎開希望学童の概数の報告をしておいてからの非常呼集であったから、なかには一応報告しておいたことでほっとして、一時学校をあけている校長もいたのであろうか、それから間もなく集まって来たのは、垣花(かきのはな)、上之山(うえのやま)、那覇(なは)の三校だけであった。
市役所の建物はいかにも古色蒼然(こしょくそうぜん)としていて、市長の応接室も日の長い真夏のことなのに薄暗かった。
市長富山徳潤(とみやまとくじゅん)は、不機嫌な顔をして市長室にいた。
「暑いですな、市長さん」
渡久地(とぐち)垣花(かきのはな)国民学校長は、いつものおだやかな調子で挨拶した。
はいって来た市長の、不機嫌に口元をゆがめた顔に圧迫感があって、全員が一瞬に不機嫌さに感染したようだったが、渡久地校長は、それに意識的に抵抗した。
「夏だからな」
市長は無駄口をきくなと言いたげであったが、その言いかたが、子供がすねているような響きをもっていて、おかしかった。
校長たちの表情がやわらいだ。
「二回目の連絡では、残りの校長もそれぞれ学枚を出たそうですから、もうすぐ全員集まるでしょう」
奥村視学がそう言っているうちに、親泊(おやどまり)泊(とまり)校長が、「暑い、暑い」と言いながら、頭の先から首、顔をごしごしスフ(代用綿)の手拭でふきふき、はいってきた。
そして、甲辰(こうしん)、久茂地(くもじ)と続いた。
「疎開は、みなさんも承知の通り、挙国一致(きょこくいっち)、国土護持(こくどごじ)のために、国家の方針として遂行されるべき大きな義務ですぞ。だいたい、時局はですな……」
校長たちは、またか、いった顔をした。
この市長が、「だいたい、時局はですな」と言い出すと、わかり切った時局論を長々と弁じるのが常であった。
同じことを何度も聞かされて、うんざりしているのである。
校長たちの思惑にかまわず、例の調子でしゃべり始めたが、途中で気がついたように話をはしょった。
「もう一度、連絡させてみなさい」
天妃(てんぴ)、松山(まつやま)両校の校長が見えない。
「疎開希望者が少ないのは、みなさんの努力が足りないと断ぜざるを得ない」
市長は、叩きつけるようにいった。
「ですが、何しろ急ですからな。一学期の事務整理やら何やら、先生たちも大変なんですよ」
泊校の校長は、おとなしく抗弁した。
「それは文句です。――
天妃の校長の如きは、潜水艦が危ないがそれでも行くか、と朝礼で言ったというではないか。
話にならん」
市長は、テーブルにドシンと音を立てて拳(こぶし)を置いた。
「校長ともあろうものが、これでは時局認識もどうかと思う」
その天妃校長は松山校長と前後して、
「どうも、遅くなってすみません」と詫(わ)び詫び、入ってきた。
「私も家庭訪問に出ていまして、学校に帰ってから聞いたようなしだいでして……」
松山校の枚長は、そういいながら腰をおろした。
「とにかく、みなさん自身が、よく時局を認識し、戦局の容易ならざる事態を見きわめてくれなければいかん」
ごもっとも――というかわりに、みないっせいにうなずいた。
「今のところは、父兄のなかにも迷っているのがたくさんいるでしょうが、二十八日までには相当数集まると思います」
「努力せんで集まるわけがない」
市長は、吐(は)き捨てるように言った。
「いいえ、先生がたの苦労は大したものですよ。
一学期の整理事務やら作業、家庭訪問、父兄会、なにしろ、一昨日から今日まで、それこそ寝食を忘れています」
「それでいて、たったあれだけか」
「まだ二日間ですから……。二十八日までには、ずいぶん集まる予想をしています」
それから校長たちは口々に、だんだん申込者が増えつつあると強調し、父兄が一番気にしているのは何かという雑談みたいな話し合いになった。
たったそれだけのことで、臨時呼集をしたのかと、八校長は不満に思っていた。
市長も、訓辞をひととおり述べてみると、もうあとに言うことはなかった。
希望者が少ないから、もっと努力しろと言うだけのことであった。
しかし、不機嫌はなおらなかった。
苦虫(にがむし)を噛(か)んだような顔で、校長たちの話を聞いていた。
「ところで、学童の乗る船ですが、これはひとつ軍艦にしてもらいたいですな。――
市長さん、軍のほうにお願いして下さい」
平良(たいら)天妃校長は、みなの話から急に逸(そ)れたようにいった。
小柄だが、外柔内剛の風格がある。
市長はほかのことを考えていたし、相手が遅刻して来た上に、朝礼で疎開に反対のようなことを言ったと伝えられている平良校長であったから、にらみすえたまま、急には返事をしなかった。
「そうですな、軍艦でやってもらうと助かりますよ。このあいだ軍艦が疎開者を乗せて行ったという噂もありますし……」
「父兄の関心も、それが一番です」
「軍艦だということがはっきりすると疎開を勧めるのも、やり甲斐(がい)があるというものです」
校長たちは言いかたは違っても、市長に、学童の乗る船は軍艦にするよう交渉してくれと頼んでいることは同じだった。
平良校長だけなら、できないと断わってしまえたが、みんながそれを言い出すと、そうはいかない。
「できるだけの力をつくして、軍艦にしてもらえるよう交渉する」
校長たちは、市長の交渉の結果を信じたかった。
top
**************************************** |