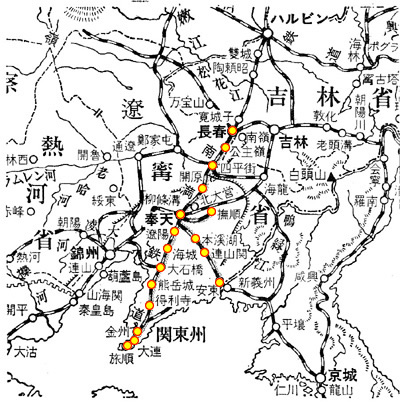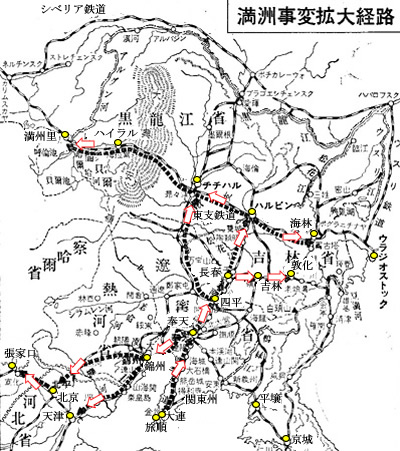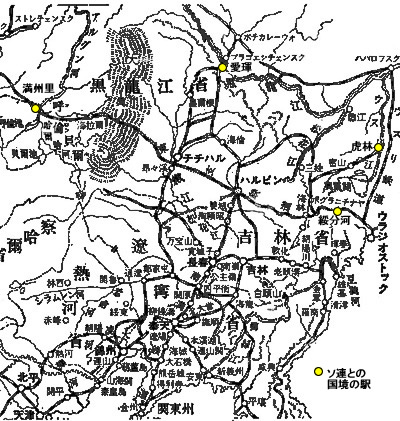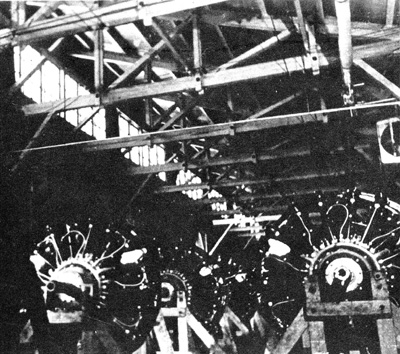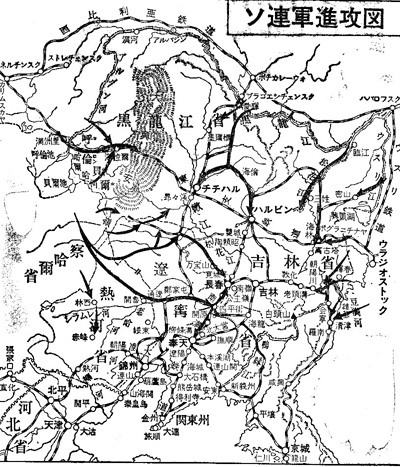|
������������������������������������������������������������
���S�Ɗ֓��R�@���a�����̓��t�@�l���Y�K�@��Η玟�Y�@������d�Y�@���{�B�@���c�N���@���c�[���@�L�c�O�B�@�F�_�ꐬ
�Ô����F�@�\�͐M���@��J�h��Y�@�Ό��Ύ��@�X���@���O�@���{�d���@2�E26�����@�����푈�@
���B���c���@HOME
���S�Ɗ֓��R
�i���S���S�j�@�|�X��j���@1970����蔲��
�j
| 1�@�������Ƃ̖���5�S���̌����c
top
�@�����m�E���ꗝ���Ƃ��āA���S�֓������̂́A�吳10�N�i1921)�̂��Ƃł������B���L�m��Y���قɑ���āA�R�{�Y��5��ڑ��قɏA�C�����Ƃ��A�����͕����قɂ̂�������B���̐l���ɁA���O�Ƃ��Ɉ٘_���ƂȂ���҂̂Ȃ������̂́A�l���A��r�Ƃ��ɍ��������Ă���؋��ł��낤�B�Ƃ��ɎR�{�́A�c���`�ꑍ���Ɂu�������قɂ���Ȃ�A���ق������Ă������v�Ƃ����������o�����قǁA�������Ă����B
�@���a2�N�i1927�j�̏A�C���X�A�R�{�V���ق��肪�����d���́A����5�S���̌��݂ɂ��Ă̌��ł������B�O���َ���ɒ����ƒk�����J��Ԃ��Ȃ���A����̉^�тɂ����炸�A�������ꗶ���Ă����吳2�N�ȗ��̖��S�̌��Ăł������B�������R�{��O�ʂɗ��ĂāA�ꋓ�����̕��@�������������̂́A�c���`��ƒ������̊W���v���o��������ł���B
�@���܂��V�R�̑��i�ߊ��A�k���̑匳���ł��钣�����́A�����������Δn���o�g�ŁA�����ڎ���ɖ��B�R�ɕ߂炦���A�����e�E�Ƃ��������O�A�����Q�d�������c���`�ꏭ���ɏ�����ꂽ�B�����ɖ�S�Ƃ̒��������A�s������̉��`��Y���悤�Ȃ��Ƃ͂���܂��B����͒����̑匳���A����͓��{�̑�����b�ɂȂ��Ă���̂��B�������ʂ���A�����Đ�ɐ�������`�����X�A�Ə����͌����̂ł������B
�@�R�{�͏����Ƌ��c�̂����A�k���֕������B���@�Œ������Ɉ������R�{�́A1�T�Ԍ�Ɂu������v�đ�A�֖߂��Ă����B���Ȃ킿����5�S�����̂����A������7���̑�j�������̂ł���B
�@�@�։��|�}���
�A�@���t�|���͊�
�B�@�g�с|���
�C�@�`�`�n���|�����Q����
�D�@����|�\������
�E�@�V�@�|��V�Ȗk��
�F�@���g�|�C�ъ�
�@����͌��݂S���������A������؊��Ƃ���A�Ƃ�������ŁA�c��̌��Ă͂��̌�̌��ɂ����Ē����������邱�ƂɂȂ����B��́A���S�̑������O�ۂƒ�����ʕ��Ƃ̎����Ղ����ŁA���������_��������͂��ł������B
�u���t���́A���ɋ@�����ǂ�������B���k���āA���̖��͋C�ɂ������Ă������̂т̂тɂȂ��āA���ɂ��܂�A�Ɠ������������炢���v |

�R�{�Y��10�㖞�S���فA�O�䕨�Y�̏��Ѓ}���Ƃ��Ċ���㐭�E���肵���F��̊����ƂȂ�B
���̌㖞�S���ُA�C

�����m�E�����فA���̌㐭�E���肵�O����b
���{�̍��ۘA���E�ނ���ƈɎO���������哱���� |
�ƁA�R�{�͑������̎Ј��������i�炢�炭�j�Ɍ��������A���Ƃ̉�k������قǃg���g�����q�ɂ������͂Ȃ������B
�@�R�{�ɂ͓c���`��̑����������Ă�������ł���B�吳15�N�i1926�j�ȗ��A�Ӊ�̖k�����͂��܂��āA�������̔s�k�̐F�������n�߂��Ƃ��A�c���͒��Ɍ�������Ă����B��������m���Ȃ���A�O���̃e�N�j�b�N�Ƃ��āA���ɓc���̒��x�������������B
�@�������A�c�����Ăђ��x���ɕς�����̂́A�R�{�̗v�������Ē�������5�S���̒���������Ƃ����A�R�{�|�����̋�������}�ɓ�������̂��Ƃł������B
�@�����A�O���̋�����͗L�ד]�ρA��������̕��G���ɂ����ŕϖe����B���Ƃ��A���������x�����Ă����֓��R���A�����K�����ƕς��ĕ�V�R�̕��������ƒ��̉�����l���͂��߂��Ƃ��A�c���`��͒����x�����Ė��B�A�҂����A���B���ؖk���番�������āA���ɖ��B�������悤�ƁA�k�����{����̊t�O���g���̊������n�߂����Ƃ��B
�@�܂��A�k���ɂ����G�ȓ���������N���邽�߁A���̐S�͔L�̖ڂ̂悤�ɕϖe�����B�����O�Ȃ̔r���^�����œ|���{�鍑��`���f���čr�ꋶ���A�s�{���l�������u21�����v�̎�������ǂ��ăf�����J��Ԃ������ɂ����ŁA���́u���Љ^�����ցv�̕z�����o���Ȃ���A�u�R�{���v������ނ�ɂ��悤�ƍl���������̂��B |
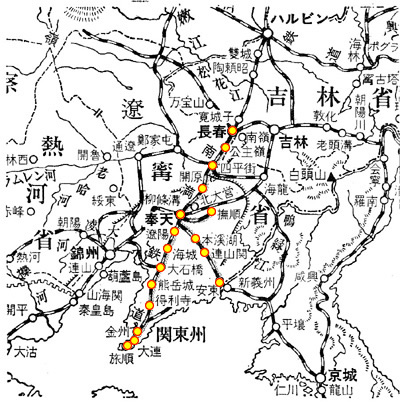
�����̖��S�͑�A�|���t�Ԃ̓얞�S���ƕ�V�|�����Ԃ̈���������Ŏ��Ђ̓S���Ԃ̊g�傪���߂��Ă����B |
|
�@���a3�N�i1928�j�̐����x�݂�ԏサ�āA���������ق͑������O�ۂ̉ے��A�Z�t�ƌ��������_��Ă�����ŗ��肠�����B�����I�ȐՂŌ_�����킳��邱�ƂɁA�b�����Ă����̂ŁA���ق̌_���܂Ōg�s�����A�ے��ȉ�3����k���֑������B�Ƃ��낪�k�����{�͂̂�肭���A��̂킩��Ȃ������킯�����Č_��������A���𗧂Ă�3�l����̖��S���_�ŐK���܂��������A��l�A���̓i�}�R�̂��Ƃ��Ԃ�Ԃ悵�ĕ߂��ǂ��낪�Ȃ������B
�@���̒������O���́A����{�̒���ŋC�Z�ȓ��{�l�����肳�����B���Lj�l�ŋ��̃L���L�������ŁA�������A�h������A�|�M���ꂽ�܂܁A�������ɖʐڂ����邳�ꂸ�A40���Ԃ���������A���̂Ȃ��̑��و鋃�����������̌��ʂɏI�����B
�@��������畏��ƕϖe���A���̂悤�Ȍ`�Œ�����l�̑ԓx�ɂ����ꂽ�̂ł���B��̒j���q�ǂ��̎g���݂����ɁA�Ȃ��Ƃ���Ȃ��A�r�ɂ����Ј��́A�S�邽��C���Łu���̗��؎ҁI�v�Ƌ���A�����ڂ�Ƙr��g�肵���B
�@���ƍ��Ƃ̐����A���قƑ匳���̊O���\�\�Ƃ͂���Ȃ��̂łȂ������B�����Ȃ���A�����l�̎ς���ʘV�Ԃ��ɕ������B�܂�ʼn�������ɏ��������Ă���悤�Ȃ��̂��B���̒�ɖ��C���Ȕr���̓{����m���Ă��Ȃ���A���Ȃŏ��V�̋@�^�ɏ��A��������Đ�����i��ł���ƐM���ċ^��Ȃ����S�Ј��ɂ́A�����ƕ��Ȃ���ł������B������ɂ���A�����قɍ��킹��炪�Ȃ��B
�@�������A��������Ă���܂�A���������Ɏv���߂Ă���3�l�ɁA�����͔����Č������B
�u�\�\�Ђǂ��ڂɍ������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͒��ёO�̂��Ƃ���B�S�z���邱�Ƃ͂Ȃ��B�N�B�͈ꐶ�������������v |

�V�Ò��Ԃ̕ČR�i�ߕ��O�̒������i�����j�ƃR�[�i�[�ČR�i�ߊ�(�E�j
���͔n������g���N������V�R���̑��t�Ƃ��Ē���h�̌R����j��A�ꎞ�͖k���ɂ����Ėk�������𐧈����u�匳���v���ď� |
�@���̂��炢�̂��ƂŁA���������ł͂Ȃ������B���肪�����ł���A���̎��łB���ꂾ���̂��ƂŁA���S�̌��Ă����X�ɉ������Ă䂫�A�m�ŕs���̕��j���т����߂ɂ́A���G�Ȓ�����̈É_��D���Ĉ����������J���Ă䂭�����̂��Ƃ��B���̑���͖ڂ܂��邵���ڂ�ς��A����ΐ퍑�̑Β�����ł������B
�@���͒��������������͗k�F軂�������Ȃ����A�g�ʏ˂ł��邩������Ȃ��B�k������������ΏӉ�ɂȂ邩������Ȃ������B�����̕��肪�A���{�̑Β�����я��O���Ƃ̔����ȓ����̒��ŁA�ǂ̂悤�Ȍ`���Ƃ�̂��͐����������Ȃ��B�O���̂܂����͓�����O�̓��풃�ю��������B�l�ԕs�M�Ȃǂɂׂ͊��Ă����Ȃ��B
�@�������̕ϖe�̗��j���l����܂ł��Ȃ������B�����āA�������{�������Ȃ̂ł͂Ȃ��A�푈�ɂ�闘���̊l���A����ɒD���A�D���������Ƃ�������̉Q���̂Ȃ��ł́A���E�̐����̖e�i�����j�͉����łȂ����̂͂Ȃ������B
�@�����͋@���킹���R�{���قɈӌ���\�����B�R�{�͍Ăіk���֏�荞�B���Ȃ킿�A��2���k���R�̍U����O�ɁA���������Ă��钣�������Ƃ炦�A���d�ɒ�������߂��B�����āA������7�����������_��ƂƂ��ɁA�������A�������A����ɋg�։������A������̌_��𐬗��������B�ʂƌ����ẮA�������̒���������킯�ɂ͂����Ȃ������̂��낤�B�g�ܐ������́A���̕�V�A�Ҍ�ɒ���\���������s�Ȃ��A3������Ɍ��ݎ��{�ɓ��ݐ邱�ƂƂȂ����B�\�\���a3�N5��15���̂��Ƃł���B
2�@�������̔��E top
�@�Ƃ��낪�A�����1�������o���Ȃ�6��4���̕��ŁA��V�Ɍ����Đi��ł����������̓��ʗ�R���A���S�A�����̃N���X�n�_�Ŕ��j���ꂽ�B8���ڂ̋M�o�R�ɏ���Ă������́A�d�����ĕ�V����̑匳���{�Ɉڂ��ꂽ���A�ߑO10�������5�v�l�Ɍ�����Ȃ���A56�̐��U������̂��B���܂����Ǝv�����͎̂R�{�A���������ł͂Ȃ��B���@�̓c���`��͌��n����̓d��ɐڂ��Ċ�F��ς����B
�@����Ɩk���T�ނɓ��ݐ������������V�Ɍ}���邱�Ƃ́A���S�ɂƂ��č���̌��ĉ������~���ɐi�ނ��Ƃł�����A���{�̒������ɂ��Ă��A�Ӊ���k�������Ƃ����ꂽ��A���B�܂ł͍U�ߓ���ӎu�̂Ȃ����Ƃ��m���߂Ă����̂ŁA����������`�̃x�[�����܂Ƃ����܂܁A�c���̐����I�Ӑ}�͒B�����ꂽ�悤�Ȃ��̂ł������B�Ƃ��낪�A���҂̎d�Ƃł��邩�A���̕�V�������O�ɔ��E�Ƃ����厖�����N���Ă��܂����̂��B |

���a3�N6��4�������A��V�w�������O�ɁA��������������W�]�ԂƐH���Ԃ̒��ԂŔ������W�]�Ԃ͎ԗւƏ����c���Ĕ�U�A�d�̂̒��͕�V����ɉ^�ꂽ�����S�����\���ꂽ�̂�19���A����������̓��{�l�̌R���ږ�V�㏭���͖����������B |
�@�����͑�A����V�����ɔ��Ō�������@���A���̎��فA�Ɨ�������A�֓����x�@�Ȃǂ��K���āA�����O��̏����W�߂��B���j�̌���ɂ́A2�l�̒����l���h�E����Ă����B���̂����2�̔��e�ƁA3�ʂ̎莆���������ꂽ�B���̒���2�ʂ͓�����̔��j���߂ł���A�c���1�ʂ͍������{�̏����g�i�m���j�A���̕�Ⳃɂ������߂����j�v��̖����ł������B
�@�������A���E�����̂�2�l�ł���͂��͂Ȃ������B��Ԃ̔��j�́A�S���̋��r�̏㕔�ɑ��u����100kg�ȏ�̉��F����ŁA���ΐ��̓d���́A�����200m�̒n�_�ɂ��������l���܂ŕ~�݂���Ă������B6��12���̗��R�Ȕ��\�ł́A
�u����̎������ł��邱�Ƌ^���Ȃ��v
�ƒf�肵�����A�������̂��킴�ɂ��Ă͑傪����̂��̂ł������B
�@���łɗ\���͂��Ă����̂����A�����͏L���Ƃɂ�B1�����e������ēS���֔����オ�낤�Ƃ����e�����X�g�̒����l2�����A�d�v�Ȕ��j���߂̖�����3�ʂ������Ă��邱�Ƃ������������A������̕��Ɍ������ĊȒP�Ɏh�E���ꂽ�Ƃ����̂��A�Ԃ������Ă����B�U���ɂ��Ă��A�^�}�̂�邢�U���������B�l���܂�200m�����ΐ��̓d�����Ђ��A����ɓd���̃X�C�b�`���������ֈߑ��������̂ł��낤���B�����W�]��エ��я���̕����m��Ȃ��������͂Ȃ��B�����܂ōl���ď����͋}�ɃM���b�Ƃ����B�܂������֓��R��������̂��B
�@�֓��R�́A���B�ֈ����グ�悤�Ƃ����V�R���������A�������̉�����������悤�Ɛ}���Ă����B�����ő�14�t�c�ƒ��N�R������40���c���V�ɏW�����A�яB�o���������������A�u�҂����v���������͓̂c���`��ł���B�����͊֓��R�Ɂu���R�̓S���A���Ɋւ��鋦��v�𔗂�ꂽ�Ƃ��A�ƒf��s�̋C�����������\�������āA�����s�����������B�c���ɂ���Ċ֓��R�̕@�����͐܂�ꂽ���A���̕������āA���������E�̖d���ɓ��ݐ����̂ł͂���܂����B
�@�s�K�ɂ��āA�����̐����͓K�������B�֓��R�͈ӊO�ȂƂ��납��A�K����͂܂�Ă��܂����̂ł���B����܂Ŋ֓��R�͎��������̏��ڍׂɕ`�����u�،��v�d��𗤌R�Ȃɑ���A�����܂�
�u������̖d�����낤�v
�Ǝ咣�����B���R�Ȃ�
�u�킪���n�R�ɐӔC�Ȃ��v
�Ɣ��\�����B�c���`��͎��������{�R�ɖ��W�ł��邱�Ƃ�V�c�ɐ\���������B���ꂪ�����ɂł肩�������̂́A�����̊�������ł͂Ȃ������B��V�̕��C���̂��₶����ł���B
�@�����A�����Əe���������C���̂��₶�́A�Ȃɂ��ƂȂ��ƌ���}�s�����B�쎟�n�ɂ܂����āA���킲�펀�̂ɂȂ��Ă���2�l�̔Ɛl�̊���̂�������ŁA�����Ƌ��B���A�U�������A��ɓ������Ă������j����3�l�̂�����2�l�ŁA��V���߂Q���Ă���A�w�����Ŋ��҂Ȃ̂��B�������T�b�p�������ߕ��ɒ������A�@�̂܂���ɋA���Ă������Ƃ����B�@���₶�͑ȊNJ��̊֓����x�@�ɒm�点�A�g����ɂ��������āA���g�ьR�n�c���̗��Ƃ����j�������т��������B���͐ΒY�̔��Ƃ̑嗤�Q�l�A�ɓ����O�Y�ɗ��܂�āA3�l�̕��Q�҂�����B�ɓ��͈�l�S�~�Ȃɂ�����3�l�̖����A�֓��R�����Q�d�͖{���卲�Ɉ����n�����B�͖{���c�z�ق̎����ŁA���e�ƋU�̔��j���ߏ���3�l�Ɏ������A�����ԂŌ��n�֑������B |

�͖{����@�吳15�N3���֓��R�����Q�d�ɏA�C�A���������E�̐ӔC����ꏺ�a5�N4���\�����A���̌㖞�S�����A�R���ȎR�������В����C�A��Ɨe�^�҂Ƃ��Ē����ŕa���A73�� |
�@�d���̃X�C�b�`���������̂́A��V�Ɨ���������̓��{��тł������B��т͕����ɖ�����3�l���h�E�����悤�Ƃ����B�������A�����삯�t�����Ƃ��A3�l�̂����̉��Ƃ����j���p������܂��Ă����B���ǁA2�l�ɔ��e����������܂܁A�e���ŎE��������������ɓ]�����Ă������B
�@�����̖d���́A���̕��C���̂��₶�̏،������J���Ă������̂����A�s���̔��e2�͏؋��i���ׂ̒i�K�ŁA��V�̌Ó������A���{�̌����������Ă��������Ƃ����������B�������A�����炪�瓦�����������Ƃ����j�͂ǂ��ւ������̂��B�A�w�����Ŋ��҂ŁA�S�~�Ŗ��̔����钎�P���̂悤�ȑ��݁A�Ɩd���R�l�݂̂Ȃ����j���l�Ԃł������B���Ƃ������Q�҂̎Ƒ����݂��A���܂����`�Ŕr������̒�ɗ���A�����l�̈Â��߂��݂��������Ă������ƂɁA���̌�A�����͂���Ƃ����قǒm�炳��邱�ƂɂȂ�B
|
3�@���w�ǂ̏Ӊ�Δh���� top
�@�������̌�p�҂͌䑂�q�̒��w�ǂł������B�������A�������{���k�������Ƃ������ƁA�w�ǂ͏Ӊ�̌R��ɂ�����Ƃ����\�����ɓ����Ă����B���܂܂ł̌ܐF����p���āA�������{�̐V�������ɕς��A��������Ƃ����\�ł���B�Ӊ�͒���܂ŌR��i�߂Ȃ���A�w�ǔh�Ɍ�������܂��ĉ��_����ƂƂ��ɁA����ւ̕��]�����܂����B�k�����������������v���R�́A�Ƃ̕s��������p�������B���{�ɑ��Ă�1896�N�̓����ʏ���������I�ɔp�������B������ׂ��炴�鐨���Ȃ̂ł���B�����ŁA���w�ǂ̍������{������j�~���Ȃ�������A�ǂ�ȕs�����N���邩�킩��Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A�ǂ������킯���A���w�ǂ͊֓��R�i�ߊ��ɑ��āA���������o�ς̑S�ʓI������A�\���o�Ă����̂ł������B�g�҂͕�V�R�ɖ͔͑��𗦂��Ă��錳���{���R�R�l�̍r�،ܘY�ł������B�������w�ǂ͏Ӊ�ɕ������Ȃ��œ�����������s����ȏ�A�H���Ƃ��ē��{�~4���~��K�v�Ƃ���ƌ����A�ً}�̎؊���\���ł��B�@
�����͑����i�ߊ��ɌĂ�A
�u�c���ɋM������������Ă��炢�����̂��v
�ƌ���ꂽ�Ƃ��A�w�ǂ̌��ӂ�F��Ƃ��Ď���Ȃ���A�s�v�c�Ȃ��Ƃ��Ǝv�����B
���̍�����d�E�����֓��R�ɓ���������Ă��Ă���Ƃ́A�퍑�����炵������肩���������̂��A�ƁB |

�������̑��q�Ō�p�҂̒��w�ǁB
�Ӊ�̍����R���炳��Ɏ������̒����R�ɓ]��������A���͑�p�Œ����H�����𑗂�A�Ӊ�̎���A�����J�ɓn��B |
������ɂ���A��ď����̂Ȃ��ɁA���S�Ɩ���5�S���̍�������і��S�t���n�̓P�p�ȂǂƂ����������܂܂�Ă���W��A���{�̈ӌ��������K�v������̂ŁA�R�{���قƋ��c�̂����A�����͓����֔������B
�u4���~���肵�悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ����B�������z���傫������v
�ƁA�c���`��͎���Ђ˂����B
�u���͓��{�ƍ������{��V���ɂ����Ă���̂�������v
�����̐��{�����͓�q�����B
�Ȃ�قǁA�������ɑ����Ċw�ǂ��x�����������A�y�e���ɂ������肽���Ȃ��B
�����Ɗw�ǂƘb�������A�^�ӂ�T���Ă���ɂ��悤�A�Ƃ������_�ɂȂ����B
�����͖��B�֖߂�ƁA�����ɐ��{�����`�����B���ꂪ�w�ǂɓ`��������A�����͕�V���̎��̖K������B�ё��̎��͔ߒɂȊ�Ō������B
�u���͒��w�ǂ̌Ăт������������̂ł����A����܂�����B
����5�S���̌_��͔p������A�ƁB
���̌_��͕��̎����p�����̂ŁA�������A�ƌ����̂ł��v
�u���A����ȁc�c�v
�Ə����͎v�킸�h�����B
�@�ё��̎��̘b���Ă��邤���ɁA�����͐�ɂ����B
���ڏG��ȎႢ�w�ǂ̊�́A�����₽�����ʂ̂悤�ŁA���炮�炽���鑞���݂��݂��Â��Ȑ��̒�ɁA
�u�e�����E�����͓̂��{���B4�����炢�ق��ďo�������Ĉ�������v
�Ƃ����}�M���������̂�������Ȃ��B
����A���Q�̈ꖋ�������̂��낤�B
�w�ǂ��֓��R�i�ߊ��ɒ��ڒ�Ă����̂́A���܂������݂̚}�M�������̂ł͂Ȃ����B
�т͌������̂��B
�u�����炪�瓦�����������Ƃ������Q�҂��A�w�ǂɂ����܂��Ă�����ł��B���͂Ȃɂ������w�ǂɕ��Ă����B����������ӂ�����߂Ȃ���A�w�ǂ͕��e���S�E�������{�R�Ɉ�A�ӂ����悤�Ƒ_���Ă����̂�������Ȃ��c�c�v
�@���w�ǂ̖{���̋C���͂킩��Ȃ��B
�������A���{���{�̎ς�����Ȃ��ԓx�ɋƂ��ɂ₵���̂��A���ꂪ�����Ǝv�����̂��A�w�ǂ͍r�ɓ�������̒��~��\���o�Ă����B
���{���{�������邢�Ƃ܂��Ȃ��A�w�ǂ͍������{�Ƃ̑Ë��H���i�߁A���ɏӉ�Ǝ������ɂ��������B
�^����ꂽ���w�ǂ̃|�X�g�͕ۈ����i�߂ŁA�g�сA�����]�A��V�̓����O�Ȃ����������B
���B�ɐV���������Ђ邪�������̂́A���a3�N12��29���ł������B
�@�����ɁA���{���{�͒������x���̕��j�ȗ��A��V�R�i����f����ꂽ�킯���B���̎��s�̌����͐��{�ƌR�A����A�R�Ɗ֓��R���ꗁi�����j���痈�����̂ł��邪�A�c�����t�̖����ɂ��Ȃ����̂ł���B
�M���@�▯���}�͓c����ӂ߁A�������̔����������֓��R�ɊW����Ȃ�A�����R�@��c�ɂ����Č��d�Ȏ撲�ׂ��s�Ȃ��A�������ׂ����Ɣ������B�R�Ƃ��Ă͈�̖\�I�������̂��܂�A�R�@��c�̊J��ɔ������B���̊Ԃɋ��܂��āA�����̂Ƃ�Ȃ��Ȃ����c���́A�ꂵ�܂���ɍs�������Ăʼn������悤�Ƃ������A�V�c�͓c���̓��{�����B
�@��͓V�c�̐M�C�����Ȃ��A�R�Ɛ��}���狲�ݓ��ɂ����Đi�ނ���܂����c�����t�́A���a4�N��7���ɕ����B�����āA��������������������ɖ��C���Ȗ��𑱂��Ă���Ȃ��ɁA���R�Ȃ͎��̂悤�ȏ����\�����ɂ����Ȃ������B
�i���֓��R�����Q�d�j���R�����卲�@�͖{���i��E�j
�֓��R�i�ߊ��@���R�����@��������Y�i�\�����j |

�c���`����t�̃����o�[�A������O�y���������A�c���A�R�{���Y�_���A���약�g�S�����A�v���[�V�������i���a3�N8���j
�����������œV�c�̎��ӂ����F��̓c���`����t�͑����E���A�����}�̕l���Y�K���t�ɑ���B |
�@���̂悤�Ȍy���������A�����l�̋^�f��[�߁A�r���ɔ��Ԃ����������Ƃ͑����Ȃ��B�������A���B�͈ꉞ�������Ƃ���֗������A�u���B�^�d�厖���v���\�ʂ̓P���������悤�ɂ݂����B
���̒ꗬ�ɂ��錃�����Q�����́H
�����͖��S�ɔ���ُ�ȋ����A�\���������ʕ��G�Ȏ���̂��˂�̒�����A�q���ɂ����Ƃ��Ă����̂ł���B
4�@���S�̋�Y top
�@���������ق̊��������S�̋��́A�����W�̈����ƂƂ��ɁA��3�����D��Ȃ����B�̌��v�����̗��j�̂����ɐ����Ă������̂ł��邪�A�������̔����ł��I�ȑŒʐ��i�ŌՎR�|�ʗɁj�A�g�C���i�g�с|�C���j�̌��݁A�c�Ƃ̊J�n�ŁA����I�Ȍ`�ł̂��������Ă����B
�@�������A����38�N�ɒ��������u�����Ԃ̖��B�Ɋւ�����t���閧����v�ŋ֎~����Ă������̂��A���������j�����̂ł���B���{�͌��d�ɍR�c�����B�������A�����͍����̂悤�ɂ͈���������Ȃ������B�����ɁA���O�̔r���^���̌��������e�R�ɂ�������Ȏp�������݂Ƃꂽ�B�����͒����̋��d���̔w��ɁA�A�����J������̂ł͂Ȃ����A�Ɗ������Ă݂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B
�@�A�����J�͒��ږW�Q����킯�ł͂Ȃ��B������˂����A�X�L�����Ă͖��S�̗������������悤�ȃ`���b�J�C�����Ă����B�����ɂ́A�S�����n���}���̋��J�����������Ă��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B���{���{��]���Ƃ̊ԂɁA�얞�B�S���̓��ċ����o�c�ɂ��Ắu�o���v���������Ȃ���A�����둫����������悤�ɂ��Ĕj�����ꂽ�n���}���̎��]�A���S�A���{�ւ̕s�M���A�A�����J�̑Β�������̒��ɁA�������c���Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���S�̓��{�Ɣ��̌o�c�ƈӊO�Ȑ������A���C�Ȗ��S�Ј����A�����A�n���}�����Y�扻���āA���|��̏o�����̂ɂ́A���Ȃ炸�������ʔ����A�uGo home �n���}���I�v�������������̂��B�A�����J�����ɂ������ʂ�̂����R�ł��낤�B
�@�������ォ��A�u�k�����v������悤�ȓS���̌��݂�āA�p�A�I�Ȃǂ�ʂ��āA�����ɐi�߂Ă����̂́A1����2���ł͂Ȃ������B
���ׂĔ閧�����3���� |
|

�j���Y���t���̏��������Y�O��
|

�A�����J�̓S�����n���}��
|
|
���I�푈�ɏ����������͑S����g�Ƃ��ă��V�A�Ƃ̔������ɗՂ��[���Ȑ��ʂ������Ȃ������B���̊ԃn���}���͖��S����{�Ƌ����^�c���邱�Ƃ�\�o�Čj����U�͌_���B����������������A�����������͂�����Č��{���n���}���Ƃ̌_���j���������B |
|
�u���S�̕t�߂ɂ����Ă������͂���ɕ��s���Ă������銲�������~�݂����A�܂����S���̗��v�ɊQ���邢���Ȃ�}�������~�݂����v
�R�ƐN���A�@�ɖ�S���i�V���ԁ|�@�ɖ�j�̂Ƃ��̓C�M���X�ƁA�Ȉ��S���i�яB�|�`�`�n���|����j�̂Ƃ��̓A�����J�ƁA�ƒf�I�ɒ����̂ł������B
�������A���{�͋��d�ɍR�c���ēP�����B
�@�A�����J�́A���炭�����߂Ă������A1920�N�Ɏl���؊��c�������āA���S�����₩�����B�����1911�N�ɐ����Ƃ̊ԂɌ��u�����������v����ю��ƊJ���؊��v�����āA��X�I�Ȓ����Ƃ̍��َ��Ƃ��n�߂悤�Ƃ����A�h���ɂ��U���ł���B�l���؊��c�Ƃ����̂́A�����K������A�N�[�����[�u����A���i�V���i����s�A����ёS�j���[���[�N���������č����c�A�����s�A�ƈ���s�A��x�x�ߋ�s�Ȃǂ̎؊��ŁA���B�̍��َ��Ƃ̑啔���͎l�����c�ɋA���邱�ƂɂȂ肻���������B
�@�A�����J�̑_���́A1922�N��9�������Ŗ��炩�ƂȂ����B����1914�N�A���{�̖��B�J���̂����܂����ɋ����A��������
�u���{�̖ړI�͒����ɂ�����̓y�g�������߂�ɂ��炴�鎖�v
�ƓB�������Ă������Ƃ����������A9�������̖`���ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B
�@�����@�������O�̊e�������͍��̒ʂ��肷�B
�@�@�����̎匠�A�Ɨ��Ȃ�тɗ̓y�I����эs���I�ۑS�d���邱�ƁB
�@�����ɂ�������{�̐N����H���~�߂悤�Ƃ���Ӑ}�������Ȃ̂��B����܂ł́A�����̏��ᔽ��f�łƂ��Ē��˕t���A���̓s�x�A���o�����Ă����A�����J���A���{�̐��_�Ƌ��d�ȑԓx�Ɉ����ނ̎p�����݂�����
�\�\���x�̑Œʐ��A�g�C���̌��݂́A�����ɉ�����ꂽ�`�������B
�@���S�̕��s���ł��钆���̐V���́A���S�̉^�������������B���S�̑傫�Ȏ������ł������k���̑哤�́A���S��������āA�Œʐ��̃��[�g�ʼn^���悤�ɂȂ����B�Ɏ�́A�Ă��߂����B�����炱���A�������Ă����̂����A����ǂ��������ƂɂȂ�̂ł��낤���B
�@�����Ă����A���߂��A�S�����h�����ɈႢ�Ȃ��B���ɍ�����̒��݂��n�߂Ă����B�ً}��v������̈ȊO�A�y�؍H�������~���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���S�o�c��̃X�L���Ƃ炦�A�A�����J�̃h��������ނ��n�߂�̂́A�킩�肫�������Ƃ��B�����̋����ɂ���āA���V�̐������������S�́A�n��25�N�ɂ��đ傫�Ȋ�@�ɂ��炳��Ă����̂ł���B
�@��Γ��t�̕����O���́A�S�����Ɏ��g���A���ʂ͏��Ȃ������B�������́A��R�U���ɓ]���A���a6�N�i1931�j5���̍�����c�ŁA�����A��A�̉���A���S����A�֓��R�̓P�ނȂǂ��c���ɏ��قǁA���V���Ă����B�����������͋C�̂Ȃ��ŁA�����O���ɂ��A�S������������Ȃ��̂����R�̂��Ƃł������B�������́A���{���̂��̂B����ǂ��炢�����̂�����\�\�B
�@�O�������̏����́A�s�g�ȗ\�����o�����B���{����ق���������Ă�����Ȃ��ƁA�����̕��͏Փ˂��K���N����A�����푈�ɔ��W����ꍇ�́A�ĉp��G�ɂ܂킷���Ԃ��������˂Ȃ��B���j���t�]�����āA���S�n���̍��̐U��o���֖߂��Ȃ�\�\�Ə����͍l�����B
�@�n���}���Ƃ̋����o�c�����A�S�N�̓��@�͂������������ł͂Ȃ������̂��B�����A�����J�Ƌ����œ얞�B�S���̌o�c��i�߂�Ȃ�A�����̏o����������ł��낤���A���j�͕ʂ̋Ȑ������ǂ�ɈႢ�Ȃ������B���������Y�O���̔M���Ԃ肪�����̐��{��]�����|�����������́A���ɓ��{�I�ȃh���}�ł��낤���A���E��̊O���Ƃ��ẮA�q���̈��E���Ă��Ȃ��B�S�N�̌v�@���A�����̈ӌ����̑�Ȑ����Ƃ��~���������B������v���A���O�̈��ɐs����B
�@�������ɓ����Ă��A���{���{�͒����Ƃ̋�����}�낤�Ƃ��Ă����B�������A�����錴���̎}�����W���āA��͂Ɛ����A�N����ׂ����ċN������j�̓{���́A��l�̐l�Ԃ̐��~��������̂ł͂Ȃ��B���{�̓��O���ɂ���āA���S�͌o�c��Ɋׂ���A���ւ̌��v���N�����댯������Ɣ��ɔ����Ă���ƁA�Ⴂ�Ј������͂����Ƃ��Ă����Ȃ������B
�@�u�������ݖ��N���c�����ė������Ȃ��ƁA���ւ̌��v�ǂ��납�A�ݗ��M�l�����ʂ������邩�̐��ˍۂɗ��������B������q���Ă�낤�v
�Ƃ����������S��������N����A���ꂪ��A�V�������āA���B�N�c��̎����ƂȂ����B
�c���
�u�͋[���t����ѐ��K�̎葱���ɂ���o����c�Ă�R�c�A�_������\�\�v
�ƌ��@��搂��A�S����210�I����ɂ킯���B�c����910���A���S�Ј��𒆐S�ɂ����c��ł��������A�����[����84����ɒB�����B
�@���B�N�̌��W�Ɣ����͂͂����܂����A���S�Ј���W�������u��Y���v�ƍ��̂��A�S������ɏW�߂�u�N�A���v��g�D����Ɏ������B
���ɖ��S��200���~�̌����i���a5�N�x�j�Ƃ�����@�Ɍ������A�����I�Ȍ���𐿊肷��Ƃ��������Ԃ�O�ɁA
�u���S�͂ǂ��ւ䂭�H�v
�̔ߑs�̐��X���A�ݖ�210���M�l�̐S��h�邪�����B
�N�����͋��B
�u�\�\���̂悤�ɒǂ��߂�ꂽ�̂́A���ۘA�����������āA���{�̐i�o��W�Q���悤�Ƃ���āA�p�A���A���̐����ɂ����̂����A���{���{�̑Ζ���������Ă��邩�炾�B���n�̉�炪�B�R�Ƃ��ċN�����A�ꍑ�̑Ζ��\�_�����N����ƂƂ��ɁA���{�̌��ӂ𑣂����ł͂Ȃ����I�v
�@���ɐN�A���́A���c�Ҕn�ȉ�5����A����\�V�����Ƃ��ĕꍑ�֑������B�����̓����́A�Ј������Ŋ����Ƃ�����@�́A��ނɂ�܂�ʕs�����猃�����������^���̐�����ł��������A�֓��R�ł͕ʂ̃R�[�X����A���j�̔����_�͂ɂ���ē_����A�u���̗֗L�v��v�̎�����_���Ă����̂ł���B
5�@�֓��R�̐Ό��\�z top
�@���S�����ۂ̍����ے��́A�֓��R�̐Ό��Ύ��i���j�Q�d�ɁA���֖��̒����A�����ɂ��āA�S�ʓI�ȋ��͂����߂�ꂽ�B�����͐Ό��̔M�ӂɓ�������A�����������A������^�����肵���B�֓��R�̒q�d�Ƃ���ꂽ�Ό��́A�S�苭�����s�͂ɕx�����Q�d�̔_���l�Y�Ƒg��ŁA�֓��R�����Ɉ����Ă����B�����͎�Ȃł��A�Ƃ��Ƃ��Ɠ��{�̍��h�▞�֖���_���Đs���Ȃ��Ό������āA�˂Ɍh�����Ă����B�Ȃ��Ȃ��_�̃f�b�J�C���͂ɕx�l���Ȃ̂��B
�@�u�푈�j�v�Ȃǂ��q�ׂ�ƁA���E�I�ȗ��j�Ƃ̊ј\������������ꂽ�B�����ȃ��[���b�p��j�̌����̌��ʁA����̐푈�`�Ԃ�����̎��Y�ɂ���Č�������̂ł͂Ȃ��A�S�������Q���̊��S��Ő푈�Ɉڂ邱�Ƃ��A�\������������Ȃ��B���������b�ɂȂ��Ă���ƁA��[��f���̔M�ŁA�������܂ō����𗣂����Ƃ��Ȃ������B���֖��ɂȂ�ƁA�u���{�̐N���v�Ƃ����̔������₵���B
�u���E�̐푈�͂܂��鍑��`�I�ȐN���̒i�K�ɂ���B�Ă߂����������āA��������Ȃ����v
�ƐΌ��͂��������B
�u���̓��{���A�ߑ㍑�ƂƂ��Ĕ��W���Ȃ���Ȃ�ʉ^���������{�鍑�ł͂Ȃ����v
�ƌ����Ă����āA������u�Ό��\�z�v���J��Ԃ��̂������B
�u�l�����c��オ��A�H�Ɩ��ł��s���l�܂���݂��Ă�����{�́A���������l�������v�����A����𑫂�����ɁA���ւŊ��H���J�����Ƃ���͓̂��R�̂��Ƃł͂Ȃ����B
�����͂����������N���Ă��āA�匠�m����������B
���{�̗͂Ŏ����ێ����s�Ȃ��A�e�����������h�ł���Ă䂯�A���W�͖ڂɌ����Ă���B |

�Ό��Ύ��A����22�N�R�`�������Ő����B���a3�N�Ɋ֓��R����C�Q�d�Ƃ��Ė��B�ɕ��C�����S�ɋ����e���͂�^�����B���g�̍ŏI�푈�_����ɂ��Ċ֓��R�ɂ�閞�̗֗L�v��𗧈Ă���B���a6�N�ɔ_���l�Y��Ɩ��B���ς����s�A����ɖ��B���𐬗�������B
���̌㓌���p�@�ƑΗ������J�A���̂��ߎ��g�̎v���Ƃ͈قȂ��ƂɂȂ�Ȃ������B
���͏����́u���R�_��v�ɂē��u�Ƌ��������𑗂����B |
�������{�����̗��v���l���Ă���킯�ł͂Ȃ��B
���{�����ւ�̗L���A�������@�͑����ɂ���B
���{�l�͌R���Ƒ�K�͂Ȋ�ƁA�����l�͏��ƂƔ_�ƁA���N�l�͐��c�A�Ðl�͖q�{�A�Ƃ�������ɂ��̂��̂̓��������������Ƃɂ���̂��B
�]���Ė��̗֗L�̍\�z�́A�ݖ�3�疜���O�̋����̓G�A���k�R����|�����ƂŁA�e�����̍K���Ɣ��W�𑣂����Ƃ��ړI�ƂȂ�Ȃ���Ȃ��B
���B�̌��Z���͊���������a�����ɋ߂��B�v
�@���B�N�A�����N��������������_�ŁA�Ό��\�z���ƁA�ނ��댌�N�������̊�����������������Ȃ��B�����ɁA�֓��R�Ƒ��̊댯��\�m�ł����Ƃ��Ă��A�Ό��̑�`�����͖������̂��̂���������ł���B
�@�鍑��`�푈�⑼���ւ̐N�����A�ԈႢ���Ǝv���l�X�ł���A���ɐA���n�ƕx���ߋ��̐N���푈�ɂ���ď�������Ă����i���A���{�̑䓪�����������悤�Ƃ��Ă��鎖���A�͂͗͂Œ��˕Ԃ��Ȃ���Ȃ�ʗ��j�I�����̐^�������ɂ����āA���ւ���{�̐������ƍl�����B�ǂ����������A���{�͓����E���I�̐푈�ɏ����A�ߑ㍑�Ƃ̌`�𐮂��đ�ꎟ���ɎQ�����A���{�鍑�Ƃ��ē˂��i�܂�������Ȃ��^���I�Ȏ��_�ɂ���������ł���B
�@���S���������Ό��ɋ��͂����̂͂��̂��߂ł��������A�������헪�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�Ό��́m���ւɂ������̒n�����Ɋւ��錤���v����肠�������A��V�R�U���̏������͂��߂Ă����B�������A�����́u���A������ł����v�Ƃ����₢�����ɂ��ẮA�������ɕs�ސT�Ȕ����͂��Ȃ������B
�@�Ό��\�z�̎����́A�����A�R���̑�����܂�ł���A���{�̕��j�Ƃ��ē��ݐ�Ȃ�������A�֓��R�̓ƒf��s�Ő�����������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����͐Ό��\�z���\�z�Ƃ��ĕ����A�������������������Ƃ��Ă��A�������_�̐���オ���A���}�����̋����O���𑱂��鐭�{�̕��j�A��3���̓����Ȃǂ��l�����킹�A�@�̏n���閘�ɂ͂Ȃ������̎�����v������̂Ɣ��f�����B�����͐Ό��ɉȊw�I�Ȗ��ւ̎�����^���A���B�ɐV������A�Ƃ���������̈ӌ����q�ׂ����A�֓��R�̓Ƒ������߂�z���͖Y��Ȃ������B
�@���̂Ȃ�A���t�ȓ���L���ɂ킽�閞�S�����ɔz������Ă��镽���̐��̊֓��R�́A�͂���2�����������̗��ȕҐ������ł���A����ɂЂ��������k�R�͕�V�𒆐S�ɁA���t�A���}�A�P����Ȃǂɐ����̕������Ԃ��Ă���A�����Ȃ�헪��������210���̓G�ӂł���̂��B
�\�\�����������{�����͂��Ȃ��ꍇ�A�֓��R�̖\���͖��B�ɑ卬�����䂫�N������ł���B
��Q�҂͖��S����эݖ��M�l�ł��낤�B
�������A�����͖��S�������Z���ӂƉk�炵�����t�̒��ɁA
�u�܂��A�@�̏n����̂�2�N�ゾ�낤�v
�Ƃ����Ό��̌��ӂ�m�����B
�@�����̎҂�2�N��A�ƐΌ��������Ă���̂́A���ꖘ�ɒ������{�������������肩������Ȃ������B�����A���S�́A�̕t���悤�ȌR����Ԃ̎�z��\���t����ꂽ�B����͉����ɕ��U�z�����Ă���֓��R���A��V�t�߂֏W�����邽�߂̗A�������ł������B
�@�����ɂł��A���̋N�肻���ȋC�z�ł���B���S�ً͋}�ɏ������s�Ȃ����B�����͂킩��Ȃ����A�R�̎w�߂����ۂ�A�[��Ƃ����ǂ��w���͓�������A�v���ɗ�Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��V�ւ̐撅�����ƍŌ�ɓ������镔���̍��́A2���Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����B
�@���̗A���v�悩��݂�d���I�ȌR���̕�V�W���́A���k�����̒����ł���A��V�R�̐��s���W�߂���V����ꋓ�ɉ�ł��A�����̒����𐧈����ĒZ���ԂɁu�Ό��\�z�v���������邽�߂ɈႢ�Ȃ������B���ꂪ�������{�̕��j�Ȃ̂��A�P�Ȃ�֓��R�̓ƒf��s�Ȃ̂��A���S�ɂ͂킩��͂��͂Ȃ��B���悢����̂��A�Ƃ�����ɓI�ȋ����̒��ŁA��A�{�ЁA�V���������A��V���ǁA�e��v�w�͂��킽�������C���ɂ����B
�@���a6�N�̂������������A��A�`�ɐ_�˂���̋q�D���������B��A���S�u���������̌j�͕u���ɗ����Ă����B�q���ו��������Ċݕǂɍ~�藧�����B���̋q�D�ɂ͑傫�ȉݕ������ڂ���Ă����B�ɗ̎҂̒������𒅂��Ⴂ���{�l���A��͂��w�����āA�q���S���~�肽��̃f�b�L���狐��ȉݕ����~�낵���B��͉͂��ꂽ�������𒅂Ă��邪�A�F�ȓ����ۊ���ɂ������{�l�������B�ݕ��͌��d�ɕ����Ă����āA���g�͂킩��Ȃ����A�����d���炵���B����ȑ傫�Ȃ��̂��A�ݕ��D�ʼn^�Ȃ��̂́A�l�̖ڂ��떂�������߂ł��낤�B
�@�j�͍ɗ̎҂̓��{�l���A�Ɨ������2������̏��Z�ł��邱�Ƃ�������ꂽ�ق��́A�R���i�g������і��S�{���A���ւ��Ƃ����A�u���C���𐋍s���鑼�͉����m�炳��Ă��Ȃ������B
�@���̉ݕ�����V�w�ō~����邱�Ƃ����킩���Ă���B�B���A���̉ݕ��͂������������낤�B�ݕ��͋�͂������{�l�����̎�Ŋ��Ȕ��̒��֓����ꂽ�B���̔��͓B�Â�����Ĕ����z�ŕ���ꂽ�B
�@�S�H�֘A�����閳�W�ݎԂɓ����ꂽ���A�j�͍D��S�ɂ����čɗ̎҂̏��Z�ɐq�˂��B
�u���鍂���̞l����v
�ƁA���Z�͐^�ʖڂ������ē������B
�@�l�ɂ��Ă͑傫�������B
�d�ʂ͐l�Ԃ̉�10�{�����肻�����B
�m���ɁA�卂���̎��̂����̂��Ƃ͂���B
�j�͈�T�Ԃقǂ��ĕ�V���ǂ֏o�������B
���̂Ƃ������̌I�c�ɞl�̐��̂��n�߂ĕ������ꂽ�B
�u����B���̞l�͂ȁv
�ƁA�I�c�͏��Ȃ��猾�����B
�u���a5m�A�[��1m�̌��̒��֖������ꂽ��B
������ł͐��j�p�̃v�[�����@��ƌ����Ă����ˁB
���̂́A��������𐁂���������B
����́A��V����Ԃ��������߂́A24�T���`�֒e�C�̖C�g�Ȃ̂��B
���悢��A����Ȃ����ȁv
�@����͒����l�̖ڂ��떂�������߂̋U���ŁA�֓��R�����R�ȌR���ے��i�c�S�R�i�̂��ɌR���ǒ��ƂȂ�A�����Ɏh�E����j������Ɛ��������A�Ɨ������2����̔��C�Ƃ��ĉ^�э����̂ł���B
��R���͌ߌ�11�������ɕ�V�̑S�����R�ɑ��ďo���������߂������A�ډ�����Ɍ�풆�ł���B
�i���������V���j���O�̌��o���́A
�\�\�k��c�����S�ɐ苒
�\�\�k�˕t�߂ł����
�\�\�}�s��Ԋ낤�����j�����
�\�\��V��֖C�����J�n
�\�\�R�i�ߕ���V�ֈڂ�
�@���̂悤�ɂÂ��̂ł��邪�A�Ȍ��ȑ���ɂ�������炸�A��V�R�̌v��I�s�ׂł��邱�Ƃ�f�肵�A�\���̕�����K�������Ă���B�����̏u�Ԃɂ́A�^�����������ޗ]�T�ȂǂȂ������̂�������Ȃ��B
�@�����̖k��c���ɂ��̂����Ɨ����������2����́A��2�t�c������29�A���Ƌ��͂��āA��V����U�������B���24�T���`�֒e�C���З͂������̂͂��̂Ƃ��ł������B���S���c���ق́A�������{�̕s�g����j��m�������A��̃��c�{�Ɖ��������n�̏̂Ȃ��ŁA�֓��R�̗v�������ۂ���킯�ɂ����Ȃ��B�e�S����������ю�v�w�ɁA�]�R�Ј���Ґ��A�z�u���ċ��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@���c���������ɋ^�f�ɂƂ炦���Ă������̂́A���{�̕s�g����j���R����āA�֓��R���ƒf��s�̋��ɏo������ł������B�֓��R�͒��N�R����c��ƒf�z�������āA�g�тō������A�k���������}�i�����B���t���̌�A�c���A�P����̕��R�������A�яB�̔����ɑ������āA�`�`�n���������ĂĂ���B
�@����́A2�N���\�z���Ă����u�Ό��\�z�v���A�����Δ��j�Ƃ����˔���������A�ꋓ�Ɏ������悤�Ƃ���̂�������Ȃ��B�������A����������ƁA�����Ǒ��Y�����ŔR���������ݖ��M�l����ѓ��{�����̓{����@�Ƃ��ĂƂ炦�A�܃��N�v����n�߂��\�A�̖��B�ɑ���S�̎蔖�ɏ悶�A2�N��̍\�z�����݂ɓ]�������Ƃ��l������B
���ɒ��������E�����Ŗd���̑O�Ȃ������Ă���֓��R�́\�\
�Ƌ^���n�߂�ƁA�v�������t�V���Ȃ��ł��Ȃ������B
�@�����̓���A10��������ɔ��j���ꂽ�Ƃ��A�}�s��Ԃ͂��̒��O�ɒʉ߂��āA���Ƃꂽ�B�Ȃ���V�R�͗�Ԃ̓]����}��Ȃ������̂��B���������V�R��|��������A���j���̓_���ƕ�C�̂��߁A�@�ނƕې��W������}�s�����B�唚�j�̈�ۂ�^���������́A�k��c�̍U���Ƃ����܂����퓬�A��V��̖C���Ƃ����W�J�̎d���ɁA�����������������������Ȃ������B
�@�Ƃ��낪�ې��W����j���z�����Ă�����������́A����߂ď��K�͂ȑ����ɂ������A��C�͓��P�ɂł�������A����̗�Ԓʉ߂ɂ��x�Ⴊ�Ȃ������B
�@���Ȃ킿�A����͓G��������̂ł͂Ȃ��B���B��̂̌��������邽�߂̖d���ŁA�����̓S�����߂���߂���ɔj��킯�ɂ͂����ʂƂ����A���{�l�̔ƍs���t�Ǝ˂��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�����A�������Ƃ���u�Ό��\�z�v�̈̑傳���A�ړI�̂��߂ɂ͎�i��I���Ƃ����A�����ɂ����Ȃ炵���d���̎���́A�����s�����ɂ�����炸���{�鍑��`�̉��J�ɁA���肩�����Ă��܂����낤�B
�@���c�͈Â��\��Łu�Ό�������Ȃ��Ƃ�����킯�͂Ȃ��v�ƁA���{�l��ٌ삷�邩�̂悤�əꂢ���B
�@������̋~���́A���B�����V���{�Ђ̋{��L�҂̏،��ł������B�{��͓���A�����˔��̑����d�b�Ŏ�ƁA�u�֓��R���c�c�v�Ɩd���̏L�������������A�킯�t�����֓��R�i�ߕ��͂Ђ�����Ƃ��Ă���A�������Ȃ������悤�ɐQ�Â܂��Ă���B�߂��̎O��Q�d���̓@��֑���A�Q�ڂ���̎O����Ɏ��������������A
�u�ȂɃb�v
�Ɗ�F��ς��A�₪�ē{��ɔ�яo���ڂ�V��ɂ����Č������B
�@�u�܂��A��������ȁB���w�ǂ̈����ǂ����c�c�v
�@�֓��R�Q�d�����ŋ������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B
�@�O��͊e�Q�d�ɏW���𖽂��A�{����Ƃ��Ȃ��Ďi�ߕ��֏o���������A�r���łӂ肩����A
�u�������ɐV���Ђ̑����ɂ͋�������B�킵�̒m����Ɂc�c�v�ƌ������B
�{��͎i�ߕ��Ŗ{���i�ߊ��Ɉ��������A�������{����A��������̏��R�͐Q���ɐ��̕\������B
�@�Ȃ��ł��A�V��A���c�A����A�Бq�e�Q�d�̂Ђ��Ђ��b�����ɋ���ŁA����͊֓��R�̖d���ł͂Ȃ����A�Ƌ{��͊m�M�����B�l�l�̖����͉����m��Ȃ������̂ł���B
�@����ł́A����A�k��c���V��̍U�����߂�^�����̂́A�N�ł��������B
���R��V�ɗ��Ă��������Q�d�_���l�Y�̓ƒf�ł������B
�_�͓ƒf���s�̌�A���㏳���̌`�Ŏi�ߊ��֓d�b���A
�u�@���������ɐ�ǂ̓K�Ȏw�����s�Ȃ��܂����v
�ƌ����A���K�̍�햽�߂��̂ł������B
�������A�[��̌R�i�ߕ���c�ŁA�Ό������܂������Đ����S�R�U���̒�ẮA���̍ۈꋓ�ɉ������悤�Ƃ������֖��Ɨ��݂����āA�e�Ղɖ{���i�ߊ��̌��f�𑣂����Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�{�����R����Y�����̂��B���ɖ�͕�����Ă���B
�@�풆�̌��n����u�ډ���풆�A��쒆�яd���v�Ȃǂ̏�����Ă���ƁA���ɖ{���͌��ӂ����B
�@�u�悵�I�{�E�̐ӔC�ɂ����Đ��s����v
�Ɣߑs�ȕ\��Œf�Ă��������Ƃ��A�����ꓯ�A���܂��ďl�R�Ǝ�����ꂽ�B
�@�����A����͊֓��R�d���̓���������c�c�Ɗ����Ȃ���A�N��l�A�Ό����܂���������ŐG��悤�Ƃ��Ȃ������B�����炭�{���́A���������E�����̂Ƃ��A�͖{�卲�̓ƒf��m��Ȃ������i�ߊ����ӔC���ăc������炳�ꂽ�悤�ɁA���Ƃ��֒m���Ȃ��ꕔ���̖d���ł��낤�Ƃ��A�吨�ɋt�炦�ʂ��Ƃ��A���̂Ƃ��ϔO�����̂�������Ȃ��B
�\�\�������Ė��B���ςƂ����v���I�Ȏ��Ԃ͉��҂�����ł��Ȃ���g���ƂȂ��čr�ꋶ�����B |

�����ٔ��Ř_�����_���l�Y�E�������B���̍ٔ��Ŏ��Y������������B�Ό��Ύ��ƂƂ��ɖ��B���ς��w�����A���R���́u����h�v�ƑΗ������u�Ό��h�v�̏d���ł������B |
7�@�B���ꂽ�����̐^�� top
�@���S���ق̓��c���݂��k���オ�����̂́A���ꂩ�����Ȃ��̂��Ƃł������B
�u�֓��R���L���v
�ƒ������Ȃ���A���ʔے肵�悤�Ƃ��Ă������҂������ɗ����A�d���̊m�������������ł͂Ȃ��B���S�̑����ɉ��t�����̂ł���B
�@�֓��R�̖d���ɂ́A��d�d�����d�|���Ă������B�܂�A���S�����j�͒����R�̖\���Ƃ݂������Ȃ���A���͓Ɨ�������ƕ�V�����@�ւ̐N���Z�������̂����Ď��s�����A���������̎��s�҂͖��S�Ј����������āA���j�̃X�C�b�`����ꂳ�����A�Ƃ������ݓ������g���b�N�����c�̎��ɓ����Ă������炾�B
�@18���̖�A���S��V�����̕ې���ŁA�Ⴂ�ې��W�������@�ւ̏��Z�ɌĂю~�߂�ꂽ�B
�@�u���c���т����A�����Εt�߂̐��H�����@�������B�ē����Ă��炢�����̂��v�ƁA���т͌������B
�Њd�߂����Ⴂ���Z�̖ڂ̌��ɁA�ې��W�͑f���Ɏ艟�Ԃ���H�ֈ����o���Ă����B
�B���̎��@�炵�����Z�̓J���e���̌����������Ƃ𖽂��A�艟�Ԃɏ�荞�ނƈꌾ���������A�ł�D���Ė����ɒB�����B
�u�悵�I�v
�ƌ����āA��э~�肽���т̔w�ɁA�����S�C���܂���̂����������A�ې��W�͎��@�̊Ԏ艟�Ԃ̒��ő҂��Ƃɂ����B
���Z�̎p�����H�Â����Ɉł̒��֏������Ƃ��A�ނ��P���A�\�������Ȃ��^����������Ɏ����Ă��悤�Ƃ́A���ɂ��v���Ă��Ȃ������B
�@��≓���ł̂Ȃ��Řb�������������悤�ȋC�������B
�@�����̏��Z�����Ă���炵���B����Ƃ�������̓����Ɉ������̂��B
�@�ڂ��ڂ��b�����������r���ƌC�����߂Â��A�u�����A�~���v�ƍ��c���т̐��������B
�@�ې��W�͔��j�n�_�֘A��čs���ꂽ���A
�@�u�����A���̃X�C�b�`������v�ƁA��������܂ł́A���̂��Ƃ��킩��Ȃ������B���ɔ����u����Ă����B
�@���Z�͓��Ηp�̓d���������A�u���j������A�����艟�Ԃœ�����v�ƌ������B�Ⴂ�ې��W�͐��Ȃ����B
�@���̂��߂ɁA���S���j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�킩�炩���B
�@�ނ̒��ɂ��閞�S���_�����o�����B
�@���S�̏�i�̖��߂Ȃ�A���Ƃ��d���ł����Ă��A�X�C�b�`����ꂽ��������Ȃ��B
�@�������ł���ȁA�ƕې��W�͐�ɂ̂����ɁA���������E�������v���������B
�@���̔��j�ɂ���āA�N�A������]���Ă��閞�֖������̒[������J�������̂Ƃ��Ă��A�����Ȃ�A���S�Ј������S����j��ȂǂƂ́A�����邱�Ƃł͂Ȃ������B
�@��肽���Ȃ�A�Ȃ��A�����ł��Ȃ��̂��B�u�ł��܂���v�Ɣނ͒f���Ƃ��ĝ��˕t�����B
�@�u���I�v�Ƌ��сA���c���т͌R���������������B
�@�E���Ă��A��炷���肾�ȁA�ƕې��W�͂��������Ƃ��Ƃ���������Ȃ���A���|�ɔ�яo�����ڂ����Z�Ɍ������B
�@����ȏ��ŁA�킯�̂킩��Ȃ��z�ɎE���ꂽ���Ȃ��B�Ȃ�Ƃ����Г�B
�Ƃ����ɍl�����̂́A�����āA���̎�����i����ׂ��ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ������B
�@�u���O��������Ƃ������Ƃ́A�N�ɂ�����Ȃ��B���̈ꑶ�Ȃ̂��B���O���A�����Ă������ȁB�������A���ĂΊ��R���B���܂��͉p�Y�I�Ȏd�����������ƂɂȂ邾�낤�B���I�v�ƁA�R���͈łɂ���߂����B
�@�����Őg���Ђ邪�����A�Ⴂ�b�̂悤�ș�����Ȃ���A�ې��W�̓X�C�b�`�Ɏ��L�����B
�@�������Ɏ育�������������B�ނ͑��肾���A�艟�Ԃɔ�я�����B����̂Ȃ��̊�ȕ��S�\�\
�@�����[�g����������݂��Ɏ艟�Ԃ����Ă������A�ˑR�A�y�鍌�����������B
�@���ꂪ�c�c���ꂪ����Ă��܂����A�ƕЎ�Ŋ�������A���������������B
���@���̂悤�Ȍ��ꂩ��ꍏ����������悤�Ǝv���Ă��邾���������B
�@�������A�w�ォ��P���������Ă���S�S�̖y�A
�@�u�\�\���j��������̂́A���S�ȂB���S�̖d�����B�A�b�n�n�n�v�Ƃ������X���t�サ���Ⴂ�ې��W�̍��S�Ɉ������B
�@���c���ق͉B�����ɁA���̊��킵�������̐^�������������B���S�̎҂Ƃ����������đP�������c�������A�d���̏d�含���l����ƁA�����Ɣ閧�ɂ��Ă������d�����Ȃ������B
�@���Ɋ֓��R�͍s�����������A���j�͒����R�̖\���̒����s�ׂł���ƁA���E�ɐ�`����Ă����B
�@�������Ă�Ƃ��ł͂Ȃ��B�c�O�Ȃ��Ƃɂ́A����A���S��肪�ǂ̂悤�ɓW�J����悤�Ƃ����S�Ɗ֓��R�̊W�͈�@��̉^����Ƃ��B
�@���c���ق͎�������A���S��d���ɗU������̂��A���X�ɒNjy���邱�Ƃɂ����B
�@���̎������_�@�ɁA���U�����i�����ԁj���Ă������S�̊֓��R�ɑ���s���Ɠ{�肪�A����ɍ��������̂ɂȂ��Ă������B���{�����Ƃ��āA�i�v�Ɍ�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤���A�B���ɒT���������ʂ𑍍����A���S�͊֓��R�̖d�������̂悤�ɔ��f�����B
�@�@����̍s���́u�Ό��\�z�v���̋ٔ��ɂ��2�N���������������ƁB
�A�@�d������}�����̂͐Ό��Q�d�A�ӔC�҂͔_�����Q�d�A���j�̎��s�҂͓Ɨ�������͖̉{���сA�����@�ւ̍��c���тł��邱�ƁB
�B�@���S�ې��W���g�����̂́A���s�҂̓ƒf�ł��邱�ƁB
�@���s�҂̐S���́A���ꂱ�ꉰ���͈̔͂ɗ��܂������A���S���\�ʊ֓��R�ɋ��͂��Ȃ���A�S�̒�ɔ����Ɣ͂��߂Ă��邱�Ƃɑ��ẮA�ł��܂��₪�点�Ƃ��Ƃꂽ�B�������A���̎����͓��c���ق̐S�_�������炵�߂����A�ɔ�ɂ���Ă������߂ɁA�w�ǂ̖��S�Ј��͐^����m��Ȃ��B
8�@���c���S���ق̖{������ top
�@�֓��R�͕�V�𐧈���������łȂ��A���B�S�y��Ȍ������B���N�R�̉������Ƃ͂����A�ꖜ�]�̕��͂�10�{�A20�{�̓G�ɑł��������̂�����A�������Q�̈��ɂ���B����������͎҂ɁA���S�͗����������u�Ƃ��Ă��A�������������邱�ƂɂȂ����B�ӋC���V�̊֓��R�ɌĂт����āA��V�̎i�ߕ��֊���������\�͐M���i��̍��S���فj�́A�����Ȃ�݂��グ��H�����B
�@�u���S�͂����ǂ邼�I�v�֓��R�̌������͂����ł������B
�@�u�����ق��Ă��������A�ߍ��̖��S�͍��ƓI�o�c�Ƃ������_�������悤�ɂȂ����B
�@�܂�ʼnc���{�ʂ̊�����Ђɂ����ʁB
�@�����Ƃ������Ƃ��������ĂĂ��邪�A�ǂ������k�����̕@�������������Ă���悤�Ȑ���Ƃ����݂��ʁB���S��������Ă���̂́A�R�̈З͂ł���B
�@�����Y��A�ǂ����R�̗v���ɂ������ĕs�[���ȋ��͂������Ȃ��B
�@����ȏ�Ԃł͖������v�������B����A�Ⴂ�Ј������͐ϋɓI�ȂB
�@�Ƃ��낪�A����̎�]���̑ԓx�Ɏς�����Ȃ����̂�������B��A�M���ɕ��������Ă��炢�����I�v |

���c�N�Ƒ�12�㖞�S���فA�O�����o�g�Ő�O�̊O����b�����x�����߂Ă���B�Ό��Ύ��̉e�����\�͐M���Ƌ��Ɋ֓��R�ɐϋɓI�ɋ��͂���悤�ɂȂ����B |
�@�֓��R�͖��S������̊v�V��v�]�����̂ł������B�\�͖͂��S��]���̎ς�����Ȃ��ԓx�̌�����m���Ă����B
�@�Ƃ��ɍ]�������ق͓��炸�G�炸�̔����I�ȑԓx�Őڂ��A�O�S���̖ؑ������͒������Ƃ̋�����厖�ɍl���A�ޓ������͉��^�I�Ȏp���������Ă����B���ꂪ�R�̖ڂ����ɂȂ��Ă����̂��B
�@�����͗����Łu����������������v�R�l��遂肪�A���S�o�c�̓����ɂ܂ŗ������낤�Ƃ���̂��A�ߍ���X�����v���Ă����B
�@���S�́u�R�͓S����ی삷��̂��C���v�Ƒ吳8�N�̊������v�ȗ��l���Ă���A�R�́u���S�͌R����̗v�����[��������̂��v�Ǝ咣���Ă����B
�@���S���ق͊֓��������̐�Ό����������Ă���A�֓��R�͌R���A�����̑��R����ɂ��ƂÂ��w�������������Ă��Ȃ��B���A�S���S�Ȍ��̎��͂���������֓��R�́A�R����̗v�������ł͂Ȃ��A�����͂̒��j�ƂȂ��đS���̌��͂�����A���S�����̏������Ɏ��߂āA���ݍ���ł��܂����Ƃ���C�z���A�\�͂̓n�b�L���������̂������B
�@�u���S�͋��͕s�[���ł���B����A���S�̑��͂������āA�֓��R���x�����Ă����˂Ȃ�ʁB
�@����ɂ��āA�i�ߊ��t���Ɠ��c���݂Ƃ̍��k���K�v�Ȃ̂��B��̓����ɂ��đ��k�������v
�u�킩��܂����B���̂悤�Ɏ��v�炢�܂��悤�v�ƁA�\�͖͂����B
�@�u�d����֖������̈�{�ɍi��܂��傤�v
�@�{���|���c��k�����A���S�̑̎����֓��R��{�ɐ��߂�����[���ƂȂ�̂�������Ȃ��B
�@����́A���͂�A���߂ł������B�\�͂͂����l�������A�吨�ɋt�炤���Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�����A���k��̂��V���ĂɎ��|�������B
�@�������āA���c���ق�����r���̌R�i�ߊ����ɁA�{�����R��K�˂��̂́A���a6�N10��6���̌ߌ�2���ł������B
�@�������̂Ɋ�����悤�Ƃ���V��̓��c�́A�ė����ɓI�Ȏp���ŁA�i�ߊ����w�[��������ꂽ�B
����̖{���͔��ׂē��������A����Ɍ}�������A�R�̕��j���I���Ēf�����͂𐾂킹��A�ϋɓI�ȋC�����̑S�̂ɟ������Ă����B
�������̓��c���C������đ������B
�����ɂ́A�Q�d���ȉ��Q�d���e�ے��A�y�쌴�卲�Ȃǂ��ٗl�ɋْ������ʎ����ŁA�Q�d���͂������߂����A�Y�����̂��Ƃ�����ł�������ł������B
�u���̂��т́A�������ŌR���A�����~���ɂ䂫�A�܂������̗L�\�Ȑl�ނ𑗂��Ă��������A�܂��Ƃɋ��͂����ӂ��Ă���܂��v
�ƁA�{���͗��s���Č������B
�@�{���������Ԃ������Ď��ς̌o�߂ƁA���֖������̋�̈Ă��q�ׁA�Q�d���e�ے��A�y�쌴�卲�Ȃǂ���X�̋C���Ǝ��M�������ĕ⑫���������B
����ɂ��ƁA�֓��R�́u���֔ЗL�v�Ă���������v����̂āA�u�Ɨ����ƌ��݁v�Ăɐ�ւ��ď����ɓ����Ă���A�Ƃ����̂ł������B
����́A�Q�d�{������A�֓��R�̓Ƒ����������邽�߂ɏo�����Ă��������핔���Ƃ̘b�������ŁA�k�_�����̌��ʓ����Ë��_�ł������B
����͒������̈ӌ��Ƃ��Ď��Ϗ������u�������{�匠���̐e�����������v�Ă������������A�֓��R�ɂ��Ă݂�ƁA�Ƃ�ł��Ȃ���㋦���ĂƎƂ����B
����������́A���ꂾ���Ē����������݊�����ϋɈĂł���A���J�Q�d������엤���Ȃǂ͎��ς�P�Ȃ���������Ƃ��Č��n�����A�����܂ŕs�g����j�������Ă���Ƃ����̂ł������B
�u�����ŁA�Ɨ����ƌ��݈Ăɋ��邱�ƂɂȂ������A���ւ𒆍��{�y����藣���āA�V��������������Ƃ����킯�ł��B
�����A���B���Ƃ������̂��l������̂ł����A�\�ʌ��n�l�ɂ���ē�������邽�߁A�N��������ǂɂ����邩�\�\
����͂Ƃ������Ƃ��āA��V�s�����܂����n�l�Ɉڂ�����ł��v
�@�{���͗��ɑ�ǂ��Ƃ炦�ĉ����ȕ������q�ׂ��B
���A����������������ސΌ��̌��t�͉��̂悤�ɔM���ĉs�������B
�u�V�����͂��邪�A�R���E�O���E��ʁA��������I�ɂ͑S�ĉ䂪�蒆�ɔ[�߂�̂ł��B
���S��]���̂Ȃ��ɂ́A���ۘA����A�����J�̌��w���C�ɂ��āA�싞���{�Ƃ̌��Ƃ��P���Ȃǂ�_���Ă���҂�����ƕ����B
�������{�̕@����`�Ă��邩�炾�B
���Ɋ֓��R�ƈ�S��̖̂��S���A���ɉ̕��𗁂тĂ���Ƃ����Ƃ��Ɂ\�\
���͖��X��A���{������Ȃ��ꍇ�A�ꎞ���{�̍��Ђ𗣒E���Ă��ړI�B����簐i����o��ł���̂ł��I�v
�@�Q�d���̉ے��̌��X����u�ܑ����a�v�Ƃ��u�����y�y�v�Ȃǂ̃��[�g�s�A��`�����t�������ꂾ�����B
�@���c�͔_�ƐΌ��̊�����閈�ɁA�P�ǂȕې��W��d���Ɋ������ߕ��������g���A�����ߑR�Ƃ��Ȃ����̂����������A���ǂ́A���͂𐾂�Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B
�@�Ō�ɖ{�����ւ肭���������q�ŁA�u�O���E�̒��V�ł�����c���̐s�͂ɂ���Đ��{�v�H��������Ă��炦�܂����v
�ƌ����Ĉ�G�i�߂��Ƃ��A���c�̏��ɓI�Ȏp���́A�O�����ɕς��Ă��Ă����B
�@��M�I�ȃM���M������悤�ȎႢ�Q�d�����Ɉ͂܂�āA���������Ȃ�Ȃ��Ȃ����i�ߊ��̗���ƐS�ɂ��A�l�ԓI�ȋ����ł����ē��c��h�蓮���������炾�B
�@���c�͊֓��R�̖d�������낤�ƂȂ��낤�ƁA�i�����炩�����o�����̂͐@���Ȃ����_�ł��������j������́A���̂悤�Ȏ��Ԃ��������ɈႢ�Ȃ��A�Ǝv���Ԃ����B
�@�n�܂����ȏ�́A���z�I�Ȑ������͂ɉ����i�߂���d�����Ȃ��B
�@����͐^�Ɂu�ܑ����a�v�Ɓu�����y�y�v���ԍ炩���Č����邱�Ƃ��B
�@�����A���j�̔g�����ߋ��̍߉Ђ����������A���ɓ]�����������J����Ȃ�A�������W���Ă����������̓��{�l�̋�Y�ɂ���āA�������������邩���m��Ȃ��B
�@���c�͖��S�̊֓��R�ւ̋��́A�\�\�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���c�l�����ǂ����j�̋O���邽�߂ɓ��{���{�Ƃ̐Ղɂ�����A�w�͂����Ă݂悤�ƍl�����B
�@�֓��R��ᔻ���A�Q���ɓۂ܂�Ă��鎞�ł͂Ȃ������B
�@�u�킩��܂����B�V���ɕڑł��A���邾������Ă݂܂��悤�B���E�̖��Ƃ��đP�����Ă݂܂��v
�@���c�͊֓��R�̖��߂ɂ���Ăł͂Ȃ��A��̓I�ɋN���オ�����ƌ����ׂ��ł��낤�B
�@�������A���̍��k��͖��S��S�ʓI�ȋ��J�w�����킹�����ƂŁA�֓��R�̎v���ʂ�ɂȂ����킯���B
�@���c�͐��̎��@�̌�A�_�A�Ό��B�Ƃ���ɍ��k���d�ˁA���������ďo�������B
�@���S�����ł́A�\�͗�������V���݈��ƂȂ��āA�֓��R�Ƌٖ��ɋ��͂��A������֖������ɍi��A��C�͈�ς����B
�@�֓��R�͐苒�n�s���Ɩ����������邽�߂ɁA�Q�d����3�ۂ�V�ɐ݂��A���S������͗L�\�̎Ј����I��ėv���ɏ[�����ꂽ�B
�@�\�͗����͂���Ɍ�ʈψ���̎�Ȍږ�ƂȂ�A���S�͑��͂������ČR�̎P���ɒy���Q�����̂ł���B
�@���c���ق͌��n�̏���q�ׁA�֓��R�̕s�ޓ]�̌��ӂ����A���֖������̂��߂́u�Ɨ����ƌ��݈āv�ɂ��āA�A�����{�v�l������������A���͓��P�ɉ^�Ȃ������B
�@�����ł�10�������i���{��ܘY�����𒆐S�ɂ��ċN�����������̖{���̃N�[�f�^�[�j�̔g�䂪���܂��Ă��Ȃ������B���R�������̐_�o���h�������̂́A���{�����̑匾�s��̂Ȃ��Ɂu�֓��R�͓Ɨ����悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ����A�^���₩�Ȉ�������������炾�B
�@�V���b�N�����������͔���叫�B�ɔh�����A�Ɨ��j�~����і\����}�����悤�Ƃ��Ă����B
�@���������̂Ȃ��̐����͓�����A�ނ�����c�͒��˕Ԃ����ꂽ�B
�@�������͖k���ɂ͐i�o�����Ȃ����Ƃ����߂Ă����B
�@���{�͗��R�i�֓��R�j�Ɉ���������댯�������A����ɍr�ؗǕv����ǂɁA���͌R�����t���������悤�Ƃ��Ă��鏭�s�R�l�̓����ɁA�R���̐����֗^���x�����n�߂Ă����B
�@���ČR�����������A���{�̕��j�ɏ]�킹�A������ł��o��̓Ƒ���j�~���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@���{�̋�Y�́A���Ɏn�܂��Ă��鐭�}�ƌR���̑Η�������ɕ����A����̎��ς̍��ۘA���ɗ^�����s�M���A�����ɒ������Ă������Ƃ����A���J�O���̐^�������ɗ�������Ă����B
�@���ꂪ�A�킩��킩��قǓ��c�͏ŗ������B
�@��Ȃ��Ƃɓ��c�́A��������֓��R�̑��ɗ����A�d�������{������ɏ��ŁA���B�ֈ��Ԃ��Ă����̂ł���B
9�@���B���̐��� top
�@���c���ق��{���R�i�ߊ��ɖʐڂ��āA�㋞���̕����Ă���Ƃ��A�V�ÂŖ\�����N�����B
��ł킩�������Ƃ����A���c�̗��璆�A�֓��R�͒������̐��P�����āA���X�Ɓu���B���v���݂ɂނ�����簐i���Ă����̂ł���B
�@�{���͓��c�Ɍ������B
�u�����A��V�͓V�Â�E�o�����ł��낤�c�c�v�ƁB
�@��V�s���𒆍��l����Ӕ��ɏ������y�쌴�卲�́A�V�Â֔��ŁA���Ɛ����̐铝��E��V�i�ӂ��j�i���̔C���ɂ����B
���B�ɓƗ����Ƃ����݂���Ƃ��A�ވʌ�V�Â̓��{�d�E�Ŕ߉^�H�̓����������Ă����V����ǂɌ}����Ƃ����ẮA���ϑO����u�Ό��\�z�v�̂Ȃ��ɂ������B |

���A�������̐��b�ň�ʏ����ɂȂ������B���̟�V�c��ƍč�����̒��������A��V�̐���Ȑ��U�̓��X�g�G���y���[�Ƃ��ĉf�扻����Ă���B |
�������������ɂ������āA�K���V�Ñ��̎���ʂ��A��V�E�o�̑Őf�����Ă����B
�������A�V�Âɒ������y�쌴�́A�K���̈ӌ����ĈÏʂɏ��グ���B
�@���Ȃ킿���{���{�͟�V�̒E�o����]�����A�����̊C�R�͟�V�̘A�ꂾ���ɉ����悤�Ƃ��Ȃ������B
�K���͊O���Ȃ���
�u�֓��R�̈Ӑ}���͂݁A��V��E�o�����Ȃ����߁A���d�Ɍx�����邱�Ɓv
�Ƃ����P�d�ɐڂ��Ă����B
���̎����̌x���ƁA�������̊Ď��̖ڂɝp�܂�ẮA�ƂĂ���V�̒E�o�͕s�\���B
�y�쌴�͔_�Ɛ}��A���̎�i�������ĖړI�𐋍s�����B
�����ɂ��\���ł���B
�@�����߉��̂ǂ������܂���ɁA��V�͐g�̊댯�������āA�y�쌴�̈ӌ��ɏ]�����B
�V�Ö\������g�����Ƃ������R�ŁA�E�o���͂�������V�́A�H�����A��p����Ȃǂ̓��{�l���܂�5�l�̏]�҂Ɍ�q����āA�Ö�ɂ܂���Ĕ��͉݂͊ɏo���B
���ɗp�ӂ̃����`�ɏ���āA�����������A�X�D�̒W�H�ۂɏ�肩�����B
�Ö�B���̒E�o�ɁA��̖��B���c���11�����{�̋ł̊����Ɍ������ڂ߂Đk���Ă����B
���ܖX�ɍ��ዾ�p�̔��K�̋M���q�́A�v�������ʉh���Ɩv���́A���j�̉Q�Ɋ������܂�āA�N���̎�ʼn^��Ă䂭�������B
��V�͉c���ɒ����ƁA���b�Ԃɏ��ڂ��āA�����q����։^�ꂽ�B
���ꂩ�痷���̃��}�g�z�e���w�\�\
�@���ǁA�֓��R�͒������̐��P���������āA���͂Ŋ����̎����A�����H����������Ă��܂����̂ł������B
�����������ɐV���ƌ��݂�F�Ƃ߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B
�������Ĕ��V�������Ƃ��閞�B�����a�������̂́A���a7�N�i1932�j3��1���̂��Ƃł������B
�@���͂�A���S���֓��R�̕��Ђɕ������̂��A�@���Ƃ������������j�̐����ɊO�Ȃ�Ȃ��B
�����A���c���ق́A�����̖��S�����j�Ƃ����֓��R�̖d���ɂ��ẮA���܂ł��ߑR�Ƃł��Ȃ������B
���A�ǂ̂悤�ɂ��āA���̎��������炩�ɂȂ邩�A���邢�͉i�v�ɑ��苎�������̂��B
�@�̂��ɓ��c�́A�{���i�ߊ����V�c�ɐ\���グ���Ƃ����A�d����ے肵�����t��l�ÂĂɕ������B����͎����̂悤�Ȗⓚ�������Ƃ������Ƃł���B
�u���B���ς͊֓��R�̖d���ł������Ƃ����\�����邪�ǂ����v
�u�ꕔ�R�l�Ɩ��Ԑl���A���悤�Ȋ�Ă������Ƃ����\�����ɂ������܂������A�{�E�Ȃ�тɊ֓��R�Ƃ������܂��ẮA������ɖd���Ȃǂ͂������Ă���܂���v
���Ԑl�Ƃ������Ɋ܂݂�����A�Ɠ��c�͎v�����B
10�@���ۘA���̃��b�g�������c
top
�@�k�����痈�Ė��S���ɏ�肩�������ۘA���h���̃��b�g�������c�́A��V�Ɍ����Ă����B���ؖ������{�́A���{�̖d���ɂ���Ė��B�����ł����������ƐM���Ă���̂ŁA�������Ȃ����肩�A�킪�̓y�ɋU�����Ƃ����Ƒ������A���ۘA���ɒ������˗������̂ł������B���b�g�����͂��̂��̂����������]���āA���a7�N2��27�����l�֓��`�A�����ɏ�C�A�싞�A�k�����o�āA�������̑劽�}���Ȃ���A���B�֓������̂����A�ݖ��M�l�ɂƂ��ẮA���܂芽�}�ł��Ȃ��q�ł������B
�@���S�͓��ʗ�Ԃ��d���Ăė�����������A�����ɓG����A�Ƃ����悤�ȕ��G�ȋC���𖡂���Ă����B�֓��R�����S���A���ۘA���Ƃ��������̑O�̔퍐�ł��������炾�B�Ȃɂ���A���B�������ƂƂ��ɁA�r�������͊e�n�ōr�ꋶ���A�\���⏝�Q���������Ƃ�f���Ȃ��B |

�������̐\���ō��ۘA�����烊�b�g�������c�����B�ɔh�����ꂽ�B���̕�����{�̍��ۓI�Ǘ����n�܂�A���ۘA���E�ށA���ƈɎO�������A�����m�푈�ւ̓���i�ނ��ƂɂȂ�B |
�@���̒����������̗���ŁA���ۘA���֑i�����̂ł��邩��A�����c�̕ɂ���ẮA�ǂ�Ȃ��ƂɂȂ邩�킩����̂ł͂Ȃ������B�X�l�ɏ��҂̂́A�֓��R�ƈ�@��̖��S�ł���B�\�\�����̖��S�����j�̐^�������ꂽ�玖���B���c���ق̐S�ɂ͂����ɂ������B
�@���b�g�������c�͕�V�֒����ƁA�����d���ɂ��������B�܂��A�Ȃɂ��������̓S�����j����̎��@�������B�Ȋw�I�ȖȖ��Ȓ����̂̂��A���b�g�����͓��c�̋���Ă����_�������ɊŔj�A�w�E�����̂ł���B�u���j�͐\������x�̏��K�͂Ȃ��̂Ƃ݂�B�C�����ȒP�ɏI�������Ƃ̏؋��ɁA���̋���ȍL�O�̖��S��Ԃ�����ɒʉ߂��Ă���B�k��c�̒����R�̏،��͐������B���B��̂̌��������邽�߂̖d���ł��낤�v�ƁB
�@�����̌��ʂ͋ɔ�ŁA�^�����Ŕj���ꂽ��������ʂƂ����s�����c���A�����c�͕\�ʂɂ��₩�Ɉ��g�����U��܂��A���B�����Ƃɂ����B�������e�̈�[�ł��m�肽���ƒ���@�ւ͂�������p���āA�����c��_�������A�ꕪ�̃X�L���Ȃ������B����@�ւ��n�c�ʓ��̂́A�������ɏo�������ꂽ������m��������ł���B�������{�͒����c���싞�ɑ؍ݒ��A��r���т̂��ĂȂ��ł��������X�L�ɁA10���~�Ń^�C�s�X�g�����Ă������̂ł������B�������̓��e�̓^�C�s�X�g�̎ʂ��ŁA����A�X�p�C�̎���ւĒ������{�֓`����Ă����̂ł���B
�@���b�g�������c�̓��ʗ�Ԃ͑�A�Ɍ����Đi��ł����B�[��A�������������ăz�b�Ƃ����̂ł��낤���B�A���̔����o�āA�c���͓D�̂悤�ɖ����Ă����B���̂Ƃ��l���̂悭�Ȃ����N�̓��{�l���斱�����ւ̂���������Ă����B�ނ͐����Ђ��߂Č������̂��B
�u���͓��{���{����h������āA���b�g�������c����s���Ă�����̂����A����d��������B
�����g���A���Ƃ̓J�����Ŏʂ����B
�����h�W�Ƃ��͒E�o���邩��A���S����̋��͂����݂̂����v
�u�X�p�C�ł����v
�ƎႢ�斱���ْ͋������B
�u�d�����āA�ǂ�Ȏd���ł����H�v
�u�����c�̕��𓐂݂����d�����B���Ԃ͏\���l����v
�斱���͐ӔC���ɋ������B
����ȑ傻�ꂽ���Ƃ����āA�������s�����Ƃ��͂ǂ��Ȃ邩�B
���ނ͌��d�ɕ���A���̂��������g�����N�̒�ɂ��܂��Ă���ɂ������Ȃ������B
�ǂ����ĔE�т���ŒD���̂��B
���A���ꂪ�ڂ����܂����킩��Ȃ��̂��B
�\���l�̖\�k���P��������Ƃ���A���S�Ƃ��Ă��A�ʂ����Ȃ��s�ˎ����ƂȂ�B
�ڂ����܂��������c�̈�l�����e�˂��邱�ƂŁA�W�J���錌�Ȃ܂������C���ꂪ�斱�����قɕ����B
�@�Ƃ��낪�ł܂ŃR�\�Ƃ̉������Ȃ������B
�����c�̈�l���N���������Đ��ʂɂ䂭�̂ɏ斱���͏o������B
�������Ȃ������̂��B
�悭���������Ƃ̎Ⴂ���l�̊�͖��������ɖ��邩�����B
�X�L���Ȃ��Ă��Ȃ������̂��ȁA�Ə斱���̓z�b�Ƃ����B
�u�₠�A���͂��肪�Ƃ��B���̉w�ō~��邩��ˁv
�ƁA��̃X�p�C���ɂ��ɂ����ď斱�����֓����Ă����B
�u�������Ŗ����I�[�P�[�ł��B�l��߂��đ�R�������v
�斱���́A�J���������ǂ���Ȃ������B
�ނ̓��b�g�����̐Q��ԂɔE�т��݁A�����ƃ}�|�N���Ă�����������̃g�����N�𓐂݂����ƁA�����g���ĊW���J���A���o�������̓��e���J�����ŕ��ʂ����̂��Ƃ����B
�N�₩�Ȏ�ۂ͐l�Ԃ킴�Ƃ͎v���Ȃ��B
���b�g�����͐Q���������Ă��m��Ȃ������ł��낤�B
�ނ͂������Ɉ�A�̉��ŏ��A
�u���Ƃ̒ʂ�ɕԂ��Ă���������A���A��ɂȂ��Ă��䑶�m�Ȃ��ł��傤�B
���{�̃X�������ɂ���v
�ƁA�����Ԃ����B
�@���{�鍑���{�́A���{������ꂷ��X����I�����Ė��B�}�h���A���b�g������s����s�����A���ۓI�q�r���������̂ł���B���ʂƂ��ẮA�ɉ��Șb�ŁA�m��ʂ����̃��b�g�����̊���v���������ɁA�斱�������̏��͎~�܂�Ȃ������B
�@�������u���B���v�����F�������{�́A�A�����J���͂��ߐ��E�̔�������g�ɏW�߂邱�ƂƂȂ����B���b�g���̌��ʁA�W���l�[�u�ŊJ�������ۘA���{���̑���ŁA���{�͊��S�ɌǗ������B��ȑS���Ƃ��đ���ɖ]�̂́A���B�Ƃ͐��Ă���Ȃ������m�E�ł������B�ނ̓A�����J�Ƃ̊O���̎��s�A�i���͓얞�B�S���̍����o�c�����ۂ����Ƃ��ɂ���j�֓��R�̓Ƒ��������̂ƒm��Ȃ���A�������ɗ��������������{�̖ʎq�i���B�����F�𐢊E�ɔ��\���đ������ɂ��炳��Ă���j�𗧂Ă邽�߁A�f�����ۘA���E�ނɓ��ݐ�˂Ȃ�Ȃ������B
�@����́A�O���Ȃ����R�̗͂ɋ������A���R�������܂��A�֓��R�̓Ƒ��Ɉ��������A�ۂݍ��܂�Ă�����������Ƃ�������B���{�͈�C�T�Ƃ�����ȉ^��������I�сA���ۊO���̕��䂩��~�肾�B���̌��ʁA�����͐S�̒�Ńs�G���̒Q���������Ȃ���A�O�ɌǗ�����[�߁A���ɌR���ƍق̓����͂����ނƂ����A�^���I�ȁu���E�I�p�Y�v�̖�����S���āA�}�i���邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�@�������ł����̂�����Ȃ������߂̌و����A���B���֕��C�����Ƃ���������N���X�̃|�X�g�Ă����A60�~�̌��3�{�ɂȂ��Ă����B���S�̐��Ј��ɂȂ邱�Ƃ́A���B�ł��G���[�g�ł������B���̂������{�͕S���l�ږ��v������āA�_�ƊJ��яd�H�Ƃ̊J���𑣂����Ƃ��Ă����B���B�ցA���B�w�\�\�̌Ăѐ��͖��B���̔��W�ƂƂ��ɁA�����Ȃ��Ă䂭���肾�����B
�@���S�͓��n�̐N�������}�����ꂽ�B�x���A�}�����Ԃ̖ڂ̂悤�ɑ���A�тʂ��A��������S���́A�V�݉w�̑����ɔ����āA���{�l�̌��ƈ���K�v�Ƃ����B�V���S�Ј��̍Ȃ►�����́A���n�ł݂͂��Ȃ��D�u�Ƃ����^�C�v�ɕϖe���A�嗤�̋�C���S�������đ�҂ɕ����Ă����B���B�ɟ������V�N���h�̑������́A���{�����̗D�G��������킵�Ă���悤�ł���A���S��Ђ͂܂��Ɂu�����y�y�v�����݂����u�S�����v�Ƃ݂����ɈႢ�Ȃ��B
�@������v���Ζ��̒��̏o�����̂悤�ł����邪�A3000���̌��n���O�͔���̃h���C�Ƃ����f��Ȃ������̂ł͂���܂����B�Ј��̉Ƃ̃{�[�C�≺�j�≺�X�͂��ׂĖ��l�ł���A�n�Ԃ�l�͎Ԃ��g���ē��{�l�𑗂�}�����閳���̊X���f�҂́A�n�������n�l�ł������B���S�̋����ƂƂ��ɁA�J���͂Ƃ��ăh�V�h�V��A�ɂ���l�����́A�Q���������̒����l�A���N�l����юR����͂ł������B�A���n�̓����҂͐F�ӂƂȂ�B�����̍��ʂ͕ʂƂ��Ă��A���B�������ɂ������Ċe�|�X�g�ɂ������B�l�n�����̒n�ʂ́A�������ɓ��݂ɂ����Ă������B
�@�u�Ό��\�z�v��搂�ꂽ�u�ܑ����a�v�̃X���[�K���́A���B�l�n�����Ɏx�����ꂽ�̂����A���̂܂ɂ��E�������ɂȂ��Ă����B���̂Ȃ�A���B���̎w���͓��n�����̎�ōs�Ȃ��ƋK�肳��Ă���A���{�̗v�l�͓���}�����ĉ���ł��Ȃ��Ȃ�A��V�c��̓��|�b�g�����A�U���Ƃ̐��i�����킵�͂��߂�����ł������B
12�@�֓��R�̋����Ɠ����푈�̎n�܂� top
�@�Ό�������{���t�ƂȂ��Ė��B������A�����M�`�i�ߊ��Ƌ��ɁA�֓��R�Q�d���̐w�e����V����ƁA�֓��R�ƍق̋��͂Ȑ��������ꂽ�B����́A���B�����ꉞ�g�ɂ�����́A�\�����������h�̑����ƍl���A���B�͓��{�̍��h�ɂȂ���Ƃ������R���|�ɁA���{�����B���ɒ������������˂Ȃ�ʂƂ����A�V�������h�S���̔C��������ł���B���Ȃ킿�A�֓��R�i�ߊ��͊֓��������A�����S����g�����ˁA�O�ʈ�̂̑̐����Ƃ��Ė��B�ɌN�Ղ����B�u�Ό��\�z�v�̗��z���������ɕϖe���Ă����̂́A�֓��R�̋����̉ʂɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���S�͖��B���̐����ƂƂ��ɑ��𐁂��������A�ӂ����ђ��l�I�ȗ͂����āA���݁A�o�c�̂����镔��Ŋ������͂��߂����A�ߑR�Ƃł��Ȃ��̂́A�֓��R�i�ߊ��̌��͂̋����ł������B
���͂▞�S���ق͑��Ђ̉�̒n�ʂɗ����ꂽ�Ƃ����ׂ����B�֓��������ǂ���ł͂Ȃ������S����g�ƂȂ����i�ߊ��́A���S���͂��ߖ��B���S�̂������ɔ[�߂����ƂɂȂ�B
�@���������������֓��R�́A�S���B�ɖz�����݂̍s����F�߂��A�K�v�Ƃ���Ή����̑�R�������ł���̂ł������B���łɖ��S������邾���̎�����ł͂Ȃ��B���S�����̂Ȃ��ɂ́A�����ɂ̂��ĉؖk�ɕ���i�߂��֓��R�́A�Ƃǂ܂邱�Ƃ�m��Ȃ��\���ɕs��������Ȃ���A�u���ؐ푈�ɂł��Ȃ����玖�����v�Ƙb���������B�Ƃ����̂́A���B���ό�̖��S�̔ɉh���A�c�O�Ȃ���֓��R�Ƃ������͂̏��̂Ȃ��ŁA�E���������Ă���ɂ����Ȃ�����ł������B���ǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ��Ƃ����s���́A�B������Ȃ������B
�@���S�Ј��ɑ���R�l�̑ԓx���A�܂�ŕς����B�w�L�𒅂Ă��閯�Ԑl�͓��R�R���h���ׂ��ł���A���܂��������В����Ă�����̂͌R������Ă��邩�炾�A�ƌ�������̑ԓx���I���ɖڗ����Ă����B���m���܂ł������������B�u����ɉ����ɂȂ�₪�����ȁv�ƎႢ�Ј������͐�ł��������A��������ɂ���킷���Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�֓��R�́A���B���̎�s��V���i���t�j�Ɍ��߂�ƁA�����̎i�ߕ���V���哯��X�Ɉڂ����B���É���������ǂ����S�ؘZ�K���̍��Ȏi�ߕ����������A���ʓV��t�ɋe�̖�͂�����߁A����ɓ��͊����Ђ邪�������B���̈Е��͑S���B�����n���Ј����邩�̂悤�������B���S�͕\���ւɈʒu����Ƃ����n�Ƃ̐��_���������A��A�ɓ��ݎ~���ē������Ƃ��Ȃ������B���ꂪ���߂Ă��̊֓��R�ɑ����R��������������Ȃ��B
�@���БS���B��Ȍ����A��]�Ƃǂ܂邱�Ƃ�m��Ȃ��֓��R�́A�ؖk�H��ɏ��o���A�{�������n�тł���͂��̗����n��������B���������B����ɐ��͂��͖k�A�`�`�n�����ȂɐL���A�Ӊ�̒��������j�����Ƃ����B�A�����A�A�����Ǝv���Ă���ԂɁA���S���������̕s���͌����̂��̂ƂȂ����B��������ɓ��ݐ����Ӊ�̑Γ����d�A���a12�N�i1937�j�^�����b�a���������܂˂����̂ł���B
�@���S�̗��������͐V�����O�́u�������R�k���i�x�O�j�Ō��c�c�������˔@�s�@���C�v�Ɋz�����߂Ȃ���A�܂��A���{�R�̖d���ł͂Ȃ����Ǝv�����B
��x���邱�Ƃ͎O�x����B�������A���n�ɔ��ł����V���L�҂���A�����̂悤�Ȑ^�������B
| �@�L��̒��ԌR�������A�b�a���߂��Ŗ�ԉ��K���͂��߂悤�Ƃ��āA���x�~��A�����_�Ă�����ƈ�l�̕����̎p���݂��Ȃ��B7��7���̖�̂��Ƃ������B���͈͂łŁA���������̂��킩��Ȃ��B�s�R���ɒx��Ė����A�v�N���̂Ђ�����29�R�ɝf�v���ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����ӌ����o���B29�R�̕��ɂ͋߂��̈�����ɂ������B�ߗ��ɂȂ�Ε����̕s���_���B�����̉T��������̂ŁA��ԉ��K�͂��Ƃ܂킵�ɂ��Ĉ�����֏�肱�B�˂��Ă����̂́A29�R�̕�����ł������B�����炪���킷��͓̂��R�̂��Ƃł������B
�@���ꂪ���������ŁA�L�䒓�ԕ����̏o���ƂȂ�A������A�L�V�A�k���Ɛ�͊g�債�A���ɏ�C�ɔ���āA���������̃h�����푈�A����A���{��ߎS�Ȕs��ɒǂ���鑾���m�푈�Ɣ��W���Ă䂭�̂ł��邪�A�\�\���̎��́A�V���L�҂̕��Ȃ���A���������͏����낰���̂ł������B |

�X��͂ɂ�����ḍa���͕ʖ��}���R�|�[�����ƌĂ��嗝�Α���̋��A���a12�N7��7����A���̋��̏㗬�Ŕ��������ꔭ�̏e�����ߌ��̓����푈�̓��ΐ��ƂȂ����B���͂��̋��͖k���̊ό������ɂȂ��Ă���B |
�@���Ȃ킿�A29�R�ƒ��ԌR��������Ō�풆�A�����Ă�����l���̕������߂��Ă��āA�u�\����܂���B���f����𗣂�A�p�ւ����Ă����̂ł���܂��B�������ɖ�ԉ��K�ɎQ���������܂��v�ƁA�����̑O�ŕs���̎p�����Ƃ����B�����͈��R�Ƃ������A����ǂ���ł͂Ȃ��A����̍Œ��ł������B
�@������L�҂͖ʔ������������A�����҂�����������̂́A�ؖk���ԌR�i�ߊ��A�k�������@�֒��A29�R�ږ�A��g�ٕt�����⍲���Ȃǂ��z�����A�Ǖ��I�����̌��ʂ��������Ƃ������Ă�������ł������B�����͍��ׂȗ��R�̐ڐG�ɂ����Ȃ��B�����Ɉꕺ�m�̗p�ւƂ����G�s�\�[�h�����炩�ɂȂ����ȏ�A�푈�ɔ��W���锤�͂��͂Ȃ��A�ƍl�����͓̂��R�ł��낤�B
13 ���B���̔��W�Əd�H�Ɖ�
top
�@�����푈�̊g��ƁA�\�������̕��������́A�֓��R�̋��剻�������߂��B���B�֖��B�ւƂ����R���͂̑����́A�ƃ\��Ŏ蔖�ɂȂ����\�A�ɓ��R�̋������āA������˔j���悤�Ƃ����_�������������炾�B����E���i1939�j�u���ȗ��A���������ɂ����ēƈɂ̗D�����`����ꂽ�B�t�����X���h�C�c�ɍ~���i1940�j����ƁA���{�R�͕���i�x�g�i���j�ɐi�����A9��27���Ɂu���ƈɎO�������v����������B�@���������A�\�A���t�����Ƃ����_���ł���B
�@���B���̎Ⴂ������A���S�Ј��̒��ɂ́A�u�R�͖��B������Ă���邾���ł������ǂȁB�ʂɃ\�A�ɐ푈���d�|�Ȃ����Ă��v�ƁA�R�̎��ȉߐM�ɔ����Ђ��߂�҂��������B���́A�����푈�ł��肬��̔��Ȃ̂��B�֓��R���������Ҍ��̂悤�Ɍ������B�m���ɁA�����b��a���݂ɒu�����Ԑl�ɂ́A�푈�Ɍ������Ė҂苶���R�l�̃G�l���M�[���A�C�������݂�����ǂƌ�������������Ȃ��B
�@�����푈�ł��肬�肾�Ƃ��������́A���{���{�����B�̏d�H�Ɛ��Y�ɒ��ڂ��A��ꎟ�Y�ƌ܃��N�v��̊g���ǂ��Ă�������ł���B������̓D���ɂ̂߂荞���{�́A��������R�������̎��v�������Ƃ��ł����A�Ƃ��ɓS�A�ΒY�Ȃǂ̏d�H�ƕ����̕s���ɔY��ł����B�����Ŗ��B�̏d�H�ƊJ�����}���ł����̂����A���{�̎��Ǒ�Ă��݂�ƁA�Y�Ƃ̑̌n���m�����Ă��Ȃ����B���̌o�ϗ͂ł́A�I�C�\���Ɖ������鐔���ł͂Ȃ������B�����œ��Y�В��̈���`��𑍍قɁA���B�d�H�ƊJ����Ёi���ƂƂ���ꂽ�j��ݗ��������A�v���悤�ɒ���Ȃ������B
�@�ŏ��A����̍\�z�͑s��Ȃ��̂ł������B���E�I�ȑ厩���ԍH�Ƃ��������ƂŁA�A�����J�Ƃ̌o�ϒ�g�𐬂��Ƃ��A���ĊW�̈��������ɘa���悤�Ɛ}�������Ƃ��B���ɑŐf�̌��ʁA�A�����J���{����ыZ�p�A�@�B�̓����Ȃǂ̌��ʂ������A���Y�B�Ɉڂ����Ƃ��A�ނ͉p�Y�I�ȕ����ŋ���c��܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B
|

���B���̎�s�V���i���t�j�̌����̐V���w�A�V���̃��[���X�g���[�g�͋ߑ�I�œ����ɂ�����o�����o�����B
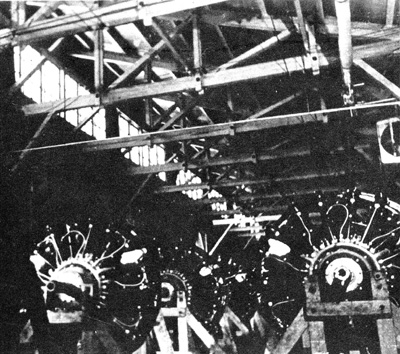
���B��s�@������V�H��A���a13�N�n���ȗ��g�[���d�˂āA�R�p���K�@�ł͌��Y�P�W�O�@�̔\�͂����܂łɂȂ������A19�N��B29
�̔�����2��ēO��I�ɔj�ꂽ�B |
�@���Ȃ킿���삪���B�̓Ɛ莑�{�̉������߂�Ƃ��A���S���܂����̎P���ɕ�܂��邱�ƂŁA�n���}�����ȗ��̓��Ė�肪��������B���̂悤�ȑ������������̂ł͂���܂����B�������A����͎��ƉƂ̖���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�u���[���A�������ς����N��Ȃ���v�ƁA�ނ͐�ł�������������Ȃ��B���ςɂ���ăA�����J�̑ԓx�͍d�������B��̊g��Ƌ��ɂ��悢�戫���̈�r��H���Ă������̂��B
�@�����ň���͎��Ȏ��{�i���Y�̊�������2��2,500���~�j�ɁA���B���̓��z�o���������A���{��4��5,000���~�̓���@�l���B�d�H�Ɗ�����Ђ�ݗ����邱�ƂɂȂ����̂��B���ꂪ���߁A5���N�v��̉����g��𔗂������{���{�́A����������]�k�Ȃ�����A���a14�N�ȍ~�ɂȂ�ƁA�N��10���Ȃ���12���Ƃ�������ȋ��B�֒������B����ł��R�������͕s�������B�̌o�ϕ����������߂��Ă��鎞�A�܂��\�A��ɂ������Ȃ̂��B
�@�S���閞�S�}���͔����Ђ��߁A�R���D��̃A���o�����X��ᔻ�����B�����Ƃ����ɂ́A���̍ۃh�C�c�̏����ɕ֏悵�ă\�A��@�����A���\�����Ɍ�ڂ̗J�������������悢�A�Ƒ������҂��������B���̂悤�ȏ�̒��ł��A���S�Љ͓̂S�H��`����ċ����A�V�ݐ�����ѕ����̌��݁A�ΒY�A�S�z�̑��Y�ɗo�z�F�̉ΉԂ͎U��A�u���A�`�p�A�͐�̊Ǘ��A�s�s�A�����̌��݁A�z�e���A�a�@�A�w�Z�A�_�Y�����Ȃǎ{�݂̌��݊g�[�ɁA�S���͂�ł�����ł����̂ł���B
�@���Ȃ킿�A���B�̓��{�l�́A���̂˂苭���ΘJ�A痂��������́A�J�_�������Ĉ��������݂̌L��i�߁A���̂܂ɂ����B���i�U���ƂƉ]���悤���j���A�ߑ㍑�Ƃɑn�肠���Ă��܂����B���B�֖��B�ց\�\�Ƃ����͔̂_�ƈږ����܂߂āA���^�ȊJ�_�Ɋ�����Ȋg�[�ł������B�R�̖ڎw�������̂Ƃ́A���̂��������Ă����B�R�l�Ɩ��Ԑl�̒��a�Ȃ��G�l���M�[�́A�����A�����̔ߌ������Ă����ɂ����Ȃ��B
�@���B�֓n���Ă������{�l�́A�����֗����Ƃ͎v���Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B������s�s�ɂ܂�����Ȃ��u���{�v���������Ă����B�V���̃��C���X�g���[�g������A���X�Ȃǂɓ����ĐV�������߂����Ă���ƁA�����̊X�ɂ���悤�ȍ��o���N���������B���S���ɂ͎���130km/h�̗����^���}�u�������v��������A�V���A�����A����A�}���قȂǂɁA�ނ���V�N�ňӋC����ȕ����̑��������������B���S���Ƌ��ɁA���X�Ȃ��瓯�E�̟v��j���čL�X�����V�n�ɐL�т�A���͂�ڂɂ��āA���������ɈႢ�Ȃ��B���̈��S���́A�֓��R�ɑ��閳�ӎ��̐M�����痈����̂ł��������A�N���ȂǂƒN���l�����ł��낤���B�C��n���Ă�����ʂ̓��{�l�́A�����ŁA�^�ʖڂɓ������ƍl���Ă��������̂��Ƃł���B
14 �m�����n�������ƃn�C�����w
�@�������ɋ߂����S�̊e�w���́A�\�������ŕ����������閈�ɔ��Ɉ������B�S�ʐ푈�͂Ƃ������Ƃ��āA�\�A�R����������˔j���Ă���悤�ȕ����ɂł��Ȃ�A��ɒ��ڊ������܂��̂́A���{�R�i�v�w�n�̂����v�w������ł������B
�@���B���̖h�q���ɂȂ��֓��R�́A�������ɍ����������z�u���A���a���N����\�O�N�܂ł̂������ɁA���J�A�䎉́A���ډ́A�Փ��A��Ӕ��ÁA����A���́A�C�f���ɉi�v�w�n���\�z�����B
�@����ɒ��X�ƍ\�z�͂Â����Ă���B
�@���łɃ\�������Ƃ������A�\�������ƂȂ��Ă����B���{�ƃ\�A�����B�̍������͂���Œ��ڑΛ����Ă��邩�炾�B���̂��̂��������ւ̕��͏W���Ɖi�v�w�n�̍\�z�̓������݂āA�ڂƕ@�̂����̃\�A�ɓ��R���ق��Ă���킯�͂Ȃ��B
�@�R���ċɓ����͂̑����A�����w�n�A��ʁA���ƁA��s��̐��������ɂ�����A�R�p�@�����ł��O�{���̐��S�@�ɑ��������B
�@���̂����痼���̑䓪�͗d�_���͂�݁A��G�����̊�@�����������������B�����ė�������̏������͊e���Ő��������̂ł���B
�@�����̓m�����n�������i1939�j��������܂łɂ��A�猏�߂��L�^����Ă���B�@�قƂ�ǂ���A�̉z�����珬�e�̉��V�Ƃ������x�̂��̂ł��������A���a12�N�̊���q�i�J���`���[�Y�j���������K�͂̕����������悤�ɂȂ����B |

�����܂��ȍ������ł��݂��ɏ����荇���������
�m�����n�������ւƔ��W�����{�R�͎�ɂ���
���B������֓��R�̓Ƒ��ł������B
|
�@����͍��͉w�̉w�����̂��Ԃ��ĂȂ�䂬���݂܂����������ł��邪�A�����]�i�A���[���́j�̂Ȃ��̏����J�\�`���[�Y�A�{���V���C��2���ɓ����l���z���㗤�����̂��͂��܂�ŁA�\�A�R�̖C�́A�C�������Ɗ֓��R��t�c���Λ����A�\�A�C����ǂ��������ꂽ�B
�@�����̓\�A����̏����ŗ����������A�̂��̒��ە��i1938�j�ł́A�֓��R�̈�t�c���ܕ��̈�������Ĕs�ނ����B
�@�����̓\�A���A�N�̍����ɂ��钣�ە�i�W����150���[�g���j����ɁA�\�A�R���z���w�n�\�z���͂��߂�����ł������B���̂悤�ȕ����́A�������̂����܂��Ȍ����甭�������B
�@���Ƃ��Β��ە�͕s���m�ȍ��������͂���ŁA���\������������������Ă������߂ɂ��������̂����A���ە獹����ɂ�����Ő����A���R�̏���ȉ��߂���A����邪���苒���A����̓I���̗̕����Ǝ咣���Ă����Ƃ���ł������B
�@�������̕s���m�Ȍ��͂������������B���B�����������Ċ֓��R�̖h�q�̐����ł���������
�Ƃ��A�\�����������m�肷�邽�߃\�A�ƌ��������A�\�A�́A1689�N���V�A�Ɛ����̂������ɒ������ꂽ�u�l���`���X�N���v���Ŏ������B
�@�Ȃ����������ɕ����U�킵�����E�W�������܂��ȓ����̍��������A���̂Ƃ��̂܂܁A�ƌ�������\�A�̐S��Ɂu���B���v��f���݂Ƃ߂Ȃ��Ƃ����A�����点�����邱�Ƃ��������֓��R�́A���Ȏ咣�̍��������������ĈЈ����������A�͂ɂ���Ď�����u���B���v���݂Ƃ߂����悤�Ƃ����B
�@���̂����������ƁA�G�ӂ̂����ɁA����ɗ����̊W���}���ɗ�p�������̂́A���ƈɖh������i1937�j�̒���ł������B�m�����n�������́A���̂悤�ȓ��\�W�̈������A���݉��������̂ƌ�����B
�@�n�C�����w�̉w�����u�m�����n���v������m�����̂́A���a14�N�i1939�j��5��14���ł������B���ł�12�������Ƀn���n�͕��ʂŖC�����������悤�Ɏv�������A�n�C�����̍���������̏o����ڌ����āA���Ȃ��K�͂̐퓬�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��@�m�����B
�@�w���ْ͋��������A���̌�̏��ɂ���āA�O�Õ����n���n�͂��킽���ĉz�����A���B�R�Ǝ���������A�G�̑����ƂƂ��Ƀn�C�������Ԃ̑��\�O�t�c�̈ꕔ���o���A�������Ƃ������Ƃ��킩�����B
�@�w����q���邽�߂̎��������������A�Վ��̉q�����z�u����āA���̂��̂����C�z�ƂȂ�������ǁA�u�Ȃ��ɁA�債�����Ƃɂ͂Ȃ��ł��悤�v�ƁA��Ȃ��݂̉��m���͉w�����Ȃ��߂��B
�@�ŏ��z�������O�Õ��͖�700�ł������B���Ȃ葽���̕������z�����A�킪���̉���ɂ������A����������Ƃ����Ƃ���ɁA���܂܂łƈ�������̂�������ꂽ�B
�@�������A�O�Õ��̉z���͈�x���x�ł͂Ȃ��A���B�R�����e�ł��ǂ������A�Ƃ��ɂ͌��Č��Ȃ��ӂ�������B�Ƃ����̂́A���̍�����������߂Ă����܂��Ȃ��̂ŁA�ǂ��܂ł��z���Ȃ̂��A���R�Ƃ��킩�Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�֓��R�̓n���n�͂̐����������Ǝ咣���A�O�Ñ��̓n���n�͓����̐����������Ƃ����B���̏ꍇ�͑啔���̉z���ɑ������āA������o�������̂ł��邪�A�債�����ƂɂȂ�܂��Ɖ��m�����ϑ������̂́A�s�m��ȍ������ɂ��Ǖ��I�ȕ����ł���A����̓^�J���O�Õ����Ƃ����ӎ�������������ɂ������Ȃ��B
�@�w�������m���̂��Ƃ�M�����B�������A�����͂܂�ň���Ă����ꂽ�B
�@�\�A�ƊO�Ấu�O�Öh�q����v�i1934�j�ɂ���āA�\�A�R���@�B�����������肾���ďo���������߂ɁA�����������A�ő�ȋK�͂����u�m�����n���v�����́A��ꎟ�A���ʂ��Đ������ɂ킽��A�z�����o�C�������n�т������Ő��߂�A���\���R�̐���Ȑ퓬�ɔ��W���Ă䂭�̂ł���B
�O�Õ�700�̃n���n�͓n�͎͂����ł������B��K�͂̐퓬�ɂ����̂́A�֓��R�����܂܂ł̕��j����ς��A�f�����łƂ����ϋɓI�Ȏp���Ɉڂ�������ł������B
�@�����炭�A��A�O�l�̉z���ł��낤�Ƃ��A�e�͂��Ȃ������ɂ������Ȃ��B
�@����́A���̎������O�ɂ���ꂽ�֓��R�́u���\�������������v�j�v�Ɋ���̂������B
�@���Ȃ킿�A���\�����ɂ�����\�A�R�i�O�ÌR���ӂ��ށj�̕s�@�z���s�ׂ��������Ƃ��́i�s���m�ȍ������͎���I�ɔF�肵�Ă����܂Ŏ咣�j�����ȏ��������������ŁA���͂̑��������Ȃ���A���������ǂ��̂����̂ł͂Ȃ��A�O��I�ɂ�����Е�������̂�ړI�Ƃ���B
�@���̖ړI�̂��߂ɂ́A�ꍇ�ɂ���Ĉꎞ�\�A�̂ɐi�����Ă��悢���A����̓��ɗU������ł��悢����A�K���������A�Ƃ������d�ȕ��j�̉��ςł������B
�@�͂��ߐM������p�I�����Ƃ����ׂ��ł��낤���B
�@�����͂����܂�����Ԑ�A����܂����ēW�J�A�g��̈�r��H�����B�n�C�����w�͐�̃��c�{�Ɖ������B�ŏ��A�����ɂ����Ă����֓��R���s�ނ̂��������݂��͂��߁A���\�A�R�̋ŊD�ԂƋA���邩�킩��Ȃ������B���\�O�t�c����Ƃ��āA���͂��Z���߂��������ꂽ�B�掵�t�c�̈ꕔ�������A�Վ��̌R����Ԃ͂��������ƃn�C�����w�ɓ��������B
�@�C���u�X�A�I��Ζ��̉w���͐������S�n���Ȃ������B
�@��ꎟ�m�����n�������́A���R���A���̑S�łŁA5��31�����{���̔s�ނɏI�������A�֓��R�͂���ɕ��͂̑�W�����s�Ȃ��A130�@���܂�̑�ґ��Ń\�E��R��n�����������B
�@���ꂪ��m�����n�\�����̂͂��܂�ł��邪�A�������͓��������̊g����l���ɓ���āA�����܂ŋǒn�����������߂����A��ꎟ�̔s�ނɋt�サ���֓��R�́A��R�̏��������ɂ����܂Łu�h�q�̐ӔC�v���ʂ����Ƃ��A����ɐ[�݂ւ͂܂肱��ł������B
�@�Q�d�{���́A�\�A�̒n�}�ɋ��鍑�������݂Ƃ߂�Ƃ����Ë������Ă��Ă��A���}�ɉ������ׂ����Ɣ��f���A���ǒ������n�ɋ}�h���Đ����ɂ����������A�֓��R�͓ƒf��s�̂������ŁA�\�A�̐��S���̐�Ԃ�ɁA���e���W�J���Ă����̂ł���B
�@�n�C�����w�́A�\�Čo���������Ƃ̂Ȃ��폝�҂̌���A�����戵�����B
�@���n�̎��҂͐܂肩���Ȃ��ăz�����o�C����m���̍�����N���Ő��߁A��Ԃ̉��~�ɂȂ����܂܈�������җ݁X�Ƃ��Đ��m�ꂸ�A�ܔM�̑��z�̉��A�����n���}�͏I�邱�Ƃ�m��ʁA�ƕ����ĉw���͐�ɂ����B
�@�w����㑗����镉���҂͏d���Ɍ����Ă���A�葫�̐ؒf���ꂽ���m�̂��߂����͌��̓����ƂƂ��ɁA�w�\���߂��B�������A�����҂����ڂɂ݂āA����Ⴂ�ɓ������i�����Ă䂭���C�ȕ��m�����B�܂�ʼnΉ��߂����Ĕ�т��މ�̌Q�̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@�S�ʐ푈�Ȃ�Ƃ������A�������z�����Ƃ��z���Ȃ����Ƃ����A�Ƃ�ɂ�����ʎ������A�Ȃ��ǒn�I�ɉ������悤�Ƃ����A�������̐��������ۂ��Ă܂ŁA������̕��m���]���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��낤���B
�@���͂�A���C�̍����Ƃ����v���Ȃ��B
�@�w���̐�ɂ́A�����q���ق�s�s�̊֓��R���A�ڂ̂܂��ŎS�߂ȕ�����𑱂��Ă���V���b�N��������Ă����B�����Ă���Ύ����͑����ɉ��������ł��낤���A�Ƃ��ɖ������ɂ������Ȃ��B
�@���{�̓��O���ɂ��炾���A���͂������Đ�������R�̌��ӂ��̂����Ƃ�����Ⴂ�w�����A���x�̎����ł͍l�����܂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B
�@�֓��R�̈ӊO�Ȏ�̂����邱�ƂȂ���A�\�A�R�̎��͂��A�͂邩�ɑz����₵�Ă�������ł���B
�@���܂�ɋ��������B
�@����������ƃn�C�����w�̔������Ȃ��A�m�����n�������͋㌎�\�Z���ɏI�������B���ǁA���X�N���ŊO�����Ɉڂ���A��틦�肪���������̂ł��邪�A�������̓\�A�R�̎咣��S�ʓI�Ɏ���ꂽ�B
�@���Ȃ킿�A�t�c��S�ł��������ʁA���Ƃ̐U�o���ǂ���ł͂Ȃ��A�֓��R�̎咣���鍑�������Ђ����߂��Ƃ́A���̍���Ȃ��푈�������������̂ł���B
�@�������A�֓��R�͊ȒP�ɒ��ɉ������킯�ł͂Ȃ��B
�@�Q�d�{���͍ēx�����Q�d������V���ɔh�����āA����������������A�e�ՂɎ�������A���ɑ喽�����ŁA�S�����̓P�ނ������������ʂł���B
�@����ɁA�������͒Ǔ�����������悤�ɁA�֓��R�����̋��d�h����|�����̂��B
�@���Ȃ킿�A�A�c�R�i�ߊ����͂��߂Ƃ��āA��J�Q�d���A���Q�d�����A���c���ے��A���������A�Ґ��M�����ȂǍ��Q�d�ɑҖ��߂����B
�@���̂悤�ȑ�؊J��p���s�Ȃ��Ȃ������Ȃ�A�֓��R�͂���ɖ\���𑱂��Ă����ɂ������Ȃ��B
�@��풼�O�A�\�A�R�̓n�C�����̔�������ѐi�U���̏������ł��������Ă����ƌ�����B
�@�����炭�n�C�����͈��@�����̐��ƂȂ�A�i�v�w�n�U�h��̉Q���ŁA�w���w�����A�����Ƃ�ł�����������Ȃ��B
�@���̂Ƃ��A���j����]����X�C�b�`���������̂́A�Q�d�{���ł������B
�@����ʼnw�����X�ƗA������Ă����V�s�������~��ꂽ�̂��B
�@�������A�֓��R�̓\�A�ɑ��鍦�����������c�������Ƃ͋^���Ȃ��B
�@�R�i�ߊ��́A�~�Ô����Y�����ɕς������A�\�A�̑ΓƊJ����@�ɁA�ɓ��R�̋������Ĉꋓ�ɐi�U��_���A�u�֓��R���ʉ��K�v�Ƃ������ڂ̑\���͏������͂��߂��̂ł������B
�@�S���̑哮���v��ł���B
15 ���B�ɑ��荞�܂��u�֓����v����
top
�@����ɂ���Ăǂ�ǂ���荞��ł����J��c�A�����A���l�A��Ј��A���s�ҁ\�\���̑��̓n���҂ŁA���S���͖Z�����Ȃ����B�t����Ăɂ����āA���n����̓n���҂̓O�b�Ɛ��𑝂��̂����A��A����ш����̉w��������ۂ̂́A�R����ԕҐ��̖��߂ł���A��10���̑啔�����V�֗A�����邱�ƂɂȂ�������ł���B
�@���悢��A���̂ł͂���܂����B�����v�����̂́A�قƂ�Lj���i���R���j�̋ݏ͂��������m�������A��Ƃ��Ė{�y�v�n�h���v���A�v�Ǎ��˖C�����v���ŁA���珢�W�����҂��肾�������炾�B���m�ɘb�������Ă݂�ƁA���n�����ɏ��W���ꂽ�̂ŁA3�����̋���P���ɈႢ�Ȃ��ƈ��S���Ă�����ɁA��Ԃɏ悹���A�A���D�ɏ�芷���A�C���t���Ɩ��B�ɗ��Ă����ƕs�������ɓ������B
�@���̂����A�^���₩�ȏ�����Ă����B���̕����͊֓��R���ʉ��K�i�ȉ��u�֓����v�j�̂��߂̑�ꎟ�����ŁA�㑱�����͉����ɘj�邩�m��Ȃ��B���K�Ɩ��ł͕̂\�ʂŁA�֓��R��100���ɋ������āA�\�A�ɓ��R���U������Ɖ]�����̂������B����Ȃ��Ƃ́A���̍U������֓��R�̐��s���A�ǂ��֍s���āA��������̂��A�������m��Ȃ����Ƃł���B����10���̑啔���i���͑P�ǂȎs�����ˑR���W�ߏ���Ƃ��������̂��Ƃ��j�́A���R�ƒ�������֓����������̂Ǝv���Ă���B���Ȃ킿100���̊֓��R�Ɖ]������ǁA�\�A�֍U��������̂́A�����̍��Q�d�ɊO�Ȃ�Ȃ��B�����Đ���Ď��ʂ̂́A���m�B�Ȃ̂ł������B�������A���悢��ƃ\��ɎQ������̂��A�w���͖����Ɋo���V�ɂ����B
�@��2�������́A���a16�N�i1941�j��7��22������W���A�����s�Ȃ�ꂽ�B����́A14�t�c��̍ݖ��N�����ɓ��n2�t�c�������Ґ����������A����450����Ȃ镔�����������ꂽ�̂ł������B���������ɂ��ƁA�֓��R��20�t�c�Ȃ���25�t�c���v�]���Ă���A�k�Ɛ���1�t�c���Ĕz�����A4�t�c�͗\���R�A14�t�c�ʼn��C�B���ʂ���уE�I���V�[���t�k�����U������v��炵�������B���S�̉w���͊֓��R�̖c���Ԃ�ɖڂ�������A�k���̊�@���Ɋ����A�Ԓf�Ȃ��ʉ߂���Ԏ���ԂɂĂ�Ă��������Ȃ���A�Ђ��Ђ��b�̂Ȃ��ɂ��c�_��2�ɕ����ꂽ�B�u�֓����v�肵�Č}����҂ƁA��Ԃގ҂Ƃł���B
�@���S�͖��߂ɂ���āA�R����A�����邾���̂��Ƃł������B�����A�ǂ��Ȃ��Ă䂭�̂��A�����ς�킩��Ȃ����A�����������ތ������Ȃ������B�c��������֓��R�̍זE�A��l�X�X�̕����琬�藧�R�����̂��̂��A�ډB������Ėc��Ă���̂��B���n�ŁA�������c���{�V�~�ɂ�����Ă�����ɁA�푈���i�s���Ă���悤�ɁB�킩���Ă���҂͂ǂ��ɂ����Ȃ������B�����u�֓����v�����肵�A��1���A��2���̓������s�Ȃ�ꂽ�Ƃ����i�K�ł́A���̐l�X���m���Ă����B�Q�d�{���̓c���V���핔���Ɨ��R��b�����p�@�ł��邪�A�ޓ����܂��A��̂��Ƃ͂킩���Ă��Ȃ������ƌ����悤�B
�@���̂Ȃ�A�ƃ\��̐��ڂɕ֏悵�āA�k�����͉��������d�ɉ����o�����c����핔���ɑ��A���R�Ȑ^�c�R���ے���Y�����͐��ʂ��甽���A����͎Q�d�{���Ɨ��R�Ȃ̊m���݁A�����ɓ�����ɏd�_��u���C�R�̔��Έӌ��������A����ɉؒ��E�ؖk�̎t�c��k���֓]�p����Ƃ����Q�d�{���Ăɑ��A�f���������钆���h���R���i�ߊ����叫�Ȃǂ�����������āA�������͂Ă�����̉Q���ɂ��������炾�B
�@�C�R�͑Εĉp��̊�@���ǂ��Ă���܂���A�k���ւ̊J��Ƃ͉������Ɠ{��A���R�̖d���I�Ȃ������x�����Ă����B�����h���R�͖k���̊J��������푈�̉������悾�Ǝ咣�����B�Q�d�{���́u�֓����v�̓������ł�i9���܂łɒZ����������s���Ȃ���ΐᏫ�R�̏P���Ɉ����j�A���R�Ȃɓ����̋}�i���{��ǂ��āA���˕t����ꂽ�B
�@�������s�Ȃ�ꂽ�̂́A�c����핔���������ɓ��𗤑��̊��@��K��A���傤�ǔӎޒ��̂ق됌���@����������������������A���R�Q�d������ʂ��āA�����Ɋւ����t�𐬌��������A�Ƃ������Ƃł���B�������A��3���̓�������ъJ��܂łɂ́A�\�f�������Ȃ�������N�����B
�@���{�A���R�i�Q�d�{���Η��R�ȁj�A�C�R�̈ӌ��̐H�Ⴂ�⌠�d�p���̍s���ӓׂƂ��Ē�܂炸�A�悤�₭������x�������Ă̊֓��R�����̑Ë��������o���ꂽ����A���݂Ƃ��Ă����ƃ\��̉_�s�����ς��Ă����B�ӊO�Ƀ\�A�R�͋��x�������B���X�N���ɐ���ꍞ�ނ��Ƃ݂����G���A���ʌ��ւ̃X�������X�N�ŕߑ����A���ނ����B�����ŁA�ƃ\������P����ԂɊׂ�A����͋t�]�A�ƌR�͑ދp���n�߂��̂ł���B
�@�����A�h�C�c�����X�N�����U�������Ȃ�A���{�̖k�����͉����͎��s�Ɉڂ���Ă����ł��낤���B��O���������s�Ȃ��A�u�֓����v�͉��K�����ŏI��Ȃ������ł��낤���B�����炭�A�����Ȃ��Ă����낤�Ǝv����B���̂Ȃ�A�c�������֓��R�͐i�U�̑Ԑ��𐮂��ă}�i�W���������A���͂�ނ��ɑނ���ʗ���ɂ���A�ƃ\��̐��s���Ȃǂɂ͓ڒ����Ă��Ȃ������B
�@�h�C�c���ꎞ�ދp���悤���������͂��������B�u�T�d�ȑԓx��]�ށv�Ƃ����A�}�ɓ���������̓d��ɕ������A���݂̐�͂œƒf�i�U�������Ď����ʂƂ����p�����������B���̂悤�ȓƑ��̌X���ƕs�ޓ]�̎��M�́A�֓��R�̓`���I�Ȑ��i�ł��������A�\�\�h�C�c�������Ă����Ȃ�A�吨�͓��R�A�֓��R�Ɉ��������Ă������ł��낤�B�u�҂����v���������̂́A�O�����ǂ̕K���ȊO�����̌��ʂł���B
�@���\�������͏��a16�N4��13���ɒ���Ă����B�e���Ƃ��A�ǂ�ȏ�������ł��悤�Ƃ��A�푈�Ƃ��Ȃ�Έ�Ђ̔��̂ɂ��ĉ��̒��y�������Ȃ��B�ƃ\�s�N����łɏؖ����݂ł������B���{���܂��\�A�Ƃ̊Ԃɒ����������тȂ���A�u�֓����v�̎����������Ă����ʂł���B���荑�����āA���j�����Ă��邩�킩��Ȃ��B
�@���̏ꍇ�A�A����c�œ��c���̌������u�\�O�����v�j�v�́A���\��������\�ʂɌf���邱�Ƃɂ���āA�����̌����ȋ�C�����A�֓��R�̖\����}���悤�Ƃ������̂ł������B���Ȃ킿�A�u�c�c�\�A�ɉ��Ē����������炵���ɓ��ɉ��ċ��Ђ�^���������A�鍑�͓��\�������̋`�������ׂ��|�𖾂炩�ɂ���i�\�Տ����̂����̒��j�v�̎�|���A�L�c�O������\�A��g�X���^�[�j���ɐ\�����ꂽ�̂ł������B
�@�֓��R���Q�d�{�����A�k�����͉�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������֓��R�́A�c�ꂠ������70���R����i�����܂܁A�ݖ��N16�t�c���������͂Ƃ��āi���͖�70���A�n��4���A��s���600�j�k���ɏW�����A�\�x���ɓ��邱�ƂƂȂ����B�u�֓����v�͑哮�����s�Ȃ��������ŁA���Ȃ����B�u�\�\�푈�ɂ͂Ȃ�Ȃ������ˁv�ƁA�w���̓z�b�Ƃ��Ě����������B�u�푈�����Ȃ���A�֓��R�̂��̂����������́A��X�ɂƂ��ė��������B
�����A�d���ɐ����������v
16�@�����m�푈�Ɩ��S top
�@���a16�N�~�A���S�̗��������́A�������ł���A���قł������������m�E�O���̊���ɋ���������A���ۘA���̒E�ނ�A���ƈɎO�����������Ƃ��Ȃǂ́A����J���Ȃ�����A�����ɐ������������Ă������̂��B�������A�q�b�g���[�Ɖ���āA�i�X�^�[�����Ƃ������Ȃ��b���������Ƃ����j���[���b�n����A���Ă��Ă���́A�����������ςɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����\���`����Ă����B���Ȃ킿�A�������q�b�g���[����ɂȂ����Ɖ]���̂ł���B
�@�A�����J�Ƃ̊O���ɂ���Ă����A����ɂ�����`�a�b�c��͐w���������@���Ȃ��A�����m�̈��S��}�邽�߂ɂ��u���ėȉ��āv�����F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��鐭�{��]�ɑ��A�����O������������ꂽ�Ƃ����̂ł���B�u�A�����J���x�����ȁB��ꎟ���̂Ƃ����Έ�E�����V���O��������тȂ���A�j�����ꂽ�ł͂Ȃ����v�ƁA�拭�ɔے肵������łȂ��A���̂��A�ƈɂɓ��Z���ɂȂ��Ă��܂����B
�@�����O���̃A�����J�s�M�́A���ƈɎO�����������Ԋ�Ղł�����A���ۘA���E�ނ̐�����l���Ă��A�X�W�͒ʂ��Ă���B�����A�q�b�g���[�̉e�������炵���p�Y�I�ȃ|�[�Y�ɋ��C���������������A�V�c�Ɍ����āA�u���{�͌��݂̒��������ł͂Ȃ��A�āA�p�A���A����\�A�Ƃ��키���ƂɂȂ�܂��傤�v�ƍ��ꂷ��Ɏ����ẮA�������������Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����\�������B
�@����ȉ\���`����Ă��邤���ɁA�߉q��2�����t���|��A�O����b�̌�ゾ���ŁA�߉q��3�����t�����������B�i���a16�N7��19���j���̑����E�͏��������߂����邽�߂������Ƃ����B�����₳�ꂽ�����͜ɑR�Ƃ��āA���߂āu���̓j�Z�V�傾�����v�ƙꂢ���B�u�V��߂��s���|�ꂽ��~�J�̗��v�Ƃ����p�Y�̖��H�߂��������c�����Ƃ����}�b�܂ŁA���S�{�Ђւ����炳�ꂽ�B
�@�����m�E�̐��E����̎��r�́A�ԁX�������݂����������ɁA�ق�ꂢ�l�ԃh���}�̈�������������̂ł��������A�����������S�ɂ������Ă���̂́A���������߂������߉q��O�����t���A�u���ėȉ��āv�����m�ɂ��āA���݂̊�@��ŊJ�ł��邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃ������B�F��Ɏ��Ă����B�M�����邱�Ƃ͖ܘ_�ł������i�łȂ��ƁA�����E�̈Ӗ��͂Ȃ��j�B
�@�H������̎Ⴂ�Ј���A�w�������ɂ́A�����܂Ő[���l������̂͏��Ȃ������B�֓��R�̑����Ŗk���̖h���͗h�邪���A�S�H�̓K�b�V������Ă���A�������������܂��Ă����B���G���̉ΎR���Â��ɖ����Ă���̂́A���\��������R�Ǝ���Ă��邩�炾�A�ƐM�����B
�@���͗B�A�^����ꂽ�d���ɑł����߂悢�A����̕����������Ă���̂������B�~������ƁA�H���͒��~�ɂȂ�B���Ⴊ�����A�~��ς����������Ԃ��r�����Ȃ���ʂ�B�L��͔���F�ɕς��Ă������B�뉺30�x�Ƃ��Ȃ�Ɖw�̕֏�������A���A�͍d����̂悤�ɐςݏd�Ȃ�ˏo�����B�������A�X�g�[�u��y�`�J���͂�Œ���������A�k����w���̊�͖��邩�����B
�@���͂�ߑ㍑�Ƃ̌`�Ԃ������A�����̊m�ۂ��ꂽ���B���́A�����I�Ȕɉh���ċz���Ă���ƁA���a�̃x�[�������肵���������ݍ��B�k�̋��Ђ��Ȃ��Ƃ����S�̕����́A�����m�푈���u��������ł��������ƂɂȂ�B���̂Ȃ�A���͉����������n�܂�A�����푈���P����Ԃ��A�����ɉ������Ȃ����߂ɁA����قǂ̕s����^���Ȃ��������炾�B
�@�܂������B�����̂��̂���u�ɐ����Ƃ��悤�ȁA�푈���N��Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B��ʓI�ɁA���B�ɂ���Α��v���A�Ƃ����l�����x�z�I�ɂ������B�킢�͓���ŋN�����̂ł���A����̏����͕�������������̂����邾���ɁA�c���ւ̉ߐM�͂��������A���B�ɃA�����J�̎肪�L�тȂ��ȏ�A��Έ��ׂ��Ǝv���Ă����B�\�A���G�ł͂Ȃ���������ł���B�\�\�������A�����̈��ތ���ĊW�̍s����������Ă������������́A�J��̂�������m���Ĉ��W�Ƃ����B
�@�u���ėȉ��āv�͐������Ȃ������B�L�c�O���������ɓ��������A�A�����J�̊�]����u�����Ԃɐ������ׂ�����Ɋ���{���R���̒����̓y���̓P�ށv�Ƃ����悤�ȍ��{���͉������Ȃ������B�R�̈ꕔ�ɋ��d�Ȕ��Έӌ�������A�߉q�A���[�Y�x���g��k������ނ�̂����ɏI�����B�����āA���ɊJ��h�����V������u�n���E�m�[�g�v��@���t����ꂽ�̂ł������B�u�n���E�m�[�g�v�Ƃ����̂́A�A�����J�̃n��������������A�쑺�E��������g�Ɏ�n���ꂽ�u���Č���b�o���v�̂��Ƃł���B
�@�@��̍��Ƃ̗̓y�s�N�̌���B
�A�@�e���̍������ɑ���s���^�̌����B
�B�@���Ə�̋@��A�ҋ��̋ϓ��B
�@����͏]�O�́u���ėȉ��āv�ŃA�����J�̎咣���Ă������̂ł��������A���ɉ�����ꂽ4���ڂ͔��e��@���t����ꂽ�悤�ȃV���b�N����{���{�ɗ^�����B���Ȃ킿�A
�`�@���{���C�R�͂��Ƃ��A�x�@���ɂ�����܂ŁA���B�����܂ޒ����S�y����ѕ���i�x�g�i���j��薳�����ɓP�����邱�ƁB
�a�@���B�����{�̔۔F�B
�b�@�싞�������{�̔۔F�B
�c�@���ƈɎO���������Ƃ��邱�ƁB |

�n���č��������A���Đ푈���w���������[�Y�x���g�哝�̎���̍��������A���{�̔s��̔N��1945�N�Ƀm�[�x�����a�܂���܂��Ă���B |
�@�Ƃ����s����b�����ł���B�܂��ɋ����A����A�Ō�ʒ��Ǝ����Ă��������e�ł������B�J��h�������藧�̂������͂Ȃ������B�������{����������ꍇ�́A��킸���ăA�����J�ɋ����������ƂɂȂ�B���炩�ɃA�����J�̐��z���Ƃ݂��B
�u���Ƃ�������ƒm���Ă��A���Ȃ���Ȃ�Ƃ�����B�j�Ƃ��āv
�ƁA����J��h�͂����肽���ĕ��m�����_���q�ׂ��B
�@�߉q�͊J��h��}����͂��Ȃ��A�A�����J�Ƃ̘a���𐄐i������r�������A���܂��s���đ�O�����t�𓊂��o�����B�������A�߉q�������p�@�Ɏ̃o�g����n�����Ƃ������Ƃ́A�߂��Ȃ��ĊJ��ɑË��������ƂɂȂ�B������t�̐����ŁA�J��ɓ��ݐ邱�ƂƂȂ�A���{�͕āA�p�A���ɑ��Đ���z�������B���S�����̒��ɂ́A�߉q�̎�C��ᔻ������̂��������B
�u�Ȃ��A���������߂������悤�ɁA���������߂����Ȃ��B
�ǂ����āA���͑�l�����t�܂ł����Ă䂯�Ȃ��̂��\�\�v�ƁB
�������A�J��h�̋��������ł͂Ȃ��A��l�̋߉q�����������ė}�����悤�ƁA�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ�����n���Ă��āA�푈�͋N��ׂ����ċN�����ɈႢ����܂��B
�@�m���ɊO����̎��s�ł��낤���A�u���ėȉ��āv�̎��@���������̂������ƂȂ����B�����A�O�����ǂ������ɑË��Ă������������Ɠw�͂��Ă��A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��K���́A��������і��B����̓P�����m��ł��Ȃ����ƁA�O��������j���ł��Ȃ����ƁA�Ȃǂł������B�������Ă��邤���ɁA�A�����J���d�����Ă������̂����A�u�n���E�m�[�g�v�̈���́A�J�픽�̖��S���������t�コ�����B
�@�u���B�����܂ޒ����S�y�c�c�������ɓP������v�Ɖ]���̂́A���B���̔۔F�Əd���āA���S�̑��݂�h�邪���Ă��邩��ł������B���S�Ƃ������t�͂Ȃ����A���̗��ɁA��������Ɍ����Ă����u���S�����o�c����R���ꂽ�n���}�\���v�������Ă���悤�Ɏv����B���ĊJ��̏h���Ƃ��]���ׂ����̂ɁA���X�Ȃ���ɑR�Ƃ���������Ȃ��̂������B
�@����ɂ�������炸�A�푈�͔��������Ƃ����F��̂悤�Ȃ��̂́A�S���闝�������̒��ɂ������B�ł��A�푈�͎n�܂��Ă��܂����̂ł���B��肾�����ȏ�A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�^��p�̐�ʈȗ��A�����m����ѓ���e�n�ɂ�����폟�́̕A�{�A�x�Ђ͂������Ӌ��̊e�w��H����������������B
�@���S�]�ƈ��̎m�C�͗g��A���݂ɗ�݂Ȃ���c���͂��悢��ł܂��Ă��������A�O�q�����悤�ɍ������͕����ł���A���B�ɐ�̋y�Ԃ��Ƃ͍l�����Ȃ��̂ŁA�v�������ʏ���̏�����퓬�̖͗l�Ȃǂ��A�V����W�I��ʂ��āA���Ί݂̉Ύ��߂�����Œ��߂Ă������Ƃ������Ȃ��B���a16�N�̏���̏������A�w���̓X�g�[�u���݂͂Ȃ���A��]�I�ϑ��ɐ����āA
�u���N�ŏ������邻�����B
�A�����J�͐^��p�ő�Ō���H�������A�C�M���X�̓V���K�|�[������ǂ��o����邾�낤�B
�����Ń\�A�����قɓ���̂��v
�ƁA�^���₩�ȃf�}�ɖڂ��P�������B
�@���������ɂ͖Y�N��̐ȏ�ŁA����ȉ�b�����킷���̂��������B
�u�d�����ŏ����Ă����āA�p�b�ƊO�����̘r���݂���B
�@������������B
������ɂȂ�����A�܂��A��Ȃ��B
�R�{�\�Z�叫���������Ƃ����̂́A�f�}�Ƃ��Ă��A�X���ɒl�����B
���N��N�Ȃ��\��ł��邵�A�K���A�b�ƌ��킹�Ă݂��邪�A2�N�A3�N�Ƒ����A�Ȃ�Ƃ��\���������܂���A�ƁB
���{�̗��C�R�͐�ɋ����B
�������A������ƂȂ�ƌo�ϓI�ɂǂ����낤�v
�u�K������B
�A���A�I��̃`�����X���ȁB�ǂ�Ȏ��ł����낤�B
����܂����傫���L������������ˁv
�u�������A�ςȂ��ˁB
�\�A�Ƃ́A���܂��s���Ă邯�ǁA�����������ɂȂ����B
���������łȂ��A�āA�p�A���Ƃ��키���ƂɂȂ�A�Ƃ��������́A���̒ʂ�ɂȂ����܂�������Ȃ����B
�\������B
����ƁA�q�b�g���[�̉e���ŁA�����ςɂȂ��Ă��킯�ł��Ȃ��ȁv
�u�q�b�g���[�ɖ������Ă����낤���A�\�A�Ƃ����A�ƌ������̂́A���܂��������B
�����̗\���̃~�X�A���ꂾ�����������v
�u�\�A�����āA�ƃ\��ő傫�ȏ���������ˁB
�Ȃɂ����{�Ǝ������܂���K�v�͂Ȃ����A�Ӗ����Ȃ��B
�܁A�֓��R�̋������h�g��ɂ��Ȃ��Ă邵�ˁB
���������A����֎���L���Ă��邵�A���݂͏d���Ă���Ƃ��Ă��A���K�v�͂Ȃ��B�v
�u���B�͂������ň��ׂƂ������Ƃ��B
�Ƃɂ����A���̂܂����Ă����Ȃ�����c�c�v
�@����̘N����T�J�i�ɁA��N�Ƃ����ʁA�ނ��됶���������������̐Ȃł������B���C���ȗ��j�̌����̒��ɂ��Ă��A���S�́A���͂�h�邮���Ƃ̂Ȃ���Ղɍ��������A�^����ꂽ�C���ɒ�g�ł����̂ł���B�����āA�V�����N���a17�N�i1942�j���}�����B
17�@�\�A�̐i���J�n top
�@����Ɍ��������Ƃ��ꂽ�������A�i���a20�N8��9���j�ߑO1�����A�\�A�͖��B�̍�������j���Đi�����J�n�����B�V���̖��S�������́A�֓��R����̘A���d�b�ŁA���J�A�R�H�͐��ʂ̃\�A���ˑR�U�����n�߁A���݁A���O�]�s�X���ɔ�����Ă��邱�Ƃ�m�����B1��������A�V�����ɔ����������A��P�x��͖���ɓ���������̎s����k���������B�͈Њd���x�Œʂ薂�̂悤�ɉ߂����������A���B�̓��{�l�Ƀ\�A�̑Γ����z���������炵���̂ł���B
�@���S�̊e�����͘T���̂����ɖh�q�̐��𐮂����B�֓��R�̍�햽�߂͖��S�ɂ��`�����A�����ʂ��U�����n�߂��G��r�����Ȃ���A�S�ʊJ��̏���������A�Ƃ����̂������B�ߑO6���ɂ̓\�A�̑Γ����z�������炩�ƂȂ�A�S�ʊJ�햽�߂����������ƁA�u�펞�h�q�K��v����сu���B���h�q�@�v�Ɋ�Â��A������̂̐펞�̐��ɓ������B���ɁA������ׂ����̂������̂ł���B�������A����Ȃɑ����Ă̔��ɁI
�@�\�A�R�͓����ʂ���N�������B10���ɂȂ�ƁA�S�ʓI�Ȑi�U���n�܂�A�{���̐����œ�������іk�N�̍�������˔j�A�k�����ʁA�������ʂ�����h�b�Ɛ�����B�ɓ��R�i�ߊ����V���t�X�L�[�����̑��w���ŁA�����������B����ۂ݂ɂ���̐����������B���S�͊֓��R�ƘA�����ēS������ѕt���n�̎{�݁A�Z���̗i��Ɣ���ɓ������B |
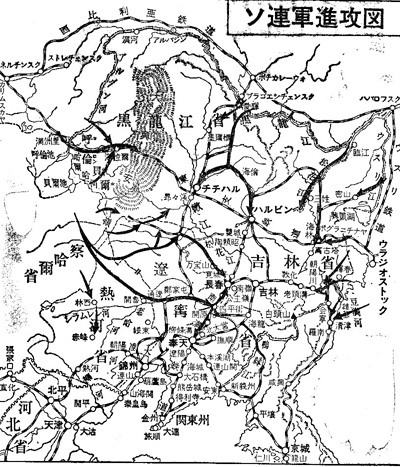 |
�@�������A�퓬�Ƃ��Ȃ�ƕ��͂ɗ��邵���d�����Ȃ��B���̗���ׂ��֓��R�͎�̂������B�������͕��̎r��z�������W�ɂ܂����A�r�[���r�́u���U����v�͉��̖��ɂ������Ȃ������B��������������Ԃ͌��ɐ��܂�����������˔j���āA��v�w�ɔ��e��ł����݂Ȃ���A��s�V���i���t�j�V���ւƂȂ��ꍞ��ł����B
�@�u�������̔��A���͂ǂ�����̂��v�ƁA���S�����͊֓��R�ɐH�������B���Ŗ����ɂȂ��Ă���Q�d�����́A�M�l�̔�ނɂ܂Ŏ肪���Ȃ������B�J��ƂƂ��ɍݗ��M�l�͖A�������Ė����炪���Ԃɏ��A��v�s�s�֓쉺���Ă������A�V���A��V�Ƃ����ǂ�����̒��S�ɂȂ邩�킩����̂ł͂Ȃ��B�命���̔�����v�s�s�ɗ����W�����邱�ƂŁA���E�̂��Ȃ��n���G���W�J����邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B���S���͎��e�~��{�݂��}������ƂƂ��ɁA���ӓ��n�т���k�N�n��ɗA������悤�ӌ���\���Ă����̂ł���B
�@����������l���Ă����Ȃ��قǁA�\�A�M�̖�]�œ|�ɑS���͂��X���Ă���֓��R�́A����ɂ�������炸�G�̋@�B���啺�c�ɑ��Ă��奂̕��ɓ�������͂ɉ����A�̂ڂ�����Ă����B���S�������Q�d�Ɋ��݂����̂́A�R��]���̉Ƒ������������J��Ɠ����Ɉ��S�n�тֈڂ��ꂽ����ł������B����ɂȂ���āA���S��]���̒��ɂ��A�}���ʼnƑ�������悤�Ƃ������̂��������B
�@�M�����̗����͌��{���āA
�u�����̎w��������܂ł͉Ƒ������ȁB
�����̎��R�ɂȂ��Ԃ������������������A�ƌ�����قǕs���_�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
����͎����̉Ƒ����������킢���̂��v
�ƁA��l�����B
�����ŁA�ꍏ�𑈂��A�S�������̑g�D�I�Ȕ��K�v�ƂȂ����̂��B
�@�֓��R�����ł��A��]���̉Ƒ����������S�n�тֈڂ����ƂɁA���Έӌ����������҂��������̂ŁA10���ɂȂ��đS�������̎��e�~�삨��ш��S�n�тւ̗A���S���Ƌ��c���A�n�т���k�N���ʂւ̔����@�����肵���B
�@�����A�֓��R�͋������̂��ƂȂǂ͂��܂��Ă����Ȃ������̂��B�k�l���ʂ��̔����V���ɎE�����A��V���A�֓쉺���Ă䂭���̂Ɠ���܂����đ卬�����N�����Ă���Œ��ɁA���i�ߕ��͓ˑR����u�i���v�ֈړ����n�߂��B
�@���肫�蕑���̖��S�͂���ɓ��ʗ�Ԃ��d���ĂĖ��߂ɏ]�������A�ړ��̗��R�́A�V���t�߂������̐��ƂȂ邱�Ƃ��݂Ƃ߁A���B�����{�@�ւƂƂ��ɓ��n�ֈڂ�Ƃ����̂ł���B�֓��R�̌����Ԃ�Ƃ��ẮA���\�S�ʊJ��̏ꍇ�́A����\�肵�Ă����ړ��ł����āA���n�̏��v�{�݂͂ł��������Ă���A���v�Ԑ��Ƃ��āA�Ō�͔����R���̗Ս]�t�߂ɂ�����̂��ƌ����B���̌��i�K�Łi�������̔��s�Ȃ��Ȃ������Ɂj���i�ߕ����������������o���A�Ƃ�����ۂ������A���S�͔ᔻ��������Ȃ������B
�@�Q�d�͗����Ɍ������B
�u��{�c�͊֓��R�̔C�����A���B�h�q����A���N�h�q�ɐ肩����̂��B
�鍑�S�ʂ̐틵����l���āA���N�����Ō�̈���Ƃ��Đ�ɖh�q���Ȃ���Ȃ�ʂƂ����B
�܂�A���B�S�y��������Ă������Ƃ����l�����B
��X�������ł���Ǝv�����B
�ʉ��ֈڂ�̂͂��̂��߂��v
�@��{�c�����B���������Ƃ����l���́A���S�ɂƂ��Ă��V���b�N�ł������B�]���āA���{���{���\���z�������Ă��Ȃ��Ƃ����܂݂́A���B�̖M�l�͋ʍӂ���Ƃ������ƂɂȂ�̂��B
�@�M�������Ȃ܂��������̂ɂ����������肱��ł���B�Ǝv���Ƃǂ���Ԃ�̉J���A���B�̒זł������邩�̂悤�ɁA�f�������l�X�̓���������������B���C���Ȑ�Ԃ̋����͍��ꍏ�Ƌ߂Â��Ă���C�z�B�֓��R�̂��G���ɂ����Ė�����̔�𗊂݂ɂ��Ă����V���̖M�l�́A���i�ߕ��Ɛ��{�@�ւ̓P���ŁA���E���ɂ��ꂽ�悤�ȕs�������ڂ����B�����ē����Ȃ��Ɗ�Ȃ��B���S�͋������̍��������A���������߂āA��Ԃ̉^�s�Ɋ��_�N�������B
�@�֓��R�Ɩ��B���̈�̂ƂȂ����R��̎����͔[���ł��邪�A����Ɋ������܂ꂽ�������͂ǂ��Ȃ�̂ł��낤���B�������A�A���̑哮���ł��閞�S�́A���ꂱ���G�R�ɐ�̂����܂ŁA�d�����������킯�ɂ����Ȃ��B�֓��R�͎��v�R��œ����Ɉڂ�A�����R�̉��[�������邱�Ƃ��ł��悤���A���S�͓S���������߂ɁA�C����������ނ���킯�ɂ����Ȃ��B�r�[���r���Ԃ炳���ĉ������Ă����������̕����́A���܂��킩���˂�Ă���B
�@�����w�����邨�̕��͐ӔC�d��ł���Ƃ��Ă��A�n�}���͂�ō�햽�߂��A�����܂ōR�������ł��Ȃ���A�댯�ɂȂ���ł�����ֈړ��ł���B���d�_��`�Łu�����y�y�v�̐l����ی삷��]�T���͂��������֓��R�́A���ɖ��S�����E���ɂ��邾�낤�A�Ƃ����s�M�ƕs�������ڂ��閞�S�Ј������������B
�@�����́A�Ō�̈�l�ɂȂ��Ă��z�����������S�������炵�����Ƃ������O�Ŋ撣���Ă������A���X���܂�j�ł̗\���Ɉ����ꂽ�B����ł��܂����{���{�͎��ł��Ȃ��̂��Ƃ������ǂ������ƁA�Ђ���Ƃ�����_���������ď��̂�������Ȃ��Ƃ�������]�̒��ŁA���ʂ������邩�A�ǂ��炩�Ɍ����邠��u�Ԃ������Ă����̂��B�B�A���B�̓y��ɂǂ�����Ɣ̍��������A��10�N�̗��j�̏d�݂ɑς��Ă������X�ꖜkm�̓S�H�����̓r�N�Ƃ������A�L��A�g���l���A�s�s���т��đ���A�l�Ԃ����̋��C�����߂Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B
18�@�I��̏d����� top
�@���S��8��14���ɖ��B�ʐM�Ђ���u�I��̖͗l����v�Ƃ������ɐڂ����B�ʉ�����R�c�֓��R�i�ߊ���4�l�̎Q�d���]���āA���킽�������V���֔����čs���̂��w���͌��Ă����B�܂��Ȃ����S�͊֓��R����́u��15�����߁A�d���������A�ޒ�����v�Ƃ������߂ɐڂ����B
�@��A�̖��S�{�Ђł́A��15�ڂ̐��߁A�e�����ɕ�����ďd����������B���A�����̂悤�ɏo���Ă����Ј��́A��i����d�������������ꂽ�Ƃ��A�s���Ɠ��ɂ����̂́u�ʍӖ��߁v�Ƃ����ň��̎��Ԃ������B���łɓG���N�����Ă����ꍇ�̖h�q�P���A�h�K�A�a�����̑g�D�ȂǂŖ��������Ă������A���͂�֓��R�͂����ɂȂ�ʂƂ����ߑs���̂Ȃ��ɁA�u�S���펀�v�̊o����߂Ă����̂ł���B������d������ƕ������Ƃ��A�u��`���E��邩�I�v�ȂǂƘr���������A������������Ȃ���A���̂ӂ������v���Łu���v��A�z���Ȃ����̂͂Ȃ������̂��B
�@��A�̓r������������ꂽ�����Ŗ��L�Y�Ƃ����Ă悩�����B�\�A�͔���q��˔j���ăn���s���A�V���ɂ��܂��Ă��邪�A��V�����A�֓쉺����܂łɂ́A�܂�������v����Ƃ݂��B����܂łɔ����͓���ǂ��ė��Ȃ�Ƃ��Ă��A�G�R�N���܂łɂ́A5����1�T�Ԃ̖��͕ۏ���Ă����B
�@����1�T���̖������Ƃ����ށB�M���M���̐�̐▽�ɒǂ����܂ꂽ�Ƃ��A���Ƃ�1���ł��낤�Ɩ����ǂꂾ����ȁA���������̂Ȃ����̂ł���������m�炳���̂��B
�u�����ė����̂͂������߂���Ȃ���v
�Ƃ������t�́A�R�l�ɂ����^����ꂽ���̂ł͂Ȃ������B
�@�����炭�B�����y������ɑ��点�Ă��鉄��1��5,000m�̉������h��D�ɗ��Ă�����A�Ō�̒�R�����邱�ƂɂȂ邾�낤���A����ł��~�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂������B��l�̓G�ł��E���Ď��ʁB���邢�͎E�����O�ɁA���������Ⴆ���Ď��ʁB�����A�d��������u�ʍӖ��߁v�Ȃ�A���{�l�炵�����ɂ������l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@�������ł��������A�G�s�Ȗ��S�{�Ђ̑����璭�߂��A�̎s�X�́A�A�J�V�A��|�v���̊X�H���ɍʂ��Ĕ������B10�{�̕��ˑ哹������L��𒆐S�ɂ��āA�u�˂ƊC�Ɉ͂܂ꂽ���m�̃p���Ƃ�����������X�͓����ɒ����A���Ƌ�A�H�Ƌ�A�Z���ɐ��R�ƕ���čL�����Ă����B����͖��S���c�X�Ƃ��Ēz�����������̊X�������B
�@�����āA������60���̏Z���͕��a�ɑ��Â��Ă���B���̖��B����㊂̂悤�ɕw���q�������܂߁A���Ɖ������ŋʍӂ��Ă��܂��̂ł��낤���B���܂�ɔ�����ῂ������a�ȊX�́A�����o�傷��Ј��̖����̊�ɁA�c���ȂقǑN��ɉf�����B�ʍӂȂǂƂ͂����̂悤�ŁA���ꂪ�������ċC�����킹��B�Ј������́A���W�I�𐘂������ŕ������܂ł́A�I��ْ̏��ȂǂƂ͖��ɂ��v��Ȃ������̂ł���B
�@�W�����e�ۂ̐l�����́A�N���⏗�q�Ј��̎p���ڂ����A���W�Ŏ��̔������悤�Ȏ������Ɠ��l�A�Ⴂ���͖̂w�ǂ��Ȃ������B |

10�{�̓��H�����ˏ�ɏo���A�L��A���̍L��ɖʂ��ē��{�n�̊�Ƃ��s����������ł����B |
���W�I�͎G���������ĕ����Ƃ��������B�������A�V�c�̋ʉ������߂ĕ����ْ��ŏl�R�ƁA�S�_�o�����ɂ��āA�����̐�ł��~�����߂Ƀ|�c�_���錾����������Ƃ����u�ς���������ς��A�E�т�������E�ԁv��ق̐^�ӂ����݂Ƃ����B
�@���߂ĕ����V�c�̋h�X�Ƃ������̂Ȃ��ɐ��܂�����z���������Ƃ�A�Е������͚j���B���炭�A���t���Ȃ���𐂂ꂽ�܂܂������B�N�����u����ς蕉�����̂��v�ƁA�|�c���ƌ������B�u�I��ł͂Ȃ��B�������~���Ȃv�Ƃ����ߒɂȐ��ɍ������āA�u���₵����I�v�Ə��q�Ј����A�B
�@���S�̌�̕��G�Ȃ���߂��B�w�ǂ̎҂��܂�@���A�ڂ�Ԃ����Ă����B��ȐS���ł������B�u�ʍӁv�ł͂Ȃ������B������A�푈�͏I�����̂������B����ɂ�������炸�A�������~���ɋ������ɂ͂����Ȃ��̂��B���̎��قǍ��������A�����Ă��܂������{�����Ƃ����ދC�����A�����ɁA���{�l����̂��̂ɗn�����킵�����Ƃ͂Ȃ������̂�������Ȃ��B
�@�₪�ė������A���ꂼ��̎������ֈ����グ�Ă䂭�l�X�̂Ȃ��ɁA���邢�ΐ��������Ă����B�_�����{�����߂Ĕs�ꂽ�Ƃ������J�Ɣ߂��݂̒��ɁA�u�h�b�R�C�A�푈�͏I�������A���͐����Ă���v�Ƃ�����������A�n���ɂ��ЂƂ����ϔO�̋����ʂ�������������ł��낤�B
�@���S�͂ǂ��Ȃ�̂��H�@
����͊֓��R�̎w���Ƃ������A�\�A�̖��߂ǂ��蓮�����ƂɂȂ�ł��낤�B����܂ł͓���ʂ�o����A�Ƃ������ƂɂȂ����B�����m���ɂ킩�邱�Ƃ͊֓��R�̕��������A���S�̉�̂Ɛ�̌R�ɂ��V�g�D�A���B���������Ȃ�A�Ƃ����O�ł���B�ǂ�ȉ^�����҂������Ă��邩�A��͂��Ȃ��C�����B
top
|