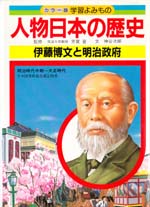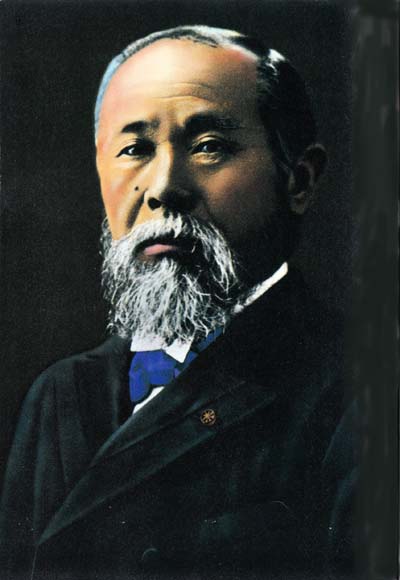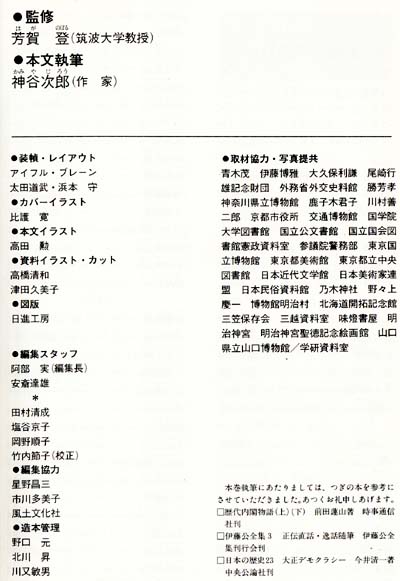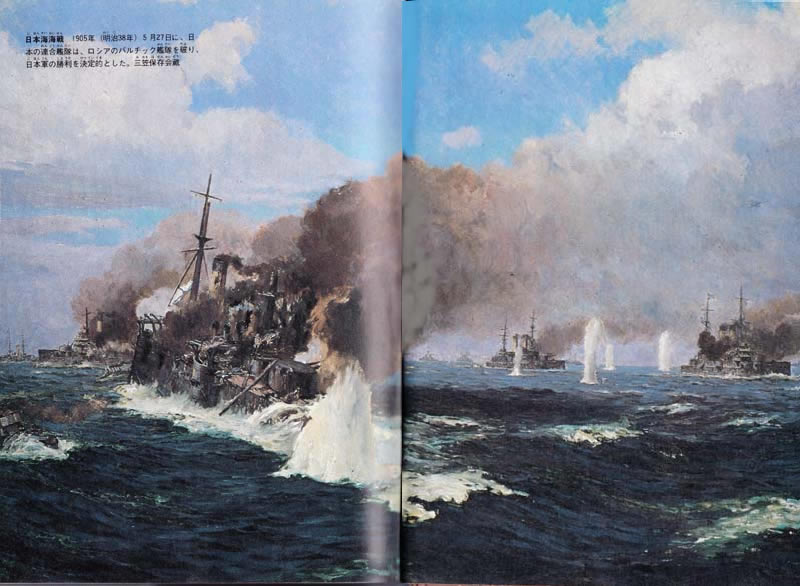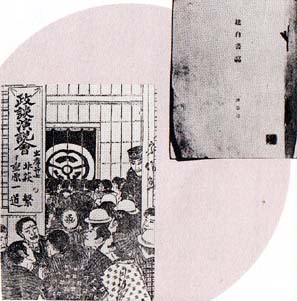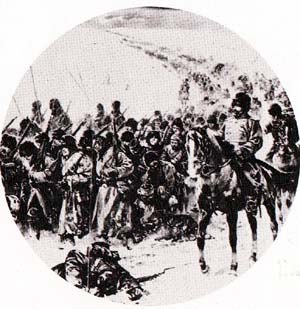|
Home@Tv@R{Ü\Z@É¡¶@¼½²·@úºìg@@úºìÆN@LbGg
DcM·@MºEªM@«¸@¹©@¡´¹·@¹Vc@¹¿¾q@ÚíÄ
É¡¶Æ¾¡{
il¨ú{Ìğj13@ÄC@Fêo@¶@_JY@wK¤Ğ@1984N§j
|
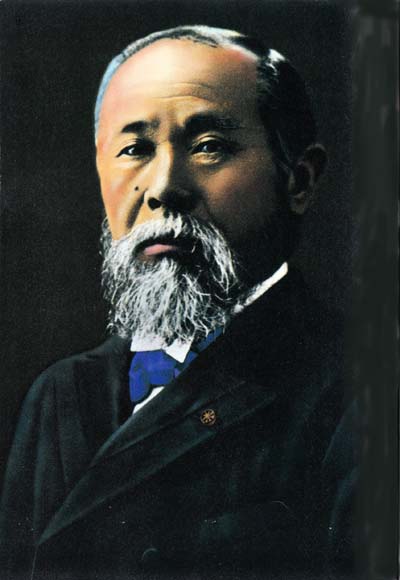
É¡¶@¾¡{ÌÅw±ÒÆÈèA
ú{ÅÌàtåbÉACµ½B
|
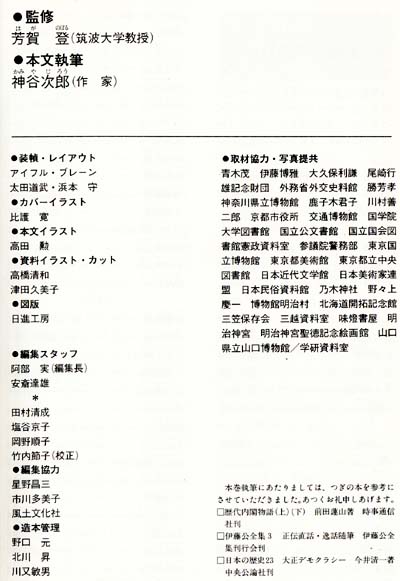
|
|
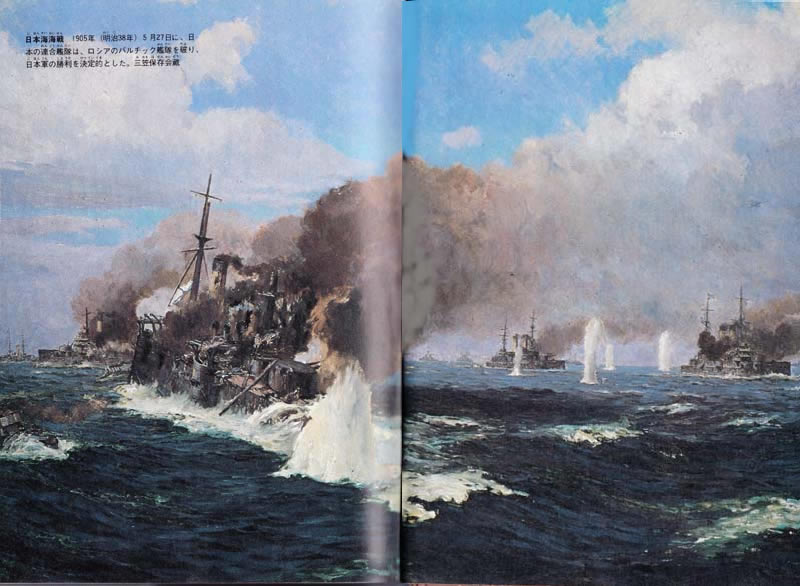
ú{CCí@1905Ni¾¡38Nj527úÉAú{ÌAÍàÍA
VAÌo`bNÍàğjèAú{RÌğèIƵ½BO}Û¶ï
|
1 ¾¡Eå³Ì çܵ
Üé©R¯ ^®
@¾¡V{Ì¡ÍAuxºvğæêÌÚWƵĨ±Èíêīܵ½B
»Ì½ßA{ÍÌàğ佩ɵæ¤ÆA¯Éd¢S
ğ¨í¹A¯ÉRàÌÍğÂæßéôğÆÁīܵ½B
@±¤µ½{ÌûjɽηélÑÆÉæÁĨ±³ê½^®ª©R¯
^®ÅA»Ì^®ÍïJİÌv©çA³çÉlÑÆ̶ÌÀèâ
üãğàÆßé^®ÖÆWµÄ¢«Üµ½B
@±êɽ¢µÄA{ͫѵ¢ÆèµÜèğ¨±È¢Üµ½ªAenÅàïªĞç©êA©R¯ ^®ÍÜ·Ü·½©ÜéΩèŵ½B
@ꪪêNi¾¡\lNjA¢É{ÍêªãZNi¾¡ñ\ONjÉïğĞç±Æğñ©µÜµ½B
@ïJİɻȦÄAÂ_޽¿
Ì©R}AåGdM½¿Ì§üi}ÈÇA}ğÂ鮫ªÉÈèܵ½B
@ܽAV·ğsµ½èAàïğĞ碽èµÄA¡Iå£ğ\·éæ¤ÉÈèܵ½B
@µ©µA{̫ѵ¢æ÷ªÂ
ëA©R¯ ^®Íµ¾¢É¨Æë¦Ä¢«Üµ½B |
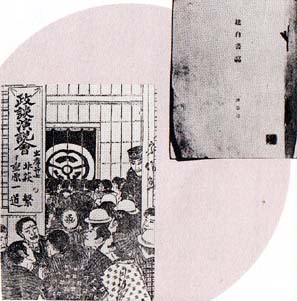
EͧuЪoµ½Ìʵ
¶Í©R¯ ^®ÆÌàïê
|
cï¡ÌͶÜè
@{ÍA©R¯ ^®ÈÇ̽{^®ğ¨³¦éêûÅA{Ìl¦Ä¢éî{ğ¨è±ñ¾@ÆA»êÉæÁÄcïğĞçd
𨵷·ßÄ¢«Üµ½B
@»Ì½ßA{ÍÉ¡¶ğ[bpɨèA@â¡Ìµİ𲸳¹Üµ½B
@Aµ½É¡¶ÍAàţxğयAÅÌà
tåbÉACµÜµ½B
@ꪪãNi¾¡ñ\ñNjAåú{é@i¾¡@jªz³êܵ½B
@±Ì@ÅÍAVcªÌå ÒƳ¾ßçêAå«È Àğà¿Üµ½B
@ܽïÍAØ°EÅà𽨳߽lEVcªC½µ½cõiºIcõjÈÇÅ\¬·éM°@ÆA¯ÉæÁÄIÎê½cõÅ\
¬·éOc@ªà¤¯çêAM°@ªå«ÈÍğàÁĢܵ½B
@êªãZNAñ©Ç¨èæêñÌécïªĞç©êܵ½B |

¾¡@Ìzğj¤lÑÆ
|
@µ©µA
Oc@cõÌI ÍAêèzÈãÌÅàğ[ß½ñ\ÜËÈãÌj«É
µ© ½¦çêÈ©Á½½ßA¯êZZlÉêlÙÇÌŵ©I Í èܹñŵ½B
@±Ìæ¤É¯Ì¡QÁÖ̹ͻêÙÇĞëÍÈ©Á½ÌÅ·ªAú{ͼÌAWAɳ«ª¯ÄA@ÉàÆÃcï¡ğ¨±È¤ÆÈèܵ½B
ğñÌü³É¬÷
@ÌÍğÂæßé±ÆA±êª¾¡{Ìêѵ½ûjŵ½B
@»Ì½
ßÉÏA]Ëą̃íèÉOÆŞ·ñ¾us½ğñvÌü³ªå«
ÈÛèÆÈÁ½ÌÅ·B
@ꪪZNi¾¡\ãNjɨ«¾m}giCMXDª¾vµACMXlªSõ©èAú{læqªSõSµ½jÉÆàȤs½Ù»ğ«Á©¯ÉAğñü³ÖÌ¢_ª½©Üèܵ½B
@{ÍCMXÆğÂğ··ßAêªãlNi¾¡ñ\µNjÉğñğü³
·é±Æɬ÷µÜµ½B
@»ÌãÍÙ©Ì®ÉÆÌü³Éà¬÷µAú{Åß𨩵½Olğú{Ì@¥Åٻūéæ¤ÉÈèܵ½B
@ܽAêãêêNi¾¡l\lNjÉÍA·×ÄÌAüiÉú{Ì»fÅÖÅiÅàjğ©¯çêé
æ¤ÉÈèA¢Eɨ¯éú{ÌnÊϽ©Èèܵ½B |

úp¯¿ğLO·éGͪ«
|
ú´EúIíÆع
@ğñü³Ì¬÷ÍA©NğͳñÅ´ijÆΧµÄ¢½ú{{ğA¨¢Ã©¹é±ÆÉÈèܵ½B
@»µÄ©NÉioµÄ¢Á½ú{ÍAêªãlNi¾¡ñ\µNjÉú´íÉÁÄumÉú{ èv
Æ¢íêéÜÅÉÈÁ½ÌÅ·B
@µ©µAú{ª´©ç¦½É¼ğß®ÁÄAú{ÆVAÍΧğÓ©ßéæ¤ÉÈèܵ½B
@àÆàÆÖÌioğÍ
©ÁÄ¢½¼ÍA¢ÉúIíÉËüµ½ÌÅ·B
@úIíÉÈñÆ©ğ¨³ß½ú{ÍA»Ì¨¢ÉÌÁÄØğA¯nƵŵܵ½B
@ñÂÌíÉÁ½ú{ÍA¢æ¢æ
¢EÌ®ÉÌÚğ ÑéÆÈÁÄ«½ÌÅ·B |
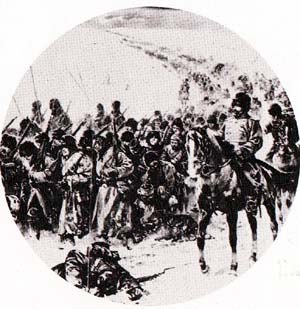
úIíÅáÌÈ©ğPŞ·éVAR
|
æê¢EåíÆú{
@êãêlNiå³ONjAhCcEI[XgAÈÇ̯¿ÆCMXEtXÈÇÌAÆÌíª¨±èܵ½B
@±Ìíͽ̮ɪQÁµ½ÅÌåíÈÌÅAæê¢EåíÆæÎêܵ½B
@ú{àAªíɽÁÄQíµA±êğ«Á©¯ÉHƶYª}¬ÉÌÑܵ½B
@µ©µA½ÊA¯Í¨¿ÌlãªèÈÇÅéµ¢¶ÆÈèAÀã°ğàÆßéXgCLਫéæ¤ÉÈèܵ½B
@±êÈãAÍğÂæßÄ«½RÌ®«ÆA¯åå`ğàÆßés¯Ì®«Æª©çİ ¢ÈªçAğjͺaÖÆŞ©ÁÄ¢«Ü·B
2 ¾¡Eå³Ì¨àÈÅ«²Æ
|
¾
¡
ã |
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1894
1895
1898
1900
1902
1904
1905
1909
1912 |
åvÛʪIöäâijÅÃE³êéB
ßqºª½ğ¨±·i|´®jB
¤Ğªïú¬¯¿Æü̵A©R¯ ^®ğ··ßéB
É¡¶ªuWïğávğ³¾ßéB
êªãZNÉïğĞç±Æªè³êéB
¯L¨¥¢³°ğ³µAQcåGdMğÇú·éi¾¡\lNÌÏjB
Â_ŞçÜğSÉu©R}vª¬³êéB
É¡¶ª@²¸Ì½ß[bpÖo·éB
åGdMğSÉu§üi}vª¬³êéB
©R}Â_ުò§Å¨»íêéB
§ßOÊfªÍìLçğÆç¦éijB
uÂÙvª®¬µAÂÙª¤ÜêéB
uØ°ßvªöz³êéB
©NÌéi\EjÅub\ÌÏvª¨±éB
ú{Æ´ijªuVÃğñvğŞ·ÔB
àt§xª¬§BãàtåbÉÉ¡¶ªAC·éB
CMXÌum}gvªïµAú{læqSõªSB
uÛÀğávªöz³êéB
É¡¶ª§@ğÂèAãc·ÆÈéB
uåú{é@i¾¡@jvªz³êéB
æêñOc@cõIª¨±ÈíêéB
æêñécïªĞç©êéB
VAÌc¾qªú{Ìx¯É¨»íêéiåÃjB
©NÉuw}Ìibß_¯íjvª¨±éB
¤@õªCMXÆÌğñü³É¬÷BÈãeÆàü³B
ú{ª´Ééíğz·éiú´íjB
VAÈÇOªuºÖuağñvÉ¡âèğ¢êéiO±ÂjB
ú{ÅÅÌ}àtiGÂií¢Íñjàtjª¬§·éB
u`acÌvÅAú{ÈǪª´Öºğ¾·ik´ÏjB
ú{ÆCMXª¯¿ğŞ·Ôiúp¯¿jB
ú{ªVAÉéíğz·éiúIíjB
ú{ÆVAªu|[c}Xğñvɲó·éB
ØÄ{ª¨©êAÉ¡¶ªãÄÆÈéB
É¡¶ªÌnrwÅÃE³êéB
¾¡VcªSÈçêA¾¡©çå³ÖNª©íéB |
|
å
³
ã |
1914
1923
1925
1926 |
ú{ªæê¢EåíÉQí·éB
uÖåkĞvª¨±éB
uÊI@vÆu¡ÀÛ@vªöz³êéB
å³VcªSÈçêA峩çºaÖNª©íéB |
top
|