|
****************************************
HOME ポーランド パリ陥落 英本土決戦 北アフリカ モスクワ スターリングラード クルスク ノルマンジー バルジ ベルリン
ロンメル戦車軍団 “砂漠の狐”
(ケネス・マクセイ著、加登川幸太郎訳)
 |
〔著者〕ケネス・マクセイ
1941年以来、英陸軍将校として戦車連隊、機甲師団に勤務、最近少佐で退役。
その間、ヨーロッパ、アジアで戦闘に参加し、MC勲章をうける。
退役後、軍事評論に専念。
著書に英国戦車部隊小史「青い草原のかなたへ」西部戦線の英軍機甲部隊奮戦の物語「ピミー丘の暗い影」本シリーズ「ドイツ機甲師団」などがある。 |
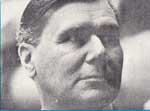 |
〔総編集長〕バリー・ビット
英国の著名な戦史・軍事評論家。ブリタニカ百科事典の海戦項目の執筆者、サンデイ・タイムス・マガジンの戦史関係顧問、ハーネス社版「第二次世界大戦史」編集者、BBC放送局制作「大戦」シリーズの監修者である。 |
はじめに “偉大な戦士”の集団 バジル・リデル・ハート卿
top
ロンメルの名は、第二次世界大戦で主役を演じた、どの将軍よりも有名である。
このロンメルの名声によって、彼に指揮されて北アフリカで戦ったドイツ・アフリカ軍団の名も、世界中に知れわたり称賛されている。
ロンメル将軍とドイツ・アフリカ軍団は、歴史に不滅の記録をのこしているからである。
しかし軍団そのものに着いては、ロンメルにくらべ、一般に、あまり知られていない。
ここにドイツ・アフリカ軍団のことをくわしく書いた本が刊行されることは、まことによろこばしい。
本書は、砂漠における軍団の驚くべき戦績、すなわち一九四一年〔昭和十六年〕二月にトリポリに到着したときから、二年三ヵ月後の一九四三年五月に、チュニジアで壊滅するまでの状況を目のあたりにみるように描写している。
一九四一年の二月中旬、アフリカ軍団の先頭部隊が、イタリア領北アフリカに到着したときには、グラチアーニ元帥指揮下のイタリアの大軍のうち、キレナイカに残っていた部隊も、オコナー将軍の英軍機械化部隊のために、ベダフォムで包囲され捕虜にされてしまっていた。
トリポリタニアに残っていたイタリア軍部隊は、この大敗北の知らせに狼狽するばかりで、そこに自国の領土を護る最後の足場をきずいて、せまりくる英軍を防ごうという勇気など、まるでなくしていた。
ドイツの輸送船の第一船は、トリポリ港に二月十四日に到着した。
ロンメルは、すでに二日まえ、飛行機でアフリカの土を踏んでいた。
輸送船で着いたのは先遣部隊だけであったが、ロンメルは、すぐこれを前線におくった。
イギリス軍の前面には、わずかイタリア軍の一個連隊しかいない。
ロンメルは、できるだけ活発に部隊を移動させて、兵力の少ないことを隠し、アフリカからイタリア軍を駆逐しようとするイギリス軍の追撃を弱めようと努力した。
ロンメルの先頭師団の戦車連隊がトリポリに上陸したのは、三月も中旬になってからであった。
そして三月の終りになっても、この師団(第五軽機甲師団、のちに第二十一機甲師団と改称)の全部は到着し終らなかった。
アフリカ軍団二個師団のあとの師団、第十五機甲師団は、五月にならなければ到着しない予定であった。
こうした状況にもかかわらず、早くも三月の末に、ロンメルはアフリカ軍団の機甲師団(それも全部ではない)だけで偵察的反撃にでた。
イギリス軍はキレナイカを通っての長距離の追撃で、力を使いはたしており、態勢建直しの最中であろうと判断したからである。
イタリア軍を説き伏せて、新しくアフリカに送られてきた三個師団の一部を、ドイツ軍の前進に協力させることができた。
この偵察的反撃は、予期した以上の大成功を収め、ロンメルは果敢にこの戦果を拡大した。
その結果、イギリス軍は最近占領したばかりのキレナイカを全部すてて敗走した。
トブルク港だけはイギリス軍の手に残ったが、英軍部隊の大部分はドイツ・イタリア軍に包囲されてしまった。
トブルク攻略は成功しなかったが、アフリカにおける戦いの勢力均衡は、すっかりかわってしまった。
五月に、そして六月にも、イギリス軍は新鋭の増援部隊をもって攻勢にでたが、その都度、ロンメルとアフリカ軍団は、イギリス軍を撃退し、依然トブルクを包囲し続けた。
十一月、オーキンレックがウェーベルにかわって、英中東軍総司令官になってから、イギリス軍は大規模な攻勢をとった。
チャーチルは、これでアフリカ軍団を撃破し、ドイツ・イタリアの枢軸軍をアフリカから追いはらえると期待したのであった。
この英軍部隊は、この時第八軍とよばれていたが、戦車兵力では独伊軍よりも優勢で、九対四以上の比率であった。
オーキンレックが“敵軍の骨幹”と強調したドイツ軍にたいしては、四対一の優位にたっていた。
(イギリス軍は七五六両の戦車と、さらにその三分の一以上の予備戦車兵力をもっていた。
これにたいして、ドイツ軍は一七四両、イタリア軍は一四六両の旧式な戦車しかもっていなかった)
この時の英軍攻勢の“クルセーダー”〔十字軍の騎士〕作戦で、ロンメルの部隊は、キレナイカからトリポリタニアの境界まで撃退されたが、イギリス軍は優勢な兵力をすっかり使い果たすほど、長く、きわどい戦闘を繰返したのである。
その一ヵ月後、おそまきながら新しい船団が到着して、ロンメルの戦車兵力が五〇両から一〇〇両になったとき、アフリカ軍団は前進を開始した。
あらたに到着した英機甲師団を撃破して、二月の初めまでに、キレナイカの東部国境のガザラ陣地を奪回してしまったのである。
五月にロンメルは、ガザラであらたに英軍が攻勢にでるまえに、攻撃を開始した。
この時、彼の戦車兵力は、二八〇両のドイツ戦車と二三〇両の旧式イタリア戦車からなっていたが、これにたいする英軍戦車は、一〇〇〇両にちかかった。
そのうえイギリス軍は強力な米国製の「グラント」戦車を一六七両ももっていた。
しかし、二週間にわたる戦闘のすえ、アフリカ軍団のすぐれた技量で形勢は逆転した。
トブルクは急襲によってドイツ軍の手におち、英第八軍の残存部隊は撃退されて、ナイル川デルタ地帯まえの最後の防衛拠点、エルアラメイン陣地に退却した。
アフリカ軍団は、激しくイギリス軍を追ったが、軍団は疲れ切っており、とうとうこの陣地線で食い止められてしまった。
この劇的な一年三ヵ月の間、アフリカ軍団は、わずか当初の機甲二個師団(それぞれ戦車二個大隊と歩兵三個大隊)と、ロンメルが歩兵と砲兵の部隊とをよせ集めてつくった、臨時の軽機械化一個師団だけで戦っていたのである。
ロンメルがエルアラメインで食い止められてから、ヒトラーはようやく増援軍として、歩兵一個師団を空輸したのであった。
ロンメルの指揮下には、イタリア軍六個師団があったが、そのうち一つが機械化師団、一つが自動車化師団であった。
(さらに二個師団が増援としてエルアツメインに到着したが、装備は十分ではなかった)
八月になると、モントゴメリー将軍が第八軍の司令官となり、イギリス軍の戦力はまして、ドイツ軍にたいし戦車と飛行機で、六対一以上の優勢をしめるようになった。
ここにはじめて、戦勢はロンメルに不利となり、アフリカ軍団も力つきてしまったのである。
それでも、ロンメルの残存部隊は、六ヵ月かけてチュニジアまで三〇〇〇キロの大退却を実行し、優勢な追撃軍に捕捉されることはなかった。
そしてアフリカ軍団が敵に崩しだのは、ドイツ軍の背後の海を、連合軍が支配するようになってからであった。
アフリカ軍団を骨幹としたロンメルの小さな部隊は、北アフリカの戦線に、イギリス軍二〇個師団以上をひきつけた。
これは全英国陸軍の作戦兵力の半数にちかかった。
要するに、ロンメルの作戦は、戦略的牽制作戦が、やりかたによっては、大成功するものであるという最高の証言であり、著者のケネス・マクセイ氏が、見事に描きあげている物語の核心でもある。
一九四二年の初め、ウィンストン・チャーチルは、下院においてロンメルに称賛の辞をのべた。
戦争中に、敵軍の将軍をほめたたえるのは、まことに異例のことであった。
「我々の前に、きわめて勇敢な、きわめて巧みな敵将がいる。戦争という破懐行為はべつとして、偉大な将軍である」
この称賛の辞は、言葉こそちがえ“偉大な戦士たち”として、アフリカ軍団そのものにも向けられるべきであり、歴史の上に記録されるべきものであることに、なんの異論もないであろう。
訳者あとがき 加登川幸太郎 top
ロンメル将軍は、まことに小気味よい軍人である。
彼は、ドイツ陸軍で幅をきかせた参謀将校団の出身ではなく、隊付将校出身であった。
このため、ドイツ陸軍統帥部のお歴々、ヒトラーの側近のハルダーやカイテルたちは、ロンメルの名声が上るに従って、こんな男に戦略がわかるものか、と冷い目でみていた。
本書にあるパウルスの記事など、そのよい例である。
しかし、スターリングラード戦の第六軍司令官パウルスと、アフリカ軍団のロンメルの指揮ぶりとをくらべると、雲泥の差がある。
人柄も違うが、実戦的きたえ方が違う。
ロンメルの戦い方は“よく計算された冒険”であるとリデル・ハート卿は賛嘆している。
また一面、激戦の混乱のなかで状況を的確に判断して解決する能力などは、天才的というべきであろう。
“砂漠の狐”とよばれ、狐のような直感力と第六感を恐れられ、同時に尊敬されたが、まことにたぐいまれな軍人といわなければならない。
私も軍人であったので、ずいぶん多くの将軍に仕えたが、ロンメルほどの人はいなかった。
日本陸軍では軍司令官ぐらいになると、作戦の細部に口をださず、後方で悠然と構えているのが、むしろ美徳とされていたので、ロンメルのような将軍は少なかった。
ロンメルの作戦指導の見事な点は、みずから戦場にいる必要のあるときは、必ずそこにいたことである。
彼には、前線の将兵との心のつながりがあった。戦場のいたるところに身を挺しておもむき、休むところがない。
彼はこれによって、部下から普通では考えられない能力をひきだした。明朗、開放的で誠実、気取りがなく、またみずからにたいしては厳格であった。
古武士的な、清廉な軍人であった。理想的な将軍といえよう。
ロンメルの、その家族にたいする愛情の深さは、残された資料によって偲べるが、まことに心暖まるものがある。
士官学校時代に相愛の仲になり、第一次大戦中に結婚した夫人ルシー・マリアや、一人息子のマンフレートにたいする愛情は、うらやましいほどである。
彼は戦場から、短いながらも、毎日、夫人に手紙をかいている。日本の軍人だったら機密保持の面で叱られたと思うほどの手紙が、本書の資料ともなった『ロンメル元帥文書録』(リデル・ハート編)に収録されている。
そのなかに、一九四二年六月八日付けで、次のような手紙がある。
ちなみに、この日はガザラの戦いの最中で、アフリカ軍団が“大釜”陣地によって苦戦していたときである。
「拝啓(愛するルーヘ)この二日間の戦闘はとくに激しかった。
戦況のことは、すでに国防軍の発表で知っていることと思う。
戦いはこれから二週間も続くだろうが、そのときには最悪の事態はきりぬけていると思う。
六月六日の戦車戦のときに、おまえのことを思い(この日は夫人の誕生日)、アフリカからの私の贈物がうまくこの日に届くことを願った……」
ロンメルの最後は悲劇的である。
なにか源義経を思わせるものがある。
二人とも生命をかけて働いたが、仕えた人の面で不運であった。
ロンメルは、隊付将校できたえあげた純粋の武人だから政治的なことには関心がなく、大戦当初にはヒトラーを尊敬していた。
のちに地位が進んでヒトラーの本質をしだいに知るにおよんで、これに反対の立場をとるようになったが、彼は暗殺のような暗い計画には反対した。
ロンメルは、ほかの将軍たちとちがって、ヒトラーに直接、意見をのべる勇気をもっていた。
これはヒトラーのような独裁者にたいし、盲目的に服従するお人好しの単純な将軍たちや、名誉心が強く時勢に迎合する政党的軍人が大部分であったドイツ(だけではないが)では、驚くべきことである。
そして「七月二十日事件に加担し、クーデター成功後の元首に擬せられていた」として、戦傷療養中に毒殺されるにいたった、彼の最期は、運命的である。
第二次大戦末期、北フランスにあってB軍集団司令官であったロンメルの参謀長ハンス・シュパイデル将軍は、のちに『ロンメルの運命とドイツの運命』と題した著作のなかで、このころのロンメルを描いているが、最後にこう結んでいる。
「ニッコロ・マキアベリは言っている。
有能な将軍が主権者に勝利と成功をもたらせば、たとえ、その成功が主権者の気に入らなくとも、必ず兵士や国民や敵から大きな喝采を博す。
だから主権者は、自分の将帥にたいし警戒せねばならないし、また彼を排除し、もしくはその威信を奪う必要がある」
歴史上、この例は少なくない。
源義経と同様に、ロンメルもこのクラスの将帥であったのである。
訳出にあたって、原文にある注と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。
日本語版監修者のことば 中野五郎 top
第二次世界大戦こそ、人類史上で空前のグローバル・ウォアであった。
しかもそれは独・伊両軍対英・米・仏・ソ連合軍の欧州決戦と、日本軍対米こで中国連合軍の太平洋決戦というこつの巨大な顔をもった、双頭の阿修羅王(戦争を好むインドの悪神)の荒れくるった最大、最悪の戦争であった。
日本軍が一九四二年八月から六六月にわたり、ガダルカナル島で悪戦苦闘していたとき、ドイツ軍は、スターリングードで血戦死闘をかさねていた。
また日本軍が一九四四年六月、マリアナ沖大海戦を戦っていたとき、欧州戦線では、ノルマンジー上陸昨戦が決行されていたし、さらに一九四五年二月、連合軍のヤルタ会談が開かれた直前に、日本軍は硫黄島で玉砕した。
このように、第二次大戦を正しく理解するためには、太平洋戦と欧州戦の二大正面を総合的に把握し、その千変万化の実相をパノツマ的に展望、批判することが肝要である。
そこに、日本最初で唯一の「第二次世界大戦プックス」の貴重な価値と、いま全国的に大反響を巻起している理由がある。さらに大きな特色は、このシリーズがいわゆる多項目、分冊形式の便利な「戦争百科事典」の役目を果していることである。
これこそ国民必読の「戦争と平和の書」である。
この原本(バレンタイン社版)の総監修にあたった、英国の世界的な軍事評論家リデル・ハート卿の
「平和を欲するならば、戦争を理解せよ!」
という警句には、我々日本国民にもしみじみと考えさせられるものがある。
 |
翻訳 加登川幸太郎(かとがわ・こうたろう)
1909年(明治42年)北海道生まれ。
陸軍士官学校42期、陸軍大学校卒。陸軍戦車学校教官、北支那方面軍参謀、陸軍省軍務局軍事課員を歴任。
第2方面軍、第35軍、第38軍、第13軍参謀として、ニューギュア、レイテ、仏印、中国に転戦、終戦時中佐。
昭和22〜25年、GHO戦史課勤務。昭和27〜42年、日本テレビ勤務、編成局長。
訳書に本シリーズ「零戦」「B29」「沖縄」「ドイッ機甲師団」がある。 |
 |
日本語版監修 中野五郎(なかの・どろう)
1906年(明治39年)7月東京日本橋生まれ。
東大法学部卒。朝日新聞社に在勤18年。本社社会部、仏印特派員、ニューヨーク特派員、
太平洋戦争開戦によりアメリカに抑留され、1942年、野村・来栖両大使一行とともに交操船で帰国。 1942年、朝日新聞退社後第二次大戦の調査、研究、執筆に専念。
主な著書「タフワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦争史」など多数。 |
付録1――北アフリカ戦線、ドイツ・イタリア軍とイギリス軍の編成表 top
|